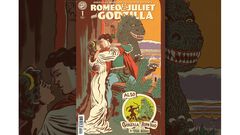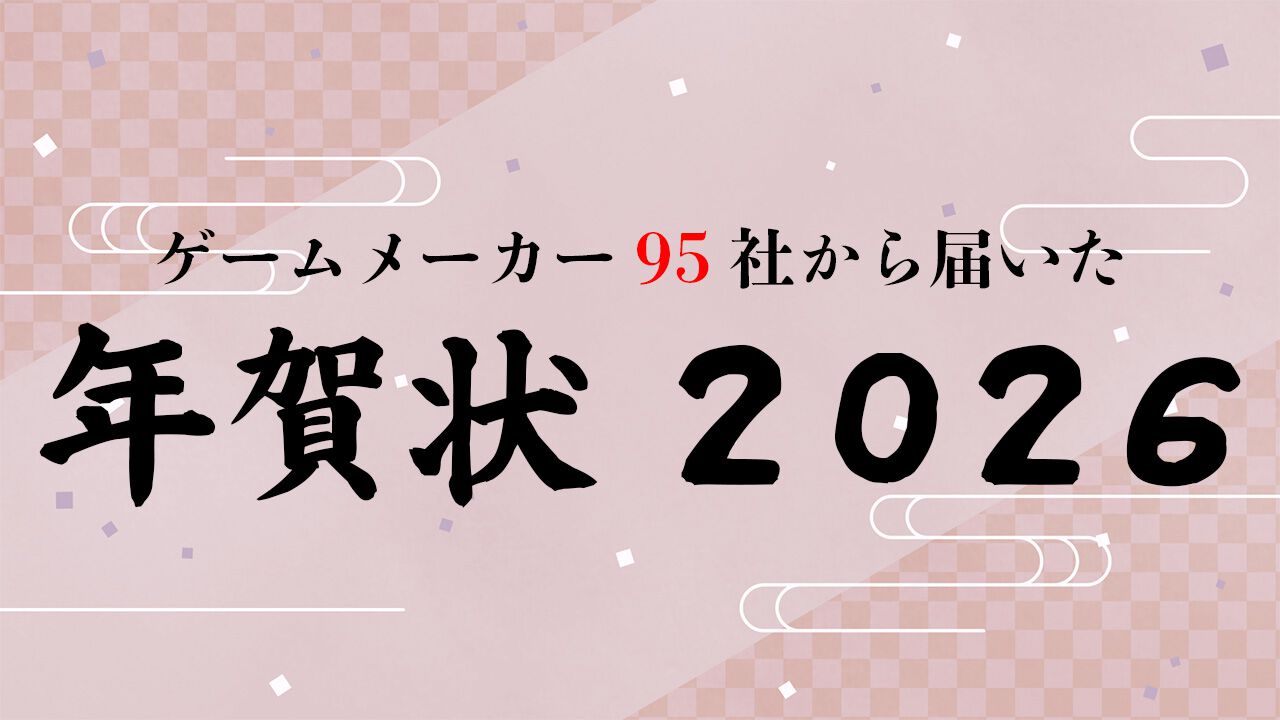すべてのメカデザイナー、あるいはデザイナーが欲する情報が凝縮!
2025年9月5日にマーベラスより発売予定のメカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』(『デモンエクスマキナ タイタニックサイオン』)。対応プラットフォームはNintendo Switch 2/PlayStation5/Xbox Series X|S /Steam。
本作は多彩な装備を組み合わせてオリジナルのメカをカスタマイズしながら、危険な敵が跋扈する戦場に身を投じるメカアクションゲーム『デモンエクスマキナ』の続編だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/add6672efec19be7d767c93094d2029a5.png?x=767)
制作総指揮を務めるのは『デモンエクスマキナ』シリーズを手掛けた佃健一郎氏。メカニカルコンセプトデザインには、アニメ『マクロス』シリーズに登場する可変戦闘機“バルキリー”の生みの親である河森正治氏が参加。前作に引き続き、楽曲はバンナイナムコスタジオが担当する。
さらに新たにキャラクターデザイナーの藤坂公彦氏と、コンセプトアーティストの幸田和磨氏が加わり、豪華クリエイターによる新チームによって開発が進められた。
今回は、本作のキーマンである佃氏と河森氏へのインタビュー対談を実施。本作のメカデザインにおける特徴や見どころを語っていただいた。
対談が盛り上がり、両氏のデザイン論やいまのメカデザイナーに必要な能力、さらにはベクトルを使ったものごとの考えかたなど、作品の枠を超えた講義レベルの話が続出。
本作を心待ちにしているユーザーのみならず、メカデザイナーを目指す者や現在メカデザイナーとして活躍している方、むしろすべてのデザイナーにとっても参考になる話が盛りだくさんとなっている。
佃健一郎 氏(つくだ けんいちろう)
フロムソフトウェア在籍中に『フレームグライド』、『アーマード・コア2』、『アーマード・コア3』、『アーマード・コア3 サイレントライン』のプロデュースを担当。フィールプラス在籍中に『ロストオデッセイ』のプロジェクトマネジメントを担当、フィールプラスとマーベラスの合併後は『デモンエクスマキナ』のプロデュースを担当。『デモンエクスマキナ タイタニックサイオン』でもプロデューサーとしてチームを率いている。
(文中は佃)
河森正治 氏(かわもり しょうじ)
スタジオぬえ在籍中にアニメ『超時空要塞マクロス』シリーズの原作、監督、メインメカデザインを担当。変形機構を取り入れた戦闘機“バルキリー”を生み出し、現在の変形メカの礎を作った。のちに制作会社サテライトの取締役に就任。『攻殻機動隊』、ソニーAIBO“ERS-220”、日産デュアリス フィギュア“パワード・スーツ デュアリス”、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ 』、『アーマード・コア』、『デモンエクスマキナ』といった幅広いジャンルのメカデザインを手掛けるほか、『アクエリオン』シリーズや『重神機パンドーラ』などでは原作と総監督を務めた。2025年には“2025年日本国際博覧会”(大阪・関西万博)テーマ事業プロデューサーに就任し、“いのちは合体・変形だ!”をコンセプトとした“いのちめぐる冒険”を手掛けた。『デモンエクスマキナ タイタニックサイオン』ではメカニカルコンセプトデザインを担当。
(文中は河森)
『デモンエクスマキナ』は3部作……の予定!
――前作『デモンエクスマキナ』の発売が2019年の9月13日でした。そこからどのように『デモンエクスマキナ タイタニックサイオン』の開発にいたったのでしょうか?
佃
じつは前作の“追加配信データVer.1.3.0”(※)を作っていたころには、次回作(本作)を開発することが決まっていました。
※2019年12月23日に配信された無料の更新データ。ダンジョン探索型の協力プレイコンテンツ。“探査オーダー”やアウターでの飛行を可能にする人体改造スキル“スカイリフター”が登場。――早い段階で決定していたんですね。
佃
そうです。当時は前作同様、外部装甲のようなアーマーにするのか、それともメカで行くのかを、テストしている段階でした。最終的に本作では小型化されたアーマーを採用したのですが、じつは本シリーズには大きな野望がありまして。
――野望とは?
佃
1作目は大型のアーマー、2作目は小型のアーマー、3作目はメカ……といった感じで、すべてのタイプを網羅し最終的にはプレイヤーが好きなスタイルを使えるようにするという目標があるんです。そういった理由から今回はアーマーにする必要がありました。
――ということは、3作目の構想がすでにあるんですね。
佃
はい。とはいえあくまで構想の段階ですし、本作が売れないことには実現しないと思いますが……(笑)。
――ちなみに前作の反響はいかがでしたか?
佃
ユーザーの皆さんからはいい反応をいただいていて、おかげさまで販売本数が70万本を突破しました。ユーザーさんの反応を見ていると、目論見通りなところもありまして。
前作の開発を行った際に、コアなメカファンだけではなく、「メカものに興味がない人にも触ってもらいたい」という思いがありました。また、「すべての“メカ好き”、“ロボット好き”が、みんな集まれるようなタイトルにしたい」と。そのために、プラットフォームとしてNintendo Switchを選択しましたし、デザインをアニメ調にしたり、キャラクター性を強くしたりしました。
結果的に、新しい層のユーザーさんに多くプレイしていただけて、メカものという枠を超えた人気を確立できたと思います。そういった意味では、狙い通りだった部分と想定外の部分がありました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a032b2cc936860b03048302d991c3498f.jpg?x=767)
――かなりの手応えを感じたと。
佃
ただ、やり残したこともたくさんありましたし、技術的に対応できないこともありました。ユーザーさんからの反応の中にはきびしい意見もあり、賛否ある部分があったのも事実です。
――それでも、確かな評価を得られた理由は何だと思いますか?
佃
見た目だけではない、しっかりとしたメカものであったことと、キャラクターの存在が大きかったと思います。メカもの、あるいはメカが登場するSFものって、どうしても入口が狭いせいで興味を持ってもらいづらいんですよね。
そこで『デモンエクスマキナ』ではキャラクター要素を強めにして、興味を持つきっかけを作りました。また、キャラクターを前面に押し出すというのはマーベラスの特徴でもあります。
――たしかにマーベラスと言えば、キャラクターを魅力的に描いている印象が強いです。
佃
しっかりとしたメカものに、マーベラスの色であるキャラクターを混ぜるという新たなチャレンジが、評価につながったと思っています。「新たなことにチャレンジしていく」というのは、河森さんの言葉でもあるんです。
――河森さんとは佃さんが『アーマード・コア』シリーズを作られていたころからのお付き合いなんですよね。ほかに河森さんからの言葉で、印象に残っているものはありますか?
佃
続編を作るのであれば、前作より「3倍おもしろいものを作らないとダメ」ですね。
河森
たしかに。昔からずっと言っていますね(笑)。
佃
昔、叱られたことも印象深いです。
河森
𠮟ったっけ?(笑)。
佃
河森さんと出会ったばかりのころ、僕がフロムソフトウェアで『アーマード・コア2』を作っていたときです。河森さんとメカデザインのやり取りをした際、僕があまりにも生意気過ぎて、河森さんに「伝えかたとかあるよね?」と言われてしまいました(笑)。
――相手のことを考えたやり取りが抜けていたと。
佃
はい、叱られました(笑)。そこから河森さんにはいろいろと教えていただきました。うまくイメージを伝えるために、河森さんのインタビューを読み込んだりもして。
河森
知らなかった(笑)。
佃
インタビューを読んでいると、河森さんはよく戦闘機や戦車、自動車など現実にあるものからたとえ話をしていました。僕もそういうものが好きなので、それらの要素をうまく使って、イメージを伝えるようにしました。河森さんから「言いたいことがわかった」と言っていただけたときは、非常にうれしかったです。
――河森さんは意図して、そういったたとえ話をしていたのでしょうか?
河森
どうでしょう、そこまで意図していた記憶はないような。聞かれかたによって、答えかたも変わっているかもしれないです(笑)。
――先ほどの「3倍おもしろく」というのは何か理由があるのでしょうか?
河森
新しいものを作るときは、“倍以上”のものを作らないとユーザーさんの期待を超えられないんですよ。1.5倍だとおもしろさが減ったと思われちゃいますし、2倍だと作り手はがんばったけどユーザーの期待値を上回れない。だから絶対に3倍はおもしろいものを作らないといけません。
河森氏が考えるデザインとスタイリングの違い
――続編を作るって難しいのですね。
河森
ホントにそれはつねに思っていますね。
佃
3倍の話を言われてからこっちはもう心が持たなくて(笑)。でもすごくいい教えなので、うちの社内でも伝えるようにしています。
あと、河森さんのインタビューで印象的だったのが、『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』(※)のクレジット表記のエピソードです。“メカニカルデザイン”ではなく、“メカニカルスタイリング”と表記した理由を語っていて、そのときに河森さんのデザイナーとしてのすごさを再認識しました。
※1991年に放送された『機動戦士ガンダム』シリーズのひとつ。河森氏はガンダム試作1号機、ガンダム試作1号機フルバーニア、ガンダム試作2号機、ガンダム試作3号機などのメカニカルスタイリングを担当。河森
僕が作ったものではなく、もともとあるガンダムにアレンジを加えただけなので、そういった表記にしています。
佃
『デモンエクスマキナ』シリーズは河森さんが描いてくださったコンセプトデザインをもとに、開発チームのデザイナーがアーセナルを作っており、それはスタイリングと同じなんですよ。
だから、開発チームのメンバーには「デザインのところに名前は載せるけど、僕らはあくまで河森さんが作ったものをアレンジしているだけだよ」という話をするようにしています。
――なるほど。デザインとスタイリングで意味合いが大きく変わるのですね。
河森
私の場合、機能をともなう部分がデザインで、形や印象といった見た目の部分がスタイリングという捉えかたをしています。その中でもキャラクターデザインというのはまた別のカテゴリーだと思っています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a18e2999891374a475d0687ca9f989d83.jpg?x=767)
――そこはアニメもゲームも変わらないのでしょうか?
河森
そうですね。今回のようなメカニックデザインは、自分の定義の中だと、変形機構や空力など、それにともなう部分がデザインで、それ以外がスタイリングです。ただ、そのスタイリングの対象が主役級のメカの場合は“キャラクターデザイン”というくくりになるんですよね。でも、“なぜスタイリングからキャラクターデザインになるのか”という部分については、いまだに自分の中で細かい定義を言語化できていなくて。
佃
そうなんですね、驚きです。
河森
メカニックデザインなら、さっきみたいにスパッと言えるんですが、どこからキャラクターになるのかはすごく難しくて……。しかも、持続可能なキャラクターとなるともっと難しくなります。
――“持続可能なキャラクター性”というのは、ファンから長く愛され続けるという意味でしょうか?
河森
はい。持続できる可能性をともなったキャラクターは非常に限られていて、しかも何が持続可能な要素になるのか、見極めるのがすごく難しいです。ガンダムは持続できる可能性を持っているからこれだけ長く続いています。そのため、ガンダムはキャラクターデザインとして優秀なものです。
ただし、機能性(メカとしてのリアリティー)は薄くて、キャラクター性が8割ぐらいを占めているのかなと。逆にバルキリーは機能性が7割、キャラクター性が3割ぐらいだと思います。
――なるほど。
河森
コンテンツとしてはキャラクターデザインが強くなければ生き残れません。そこはすごく重要なポイントだと思います。ただ、キャラクター性が強くなればなるほど、機能性が削れて嘘くささというか、ファンタジー感が増していきます。
――偶像的、象徴的な要素が強まっていくと。
河森
そうです。日本はキャラクター大国なので、いろいろと考えさせられてしまうんですよね。キャラクターと言えば、個人的にすごく気になっていることがあって。
――ぜひお聞かせください。
河森
じつは昨年、海外の超大手映像制作会社の方から「どうすれば日本みたいに新しいキャラクターをつぎつぎと生み出し続けられるのか」と質問されました。
その会社は超大手ではあるのですが、象徴的なキャラクターが目立って活躍しており、思っていた以上にキャラクターを量産はしていなかったのです。日本にいるがゆえにキャラクターを生み出すのが当たり前になりすぎてしまい、麻痺していた部分があったのかもしれません。
その問いかけがきっかけで、キャラクターデザインというものは、デザインの中でも別のカテゴリーと思わざるをえなくなってしまいました。
佃
日本は個人が制作したものを発表できる場がかなり多い気がして、その自由さがキャラクター大国になれた理由なのかなと思いました。
河森
たしかに。超巨大マスマーケット(巨大な大衆向けの市場)にいきなり行かないで済むから、それはあるとは思います。あと、宗教による縛りも関係あるのかなと思うこともあって。
佃
たしかに。それは関係がありそうですね。
河森
たとえば、日本には太陽の塔(※)があって、55年間万博の象徴として生き続けていますよね。世界にはさまざまな英雄や女神をモチーフに表現した巨大像が数多くありますが、太陽の塔のように“存在しない何か”を描いたキャラクター像というのはほとんどありません。そこにはそれぞれの国が持つ宗教観も関係しているのかなと。
※芸術家・岡本太郎氏がデザインした高さ70メートルの塔。1970年に開催された日本万国博覧会にて公開された。――確かに、日本にも仏像はありますが、キャラクターを生み出すために生じる壁は世界の中では少ないのかもしれませんね。
河森
そういった難しさをはらんでいるので、自分が主役級のメカをデザインするときは、キャラクター性をすごく気にするようにしています。
佃
仕事をお願いすることも多い立場ですが、キャラクター性のあるメカを描いていただくことって、非常にハードルが高いと感じています。
河森
いまの人はスタイルとしてかっこいいメカは描けますが、主役や作品のタイトルを背負うとなると、それだけではきびしいですよね。
佃
社内でメカのデザインというか、アレンジをしたときに、いまどきなカッコイイものにはなるんですよ。でも特徴になる何かがなくて、汎用的な見た目の域から脱しないんですよね。
河森
Aの作品に出ているメカが、Bの作品に出ていても気付かない、そんなデザインになっていることが結構ありますよね。
――ちなみに、本作ではどのようにして特徴を持たせているのでしょうか?
佃
たとえば本作に登場する銃は、自分が「こんなのどう?」と提案したのですが、銃の上にデジタルのスコープを取り付けてみました。見た目のかっこよさもありますが、キャラクターがまとっているアーマーのスコープ機能が壊れたときに、目視で撃つためのものという設定を盛り込んで意味を持たせています。
河森
そういった、ほかと同じにならないような工夫が必要ですよ。バルキリーをデザインするときも、ガンダムのようなプロポーションにならないよう、膝より下のところをちょっと長くしたり、腕のバランスをあえて崩したりしました。
佃
『交響詩篇エウレカセブン』のLFO(※)もぜんぜん違いますよね。
※2005年に放送されたTVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』に登場する河森氏がデザインしたメカで、サーフボードに乗って移動や戦闘を行う。河森
LFOはサーフィンしたときのシルエットが様になるよう、手足を細長くして視覚機能をともなったデザインに仕上げています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a9eb9cd58b9ea5e04c890326b5c1f471f.png?x=767)
メカデザイナーとしての幅をもたせたいなら一次創作者になれ
――機能から考える発想を培うにはリアルな戦闘機や自動車を見ることが重要なのでしょうか?
河森
そこはあると思います。自分のころはリアルなメカがなかった時代なので、参考にするものは全部本物の機械でした。でも、その後の人たちはどうしても先人が作ったメカを目にしてしまってから育っているので、なかなか難しいですよね。
――先入観を持ってしまっていると。
河森
そうです。二次創作だからスタイリングを洗練化させるのは早くてうまいんですよ。でも一次創作をやろうとすると、洗練させる前にメカが動くためのロジックや、航空力学・機械工学などの基本を知らないといけないので、そこで差が生まれるのかなと。そして、それを知ったうえで、エンタメにしていくためのデザイン的な嘘をついていくと。
一次創作にするという観点で自分が心掛けているのは、実際に現実で取材することです。何かの作品ではなく、現実の取材をもとに自分で考えてデザインすることで一次創作になるので、たまたま時代の背景などが似ていたとしても、ほかを真似することにはならない。
――なるほど。創作ではなく取材をもとにデザインをすることで、一次創作として成り立つんですね。
河森
あと、SFデザインにおいて大事なことは「大きな嘘を1個だけついて、小さな嘘は極力つかない」ことです。たくさん小さな嘘をつくと、よくわからないデザインになってしまいます。
佃
じつは前作の開発でメカのモデルを量産した際、アーセナルの手の大きさが機体ごとに違っていました。すべてのメカが同じ武器を使うのに、手の形が違うのはおかしいと思って。しかもメカが武器を持った際、OSが武器を認識して連動するという設定なので、手の大きさが違うのは機能としてもおかしいんですよ。それを開発メンバーに指摘したら「作りやすくなるので助かります!」と言われたことがあって(笑)。
河森
そこじゃない(笑)。もちろん量産効果としては正しいですけどね。チーム作業が主流となり、分業化が進みすぎているのもあるかもしれないね。自分のパートのことだけを考えるようになっているから、全体を見失ってしまう。
全体を見るには、さっき言った根底にあるロジックを知らないといけません。航空力学や機械工学、流体力学といった基本のロジックは何にでも応用できるので、知ることでデザインに深みや幅が生まれるんです。
でも、分業化によって一部分だけの専門家になってしまうと、そこだけが洗練されていきます。洗練されること自体は悪くないですが、全体を知らずに洗練するのは単なる再生産になってしまうので、ほかの作品に応用しづらいです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a602e8f042f463dc47ebfdf6a94ed5a6d.png?x=767)
――現実の自動車や戦闘機を参考にした以外に、河森さんが全体を見わたせるようになった理由は何だったのでしょうか?
河森
スタジオぬえが小さな会社だったにも関わらず、最初からマルチメディアだったのが大きいと思います。あのころは企画立案、アニメと歌の制作、おもちゃの監修、マーケットへの展開……と、作品プロセス全体を見わたせる仕事ができました。いま思うと本当に恵まれた環境にいたことを思い知らされます。
なので、学生には「大きい企業に就職したあとはできなくなることが多くなるので、学生時代にいろいろなことをやっておいたほうがいい」と伝えるようにしています。個人でも集団でもいいから、企画・制作して販売、または発表するところまで、ひと通り体験しておいたほうがいいと思います。そうじゃないと全体を見る力は養えませんからね。
佃
その通りだと思います。現代ではすでに、YouTubeやSNSなどを使って、どんどんコンテンツを作っている人たちがいますよね。
河森
そうそう。その人たちは鍛えられているし、だからこそ、人気があります。作品全体を作るという意味では、マンガもそうだと思います。
――すべての工程を理解していることにより、専門的な作業のクオリティーも上がりそうです。
河森
もちろん特定の分野を突き詰めることは悪いことではありませんが、いざオリジナルのデザイン企画をやろうとしたときに、いつもとは違った視点やアプローチが必要になるので、そこで全体を見る力が必要になると思います。
佃
ものすごく画力が高い人や制作力が高い人は、昔に比べるとたくさんいるんですけど。でも企画力を持っている人というのが少なくて、そういう力を持っている人は企業に行かず、個人で活動しているイメージが強いです。つまり、いまの時代を生き抜くには企画力があるとアドバンテージになるのかも。
デザインはあらゆるものに通ずる
――お話を聞いているとデザインという存在の大切さがわかりますね。
佃
デザインとは、コンセプトに基づいてどういう完成形にしていくかというものだと思います。目指す形に対してコンセプトを決めて、そこに向かいながら形を作る仕事なので、絵以外のあらゆるものごとにもデザインの考えかたが通じると思っています。
プロデューサーの役割もいっしょで「コンセプトはこれで、チームのみんなにはこういう役割があって、最後はここに到着するよ」という一連の流れをデザインしているんです。
河森
佃さんはこういった考えかたを持っているから、話も仕事もしやすいです。自分の場合も、デザインについてはスタジオぬえに入っていろんな先輩から教えてもらったので、専門学校に行っていなくてもある程度のデザイン論はわかります。
――なるほど、デザインとは何かを描いたり、レイアウトしたりといったものとばかり思っていました。
河森
「ここを膨らませて、こっちは閉じた感じにして……」みたいに、メカのプロポーションの取りかたを考える作業と、ストーリーの起承転結を考えるのはどちらもデザインだと思っています。あと、何かを考えるときは、“本質に近い階層のところから発想してくと応用がやりやすい”と思います。そして、作品を変えるときは、世界観を変えることも重要です。
――世界観ですか。
河森
自分で何かを生み出すときには、同ジャンルのほかの作品と異なる世界観を持たせるようにしています。また、ほかの方の作品に参加するときは、最初に世界観を聞いて、その世界の中で実現可能な機能性を追求するようにしています。
佃
河森さんのデザインの話を聞いていてふと思ったことがあって。デザインがうまい人はキャラクターもメカも両方デザインできるんじゃないかなと。
河森
それはあると思います。『マクロスF』からキャラクターデザインを担当してもらっている江端里沙(※)さんは、とてもメカを描くのがうまいですよ。
※アニメ制作会社サテライト所属のクリエイター。『マクロスF』シリーズのキャラクターデザインや作画監督、『アクエリオンロゴス』の衣装原案、『重神機パンドーラ』のキャラクター原案など担当。佃
そういう方いますよね。だからキャラクターデザインができる方は、食わず嫌いせずにメカも描いてみてほしいですね。
『デモンエクスマキナ』は反復で構成されている
――『デモンエクスマキナ』シリーズのメカデザインで、河森さんがこだわったことはありますか?
河森
同じユニット(パーツ)をたくさんつける“反復”は、本シリーズの世界観に合わせた要素だと思います。
佃
メカものが好きな人って、同じユニットが何個もついていてガチャガチャしたり、それが動いたりしているのが好きなんですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a7afbb1602613ec52b265d7a54ad27330.png?x=767)
――私もそういうのが大好きです(笑)。
佃
でもふつうに考えると、自動車などにガチャガチャしたものがついていたらダメなんですよね。
河森
『マクロス』シリーズなど、航空力学が必要になる作品では決してできませんね。でも本作の世界観であればそこを考える必要がないので、いっぱいつけて“らしさ”を演出しようと思いました。ただ、いっぱいつけ過ぎると、それはそれで類似性のあるメカもありそうなので、そこと差別化するために特定のメカでのみ反復するようにしました。
あと、全身の一部分を切り取って見ただけでも、その作品であることがわかるようなデザインを心掛けました。
佃
本作では、小さいユニットをあえてハミ出させて、シルエットに特徴を持たせていますよね。
河森
そうそう。メカを塗りつぶしたときに、ひと目でその作品のメカであることがわからないといけないですからね。ちなみに『マクロス』のバルキリーの場合は、人型のバトロイド時でも飛行機に見えるユニットをちょっとずつ見せたりして、メカとしてのシルエットを際立たせました。
佃
飛行機と言えば、うちの社内のスタッフは飛行機を描くのが苦手な人が多いんですよ。自動車を描ける人は少しだけいるんですが。
河森
自動車を描けるだけでも貴重ですよ。
佃
飛行機って難しくて、「それ絶対に飛ばないでしょ!」みたいなデザインになってしまうことがあるんですよね。
――航空力学を知らないとそういったものは描けないと。
河森
やはり本物からスタートしないと理論に基づかないので、どうしてもスタイリングに偏ってしまいます。そうなると、コンセプトが変わって世界観を合わせるときに、感覚だけで対応しなければならないため、できることに限りが生まれてしまいます。
――いろいろな世界観に対応できるようにするためにも、本物を知っておいたほうがいいのですね。
河森
そうですね。ただ、先ほどもお伝えしたように、本物を知りながらも、キャラクターデザインとしては嘘も必要です。飛行機はガチガチに空力に縛られてしまうので、それを考慮しつつ変わったことをやるのがとても難しい。そこで、バルキリーでは真正面から見たときの厚みを倍近くにして、本来の飛行機にはない嘘を持たせています。
そうじゃないと、変形したときに細くなりすぎてしまいまうんです。機能としては悪くないですが、ヒーローメカの魅力が薄れてしまいます。ヒーロー性を高めるためにも、上と下から見たときにどちらにも出っ張るようなデザインにしました。
佃
初耳です。へー、そうなんですね。
河森
そうです。そこをバルキリーは両方に出っ張らせて、しかも翼でそれを隠してほぼ見えないようにしています。真正面から見ると厚みがあって嘘であることがバレますが、アニメでは斜めから見せたりすることでそれをわかりづらくしたりもしています。
――なるほど。いろいろな世界観に対応させられるように、というお話でしたがメカデザインの中で難しい世界観ってあるのですか?
佃
魔法がある世界でのメカものは難しいですよね。
河森
そもそも、メカがなくても魔法で何でもできちゃいますからね(笑)。
――そういうときはどうすればいいのでしょうか?
河森
何でもできてしまう場合は、世界観と何かしらの関係を持った縛りを入れるのがいいと思います。そして、その縛りに対してどのようにアプローチしていくかが、デザインを生み出す突破口になります。
――なるほど。ちなみに縛りといえば、本作では前作時よりハードのマシンスペックが上がったことで、データ容量や描画可能範囲などの縛りが緩くなりましたよね?
佃
そうですね。本作は自由に飛行しながら、広大なオープンワールドを探索できるため、本当にどこにでも行けちゃうんですよ。思いもよらぬところまで探索できる楽しさを体感できるのも本作の醍醐味だと思います。広大なフィールドには隠し要素が隠されていて、中には“絶対に”気付かれないようなものもあります。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
――絶対に?
佃
絶対かな?(笑)。その隠し要素を見つける方法は“■■■■のやりかた”※です。
※ネタバレを避けるために文字数(■の数)も濁しています。河森
なるほどねぇ(笑)。
――たしかにそれならバレないかも……。なぜ“■■■■のやりかた”を採用したのでしょうか?
佃
最近SNSや攻略サイトなどで、ゲームの謎解きや隠し要素の答えが簡単にわかってしまいますよね。そういう時代に、絶対に見つからないような要素があればおもしろいかなと思って(笑)。
河森
すべてが解明されること自体がおかしいと思っているので、その試みはとてもいいと思います。
ゲームメカのデザインは背中を重視している
――本作で河森さんがデザインされたものを改めて教えていただけますでしょうか?
河森
アーセナル3機、ヘビーアーマー1機、バイク1台です。とくにバイクは、いままでにない変形にしないといけなかったのでたいへんでしたね。
佃
河森さんには「バイクは変形して武器にしてください」というオーダーしか出していなかったので、ほぼおまかせ状態でした。
河森
変形するバイクというのは何度かやったことありましたが、それと同じ変形だけは絶対にやりたくなかったので、いろいろと試行錯誤しました。おかげでほかとは一風変わった変形機構にできたと思います。
佃
ヘビーアーマーが戦闘機に変形するのも見どころのひとつです。変形の第一人者である河森さんの特徴を盛り込むことで、ほかのゲームにはない魅力と深みを持たせています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a59b2900aa03cb2182a51cdb520b535b6.png?x=767)
――そもそもなぜバイクを盛り込んだのでしょうか?
佃
エネルギーを消費せずに移動できるという建前はあるんですが、真の狙いは本作に興味を持ってくださる人への入り口を広げるためです。移動手段としてバイクを用意することで、そこからバイクが好きの方へメカものに興味を持ってもらうきっかけを作っています。
また、今回は依頼していないのですが、これまでまだ河森さんに自動車のデザインをお願いしたことがないので、機会があればお願いしたいですね。
河森
いいですね。自動車やりたい!(笑)。
――次回作では河森さんが手掛けた自動車があるかもしれないですね! ちなみに、メカが活躍する世界観の中で、バイクや自動車などを登場させる理由はあるのでしょうか?
佃
我々の世界にちゃんと現存するものが登場することで、世界観の土台がしっかりしてユーザーさんにも納得してもらえるんですよね。あとキャラクターにも深みが生まれます。たとえば、ある傭兵のおじさんには、稼いだ報酬をすべて自慢のアメ車に突っ込んでいて、それが唯一の生きがいみたいな設定があるとします。
河森
旧車はお金がかかるからね(笑)。
佃
そういうのが、あるからこそリアルっぽさが生まれて、キャラクター性や魅力が膨らんでいくと思っています。
――ここまでお話を聞いていて、メカへの知識や愛の有無で作れるものが大きく変わるのだなと痛感させられました。アーセナルがフェムト飛行するときに、機体が振動で揺られるところも印象的で、そこもメカ好きゆえのこだわりなのでしょうか?
佃
物体が何も震動せずにまっすぐ飛ぶことはないですし、そもそもアーセナルをまとっている人はバランスを取りながら飛んでいるので、あんな感じで振動が生まれるというのもあります。
また、アーセナルが飛ぶときに、ブースターのところに小さくて細かい塵が散らばるような演出を盛り込んでいるのもこだわりのポイントです。これは『王立宇宙軍 オネアミスの翼』(※)という作品でロケットを飛ばすときに、液体燃料がバリンと割れて散る描写から着想を得て作りました。
※1987年に公開された、GAINAX制作のアニメ映画。河森
実際のロケットでも、ボディに付着して凍った液体燃料がバラバラと崩れるんですよね。
――アニメから着想を得つつも、現象としては現実にあるものなのですね。開発メンバーの反応はいかがでしたか?
佃
実装したら、アートディレクターとエフェクターが「すごく綺麗になりましたね」とうれしそうに言っていて、印象深かったです。
――河森さんはデザインの段階から、こういったことを想定していたのでしょうか?
河森
そうですね。もともとフェムト粒子の設定を聞いたときから、背中のユニットを剥き出しにして、そういった要素に対応できるようなデザインにしていました。
佃
河森さんに描いていただいたデザインをフルに活かすことができてホントによかったです。ユーザーさんはすぐに伝わらないんですけど(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a9eb60bc8bf2b004e4db7d1cc0d5f1d8c.png?x=767)
――SNSや動画配信サイトのコメントを見てみると、意外と気付いている人もいるみたいですよ。
佃
わかってもらえるとホントにうれしいです。
――個人的に、変形したヘビーアーマーが4枚羽なのも気になりました。どういった理由なのでしょうか?
河森
そこはバルキリーと似ないようにするためです。もちろん飛行機なので、まったく違うものにすることはできませんが、世界観に合わせたデザインにできたと思います。
――先ほどの話にもありましたが、機能的に飛ばないといけないようにデザインするとなると飛行機は難しそうですよね。
河森
どのようにして嘘をつくかがだいじです。たとえば『クラッシャージョウ』(※)に登場する戦闘機のファイター1は、本物の航空機とは異なる重心位置にして嘘をついています。本来、ファイター1の羽の位置だと重心位置が合わないのですが、そこをリフティングボディの揚力を使って補い、ギリギリその位置に羽があっても大丈夫という嘘を成立させています。そうしないと、プロポーションが本物の飛行機に近くなりすぎて、SFメカっぽくならないんですよ。
※SF作家・高千穂遙氏が手掛けた小説。1983年に劇場用アニメが制作され、河森氏が本作に登場する戦闘機のファイター1などのメカデザインを担当した。佃
帰ったらもう一度見てみよう(笑)。河森さんが『クラッシャージョウ』のデザインを手掛けていた時期は、『マクロス』と同時期なんですか?
河森
そうですね。大学に行きながら『マクロス』、『クラッシャージョウ』、『ダイアクロン』(※)に、タツノコプロさんの作品に登場するゲストメカなどをほぼ同時進行で仕上げていました。
※スタジオぬえが手掛けた自動車がロボットに変更する玩具シリーズで、後の『トランスフォーマー』。河森氏はメカデザインとして制作に参加した。――帰ったらご覧になるとのことですが、佃さんはロボットアニメのDVDをどれくらいお持ちなのでしょうか?
佃
ロボットもの、メカものは大好きなのでひと通り揃っています。『ガンヘッド』(※)のDVDなんかは販売数が少なかったせいか、すぐにプレミアがついて、再販されるまでちょっと誇らしい気持ちになりました(笑)。
※1989年7月22日に公開された日本の特撮映画。河森氏がメカデザインを担当。河森
極力変えてはいるつもりですが、ガンヘッドはその後のゲームメカにおける自分の中での基礎のひとつになっていますね。
――ゲームならではのメカデザインへのこだわりというのもあるのでしょうか?
河森
プレイヤーがつねに見る背中の部分が主役になるようにデザインしています。これは『アーマード・コア』などで初めてゲームメカのデザインをすることになったときから、ずっと欠かさないようにしていることです。
佃
本シリーズでは背中の光を目立つようにしていて、そこだけ見ても『デモンエクスマキナ』のメカであることがわかるようなデザインにしていただきました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/ac00b57557743e709b8b96933432e0dfa.png?x=767)
ものごとをベクトルで考えることで、多様性が生まれる
――デザインにおいて、さまざまな文化や背景、人々の視点などの多様性を取り入れる際に、河森さんが重視している考え方を教えてください。
河森
大阪・関西万博で披露した“いのちめぐる冒険”は自然と科学(テクノロジー)は、いままで引き算して戦うという構造でしたが、それをどうやったら掛け算にできるかを模索している最中なんです。
――では、河森さんはどのようにして、掛け算を成立させようとしているのでしょうか?
河森
僕はベクトルで物を考えるようにしています。たとえば、自然と科学のどちらを取るか考えたときに、いままでは同じ平面上でどちらの量を優先するのか。ぶつかり合ったり(足し算)、足を引っ張り合ったり(引き算)していました。しかし、それぞれのベクトルが異なるものであることがわかったとき、それを組み合わせると掛け算になることが理解できました。
掛け算で考えられるようになることで、自然と科学が立体になって、初めて多様性を語れるようになるわけです。
――それまでは多様性を語ることができなかったということでしょうか?
河森
本質的にはまったく語ることができませんでした。そもそも科学は、誰がどこでやっても同じ結果が出るため、そこに多様性はないと考えています。そんな旧式の科学のことだけを用いて多様性を語ろうとしていたので、うまく行かずに生態系がボロボロになっているのではないのか、というのが万博を通して言語化できるようになったことです。
――なかなかに奥が深いです。
河森
たとえば、科学と感情の話をします。自動車を量産化したとき。誰が何をやっても結果が変わらない科学という枠の中では、それらはすべて「自動車である」という認識のみです。これでは平面です。
しかしそこに人間の感情論や感受性がともなうと、人ごとに「カッコイイ」、「カッコ悪い」、「欲しい」、「無駄なもの」という認識が生じます。これが多様性です。感情論や感受性といった評価軸は科学とは異なる次元にあって、それを使えるようになることで、立体的になって価値が生まれるんですよね。
佃
河森さんはすごく明晰な方なので、うまく言語化していてすごいですよね。
河森
ここにいたるまでに相当時間がかかりました。万博では言語化できないでいると、下手にツッコまれてたいへんですからね(笑)。
一同 (笑)。
河森
いま思い返すとアニメ『創世のアクエリオン』を作っていたときは、それを言語化できていなかったんですよ。第1話の中で「3つの矢が合わされば、折れない矢になる。しかし、予期せぬ強い力を受ければ折れる」みたいなセリフを入れていて、そうならないためのものが、ベクトルが立体になったときに生まれる掛け算という発想なんです。
だから、アクエリオンが分離した状態のマシンのことをベクター(ベクトル)マシンと呼ぶわけです。
――言語化できていなくても、その考えは当時から持っていたと。
河森
そうですね。あと作ってから気付きましたが、『マクロス』も同じ考えかたなんですよ。武力とは異なる次元にある歌というベクトルを使うことで争いを解決することができます。ただし、弱点があって、違う次元(歌)に興味がない人には響かないんですよ(笑)。
佃
じつは現実で何か争いが起きたときに、オタク文化や趣味などを使って相手に訴えかければ、争いを避けられるのでは? と本気で考えたことがありました。でもたしかに興味がない人に効かないのは致命的ですよね。
河森
でもそういうことにも向き合っていかないと、今後やってくる多様性の時代には対応できなくなるのかなと。
ベクトルを合成することのすごさ
――河森さんがものごとをベクトルで考える際、参考にしたことはあるのでしょうか?
河森
人間の能力や感覚が大事になる時代が来ると思っていて、それを調べるために、武術の達人に技を掛けてもらいに行ったことがあります。
――武術の達人ですか。
河森
はい。武術の達人というのは、必ずベクトル合成を使っています。一直線だけの力比べでは、力の強い人に決して勝てませんが、ベクトル合成を使えれば、力が弱くても対応することができます。
しかし、中国には力のベクトル合成を使っても通用しない達人がいて、その人は力のベクトルだけではなく、意識をも合成していて、ふつうとはまったく異なる次元の合成を行うんです。そのときに初めて「これで立体になるのか」と気づかされました。
佃
そういった昔からある中国拳法は学問に近いですよね。格闘技は自分もボクシングはよく見ていました。立体という視点は持っていなかったです。
河森
科学といっしょでルールという枠組みがありますからね。いろんな達人に取材したときに聞いたのがまさにそれでした。異種格闘技は相手との競争ではなく、ルールとの競争であり、ルールをどれだけ研究できるかで対応能力が決まると言っていたのが印象的です。
佃
ルールという枠組みがある以上、下の階級の人はヘビー級にはまず勝てませんし。
――私はボクシングをやっていない肥満体型なのですが、チャンスはあるのでしょうか?
佃
たとえ肥満だったとしても、その体重を支えるだけの筋力と自重を持っているので、一撃がメチャクチャ痛いと思います。そういったヘビー級の人の中でも、群を抜いてすごかったのが、マイク・タイソンです。全盛期の彼は速さが桁違いでした。
河森
タイソンが町なかにいる鳩を捕まえる映像は衝撃的でした。鳩が間合いを取る前にバッと捕まえていて、あまりのすごさに笑ってしまいました。
佃
ヘビー級のパワーとそれだけの速度を持っていたら、そりゃ誰も勝てませんよね(笑)。
――速度は正義と(笑)。
佃
でもその物理法則をゲームに持ち込むと破綻しちゃうんですよね。軽量級(軽装)は速度が速いので、敵との間合いが簡単に詰められるうえに、早ければ早いほどぶつかったときの衝撃力が上がって、重量級を上回る大ダメージを与えられてしまいます。
――たしかにそれだと軽量一択になりますよね。
河森
“力=速度の2乗”なので、速度が倍になれば4倍の破壊力が生まれますが、アニメやゲームではほぼ忘れられている要素ですよね。あと、物体に働く重力が体積に比例していて、寸法の3乗になる“2乗3乗の法則”なんかもあります。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a7b6fbd4c592d356e087a0f1053751007.png?x=767)
――重量が1000倍になって、巨大ロボットが地面に沈んでしまうというやつですよね。
河森
世界観のひとつとしてそれをなしにするというのが、エンタメのおもしろいところだったりします。
――たしかに。リアルにし過ぎると巨大ロボのロマンが失われますよね。
河森
『創世のアクエリオン』のときは、神話というファンタジー性の強い概念を持ち込むことで、アクエリオンの巨人性(ロマン)を許せるようにしました。そうじゃないと存在意義がなくなりますからね。
――イチ視聴者としてはどんどん巨大ロボットでロマンを追い求めてもらいたいところですが、作り手側はそういうわけにはいかないと。
佃
追い求め過ぎてロマンと作品性がごちゃ混ぜになると問題があるので、そこは切り分けて考えることが大事だと思っています。
――では最後に、本作の発売を待ち望んでいるユーザーの皆さんに、メッセージをお願いします。
佃
本作はメカものであり、オンラインを介して皆でつながって楽しめるタイトルになっています。いろいろな人とつながることで、遊ぶ楽しさやプレイの思い出も増えていくと思います。
前作のユーザーさんも、初めてシリーズに触れるユーザーさんも、本作を手に取って新しくなった『デモンエクスマキナ タイタニックサイオン』の魅力を体験していただければ幸いです。
河森
佃さんから本作の方針を聞いたときに、「思い切った決断をしたな」と驚かされるぐらい大胆な進化を遂げています。マニアックなたとえになりますが、プロペラつきのエンジンを搭載した飛行機が、ジェットエンジンを搭載した飛行機に進化するぐらいの飛躍をしています。
前作と同じ世界観で2作目にも関わらず、ここまで大きく発展している作品というのはそこまで多くないと思います。すごく大胆な試みで、メカをデザインする側としても魅力的なチャレンジをすることができて、すごくおもしろかったです。ぜひ本作で前作から大きく変わった部分と、前作から変わらぬ部分がもたらす相互作用のようなものを感じてもらえるとうれしいです。
―――
なお、週刊ファミ通2025年9月18日号(9月4日発売 No.1913)では、本作の発売記念特集を掲載。そちらもあわせてぜひご覧ください。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/ad642f8c3d2d6c1ab174d170d2dc8ed78.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a2b1fd4e84ea78dc88d2df2aba276e738.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/add6672efec19be7d767c93094d2029a5.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a032b2cc936860b03048302d991c3498f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a18e2999891374a475d0687ca9f989d83.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a9eb9cd58b9ea5e04c890326b5c1f471f.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a602e8f042f463dc47ebfdf6a94ed5a6d.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a7afbb1602613ec52b265d7a54ad27330.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a59b2900aa03cb2182a51cdb520b535b6.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a9eb60bc8bf2b004e4db7d1cc0d5f1d8c.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/ac00b57557743e709b8b96933432e0dfa.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a7b6fbd4c592d356e087a0f1053751007.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/ad642f8c3d2d6c1ab174d170d2dc8ed78.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/50032/a2b1fd4e84ea78dc88d2df2aba276e738.jpg?x=767)





![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)