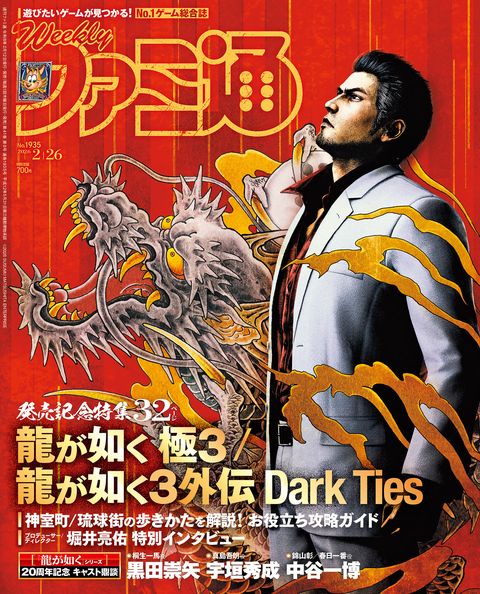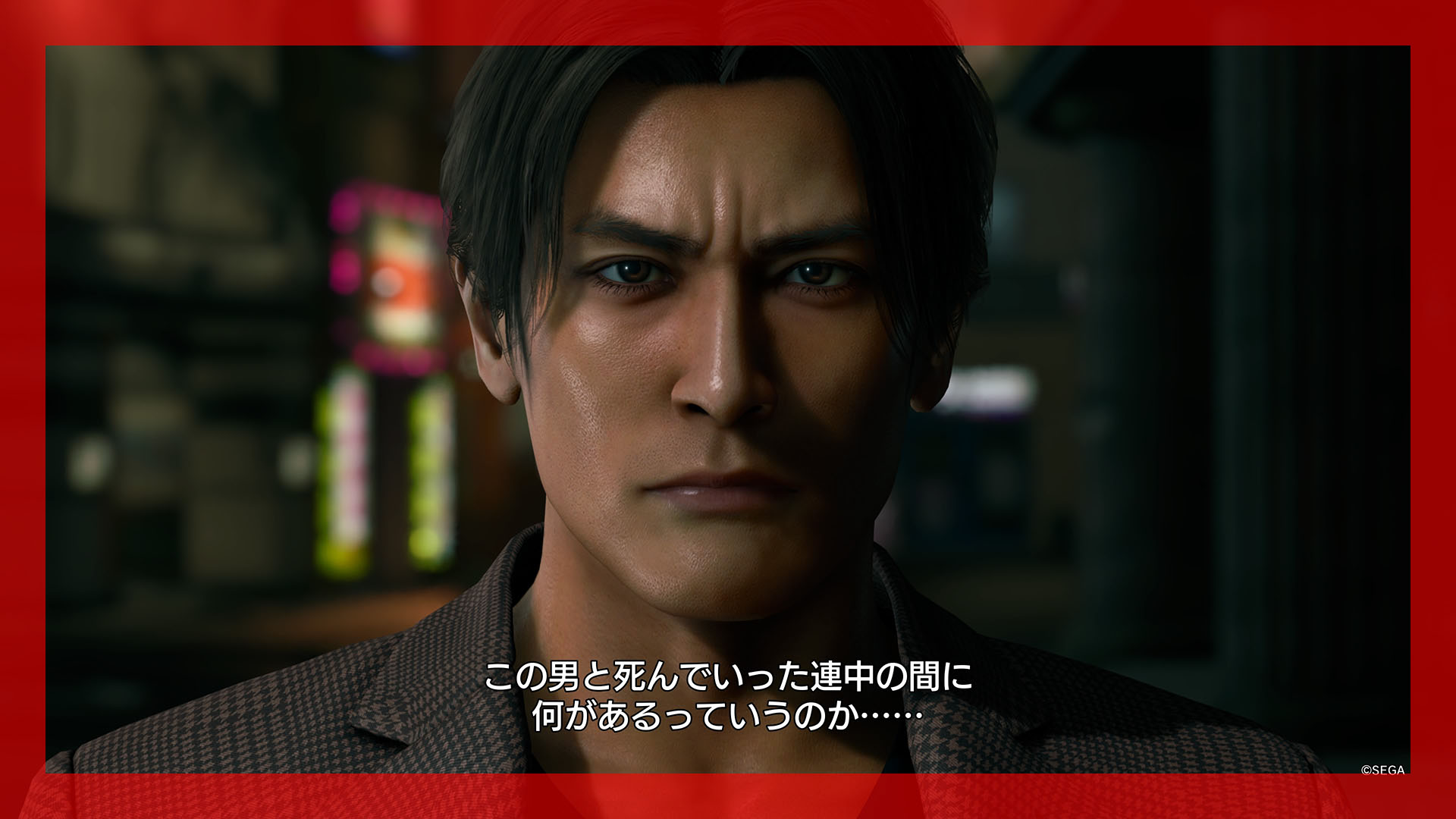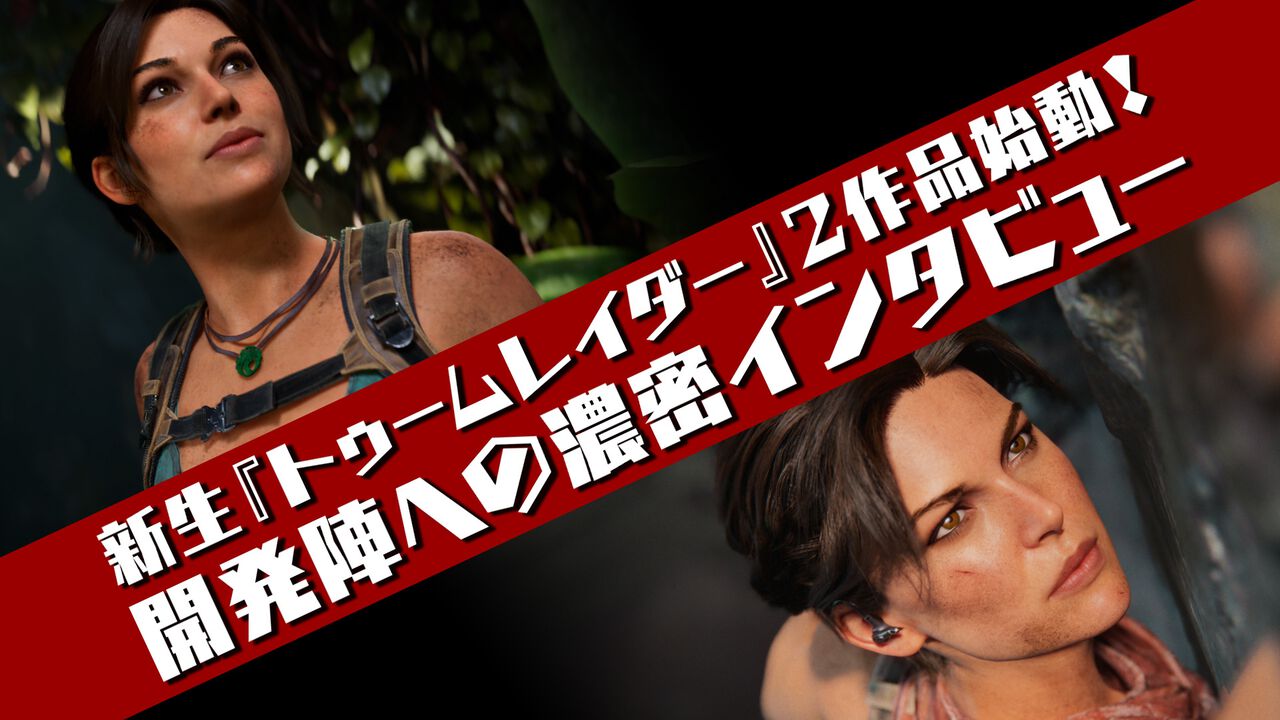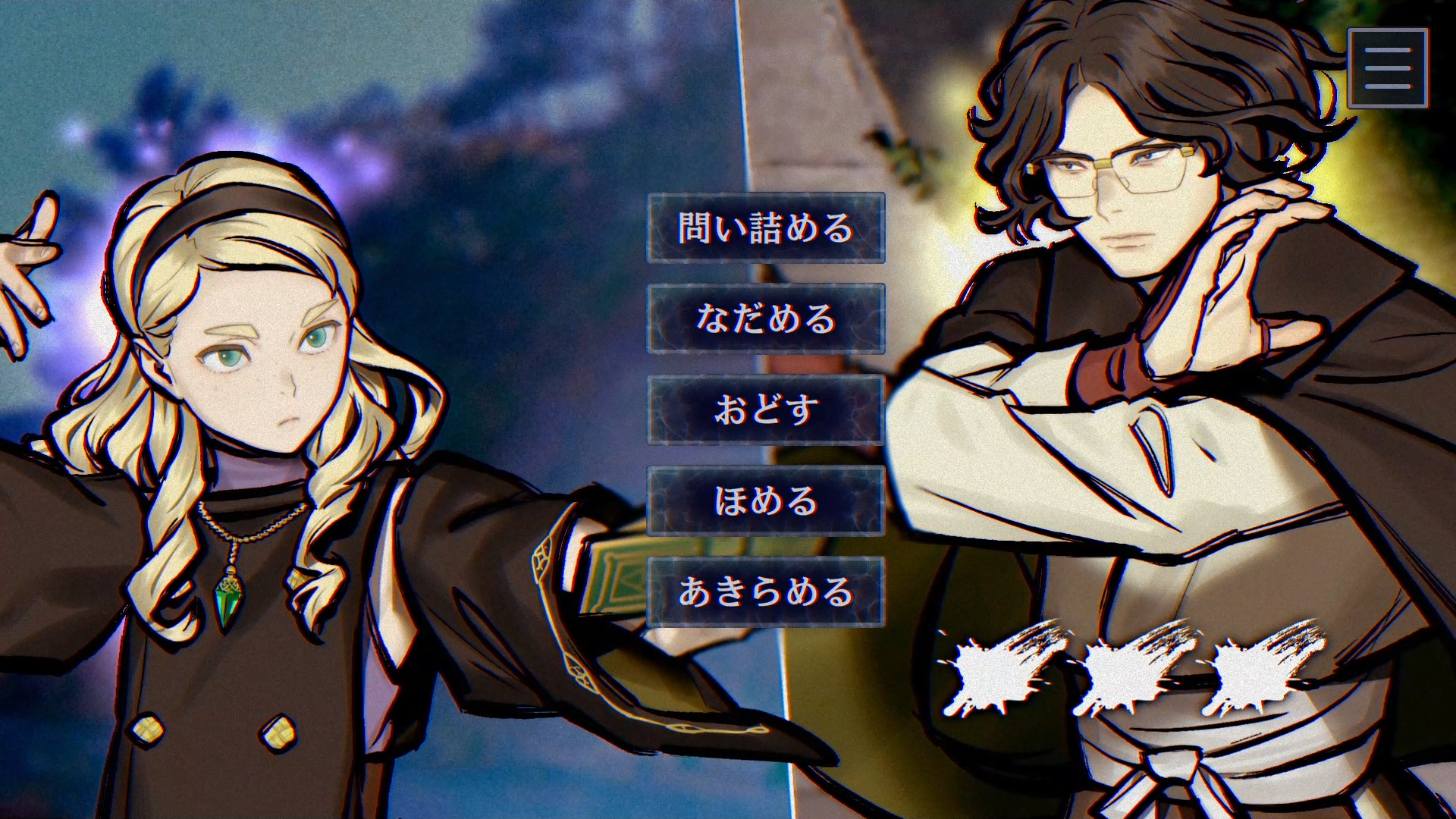![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a9bd994b1cb06e33e169c75c9b0156af8.jpg?x=767)
アクションRPG『エルデンリング』のスピンオフタイトルである本作だが、実際にプレイしてみると『エルデンリング』とはかなり異なるプレイフィールと、『エルデンリング』を初めてプレイしたときのような新鮮かつ、なつかしい感動が両立していた。
今回は、新たな冒険の地となる“リムベルド”を約4時間実際に駆け抜けてみたうえでの、ゲーム全体のフィーリングやシステム面の特徴などをお伝えしていく。別の記事ではキャラクターの手触りや戦闘に焦点を当てているので、合わせてご確認を。
また、できるだけ配慮しているが、ネタバレが気になる方はご注意を。
新たな脅威“夜の王”に3人で立ち向かう
この新たな地には、“夜の王”と呼ばれる謎めいた脅威が迫りつつある。プレイヤーは拠点となる“円卓”で最大3人のパーティーを自動マッチングで組み、4名から使用キャラクターを選択(製品版では8名)してリムベルドへと向かう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a20fd2a2d46e84a22807a8eb8f9d8602d.png?x=767)
追跡者
- 【スキル】クローショット……敵や障害物に“クロー”を撃ち込み、相手を引き寄せたり自身が飛んでいったりすることが可能。
- 【アーツ】襲撃の楔……爆発する強力な杭を撃ち込む。
守護者
- 【スキル】つむじ風……渦巻く風を放ち、舞い上げた敵を1ヵ所に集める。
- 【アーツ】救世の翼……空中へと跳躍し、敵の上空から急降下攻撃する。
レディ
- 【スキル】リステージ……周辺の敵に対し、自分あるいは味方が直近に与えたダメージを再度与える。
- 【アーツ】フィナーレ……周囲の味方とともに一定時間、透明化。透明状態でも攻撃可能。
隠者
- 【スキル】混成魔法……吸収した属性痕を3つ組み合わせて、強力な魔術を放つ。
- 【アーツ】血魂の唄……周囲の敵に“血の烙印”を付与。対象の敵へのダメージが増加すると同時に、対象を攻撃したプレイヤーのHPとFPが回復する。
マッチング成立後に使用キャラクターを選ぶことになる。なお、他プレイヤーと同じキャラクターを選択できる。全員がキャラクターを選択したら、円卓から“霊鷹”につかまって飛翔し、リムベルドへと降下していく。
ここからは3日間を生き残って最終目標を倒すか、夜のボス戦中に3人が同時に瀕死状態になったところで冒険は終了。冒険終了後は報酬を獲得し、円卓へと帰還する。出撃のたびにキャラクターのレベルは1に、装備は初期装備に戻る。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/aff42439193579995d18a4471b38d1b8f.png?x=767)
本作のルーティンは、この初動にほぼすべて集約している。探索で見つけた敵を倒し、装備やアイテムを集め、ルーンでレベルを上げていく。基本的にはこのくり返しで、プレイは非常にわかりやすい。とくに祝福のメニューはわかりやすく、レベルアップ以外のメニューが表示されないので、決定ボタンを連打すればレベルアップが済む。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a3420632a312a2fc6a1f85800d2b21aa9.png?x=767)
操作でひとつ大きく異なるのは、PS5のDualSenseでの操作となるが、十字キー下で使用アイテムを選択し、十字キー上で使用するという点。□ボタンは回復用の“聖杯瓶”を使用する専用ボタンになっており、『エルデンリング』のように聖杯瓶がアイテム一覧に含まれてはいない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a8285b50d371973d4b6b8d3640ad95273.png?x=767)
装備については、高レアリティ―のものにはレベル制限こそあれど、基本的には必要能力値などはなく、何でも装備可能だ。ただ、筋力や技量、知力といった能力値に対する適正は健在のようで、あまりダメージが伸びないパターンもあった。
それなら適性がない装備はすべて不要になるかといえば、そんなことはない。装備には“付帯効果”というランダムで備わっている能力があり、装備欄にその装備が入っていれば、未使用状態でも効果を発揮する。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a3e917f3fba7e2fe8dbf6dd0dd745fd4a.png?x=767)
また、装備には“戦技”や“魔術”、“祈祷”といった技もランダムで付与されており、『エルデンリング』のようにこれらを付け換えることはできない。魔術や祈祷も装備に付随しているので、使える魔術や祈祷は装備に依存することになる。
また、運がよければ“獅子斬り”や“王騎士の決意”といった『エルデンリング』でおなじみの強力な戦技を序盤から使えるが、本作にはFPを回復する聖杯瓶がなく、FPの回復手段がかなり貴重なので、戦技の使いどころが重要に感じた。
時間とともに迫る“夜の雨”、冒険は迅速に
だが、リムベルドはそこまで甘い場所ではない。装備集めに走っていた最初のプレイでは、ふと振り返ってみると地面に青白い光、周囲に触るとダメージを受ける“霊炎”のようなものが広がっており、それが少しずつこちらに近づいてきていた。本作では時間経過とともに、危険な夜の領域が全体マップの外周から徐々に迫ってくるのだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/aa636e3159be8d76e4cb0bcf8a2fc5e36.png?x=767)
基本として、本作は以下のような流れで進行する。
1日目の昼は探索を雨に追われつつ進め、最後の収束エリアで1日目の夜を迎えたところで、ボス敵と対決する。これに勝利すると2日目の昼が始まり、夜の領域は初期化。またマップ外周から夜の雨が迫ってくるので、2日目の昼の探索を終えつつ収束エリアで夜を迎え、ふたたび新たなボス敵と対決。これに勝利できたら3日目となり、円卓で選択した最終目標との対決を迎える。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/ad86efeed7ba5c3d33ae9b8596a1d35b9.png?x=767)
移動に関しては全般的にスムーズで、L3ボタン(左スティック)を押し込むことで発動する“疾走”で、『エルデンリング』で“霊馬トレント”に騎乗していたときとほぼ同じ速度で移動できるのに加え、キャラクターの身長の2倍程度の高さなら壁を蹴ってよじ登ることができ、落下ダメージもいっさいない。
だが夜の雨に追われていると、探索の余裕が時間的にも精神的にもなくなっていき、実際よりもはるかに広く感じるだろう。とくにマップ中央にはリムグレイブにおける“曇り川”のような渓谷が縦に走っており、崖下から崖上へ向かうルートは壁のジャンプで登れる数ヵ所や、大きくジャンプできる“霊脈”があるポイントに限られている。
崖下に間違って落ちたときには、タイムロスに震えたものだ。こうなると、自然と探索も素早く行なう必要が出てくるので、体感としてゲームテンポはかなり速くなる印象だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a558aa028b33158e2b3102fd06f825e36.png?x=767)
霊鷹につかまって高速飛行できるポイントも数ヵ所あるのだが、霊鷹は一定方向にのみ飛行するので、思わぬ方向に飛んで眼下に新たな廃墟などを見つけることも。
装備だけでなく、こうしたダンジョンをふと発見するといった探索の喜びも、『エルデンリング』を初プレイしたときの感覚そのままだ。冒険の喜びを毎プレイ時に味わえつつも、スピーディーなゲーム展開を体験できるわけで、プレイに慣れるまではふたつの感覚が一挙に押し寄せ、脳が許容量を超えそうになった。
夜のボス戦でまた“アイツ”が壁になる
今回の試遊会では『エルデンリング』に登場した“獅子の混種”や“ザミェルの古英雄”、“血の貴族”のような強敵と遭遇。これらの強敵は決まった形状の廃墟などに待ち構えているので、その場所を遠くから見つけたらとりあえず目指すというプレイも可能に。聖杯瓶の使用回数を増やせる“教会”なども、見かけたら向かうべき場所となっていた。
そして、昼の探索を終えて迎える夜のボス戦が、本作最大の難所だった。昼のあいだは死亡してもレベルが1下がって近くの復活地点でリスポーンできる(それまでに獲得したルーンは死亡地点で落とすので回収は可能)のだが、夜のボス戦ではそうはいかない。
倒れてから死亡するまでに味方に攻撃してもらうことでその場で復活できるのだが、倒れるたびに復活に必要な打数が多くなっていくため、蘇生が困難になる。そもそも蘇生してもらっても、聖杯瓶の使用回数は回復しない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/ae84a35b8fac5d413cb460e5635dbdede.png?x=767)
1日目における昼夜の攻略は、わりと早く安定。2日目の昼の探索は、1日目の探索で成長しているぶん、さらにスムーズだった。1日目は怖くてスルーしていた湖にいるドラゴンも、余裕で倒せるように。1日目は通り過ぎた場所にダンジョンがあったり、敵から集めたルーンで買い物ができる商人NPCが意外な場所にいたりと、さらなる発見も楽しめた。
この調子なら2日目のボスも余裕だろうと思っていた筆者だったが、出現したボスの名前と姿に、一気に血の気が引いた。
“忌み鬼”である。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/ad78b0b6da44bc90a6aa45031f4805e81.png?x=767)
とくに短剣をまとめて投げるモーションは、てっきり『エルデンリング』のように終わるとばかり思って回避してみたら、さらなる連投に次ぐ連投。『エルデンリング』の記憶や攻略法が染みついている人ほど、この“忌み鬼”とは、記憶をゼロにして最初から向き合うべきだろう。昼の探索でルーンを集め、レベリングすることの重要さも、ここで改めて知ることになるかと思う。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a527a050fa1e522ea9b249ef0a1be5869.png?x=767)
ちなみに今回の試遊会には3組9名ほどのプレイヤーがいたが、2日目を突破し、3日目の大ボス“三つ首の獣”こと“夜の獣、グラディウス”に挑めたのはひと組のみで、それも終了時間ギリギリの、最後の1プレイのみだった。4時間の試遊でこうなのだから、本作の骨太っぷりは推して知るべしだ。
発見の喜びと感動を、ハイスピードかつ無限に
プレイ時間に関しては、上述の通り筆者は3日目までたどり着けなかったので、1プレイの最長は約36分だった。1日の昼夜が約15分、この短時間で『エルデンリング』のレガシーダンジョンをまるまるひとつ攻略したかのような新鮮さと濃密さを楽しめるというのは、とんでもない話だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a2c5370dbecf9de3ec261ffd12b8f7e2e.png?x=767)
本作ではプレイするたびにキャラクターのレベルや装備が初期化されるのだが、遺物をキャラクターごとのスロットにセットすることで、“技量+1”といった基礎能力の上昇だけでなく、“出血の状態異常効果を付加”や“刺突カウンター成功時にHP回復”など、特殊な能力を永続的に付与できるようになる。
なお、遺物と各キャラクターの遺物装備スロットには色のカテゴリーが設定されており、各装備スロットにはスロットと同じ色の遺物しか装備できない。たとえば、攻撃的な能力が多い赤の遺物は、追跡者や守護者といった前衛キャラクターが装備可能だ。3日目までクリアーできずにゲームオーバーになっても、到達度に応じたレア度の遺物が獲得できるので、キャラクターをつぎの挑戦に備えて強化していける。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33338/a207362d845929a24b6850cde8dec320e.png?x=767)
15分、30分単位の時間で、RPGの新鮮な感動がくり返し味わえる。4時間という限られた時間でもここまで楽しめたのだから、製品版ではどれだけのものになるのかと、期待は高まるばかりだ。
新たな冒険の地・リムベルドで、まだ見ぬプレイヤーたちといっしょに何度も何度も、無限に冒険の喜びが味わえる日を願ってやまない。