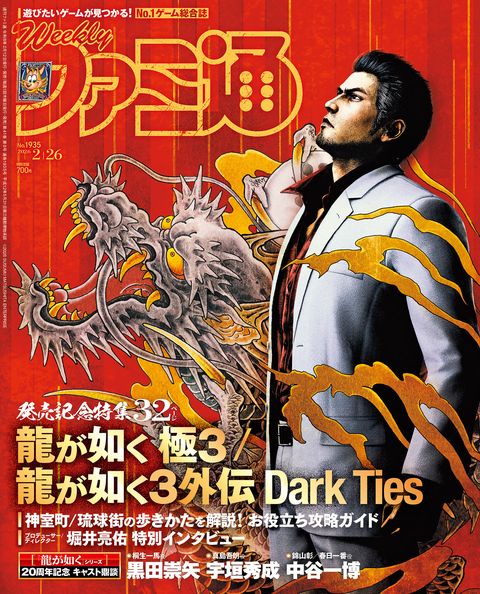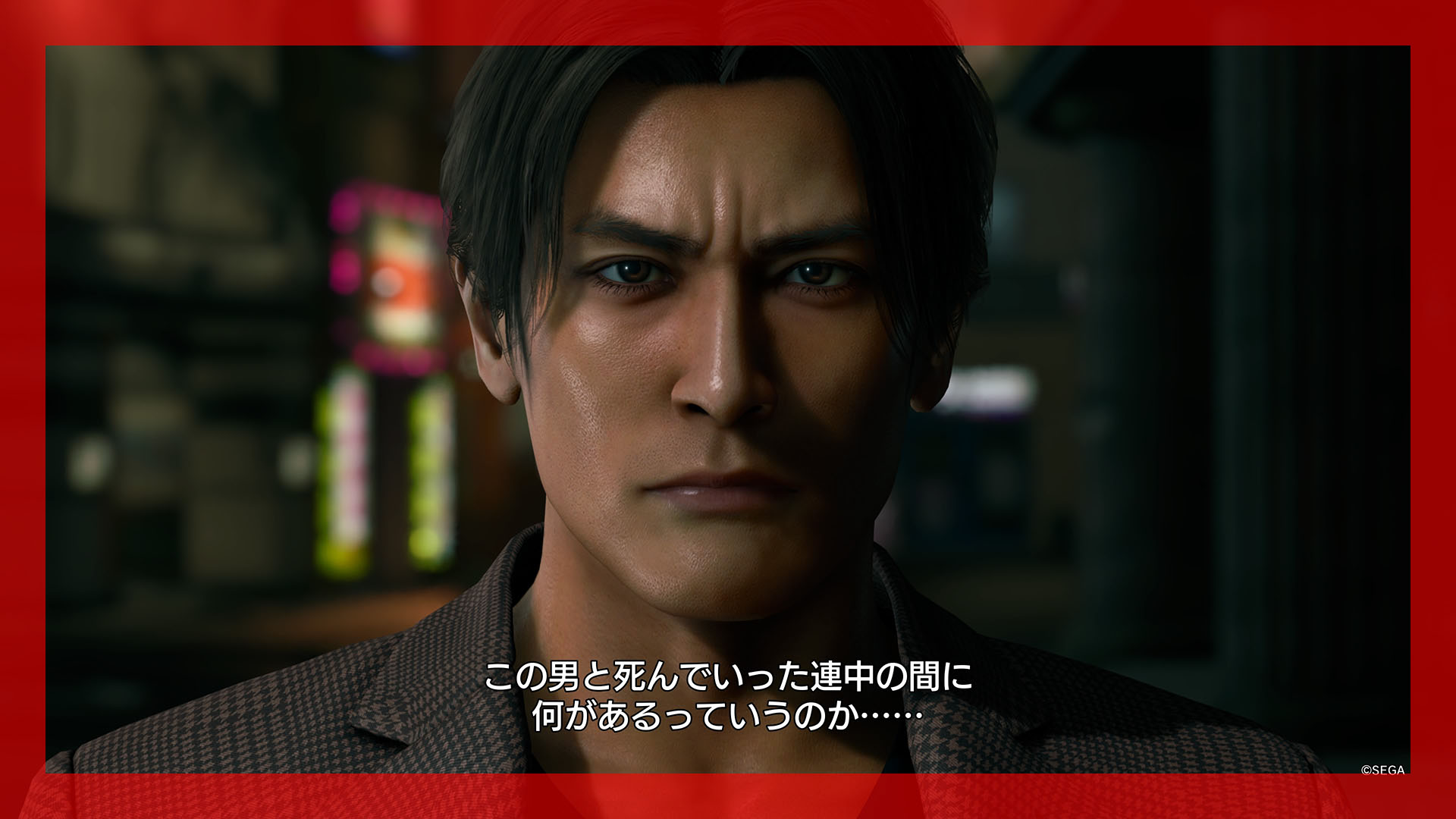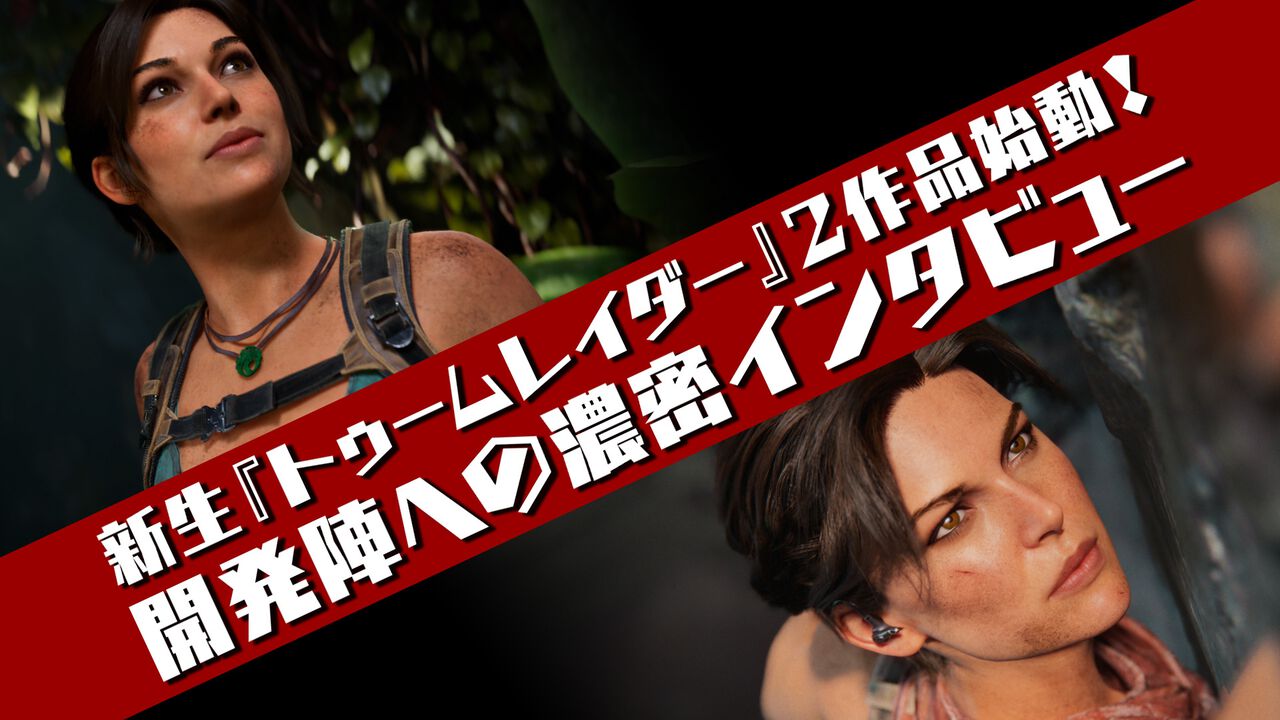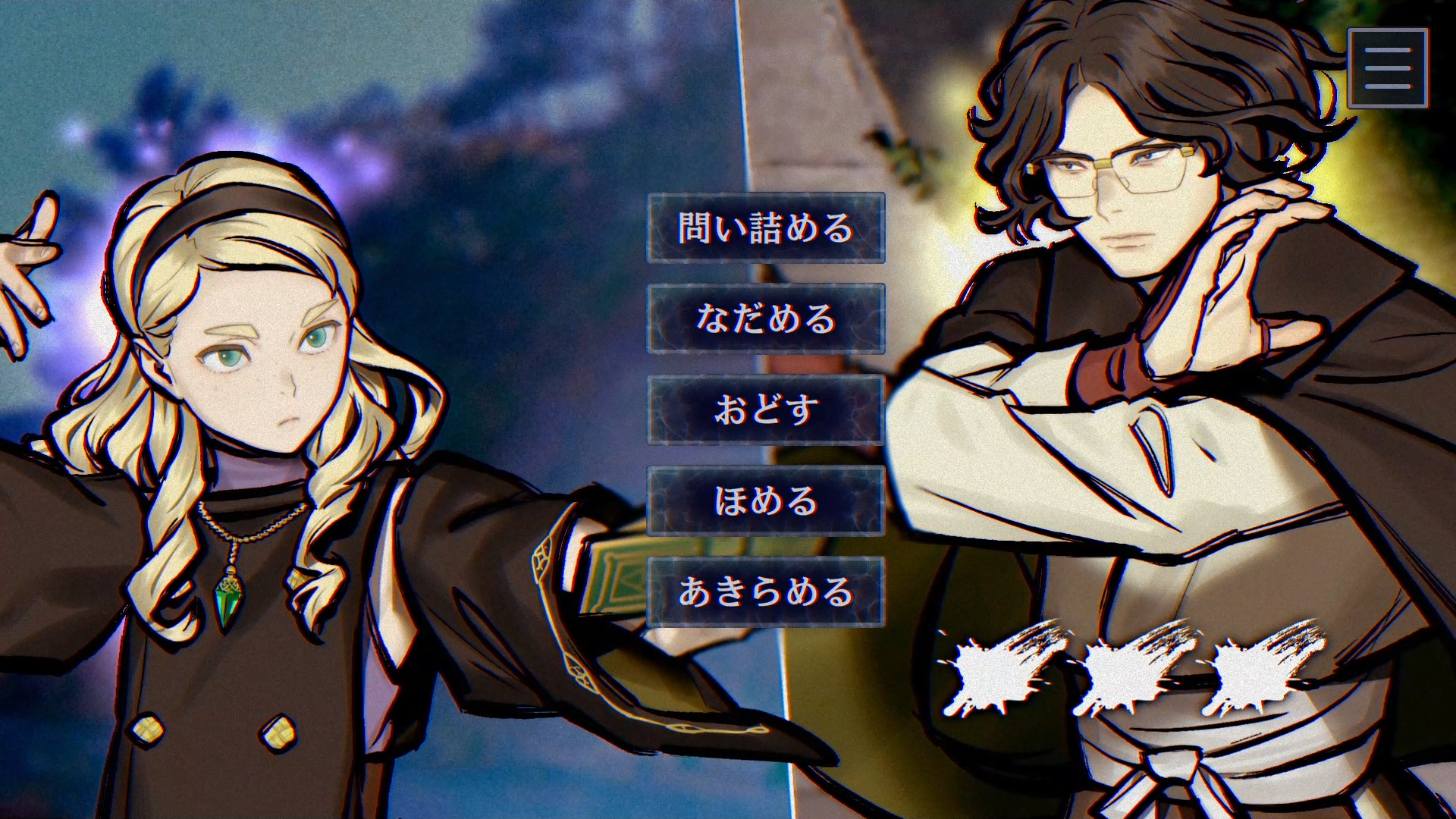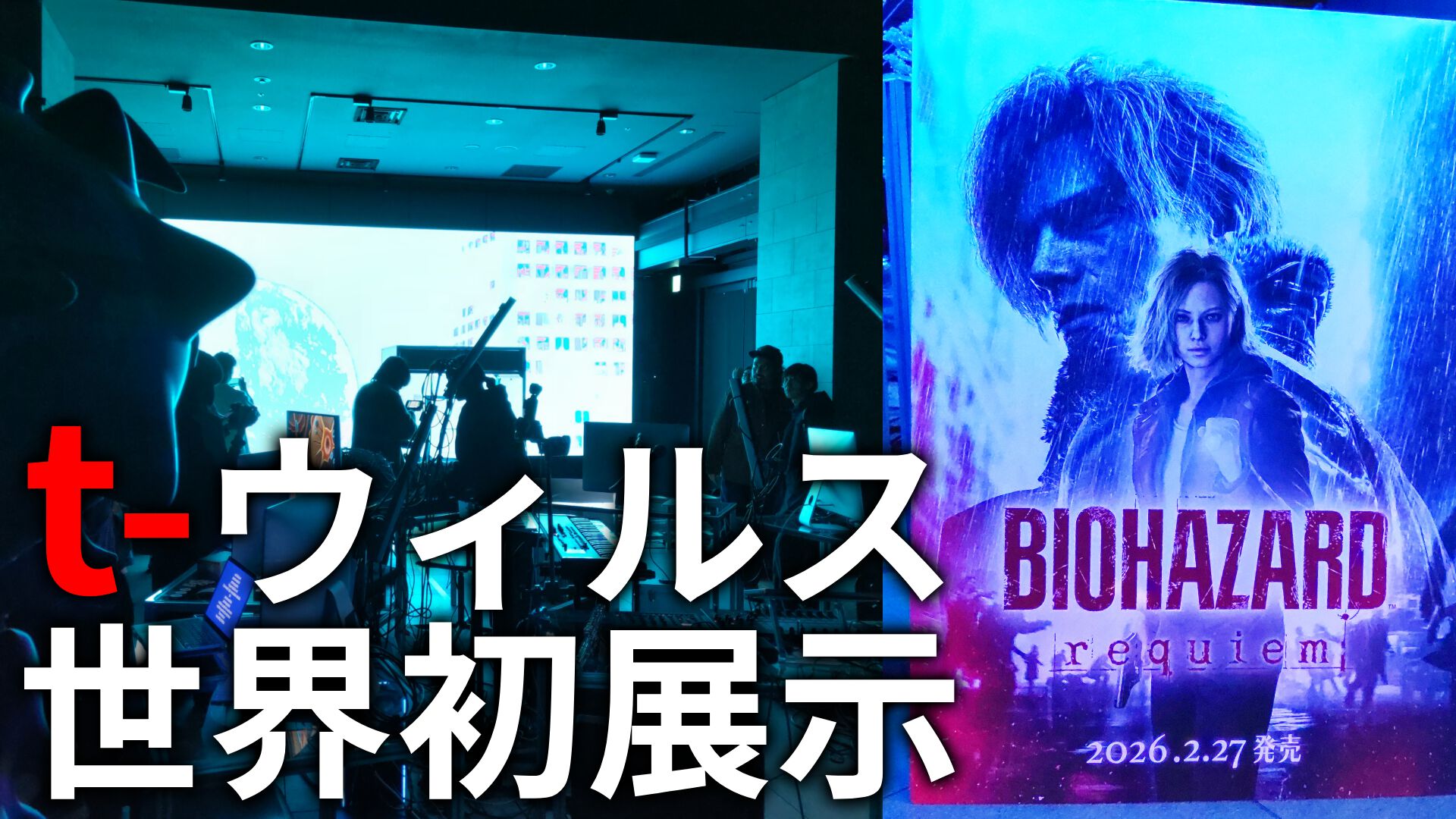![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a9bd994b1cb06e33e169c75c9b0156af8.jpg?x=767)
2025年2月14日~17日の4日間、抽選で選ばれたプレイヤーを対象にしたネットワークテストが実施される。それに先駆けて、メディア向けにネットワークテスト版の先行試遊会が開催。本記事では、試遊会で実際にゲームをプレイした感想をお伝えしよう。約4時間という短いプレイ時間だったが、本作の魅力にはしっかりと気づくことができた。
なお、ネットワークテスト版は開発中のもので、製品版では仕様や名称、パラメータなどが変更される可能性があるとのこと。
また、できるだけ配慮しているが、ネタバレが気になる方は注意していただきたい!
3日間を生き抜く、3人協力型のサバイバル
舞台となるのは、本編とは異なる“リムベルド”と呼ばれる地域。3人一組で、挑むたびに変化するフィールドを、限られた時間内に攻略していく。プレイヤーは出撃前の拠点である“円卓”で、最後の討伐対象となるボスを選択し、マッチングがスタート。3人集まれば、挑戦がスタートする。
挑戦が始まると、1日目を迎える。本作は3日間を生き延びることを目指し、冒険を進めていく。1日の終わりに夜となり、ボスに挑むことになる。そのボスを倒すと2日目、2日目のボスを倒せれば3日目を迎えられるという仕組みだ。
3日目は討伐対象に選んだ、いわゆる大ボス戦となっており、1日目と2日目は同じようなサイクルで進んでいく。もし各ボスの討伐に失敗した場合はゲームオーバーとなり、マッチング前の拠点に戻される。挑戦に失敗しても報酬はもらえるが、成功したほうが豪華な報酬が手に入りやすい。
また、1日目や2日目に入手した装備や消費アイテムは、そのステージに挑戦中のみ使用可能で、持ち帰ることはできない。ステージに持ち込むこともできないので、基本的にはすべてイチからの状態で挑むことになる。唯一持ち込めるもの“遺物”に関しては、後半に紹介しよう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a0c0ce975732452d652db032f4200331a.jpg?x=767)
操作方法について
●方向キー
上:アイテム使用
下:アイテム切り替え
左:左手武器切り替え
右:右手武器切り替え
●スティック
左スティック:移動
左スティック押し込み:疾走
右スティック:カメラ操作
右スティック押し込み:カメラリセット、ターゲットの固定/解除
●ボタン
R1ボタン:攻撃(右手武器、両手武器)
R2ボタン:強攻撃(右手武器、両手武器)
L1ボタン:攻撃(左手武器)、ガード(盾)
L2ボタン:戦技
△ボタン:イベントアクション(調べる、開けるなど)
□ボタン:聖杯瓶の使用
○ボタン:バックステップ、ローリング、ダッシュ
×ボタン:ジャンプ
●特殊操作
△ボタン+L2ボタン:スキルの使用
△ボタン+L1ボタン:左手武器の両手持ち/片手持ちの切り替え
△ボタン+R2ボタン:アーツの使用
△ボタン+R1ボタン:右手武器の両手持ち/片手持ちの切り替え
△ボタン+左右方向キー:アクション対象の切り替え
●タッチパッド
マップメニュー
●オプション
メインメニュー
基本的な操作は『エルデンリング』と変わらないが、本作独自の要素として“疾走”がある。これはダッシュよりも早い“超ダッシュ”というイメージで、“霊馬トレント”と同じような速度で走れるもの。本作には霊馬が登場しないので、プレイヤーキャラクターたち自身が高速移動することになる。
また、独自のアクションとして“スキル”と“アーツ”が追加されている。こちらはキャラクターごとに紐付けられたもので、“スキル”は汎用的に使えるアクション、“アーツ”は必殺技のような立ち位置のアクションになっている。こちらはキャラクター解説の欄で具体的に紹介しよう。
フィールド探索の基本
フィールドは『エルデンリング』で見たことがあるような場所がコンパクトにまとまっている印象で、その中を自由に探索しながら装備を探したり、敵を倒してルーン(経験値であり、お金)を集めたりする必要がある。
時間経過とともに夜が迫れば迫るほど探索可能なエリアが狭まっていくので、ゆっくりしている余裕はあまりない。侵入禁止エリアの“夜の雨”に入ると継続的にダメージを受けてしまうので、そこを避けながら探索する必要がある。
ゲーム開始直後は侵入禁止エリアも存在しないので、どこへ行くのも自由だ。しかし、ある程度時間が経過すると、最後のエリア収縮地点が明示され、最終的にはそこに辿り着く形となる。限られた時間と範囲で探索をどう進めるか、そのマネジメントを考えなければならない点は、なかなかにおもしろい要素だった。
メニューを開いて確認できるマップには、スタート時点で多くの情報が明示されており、どこに何があるのか、すぐに把握できるようになっている。たとえば、敵が集まっている拠点に行けば敵を倒してルーンを得たり、または宝箱があったりするかもしれない。マップを参考にしながら予定を組んでいくのが楽しいのだ。なお、一部のマップ地点は探索で判明することもあるようだ。
フィールドにはダンジョンもあり、『エルデンリング』に登場した“石剣の鍵”のようなもので解放されるボスも存在していた。教会に行けば、回復アイテムである“聖杯瓶”の使用回数を増やせるほか、鍛冶台で武器の強化、ショップでアイテムを購入など、さまざまなことができる。
どこに向かうのか、自由に行動できるが、やはりプレイヤーを強化するために目的地を決めて進むのが基本と言えよう。ただし、3人のプレイヤーで協力するゲームだが全員が固まって動く必要はない。それぞれがバラバラに動いてもいいし、協力してボスをどんどん撃破していくのもいいだろう。
エモートくらいしか意思を疎通する手段はないが、目指したい場所にピンを指すことで意思表示ができるほか、落ちているアイテムにピンを指すことも可能なので、アイテムがある場所を仲間に伝えつつ、「自分はこのアイテムはいらないからどうぞ」といったメッセージにもなるはず。ちなみに、武器にピンを指すとマップメニューからその武器の性能も確認できた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a94211f3639b96912f75a7532fdb54995.jpg?x=767)
手段が豊富で快適な移動
“壁ジャンプ”は、壁をキックしてさらに高いジャンプができるアクション。壁が近くにないとできないが、2段ジャンプといった感じ。“よじ登り”は、ジャンプして崖などの障害物に触れると、高さが足りている場合はその障害物をよじ登ってくれるアクションだ。
このふたつのアクションで、ある程度の高低差ならば楽々と登って移動できるようになっている。『エルデンリング』のようにジリジリと地に足を付けて探索するというよりは、ピョンピョンと登りたい場所を登っていくことができるだけでも、移動のストレスがかからない。
また、崖下などには“霊脈”と呼ばれる青い亀裂があり、亀裂に立ってジャンプすると崖を一気に飛び越える“霊脈ジャンプ”が発動する。霊馬の霊気流ジャンプに近いが、崖とは反対の方向に大ジャンプすることもできたので、少しだけ移動の自由度が上がったと言えるだろう。
なお、本作には高低差のダメージがないので、どんなに高いところから飛び降りても問題なし。ただし、エリア外の落とし穴に落ちた場合は死亡扱いとなってルーンを落とすことになるので注意が必要だ。
さらに、透明の樹木である“霊鷹の止まり木”を見つけると、鳥の“霊鷹”に掴まって、空中を移動できる。行き先は決まっているが、高低差をすべて無視して長距離移動が可能な点は有用だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a7f28f85e560e56fc37261868ad07d3bb.jpg?x=767)
ビルド:レベルについて
レベルはルーンを消費して上昇させられるもので、『エルデンリング』と同じように拠点となる“祝福”を調べることでレベルアップができる。本編ではステータスに振ることでレベルも上がっていったが、本作はレベルの上下しか存在せず、レベルを上げれば、そのキャラクターの性能が全体的に底上げされるものになっている。
時間が限られたゲームなので、祝福を調べる→即レベルアップして別の場所に行くという動きがパパッとできる。HPやFPの回復、聖杯瓶の使用回数は祝福を調べずとも、近くに行くだけで実施されるのも、スピーディーな展開につながるポイントだ。そのため、本作での祝福は回復スポット兼レベルアップする装置といった位置付けとなっている。
レベルはとても重要で、いかにファーム(敵を倒しまくる)してルーンを稼ぐのかがとても大事。レベルが1の状態は『エルデンリング』の初期キャラクターよりも弱い印象で、とくにHPがあまりにも少ない。が、レベルを1個上げてしまえばHPが大きく上がり、戦闘がかなり楽になる。
ルーンは一般的な敵を倒してもそれなりに稼げるが、フィールドに点在する強敵を倒すと大量のルーンを獲得できる。状況にもよりけりだが、強敵相手に3人で戦えることを考えると、果敢に挑んだほうが、その日の夜に挑むボス戦での立ち回りも変わる印象だ。
また、獲得したルーンはパーティーメンバー全員に分配される。3人が別行動を取っていて、ひとりが敵を倒したとしても全員の強化につながるわけだ。バラバラに動きながらルーンを稼ぐこともいいが、そのぶんボス戦では誰かが苦労するかもしれない。探索範囲が狭まってくることも考えると、チームでどう動くのかもパーティー強化の鍵となる。
なお、HPがゼロになって死亡すると、1度ダウンして瀕死状態になる。瀕死状態のとき、ほかのプレイヤーから攻撃してもらうことで瀕死ゲージがゼロになると蘇生できる仕様だ。瀕死ゲージは、短時間で瀕死状態になるとそのたびに増えていくので、蘇生が難しくなる。
瀕死状態のまま一定時間が経過すると、死亡となる。死亡すると所持ルーンをすべて落とし、さらにレベルがひとつ下がってしまう。落としたルーンを回収するとルーンとレベルは戻ってくるが、回収に失敗して再度死亡すると、ルーンもレベルもロストすることに。なお、落としたルーンを周囲の敵が拾ってしまう場合があり、その際は拾った敵を倒さないと回収できない。
なお、昼間のあいだは死亡しても何度でも復活可能だが、夜のボスとの戦いのみ、瀕死から死亡状態になることはない。全員が瀕死状態になった時点でゲームオーバー、挑戦失敗となる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a5e7b1f23ac6375dde97c76c391acddd3.jpg?x=767)
ビルド:装備について
また、武器には“付帯効果”と呼ばれる強化効果が付与されている場合がある。付帯効果の種類はとても多く、特定の攻撃力上昇であったり、特定のカット率(防御力的なもの)が上がる、消費スタミナやFPが下がるなど、その効果はさまざまだ。
付帯効果は、その武器を持っているだけで発揮されるので、試遊では武器自体の性能よりも付帯効果を狙ってアイテムを探索することが多かった。武器は性能や自分が使いやすいものを1本か2本ほど持っていればよく、ほかの“付帯効果”で自己強化を図っていくといった印象。武器は左手に3本、右手に3本ずつ持てるので、計6個の武器でビルドしていくことになる。
レアリティが高い武器ほど付帯効果などの性能が高いが、レアな武器にはレベルの制限があり、必要レベルに達していないと性能を発揮できないようになっている。
なお、防具は本作に存在しないので、装備収集は武器を集めていくことがメイン。特殊な効果を発揮する装備品の“タリスマン”もあったが、隠されたスカラベを倒す、特定のダンジョンで入手するなど、その入手手段は限られているようで、試遊時間内では探すことはできなかった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/acf9d4b8c55c721709c4ed8a3ccbbf71d.jpg?x=767)
また、宝箱以外からも装備品は入手可能で、名前の付いたボスを倒す、特定のイベントをこなしたりすると魂のようなものがドロップされるので、その中から選択して装備品や強化効果を得られる形だ。この選択式の宝箱については、パーティーメンバーそれぞれにランダムで報酬が提示されるので、取り合いになることはない。
消費アイテムは4種まで持つことができ、アイテムによって所持最大数が異なっていた。本作は消費アイテムがバンバン手に入るので、あまり気にせずに使って問題ない。また、消費アイテムは『エルデンリング』のものより性能が底上げされている印象で、とくに“火炎壷”は爆発範囲が大きくアップしており、グレネードのように使うことができた。また、消費アイテムはジャンプしながらでも使用可能だ。
ビルド:パッシブ効果について
“潜在する力”はユニークな効果を持つものが多く、筆者の場合は“回避するたびに周囲に雷が落ちる”、“ダッシュすると周囲に氷を撒く”といった、攻撃アクションが増えるものを入手できた(しかも、いずれもFPを消費しなくても使えた)。回避の無敵時間が延びる“回避性能強化”、“一定時間ごとに魔法の剣を発射する”という効果も存在し、ランダムで得られる要素ではあるが、“潜在する力”でビルド構築がよりおもしろくなっていたのは間違いない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/af1e1d0b02483cd798fc1ba83ad30d4bd.jpg?x=767)
バトルは『エルデンリング』をイメージしてオーケー
とはいえ、プレイヤーキャラクターは“疾走”などで回避性能が高く、“スキル”と“アーツ”も持っているので、基本的には難所も突破しやすくなっているように感じた。しかしながら初期装備だけで立ち向かうのは難しく、ビルドの構築で立ち回りが大きく変わる点は重要だ。
通常の敵との戦いはサクサク進められて、名前付きの強敵との戦いは骨太なのは『エルデンリング』とさほど変わらない。ただし、本作は3人協力プレイが前提であるため、3人でボスと戦える状況も少なくなかった。とはいえ、そこはフロム・ソフトウェア。「3人の共闘が基本なんだから、いいよね?」と言わんばかりに、複数体の強敵が登場することも珍しくなく、最初は1体でも、途中から通常の敵を複数呼び寄せて、多人数相手の戦闘に発展することも。
また、“戦技”は『エルデンリング』ではバンバン使用できたが、本作ではFP回復の聖杯瓶が存在しないようで、FPの回復は祝福に行くか、一部の限られた手段を用いるしかない。そのため、戦技はものすごく強力な性能になっている代わりに、“ここぞ”というときに使用するような立ち位置となっていた。
ちなみに、強敵と戦っているときに突然“忌み鬼”という別の敵が乱入してきたことも。まあ、どう見ても“マルギット”なのだが、本作では“忌み鬼”とだけ表示されていた。しかも、忌み鬼はターゲットになったプレイヤーがどこにいようと、ずっと追い詰めるような動きを見せるので、強制的に戦うしかないという……。しかも、忌み鬼に狙われたプレイヤーが倒されると、パーティー全員に被ダメージ値がアップするデバフのパッシブが付与された。
フィールドにはこちらの想像を超える、さまざまなイベントが発生するようだ。
3人協力について
協力プレイの要素は比較的薄めで、強制的に何かをしなくてはいけないという場面は少なく、必須なのは倒れた仲間の蘇生くらい。ルーンは全員に分配されるため、自分ひとりで活躍するだけでも仲間への協力につながるという“緩さ”は、個人的にはとても好きなポイントだ。
ちなみに、パッシブスキルとなる効果に“聖杯瓶を飲むと周囲の仲間も回復する”というものもあったので、パッシブの選択次第によってはちょっとだけヒーラー的な立ち回りもできるだろう。筆者の印象では、プレイを重ねていくうちに、自然とキャラクターの性能によってバトルでの役割分担が決まっていった感じだった。ほかのプレイヤーと会話したわけではないのだが、何度か挑戦していくうちに自然とそうなったのだ。
プレイを重ねてキャラクターの性能を覚えていけば、知らない人どうしのマッチングでもある程度は役回りが決まっていくのではないだろうかと予想する。挑戦開始前には、誰がどのキャラクターを選びたいかがわかる状態でキャラクター選択が始まるので、なんとなく連携も取りやすいはず(もちろん、同じキャラクターを使用しても問題ない)。
また、ほかのプレイヤーが別の世界でゲームオーバーとなった場合、その場所にプレイヤーが装備していたアイテムが落ちているという、非同期型のネットワーク要素もあるそうだ。ドロップされている武器には前のプレイヤーの無念が付帯効果として付与されており、倒されたキャラクターごとに異なる強化効果が得られる仕組みとのこと。
なお、いちばん熱くハラハラドキドキしたのが、味方が瀕死状態になったとき。本作は倒れた仲間を攻撃することで蘇生できるため、どうやって蘇生するのかが重要かつユニークな要素だった。筆者の場合は弓を装備しておき、遠距離からチマチマと味方を攻撃して蘇生することが多かったが、攻撃力の高い近接系ならば、近づいて攻撃したほうが蘇生は早い。
どのように仲間を蘇生させるのか、そこも戦術を考えるうえで大事な要素となっていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a3635e9a9c031f382692345f72e41ae9b.jpg?x=767)
使用できた4名のキャラクター
追跡者
■アビリティ:第六感
食らうと瀕死状態になるダメージを食らっても、1度だけその攻撃を回避(完全無敵といった感じ)する。命を落としにくいアビリティなので、生存能力がアップする。
■スキル:クローショット
クローを飛ばすスキル。フィールドに当てると、その地点に目掛けて移動する。小さい敵に当てると、敵を自分のもとに引き寄せる効果があった。大きな敵に当てた場合は、敵に目掛けて飛ぶことが可能。ボタン長押しで狙いを自由に付けることもできる。
敵の体勢を崩しやすく、ガードした敵にもヒットさせられる。クールタイムも短めなので、戦闘中にとりあえず撃っておくくらいの感覚で使用できるスキルだった。
■アーツ:襲撃の楔
鉄杭を爆発とともに撃ち出して、強力な一撃を放つ。パイルバンカーのようなイメージだ。ボタンを長押しすると威力がアップ。ジャンプ中にも使用できた。
威力に優れるほか、敵の体勢をかなり崩しやすい。相手の体勢を崩してチャンスを作りやすく、使いどころがハッキリとしている。とりあえずボスに撃つだけでも十分活躍できるだろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a1bd77de7bda11de0e3e1aaff44a8cec3.jpg?x=767)
守護者
■アビリティ:ハイガード
盾でのガード中に左スティック(移動)+○ボタンを入力すると、より強力なガード体勢に移行。L1ボタンを押し続けることで体勢を維持する。さまざまな攻撃をガードすることができ、守護者を使ううえでマスターしたいアビリティ。初期装備よりも強い盾を入手できるかどうか、そこもポイントになりそう。
■スキル:つむじ風
風を吹き上げて、範囲攻撃を仕掛けるスキル。巻き込まれた敵は中央へと寄せ集められ、小さい敵ならば空中へと打ち上げられる。ボタンを長押しすると、攻撃範囲がより広くなるので、集団戦で効果を発揮した。大勢の敵を一時的にダウンさせられるのも強力。
■アーツ:救世の翼
高くジャンプした後に、急降下して攻撃するアーツ。空中でも使用可能。着地後に攻撃ボタンを長押しすると、自身の周囲に防御陣を展開し、防御陣の中にいる味方をダメージから守る。
急降下攻撃の威力も高いのだが、攻撃よりも味方の蘇生に使うほうがいいという印象。高くジャンプしてから、狙った味方を救いに行く動作は、まさに“守護者”らしい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a43a0080e6cf58327281da781c0a0a48b.jpg?x=767)
レディ
■アビリティ:華麗な身ごなし
パルクールのような美しいモーションで、回避を2連続で発動できる。また、攻撃や回避アクションのスタミナ消費が減る効果もあるようだ。シンプルに連続して回避できるのは強く、そもそも回避の終わり際もあまり隙がないところが頼もしい。
■スキル:リステージ
周囲の敵に対し、直近で与えたダメージを再度与える。発動すると白い敵の幻影のようなものが見え、直近のダメージがもう1度再生される。短剣で4回斬りつけて発動したら、もう1度4回斬りつけたダメージが発動する感じだ。
トリッキーなスキルだが、直前のダメージをもう1回くり返せるのは強力。なお、発動は攻撃や回避中でも可能だった。また、味方の攻撃によるダメージも、直前のダメージを再生できる。
たとえば、追跡者がアーツ“襲撃の楔”を決めたら、自分がリステージを発動するだけでアーツを2連続で叩き込めるというわけだ。使いどころが難しいかもしれないが、レディの代名詞と言えるようなスキルとなっている。
■アーツ:フィナーレ
自分と周囲の味方を透明状態にして、一定時間姿を隠すことができるアーツ。発動後、敵は自分たちにターゲットを向けることはなく、やみくもに攻撃をくり出したりと、無防備な状態になる。基本的には“逃げ”用のスキルというイメージで、ピンチ状態になったら使いたい。とくに誰かが瀕死状態になったら、透明状態になれば安全に蘇生できる。
試遊では残念ながら“攻め”の部分でどのように扱えばいいのか、筆者は試すことができなかったが、使いかたによっては幅広い戦術が生まれそう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a01fcbf98e255af196356b264b1e64ed6.jpg?x=767)
■隠者
■アビリティ:元素制御
隠者は特殊なルールを持っており、魔、炎、雷、聖いずれかの属性攻撃がヒットした敵に“属性痕”を付与する。属性痕はスキル“混成魔法”で吸収することが可能で、その際にFPを回復できる。属性痕は味方が付けたものでもよく、かつ味方に付いた属性痕も吸収できた。FPを回復しながら魔術・祈祷を使うのが、隠者のオーソドックスな立ち回りのようだ。
■スキル:混成魔法
ひとつ目の効果は、属性痕を吸収するアクション。ふたつ目は、吸収した属性痕を3つストックし、ストックされると混成魔法を敵に放つというもの。混成魔法を発動するとストックが消費され、ふたたび属性痕を吸収できるようになる。
混成魔法は集めた属性によって効果が変わり、別々の属性を混ぜると効果の高い魔法が発動する。魔と炎を集めたとして、どちらかの個数が多いのかでも性質が変わるなど、仕様は細かくなっており、混成魔法自体を把握するには慣れが必要になりそう。とはいえ、魔を3つ集めたら追尾弾、炎を3つ集めたら地面を炎上させるなど、シンプルな効果も発揮する。
混成魔法の発動にFPは使用せず、かつクールタイムがない。連続で属性痕を3つ集めることに成功すれば、バンバン混成魔法を放てるのが強力だ。
■アーツ:血塊の唄
周囲の広範囲に向けてダメージを与え、“血の烙印”といった効果を付与する。効果はとても広く、集団戦での攻撃手段にもなる。烙印はある程度持続し、付与された敵へのダメージが上昇するほか、攻撃したプレイヤーのHPとFPが回復する。
試遊では参加者が慣れていない状態だったためか、発動しても味方が攻撃してくれないこともあった。しかし、発動までに長い無敵時間があったので、ピンチのときにとりあえず回避するための手段に使用していた。慣れないうちは自分の回避手段として使うのがいいかも。慣れてくれば、みんなで弓矢でチクチク回復できそう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/ae5ada8d2ad765c0cc3b8e8c9d4566848.jpg?x=767)
“遺物”を持ち帰ろう
シンプルにステータス効果を上昇させるものや、一部のアクションを強化するものなど、こちらも効果は多彩。キャラクター専用の遺物もあり、たとえばレディが背後から致命の一撃を決めると“姿を見え難くし、足音を消す”といった効果を持つ遺物が確認できた。
もちろんボスを討伐して3日間を生き抜くことが目標ではあるが、この遺物を集めるために戦うこともプレイヤーのモチベーションになるだろう。遺物は装備スロットが色で分けられていて、キャラクターごとに異なる装備スロットに合った色の遺物しか装備できない。
このあたりのカスタマイズ要素はじっくりと円卓で練れるようになっているので、より強力なビルドを目指して何度も挑戦するのも楽しいところだ。ちなみに、拠点の円卓では“訓練場”が常設されており、各キャラクターのアクションを練習しつつ、確認することもできた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/ac47b84f474e84498846b3eacb98b7894.jpg?x=767)
3人で戦う、高速ローグ骨太アクション!
まったりする時間が少ないので、もたもたしていると不利になってしまうという難度はある。ただ、あらゆるアクションが高速で遊べるように最適化されていて、手が止まるのは装備を吟味するときくらい。とりあえず装備品を拾ってビルドを組むだけでも、それなりに戦えるだろう。マップを開きながら移動することもできるので、移動中も装備変更や目的地の選定などの時間に当てられるようになっているのも、本作のゲーム性に合ったうれしい配慮だ。
筆者は“隠者”がとても印象に残ったので、今回の試遊では重点的に使用した。魔術系の攻撃を得意としているが、攻撃を一発くらうだけで瀕死状態になるという性能がスリリングで楽しい。なにより、プレイに慣れていくうちにパーティーの中で自然と役割分担が生まれていき、うまく役割を果たせたときは素直にうれしくなった。隠者は条件さえ揃えば遠距離から圧倒的なダメージ量を叩き出せたので、基本的にはパーティーのダメージディーラーとして活躍したと思う。
ただし、それは前衛役を引き受けてくれたふたりの仲間がうまく敵を引きつけるなどして、立ち回ってくれたからこそ。入手した装備の付帯効果に“敵から狙われにくくなる”というものがあったおかげで、安全にダメージを稼げたのも大きい。ちなみに“敵から狙われにくくなる”効果をふたつ重ねたら、確実により狙われにくくなったので、効果は重複すると思われる。
ボスがドロップした“屍山血河”(強力な戦技を持つ刀武器)を味方に渡したところ、うまく活用してくれたのを見たときも達成感があった。とくに他プレイヤーと会話したわけではないのだが、パーティーの絆も自然と深まったことが実感できたのだ。
いよいよ試遊も終わりの時間が近づいてきたタイミングで、自分を含めたパーティーが3日目に到達。今回の討伐対象である“夜の獣、グラディウス”と対決することができた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/33298/a6ec8ed7b7ea82595ca3af82a837532c1.jpg?x=767)
筆者は『エルデンリング』では、ひとりで攻略したいタイプだった。“遺灰”も使わなかったような自分でも、本作の協力プレイはしっかりと楽しむことができた。なにより仲間がいないと攻略できないような状況も多く、とある強敵が2体現れたときは「そういう次元ではないな」と(笑)。
今回のネットワークテストでは4人のキャラクターとひとつのステージのみが体験できるが、それだけでも本作の魅力はたっぷりと詰まっていた。製品版ではどのような深みをさらに見せてくれるのか、いちファンとしても楽しみだ。