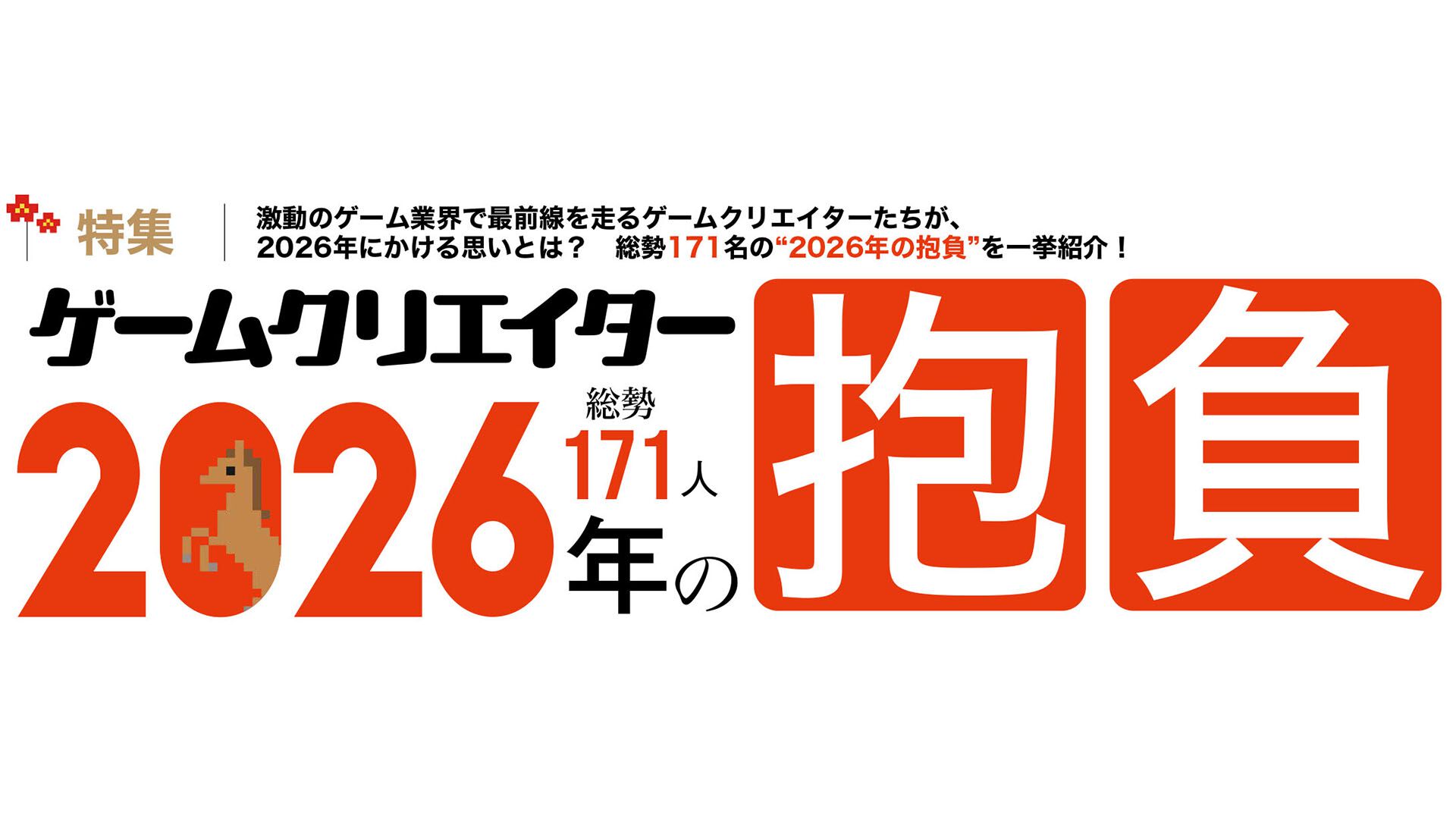2024年秋、個性派クリエイターの手掛けるゲームが続けてリリースされる。10月11日発売の『メタファー:リファンタジオ』と11月8日発売の『野狗子: Slitterhead』だ。
それぞれを生み出した橋野桂氏と外山圭一郎氏は旧知の仲。そして、偶然にもふたりの最新作はどちらも完全新規タイトルだった。お互いの創作スタイルやゲーム開発へのこだわり、作品に対する思いなどを、対談形式で紐解いていく(聞き手:ファミ通グループ代表 林克彦)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a42c7d1dacdf2bccd572181a356e63745.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/af8ac6f514525efc19420efc6ff7b07a0.jpg?x=767)
現代や近未来を舞台としたゲームに定評のあるアトラスが贈る、完全新規のファンタジーRPG。8つの異なる種族が生きる世界を舞台に、“ニンゲン”と呼ばれる謎の怪物たちと戦いながら呪いを解く旅に出る。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a57f4d0c0667b136a86a32b5f77d6740b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/af30007f987e79e1f06c33e480267267a.jpg?x=767)
外山圭一郎氏(Bokeh Game Studio)による完全新作タイトル。1990年代の架空都市“九龍”で、精神生命体“憑鬼”となって怪物“野狗子”の殲滅を目指す。バトルアクションを標榜しており、一般的なホラーアドベンチャーとは様相が異なる。
橋野桂
アトラス所属ゲームクリエイター。『ペルソナ3』以降のシリーズのディレクション/プロデュースを担当。アトラス内に2016年に設立されたプロダクション“スタジオ・ゼロ”では新作RPG『メタファー:リファンタジオ』のディレクターを務める。文中では橋野。
外山圭一郎
Bokeh Game Studio代表取締役 CEO/クリエイター。『SILENT HILL』や『SIREN』、『GRAVITY DAZE』などのディレクションを経て同社を設立。『野狗子: Slitterhead』ではクリエイティブディレクターを担当。文中では外山。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/ab2a93fc6c49359fb18a9b6dbee3aa79a.jpg?x=767)
「橋野さんは意外性の塊」「外山語を理解できてアウトプットできる人たち」
――おふたりの付き合いはいつ頃からなんでしょうか。
橋野
コーエーテクモさんにいらっしゃる柴田誠ディレクター。あの方がきっかけです。
――『零』シリーズの柴田さんですね。
橋野
僕が『キャサリン』を作ったときに、「やっとホラーを作ってくれる仲間が現れた!」みたいな感じで。
一同 笑
橋野
「『キャサリン』は別にホラーゲームって感じではないんですけど~」と返したのに「いやホラーです!」って。そこで柴田さんといっしょに、外山さんと食事をさせていただいたのが始まりかな。
外山
そうですね。初対面がいつだったかはうろ覚えだけど、柴田さん絡みだった気はします。
――そもそも柴田さんと外山さんはお付き合いがあったわけですよね。
外山
はい、それはホラーつながりなので。
橋野
「ホラーじゃないですよ」と言っても、柴田さんが「いや、ホラーだし」って引かないんですよ。外山さんもその前の『ペルソナ4』で、家電量販店のテレビが並んでる場所から潜るシーンで「あれは完全にホラーですよ橋野さん」って。覚えてます?
外山
覚えてます。すごい印象に残っていたので。
橋野
ホラー開発者(?)の一員に無理やり迎え入れられた。
一同 笑
――となるとけっこう前ですよね。『キャサリン』(2011年2月発売)のころですから。
外山
それからは、ゲームディレクターで集まって飲もう、みたいな会にいっしょに参加したり。
橋野
知り合ってからは長いんじゃないでしょうか。
――メディアでふたりだけで話すのは、これまでにありましたっけ?
外山
初めてだと思います。
橋野
ふたりで会うことはほとんどないんじゃないかな。だいたい何人かの集まりで。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a1c84ba46b6a85a54cceeb795fcea04bf.jpg?x=767)
――お互いの印象はどういう感じでしょうか?
橋野
外山さんは、陽気な人です。いろいろなことを楽しもうとしている人だという気がします。うん、趣味人って感じですね。
外山
橋野さんは、読めない人ですね。つぎに何を言ってくるのかがわからないというより「えっ、そういうふうに来るの?」みたいな。意外性の塊というイメージです。
――おふたりが新しいスタジオを立ち上げてから数年が経過して、それぞれ新しい環境で新たなタイトル作りを経験されてきたと思うのですが、新体制ができるまでに印象に残っていることはありますか。
外山
先に聞いておきたいんですよ。自分は前の会社を退社して起業して、という一般的な独立の形ですが、橋野さんは違いますよね。アトラスの中に新スタジオというのは具体的にどういうことなんですか?
橋野
独立感はないんですよ。いろいろなチームが同じフロアにたくさんいる中の、ひとつのエリアが僕らのスタジオ。独立して城を作るのとは違うので。
外山
自分の想像だと、橋野さん自身が「ここに注力する、集約する」宣言なのかなって。
橋野
そうですね。人気シリーズは人気シリーズで会社的に続けていかなきゃいけない中で、『真・女神転生』や『ペルソナ』に続いて大きいものを作りたかったんですよ。そこに乗ってくれる人たちを集めてスタートした、みたいな。
――同志を社内で募ったと。
橋野
外山さんも、たったひとりで知らない人たちを集めて、という感じではないですよね。
外山
ないですね。うん、まぁ。
橋野
気心の知れた人たちを中心にという。
外山
ん、まぁ……というか……。
橋野
違うの?(笑)
外山
いやいや、「気心の知れた」だとちょっとニュアンスが違うかなと。
橋野
気心は知れてないんだ。
外山
こういうところあるんですよこの人!
一同 笑
外山
ここでそういう発想します?(笑)
橋野
なるべく発言を拾っていきたくて(笑)。
外山
要するに、自分個人のことだったらいいんですが、人を巻き込むということは、勝てる博打、勝てる勝負を仕掛けなきゃいけない。そのために「この人がいないとな」という考えかたをもとに声をかけていったんです。僕は自分ひとりでは何もできないので。
――絶対に必要なパズルのピースがある、と。
橋野
べつに仲よしグループというのではなくて、つぎの作品を作るためのメンバーということですね。
外山
んー……。
橋野
ごめんなさい、それも違いました?
外山
いやいや、その通りです。作るうえで必要になる役割はそれぞれ違うなと。自分はある部分で突出した何かがあるから、いまこの歳までやっていけていると思うところはありますが、その反面で欠けた部分もすごく多いんですよ。その得意不得意のデコボコを合わせてもらえるようなメンツの集合体じゃないと、強みが出ないイメージがあります。そういう意識で会社のメンバーを募ったんですね。
橋野
僕も絵は描けないし、プログラミングもできないし、音楽も作れない。当然チームじゃないとゲーム制作はまったくできません。外山さんはご自身で「欠けている」とおっしゃいましたけど、その作品を作るために、まずどういう技術が必要と思ったのか、ちょっとお聞きしたいです。
外山
自分の特徴は、0を1にするとかIPを創出するとか、そういうところにあって。ただ、自分の脳内でわちゃわちゃやっているところで、「何を言ってるかわかんないよ!」と反応されたらどうしよう、みたいな不安感がワーッて来るわけですよ。そういうのをさばく能力が圧倒的に足りないから、「いや、これはこういうことでしょ」って咀嚼する役割が必要なんです。
橋野
周囲の人が?
外山
実際に手を動かすアートやプログラムのところに、自分で翻訳して理解してくれるスタッフさんがまず必須。相棒みたいなものですね。
橋野
“外山語”を理解できてアウトプットできる人たち、ということですか。
外山
そういうことですね。あとは外。外部の人との話はもっと難しいです。僕らはわかっているけど、外に伝わるようにさらに翻訳しないといけない。いっしょにものを作るうえで、それができる人はすごく貴重です。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a33133c93369138bed93d1e7956acc3a4.jpg?x=767)
――まわりにどういう人が必要かという話で言うと、橋野さんはいかがでしょうか。
橋野
最初に“この人がいないと仕事ができない”人たちで集まって始めた、という形は、もしかしたらいっしょかもしれない。 わかってもらえる人は大事です。
外山
僕、アトラスさんの中に仲よくさせていただいてる方が多いんです。副島さん(※1)や当時の目黒さん(※2)と飲みに行ったりサバゲーの場で会ったりとか。金田さん(※3)や和田さん(※4)など、いま『ペルソナ』シリーズを作っている方とも仲がいいんです。それで彼らと話していると「橋野さんはやっぱり特別だ」って言うんですよね。
※1:副島成記氏。『ペルソナ』シリーズや『メタファー:リファンタジオ』キャラクターデザインなど。
※2:目黒将司氏。『ペルソナ』シリーズのサウンドなどを担当し、現在はフリーで活動中。
※3:金田大輔氏。『ペルソナ5 スクランブル ザ ファントムストライカーズ』プロデューサーなど。
※4:和田和久氏。『ペルソナ3 リロード』ゼネラルプロデューサーなど。橋野
ほう。
外山
僕も同じで、橋野さんって何もないところからものを作るような、同じ気質を持った人なんだろうなと。
橋野
よかった。いい話でした。
外山
公然とディスるはずないでしょ(笑)。
橋野
外山さんにそう言ってもらえると、すごくうれしいですね。僕は組織の中で開発をしていて、“クリエイター”みたいに呼ばれることはありますけど、 自分の中で憧れるクリエイターというのは、やっぱり0から1でものを作る人、いままでになかったおもしろさ、気づきを作れる人だと思っているので。
外山さんはエポック的。外山さんにしかできない、なんて言うんでしょうね……。流行りの要素も散りばめられているけど、組み合わせかたの妙というか。不安の中で本人が吹っ切って「でも自分はこれが好きだから」、「ワクワクするからこれで行く」みたいなことを日々やられているんだなと。ビビりながらも止められない気持ちを感じるので、いわゆる“クリエイター”だなって思います。
外山
ありがとうございます。
橋野
これ大丈夫でしたか。心外じゃなかったですか。
外山
いえ。気恥ずかしくて(笑)。
橋野
そういうところがあるので、話しててすごく気持ちがいいですね。
自分がいた意味すら喪失することになるのが怖い
――おふたりとも作ってるゲームのテイストやジャンルは違いますけれども、独創性とこだわりが強い印象は共通してあると思います。
外山
テーマ的に共感したのが『ペルソナ4』の序盤の展開。当時も言ったと思うんですけど、 日本の地方都市にありそうなモールの家電売り場のような、誰もいないところが非現実の入り口であったりとか、途中の電柱とかゴミ捨て場の網とか、我々にとって何気ない日常と非現実のちょっとしたリアリティ。そこの掛け合わせの描写がすごく巧みで「これはすごい。すごいな」と、本当に感心したんです。
橋野
外山さんならではの視点だと思いますね。
外山
そうですか?
橋野
その絵を最初から狙っていたわけじゃないのですが、そう言ってもらえるとうれしいです。『ペルソナ4』はホラーゲームではないですけど。
一同 笑
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/aec7f76065b5c888c830bc5957aeca76b.jpg?x=767)
外山
自分の現実の足元が揺らぐ不安感みたいな。それはホラーが持つエッセンスのひとつだと思うんです。現実のはずなのに何かグニャリとし始めた嫌な感じがすごくあって。うわ、すごいなと。
――『SIREN』もそうでした。
外山
まぁ『SIREN』は露骨ですね(笑)。僕は「現実が揺らぐ」という言い方をするけど、そこが本当に巧みだなーって。
橋野
ふだんから現実を斜に構えて見てる人じゃないと、そういう俯瞰的なとらえ方はできないですよ。たとえば外山さんは食事にいくときにカメラをお持ちですよね。あれ、なんて言いましたっけ。のぞくところ。
外山
ファインダーですか?
橋野
そう、外山さんはファインダー越しに現実を見てる人なんですよ。そこがいちばんふつうの人とは違う部分だと思います。芸術家肌。
――外山さん、どうなんでしょう。
外山
うーん……。僕、カメラが好きなのはほんとにその通りで。自分のテーマで言うと、日常は消えていくもの。その中で何かしら心に引っかかりのあったものを留めておきたい意識が人より強いという意識はありますね。
ほんとにどんどん消えてなくなっていく。僕は九州の地方都市の商店街の生まれなんですよ。もう何もなくなって、ご近所の人も誰もいなくて。消えてなくなることへの……ひと言で言うと“寂しさ”がカメラへの執着につながっているのかな。
――それは起きたことをふつうに見るより、カメラ越しに見たほうが自分の中に刷り込まれる。そういう感覚があるのでしょうか。
外山
そうですね、切り取る意識があると思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a42ead9ec970ad4fec5eeebc510289ba6.jpg?x=767)
外山
そういう意味で言うと、逆に切り捨ててるものが多いというかね。 何でも残そうとはしてないんだよな、自分はっていう。そういうところもおもしろさ……おもしろさなのかな。
橋野
その見方も『野狗子』にも引き継がれてる?
外山
すごいあります。
橋野
どういうところですか?
外山
めちゃめちゃ短絡的に言うと、消えていく風景。とくに東アジア圏の都市は、10年、20年で激変して実際に住んでる人にとっては便利になったと思うけど、画一化されていたり、そこで何か切り捨てられたり、消えていくものへの郷愁。これはわりとあらゆる作品を通じて自分の根っこにあるテーマだなと最近すごく自覚しています。
橋野
ノスタルジーってことでしょうか。
外山
んー、まあノスタルジー……。
橋野
ひと言で言われるのが好きじゃないですよね。
一同 笑
外山
そういう気付きですね。なんだろう。“ノスタルジー”だと少し足りないんですよ。
――『GRAVITY DAZE』もそうでしたよね。近代的な場所とそうではないところの対比みたいなものが描かれる中で、どこか寂しさがあるとか。
外山
あー。ノスタルジーに足りないものと言うと、恐怖感だと思います。(自分の中では)自分も消えてなくなることへの恐怖が内包されてるんですよ。
橋野
それは生への執着だったり、あるいはある一定の場所に留まりたいというか土着への想いだったり……そういうイメージなんですか? 無常への抗いというか。
外山
生の執着か……。言い方はある意味正しいけど、生き物としていずれ死んでしまうのは仕方がないみたいな意識があって。どちらかと言うと、(死ぬと)なかったことになってしまう、自分がいた意味すら喪失するんじゃないかということが怖いんだと思います。本能的に考えると死ぬことは怖いけどしゃあないというか、さすがに全員に振りかかることですからね。ありとあらゆる生き物に。それは受け入れざるを得ないんですけど、なかったことになる寂しさというかね。
橋野
あー……。
外山
きっと覚えていてほしいんですよ。自分にそういう意識があるから、もの(自然物や人工物など)からもそういう感情を受け取ってしまう。写真の1枚でもいいから残してほしいと言われている気がする。
橋野
それを聞いてから『野狗子』をプレイすると少し感じ方が変わるかもなあ。
外山
うん。『野狗子』は10年、20年後とかはヴィンテージ性が上がってると思うんですよ。
橋野
どういうことですか?
――20年後にはもうない風景みたいなことでしょうか。
橋野
ああ、なるほど。そういうことか。
外山
はい。当時の残り香みたいなものを映し取っておきたかった。
橋野
写真に残しておきたい気持ちと似てますね。
外山
似てます似てます。すごく大きな動機のひとつで、じつは自分、若い頃に旅行とかできてなくて、圧倒的な憧れがあるんです。
橋野
旅行とか、いろいろな光景に?
外山
昔の九龍城があった頃の香港を飛行機がすれすれで飛んでいたと言うじゃないですか。その場にいて「うわっ」って体感したかった。自分もそのときから生きていたんだから、何かの間違いで「そこにいれたらよかったのに」という悔しさがひとつの動機です。せめてゲームの中で体験してみたい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a5de53d780910047cfa7d3c72dbbfd70e.jpg?x=767)
『野狗子』には1990年代頃の猥雑としたアジアのような場所も登場する。
橋野
なるほど。それでタイムリープなのかな?(『野狗子』にはタイムリープのような演出がある)。
外山
タイムリープはまたちょっと別で……。
橋野
それは違うんですね。すいませんでした。
一同 笑
それぞれの“チャレンジを”お互いにどう見ている?
――外山さんの目に、『メタファー』はどういうふうに映っているのでしょうか。
外山
『メタファー』は……う~ん。
橋野
PVは見ました?
外山
見ました。あんまりネタバレを食らわないように、おずおずと。「また不思議な作品を作ってるな~」って思いましたよ。それこそ『キャサリン』のときもまったく何だかわからなかったけど。今回は『キャサリン』のときよりは情報公開をしているのに、 ある意味もっとよくわからない。底が知れないですよね。
橋野
ふつうの……RPGです。
外山
やめてくださいよ、そういう使いにくい言葉(笑)。
――いわゆる“橋野流の王道ファンタジーRPG”みたいな情報は、前々から出ていましたよね。いまの映像や流れてる情報などを見ると、外山さんが想像されていたものと比べて、やっぱり違うなと感じましたか?
外山
最初のティザービジュアルの時点では、なんだろう、いまよりは“ファンタジー”をイメージさせるような雰囲気があったと思う。
橋野
ですよね。ビジュアルが固まっていなくて(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
『メタファー』のビジュアル的な印象は、いわゆる“一般的なファンタジー”とは少々毛色が異なっている。
外山
その後、実際のゲーム映像を絡めて開示されてきたときの印象は、正直、最初のイメージとは違うなと思いました。わりと現代っぽいけどよく見ると違うな、やっぱりファンタジーだな、という感じ。でもそこには、何かに寄っていないファンタジー作品があった。よくやるなあと思いましたよ。
僕もかつて『GRAVITY DAZE』を作ったときは、無国籍・無時代みたいなことを提唱していました。参考がないものを作るのは難しいんですよ。スタッフに「今回はあの感じで」とお願いできないから。「これはいったいどういう旗振りでこの世界を構築したのか? どうやったんだ?」と疑問でした。
橋野
特別、どうもしてないですね。
外山
いやいやいや(笑)。
橋野
たしかに初期の頃は、ド・ハイファンタジーの設定も検討してました。ドワーフやエルフが出てくるような。
外山
最初はそういうイメージから入られたんですか?
橋野
トールキンの『指輪物語』も改めていっぱい見ましたしね。そうとう初期のころですけど。副島さんにもたくさんスケッチしてもらって、でも“ふつう”なんですよ。自分たちならではのイメージになってこない。「もっとキャラ立てはこうであるべきだ」とか、「この部分は案外こだわらないほうがいい」などと話をしていく中で、だんだん自分たちの好みの形に変わっていきました。ただ、予定外の道に入ってしまったという印象はなくて、作りたいものをやってきた結果、こういうテイストに落ち着いた感じです。
――いちばん始めの作りとしては、いまの『メタファー』の雰囲気ではなかったんですね。
橋野
いわゆる完全王道・伝統的ハイファンタジーへの憧れはあったので。ただ、伝統的な形式にこだわってしまうと、自由なアイデアが出にくかったんですよね。もたないというか、スタッフもノッてこない。これが半年や1年で完成するならいいんですが。
――作っていてもあんまりモチベーションが高まらない、と。
橋野
すばらしいファンタジー作品は、もうまわりにいっぱいありますから。伝統的なものよりも、我々ならではの幻想の捉えかたをまず大事にして、そこだけはブレないように注意しました。あとは、まぁ……なりゆき任せです。
外山
すでにあるものをやってもしょうがないじゃない、というのはわかりますね。
――ということは、制作中に一回リセットしよう、みたいなタイミングがあったわけですね。
橋野
そうですね。表面上は「これが王道」と言われているかもしれないけど、“ファンタジーをちゃんと現代人のために描く”っていう根っこさえ変えなければ、ほかはわりと自由な発想でいい。たぶんそれがファンタジーの本当の魅力なんだろうなと気づいたんです。
いろいろなファンタジー作家さんと話をする中で、最初はそのジャンルを作るための定義とかを皆さんが守っていると思っていたけれど、なんだろう……それぞれに自由に作品を作られていると目の当たりにしたんですよ。そういうこともあって、頭でっかちなこだわりがだんだん取れていきました。
外山
ちなみに、ユーザーさんからの反応で、「これはファンタジーじゃない」、あるいは「ファンタジーだ」とか、そういうことを言われたりしました?
橋野
ファンタジーじゃない、とは言われなかったと思うけれど……。外山さんの印象の通りで、「思ってたより現代的だ」という声はありました。幻想の捉えかたの部分や、旅の捉えかたなどにこだわって作っていたので、ほかの部分はかなり自由にチームのノウハウやイメージを使えたんですよね。
新規タイトルということもあって、僕らの作るファンタジーがこういうテーマを守らないといけない、という決まりも固定観念も、まだないじゃないですか。そこは楽でした。『ペルソナ』のときはそれがあったから、ここまで変えてしまうと違うとか、IPとしてのアイデンティティーがどうだ、みたいな話になっちゃって。新規のゲームは、そういうのがないが強みですよね。
――なるほど。『野狗子』も新規IPですし、そのあたりの感覚は外山さんも同じでしょうか?
外山
んー、こういう質問をしたのは、『野狗子』をメディアに出したときの反応で、変に誤解をされてもイヤだから、アクション性をはっきり前面に出したら「これはホラーじゃない」みたいな言われかたをすることもあって。
でも単純に、怖がらせたり脅かせる部分に注力しているわけではないので、そう感じるかもしれないけど、自分としては『野狗子』はホラーであると思っているんですよ。作品に向き合ったときに心がどう動くか? という部分で必要なものは込めたと思っています。
あんまり踏み込むと危ないけど、ホラーファンの方って、熱心さも新しい作品を求めるジャンル愛もありつつ、保守的なところもある。もう少し信用してくれないかなあ、と思うこともあって。ファンタジーもそういう反応がそうとうあるだろうなという予想ですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a6c8cc684d2bf9a7a31ddbaee4d23f41c.jpg?x=767)
外山
実際には正解も何もあるはずがないんだけど、「ファンタジーとはこういうもので~」という声は意外となかったのかなって。
橋野
僕らは初めてファンタジーを作るから、「ファンタジーがこうあるべき」という感覚がたぶんないんですよね。イチから考えたので、ファンタジーをこういうふうに解釈しました、というのがゴールなわけです。
外山
ファンタジーってなんなんでしょうね。そういう意味で言うと『GRAVITY DAZE』もそうとうの割合で空想世界だし、いわゆる電気とか現実のテクノロジーと隔絶しているからファンタジーかなと思うけど、「いやいやいやいや」となるのもわからなくもない。その壁を作っているのはいったいなんだろう。
橋野
どこからがSFなのかとか、ジャンル分けがあるじゃないですか。「このアイデアならファンタジーでいける」じゃなくて、僕の場合は「ファンタジーを作ろう!」から始めちゃったんですね。何を押さえればファンタジーなのかわからなくて、たくさん調べました。
古い本で「ファンタジーとは、いまこの生きている現実が、べつにこの現実じゃなくてもいいと確認をするためにある」とあって。それってすごくハッとしたし、そこに立ち返りたい。現実生活で抱えている問題を束の間忘れるために幻想があるんじゃなくて、いま生きているこの現実を、すぐには無理かもしれないけど、変えられる。物理的にじゃなくて、意識的にでもいい。その確認をするためにファンタジーというものはずっとみんなに愛されているんだと。無意識の中に「この現実は現実じゃなくてもいいんじゃない?」とみんなが思ってくれているのだとしたら、それはすごく喜ばしいというか、ワクワクする。そこだけです、こだわったのは。
外山
プロモーションが本格的に展開され始めてから、「これファンタジーなの? 思ったよりめっちゃモダンだな」ってちょっと思ったんですよ。その後の公開された映像などをいくつか見た中で言うと、おっしゃった通り、現実とはぜんぜん違う世界でも社会が形成されていて、その中で葛藤がある。そういうことを描いていく構造なのがだんだん見えてきて、これはファンタジーだなと感じたんですよ。見れば見るほどファンタジー。どんどんそう思えてきちゃって、そこがおもしろい。異世界での人の振る舞いを描けているのがすごいんだなと。
橋野
ありがとうございます。そうだといいんだけど……。
――『メタファー』はまだ体験版しかプレイしていないですけど、ファンタジーなのに何か生々しさを感じます。
橋野
どうでしょうかね。
外山
あると思いますよ。人の振る舞いって、人が人であるゆえに変わらないというのを最近ぼやっと考えるんです。すごい雑談していいですか?
橋野
どうぞどうぞ。
外山
AIに「いろんな物語での王様は子どものころは絶対的な権力を持ったすごい人と思ったけど、現実を見ると違うよね」と聞いたら、「そうですね」みたいな反応を返してくるんですよ。
橋野
たしかに、「仰る通りです」とか言いそう。
外山
そうそう。「王様は絶対ではありません」ですとか。人ってやっぱり生き物なんですよ。猿とか犬にも似ていて、社会や群れを形成する仕組みとして王様が存在する。生き物として全然違うけど、根本的な世界観で言うと同じものを握っている。これもおもしろさのひとつ。人間の限界を感じて悲しくなるような。戦争の原因とかもそういうところだったりしますよね。『メタファー』のPVを見て「なんか違うな。全然知らない話なんだな」と思っていたら、「あー知ってるわこれ」と収束していくファンタジー感、人間のドラマだなという感覚を受け取れたんですね。全然違う世界でも、人間は人間として共感する振る舞いがあることを描いているのではなかろうか、と思いました。
橋野
……こうご期待!
一同 笑
『ペルソナ4』の世界的ヒットで与えられた勇気
――橋野さんは『野狗子』の映像を見てどう感じましたか?
橋野
バンバン惜しみなくアクションシーンがあるという話があったので、そうなんだなと思いながら映像を見ました。外山さんが作るホラーゲームで、もしかしたら求められるわかりやすい形というのは『SIREN』のような……ジャンルで言うとなんだろう。ホラーアドベンチャー?
外山
難しいですね。まぁホラーアドベンチャーで。
橋野
そこにけっこうアクションを入れたということで、純粋にそこに興味がありますよね。なぜアクションを入れないといけなかったのか。外山さんだったら意味もあるかと。ただのアクションでもないようですしね。詳しいゲーム内容はPVしか見ていないのでわからないのですが。
イヤな気分を味わいながら、気持ちよさも味わって、気持ちよく感じる自分を怖がってほしい、みたいな。“自分で操作するアクションホラーゲームである”という意味が出てくる計算なのかな。
外山
PR用の話より踏み込んだ話をすると、いくつもレイヤーがあるんですよ、考えることに。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a34d96fa14705d2a04d94176e3449c28d.jpg?x=767)
外山
その中でひとつは、業界の形態が変わって、単純に予算と時間がかかるようになった。ホラー作品のスイートスポットと主力のエンタメ部分が若干乖離しているんです。いまはホラーらしいホラーは、荒削りでもアイデアで驚かせられるし、低予算でも成立します。最近では『8番出口』が好例ですよね。個人で、アイデアひとつで、まったく新しい切り口。
でも我々は、ホラーかエンターテインメントかで大まかに分類すると、エンターテインメントを作らなければいけない規模なわけです。個人ではなく組織ですからね。となると、ホラーのスイートスポットを狙うのが難しい。
――なるほど。
外山
今回この切り口で僕が意識したのは、 やっぱり日本のエンタメなんですよ。とくにコミック。青年誌にホラー的な世界観があったとして、主人公は滅多に死なないけど、大事な人が死んでしまうとか、緊張感や恐怖感のあるドラマ性。それはホラーに近いエンタメだなと思っているんです。そのエッセンスが、僕らの規模におけるエンターテインメントかつホラーの最適解。ゲームでそこをやっている人はいないから、挑戦してみてもいいんじゃないかなと。
橋野
チャレンジなんですよね。
外山
うん。でも「これ、もしかしたらいけそうだけど誰もやってないなあ、じゃあそれやるか」みたいな感じだから、 あんまり前向きじゃないかもしれないです。「これ絶対おもしろいね」じゃなくて、「みんなが見逃してるここを拾い上げたらもしかして……」みたいな、けっこうギリギリの気持ちで毎回ゲームを作っている。今回もそうですね。
だから正直な話、PVを最初に出したときは、「これホラーではないんじゃないの?」みたいな反応が、まずは多かった。その後にストーリートレーラーを出して、ハンズオンの映像を出す中で、だんだん理解が広まりました。先ほどの話と通じることですが、ホラーファンの“愛してくれるけど保守的”という考えかたもいいけれど、「なるほどこれもありだな」と気づいてほしいというか。
――そう思ってくれるだろうという自信はもちろんあるわけですよね? 遊んだときに「やっぱりこれホラーじゃん」と。
外山
はい。とくに、いままで典型的なホラー作品は自分の範疇ではないと思っていたような方、さらに若い方に……。
橋野
怖がってほしい?
外山
んー、「これはひょっとしたらおもしろいんじゃないか?」って気がついてほしいな、と(笑)。
――おふたりとも商業的に成功させる必要があるじゃないですか。スタッフを抱えて何年もかけてゲームを作られているので。ピュアに自分たちがやりたいことに突き進むべきなのか、エンタメとしてより深く成立させるために何か別のものを取り入れるとか、最終的に成立させることのせめぎ合いとかもあると思います。そういう意識に悩むことはありますか?
橋野
僕は、あまりないですね。
外山
ないんだ!?
橋野
悩むとしたら、お客さんに喜んでもらいたいんだけど、自分が勘違いしていて、全然喜んでもらえなかったときかもしれない。しかもそれがちょっと変な設定だったりした場合、いい意味で驚いたのか悪い意味(期待してなかった)なのか、線引きが難しい。そこで悩むことはあるけど、商業作品を作ってる意識はすごく強いので。芸術家では全然ないから。外山さんはどうなんですか?
外山
僕は、ゲーム業界が大きく変わった20年ぐらいの中で注目すべきは『ペルソナ4』だと思うんです。日本のゲームファンに突き刺さりつつ、あの辺からでしたよね、海外にもコアなファンができてきて、その熱狂が日本に伝わるようになってきた。任天堂さんのゲームなんかは海外にもたくさんファンがいるけど、そうではなくて、日本っぽいシチュエーションを描きつつ、海外にコアなファンがつき始めたんだと驚きを感じたのが『ペルソナ4』だと思っていて。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a48da9143532fc800c5abbaa63f703fc9.jpg?x=767)
外山
何が違うのか。キャラクターを見ると、副島さんのデザインはもちろん魅力的だけど、「日本のキャラクターっぽいよね」と言われると思います。当時は日本と海外では好まれるものがそもそも違うとも言われていたけど、そこが刺さったのはやっぱり普遍的な何かを描いていたから。プレイした人が「これまでのものとは全然違う」と。彼らにとってはファンタジーですよね。違う世界の話だけど自分は共感できる。そういうことをしっかりやっているゲームは伝わるんです。そこは本当に日本のゲームの転換期だと思っているんですよ。
――海外ウケがいいように作ろうとか、おもねる必要はないんだと。
外山
そうですそうです。その直前が、日本市場の限界だから海外にウケるものを作ろうとして、でもうまくいかなかった時期なのかな。あの中で『ペルソナ4』は、海外に向けようってスタンスじゃないんだけど、きちんと伝わって。あれはすごく心強かったといま振り返っても思いますね。
――より多くの皆さんに遊んでもらえるゲームにする必要は当然あるけど、だからといって何かにおもねるわけではなく、自分たちの作家性を出していく。
外山
その延長で言うと、グローバル化はどんどん進んでいきました。ありとあらゆる人に注目してもらうのはもうほぼ不可能だし、そういうことを意識する必要はない。ただ、裾野が広がっている中で、自分たちらしいメッセージを受け取ってくれる人たちにきちんと真正面から問いかけると、何と言うか、商売にはなる。それは大事ですよね、つぎを作るためには。
そういう意識転換は最近もありました。『野狗子』ははっきり言ってニッチだと思います。ニッチだけど、普遍的にこういうのが好きな人たちがいると信じています。
――世界中にいるぞと。
外山
はい。世界中のニッチを集めれば、僕らがつぎを作れるくらいには届く(売れる)だろうという自負はあります。
橋野
送ってくださいね。
外山
何を?
橋野
ゲーム。
外山
送りますよ。当たり前じゃないですか(笑)。
橋野
「買いますって言ってよ」って感じですよね。
一同 笑
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a713027473e3dd295a527c5503fdc53b1.jpg?x=767)
外山
くり返しになりますけど、『ペルソナ4』は本当に衝撃でしたよ。自分たちが作るものが海外にも刺さるんだっていう、どんだけ心強いメッセージだったか。
橋野
作ってるほうはもう必死です。当時は日本のユーザーの方をまずは意識して作ってましたからね。でもやっぱり励みになりますよ。海外のイベントに行っても、日本と海外のファンの受け止め方に違いはない。これがおもしろいだろうと作ったところをそのまま受け止めてくれる人がちゃんといる。その方はたまたまコアなファンなのかもしれないけど。安心感、信頼……なんて言ったらいいんだ。彼らに支えてもらってるみたいな感じなのかな。だからいまも続けていられるってのはあります。
――日本のメーカーさんが作るゲームは、日本の市場で売ることがまず前提という時代を通ってきたじゃないですか。いまはSteamもあってコンソール機でもダウンロード販売が増えて、日本のゲームやIPが好きな人がワールドワイドに広がっている。一昔前を考えるとちょっとびっくりしますよね。
外山
まあ意識してないかなと思います。自分の息子はもう成人しちゃったけど、小さかった頃は『マインクラフト』があって。でも彼らはこれはどこのゲームとかいちいち考えないですよね。 任天堂さんのゲームを遊びつつ、『マイクラ』めっちゃおもろいなとか。どのメーカーのゲームだ、どのクリエイターの作品だっていうカテゴライズは意味がなくなっていくのかもしれない。
周囲の反応の受け取り方の変化
――『野狗子』は最初の立ち上げから終わりまで3年半ぐらいで迎えられたんですよね。外山さん的にはスケジュール通りに進められた実感はありますか?
外山
正直な話、スケジュール通りというか、「死守しないと死ぬ」と思っていたところから入ったプロジェクトなんです。
橋野
ボーカゲームスタジオとしての第1弾を、このスケジュールで絶対に出すのだという決意?
外山
スケジュールだけじゃないですね。
橋野
予算?
外山
そうです。端的に言うと予算。ただ、たとえば予算が倍あったからといって、できることも倍になるとは限らないじゃないですか。最初は最適解をめちゃくちゃ考える必要があったんですよ。
うちの陣容でいうと、このメンツでいっしょにやる強み弱みはこれ。予算はこれぐらいある。あらゆる条件を突き詰めた中で、「こういうゲームを作りたい」よりは「勝ち筋としてこの選択しかないな」みたいなことを見極めなきゃいけない意識がすごく強かったです。
ぶっちゃけスタッフもね、もっとPS5の世代に特化した先端的な表現をやりたかったと思うんですけど、当然(制限があるから)幅は狭まります。プラットフォームも複数あって、そこにふさわしいアセットを使わないといけない。いろいろなバランスを見極めて、かつ勝負して、それで凡庸なものを作ったらしょうがない。勝負できるポイントを見極めていくのは地味ですけどいちばんしんどかったと思います。
――最初の頃ですか?
外山
わりと初期です。数年後を予見するのもたいへんでした。Unreal Engineが新しくなって、「最新世代のルーメンとか新しい機能を使いたいよ」ってスタッフは言うけど、うーん……。でも、なるべく間口を大きく、幅広いお客さんにリーチするものを作って、そこがうちのスタジオの入り口になるようにしようと。単純な個人の想いというよりめちゃくちゃ議論して、そういうところに行きつきました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/aa509d92dac6bfe16bb01293fe794897e.jpg?x=767)
――『メタファー』はけっこう時間がかかったと思います。橋野さんの中ではどういう風に思っていますか。
橋野
最初の数年は準備。ほかのゲームを作りながら人をさらに集めたりとか準備してたので、あんまり動いてなかったです。それに加えて、コロナとかもあって。
――たしかに。そこが全部重なってますよね。
橋野
そうですねー。ゲームの中身はもう去年(2023年)にあらかたの調整は終えていて。今年に入ってからはマルチプラットフォームの対応が中心です。もちろんギリギリまでいじったのですが、まだ発売されてないのか感もあって、気持ちはいつもと違いますね。
――自分の手を離れてからけっこう時間が経ってるみたいな。
橋野
昔はインタビューを受けながら、「あそこバランス調整しなきゃ」とか考えることがあったんですけど。いまはもっと前の段階でゲーム内容自体の調整が終わってるので、まな板の上の鯉みたいなんだけど表面が干からびてる。やっと出せる。長かったー。
――いままでの橋野さんのタイトルって、日本で発売したあとに海外展開をされていましたよね。
橋野
日本でまず発売して翌年海外に、という流れが基本でした。マルチプラットフォーム化もそうですね。ローカライズも途中から全部いっしょに。
外山
情勢が変わりましたよね。とくにSteamの浸透がでかい。昔はほんともう発売から1ヵ月ぐらいが勝負だったけど、出してみんなが知ってから、地道な努力でよくなっていく。これはPCからもたらされた新しいおもしろさだなと。
橋野
僕はこれからですね、まだ、そういう経験が少ないので。
外山
僕も同じです。
――昔よりもユーザーの声がダイレクトに届く時代になってるじゃないですか。そういったところは作り手側からするとどう見えていますか?
橋野
あんまり意識しないようにはしてます(笑)。
外山
え、すごい。
橋野
もちろん発売直後とか定期的に様子は見ますよ。でも、見たところでもう調整できないので。調べなきゃいけない時期に一気に調べますけど、張り付いて見るのは精神衛生上よくないから。ほんと仕事で見るみたいな感覚ですよね、発売されちゃったら。
外山
ずっとエゴサするとか、そういう風なことはあんまりしない?
橋野
僕はないですね。SNSもやってないので。正直に言うとプロモーションにもあんまり出たくなくて。けど、新規IPだからかな、語ってくださいっていうお願いが多い。『ペルソナ』のときより、かなり多いですね。
――橋野さんがATLUS Exclusiveでご自身で解説されたり、登録お願いしますとまで言っていたり、「橋野さんがここまで……」って思いました。
橋野
いや、僕も思いますよ。
外山
思ってるんだ。
――しかもだんだんうまくなっているという。
外山
Summer Game Festでステージありましたよね。客席から見てました。
橋野
ほんとに!?
――すごい堂々としてましたよね。
外山
「おお~、がんばってる」って。
一同 笑
橋野
そういう経験ができるのはおもしろいですよね。新規IPだととくに。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a263a9413af314dbed98341dcaf5fff2b.jpg?x=767)
――外山さんはどういう風にユーザーに向き合ってます? 声は意識されますか?
外山
変わってきているのかなあ。たしかに従来は、そんなこと言われてもなぁ、つぎつぎ! っていう感じでした。『野狗子』では、どうだろう。サービス型のゲームじゃないから細かく調整調整ってわけじゃないでしょうけど、話はちゃんと聞いて、「あ、これなら活かせるわ」みたいなのがあったらぜひ糧にさせてほしい。(ユーザーの声を)追っかけようとは思ってます。
――これまではどうでした?
外山
うーん……。「ですよねー」と思うことはあっても、そこにかける予算がないとか、仕組み上ちょっと対処が……みたいなことがあったりも。でも独立スタジオだと、どうしても気になるから何とかしようという判断は自分でできるのかなって。
橋野
外山さんって、ご自身のチームで作ったゲームを、たとえば3年ぐらいやってて、完成間際にもプレイしますか? 僕の場合は3年以上かかってるからなおさらなんですけど、 新鮮さはないわけですよ。お客さんと同じ感覚では当然楽しめない。全部わかってるし、むしろ粗ばっかり目立つみたいな。外山さんはどうなんでしょう。自分のゲームを完成間際に「おもしろいなー」って遊べます? ピュアな感情で。
外山
そう感じられるようになるのはだいぶ後ですね。後で人の実況見て。
橋野
やっぱそうですか?
外山
「あれ、思ったよりおもしろいなこれ」って。
一同 笑
橋野
実況を見て実感するっていう。それはありますよね。
――遊んでる人の反応を見て安心するみたいな。
橋野
昔は実況プレイとかあんまりなかったんで。さっき『ペルソナ4』の話がありましたが、たまたま再生してみた実況プレイで、「おもしろそうなゲームあるな~!」と思いながら見てました。
一同 笑
橋野
おもしろそうにしゃべってくれてるからなんですけど、「ああ、これ自分たちが作ったんだな」と実感するときもありますよ。時間が経って忘れてるというのもあるでしょうけど。
外山
でもね、『野狗子』に関して言うと……。
橋野
盛り上がりそうですか、実況プレイ。
外山
盛り上がるといいな~。
じじいのシナリオに沿った予定調和がいちばんやばい
橋野
(実況されるかどうかは)けっこう意識されたんですか?
外山
いやもう全然全然。もう必死だから。僕の歳も50半ばなので、 自分の感覚がいちばん信用ならないなっていう気持ちがすごく増してるんですよね、年々。
橋野
年々?
外山
自分はおもしろいと思うけど、世間は「古っ」と感じるかもしれない。今回はそうとう若いスタッフの感覚を重視しています。破綻していないようなら意見をどんどん採用していく。自分の原案から離れてない中での新解釈が乗ってくるのは大歓迎。
これまでも自分がおもしろいと思ったわりにウケないなってことはありました。とくにアクション。自分にとってちょうどいいと、もっさりしてると言われる傾向があるから。アクションは若い人の感覚を重視して、よかったと思います。スタッフのモチベーション的にも。
――意見が採用されるわけですもんね。それはうれしいでしょう。
外山
自分としては、拾い上げるというか「こことここのお話のブリッジをどうすんの?」みたいなところはまだ活躍の場があるなと。
橋野
なるほど。
外山
今回はちょっと特殊な作り方をしました。(台本で言うと)2、3行ぐらいのシチュエーションでアクションのおもしろさを軸に考えてもらって、話がどっか行っちゃいそうになったら「ここにこんなデモを挟んでこうしようぜ」みたいに自分が介入する形を取ったんですよ。そうとうイレギュラーな作り方だなと思いながら。
橋野
難しい話だなぁ。スタッフさんが書いたものに演出的に手直しをしていくみたいな感覚ですよね、きっと。
外山
自分が雛形を作って、アクションで膨らませてくれと。シナリオを気にしてアクションを当てはめるんじゃなくて、ここにこういうアクションほしいよねと詰めていった結果、シナリオがすっ飛びそうになってるところに「この部分にカットシーンを追加してくれ」と自分が入る。おかげで予定調和にはならなかった。じじいのシナリオに沿った予定調和がいちばんやばいと僕は思ってるので。
橋野
じじいのシナリオにありがちな予定調和?
外山
シナリオに沿って周りを組み立てると、どっかで見たような展開になるじゃないですか。
橋野
あー、そういうことか。
外山
そうなっちゃうのがまずいから、箇条書きに対して膨らませたものを最低限締めるというアプローチ。
――外山さんとしては腕が鳴ると思ったんじゃないですか?
外山
「うおおおおおおお!」って。なんか楽しかったです(笑)。
橋野
楽しかったですか? この3年間。
外山
正直おもしろかったですよね。無理難題が来た感じで。「ここがまったく意味わかんないんですけど」みたいなことも聞かれるし。設定を変えていいのは僕だけなんですよ。そう決めているわけじゃないけど、どうしてもそうなっちゃう。逆に気づかされることも多いですよ。
みんながつまづいたということは、予想してなかったけど、何か問題があるはずなんです。要素を整理していくと、この登場人物がこうだからこうなったんじゃないの? と気づく。ここにこういうセリフを加えたら収まったぞ、みたいな。
橋野
設定を変えたぞって。
外山
設定も性格も変えて。収まったときは予定調和とは違う意外性が生まれるんですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/aaa21591deb5b9d6ed0bdba2bbdd81347.jpg?x=767)
――外山さんは自分の年齢的にも自信がないところは若手に……と仰いましたけど、橋野さんはそういうことはありますか。
橋野
自分はあんまりないかな……。僕も年齢が50いってるんですけど、だからこそ口を出さない方がいいとかは、必要以上に考えないようにしています。けど、単純に苦手なものがあるんですよ。
たとえば、自分はアクションゲームがめちゃくちゃ苦手で。『メタファー』も一部アクション性を入れてるので、そういうとこはもう、言わない。コンセプトの筋が通ってるかどうかしか見ないようにしています。
外山
アクション性とかスピード感みたいなものは、もう得意な人に任せると。
橋野
好きじゃない人が作ってもいいものにはならないと思うから。代わりに、苦手なプレイヤーの目線でやり過ぎていないかチェックしますけどね。
外山
そこはショート動画世代ですよ。もうリズム感が全然違う。すっごく思いました。
橋野
そういうのはありますよね。
外山
ストレスの感覚が違いますよね。ゲームの基本はストレスをかけて解消させてスカッとさせることだけど、そこの塩梅が、若い子と僕らはだいぶ違うのはさすがに自覚してます。
橋野
よくわかってないのに知ったかぶりでハイハイ言うようになるじゃないですか、ディレクターやってくと。音楽もそうですね。好きだから趣味で聞くけど、制作については詳しくないんで、もう任せちゃいます。
――そうなんですね。
橋野
もちろんその後で(関係者などから)反応が来たら、改善の必要がある情報が挙がってるよってことは伝えますけどね。
外山
ミュージシャンは違いますよね。目黒さんとか山岡さん(※5)は気が若い。いい歳なのにおしゃれ。
※5:山岡晃氏。『サイレントヒル』シリーズの楽曲を手掛けた作曲家。『野狗子』BGMを担当している。――やっぱり山岡さんや目黒さんはつねにチャレンジしていて、いいものを上げてくるなと感じていますか?
外山
あのお二方はとくに。ナチュラルに感性が若い人に近しい気がします。
橋野
20代とか30代でディレクションすると経験が浅いので、よくも悪くも勘違いできるわけですよ。若気の至りじゃないけど。本当だったら突っ走らないところを突っ走っちゃう。で、強引に体力で形にする。やっぱ若い時代にしか作れないものはありますよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a6c31aefc08c6e9a1758735706afe0fee.jpg?x=767)
外山
あるある。それは確実にあります。
橋野
そういうのはいまは作れないなぁ。知恵がついたから先々が予想できちゃうようになって、破綻しそうな藪には入らない。蛇がいることはわかってるから。シリーズをやってるとなおさらですよね。よくも悪くも経験があるから。外山さんが新規IPにこだわってるのは若さを保つためにやってるとこもあるんですか?
外山
ほんとのことを言うと、シリーズがずっと続くほどは売れないので。
橋野
そういうこと言う?(笑)
外山
僕の作品ってなんかインパクト重視なんですよ。
橋野
すごいかっこいい芸術的な話をしたと思えば、急にビジネスの話。照れなんですか、それ。
外山
そういうわけじゃないですからね。いやでも正直、毎度めっちゃ売れるんだったら全然シリーズやってますよ。
橋野
そういうことなんですね、ボーカゲームスタジオは。そういうことなんですか。ヒットしたら当然続編も……。
――いま後ろのほうから「それはあると思います」と聞こえてきましたね。
外山
そりゃもうヒットしたら喜んで!
橋野
でもヒットしても続編作んない人もいるじゃないですか、世の中には。
外山
いるいる。上田さんね、上田さん。
橋野
ああ、たしかに。
外山
かっこいいんですよ、あの人。
すでにつぎのプロジェクトは走り出している
――ちょっと気が早いんですけど、新しいスタジオを作られてその第1作目がもうすぐお互いリリースされますよね。 対談の前に『野狗子』の解説をお聞きして、その資料の中に“つぎの企画”みたいな英字があったような気がしたんですけれども。
外山
はっきりしたのは、うちはあら削りだけど、他所にないものを作ることが得意。そこをめちゃくちゃ意識してたわけじゃないけど、最近やればやるほどそういうことだなと自覚は強まっています。いまの使命は、“自分”ではないですね。スタジオ全体、というより若い人たちでしょうか。僕らが若い頃のようないい加減な感じじゃなくて、真面目なんですよ(笑)。実力があって期待しているけど、いい意味でもう少しいい加減でもいいんじゃないかな。言い方が難しいんですけど。
橋野
それ、僕ら世代の全員を不真面目に定義してます?
一同 笑
橋野
たしかに不真面目ではあるんだけど。
外山
だってほら、昔は炎上とかなかったじゃないですか。いまの子たちはやっぱめっちゃ気にするし、どう見られてるのとか。
――たいへんだと思います。でも、そこを解き放ちたいということですか。
外山
はい。ケツを持つからやってみてほしいな。わりと必死に伝えているつもりです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a5f440ac3d8be8e0388f8cc5a949ea440.jpg?x=767)
――橋野さんは、アトラスではなく橋野さんご自身として、『メタファー』のつぎにどういったものを作ろうと考えてらっしゃるんですか?
橋野
ああ、もう始めています。
――つぎの仕込みですか。
橋野
僕個人がどうとかって考えることはあんまりなくて。 アトラス全体を見て、いま自分たちのチームがどういうものを作るのがいちばんなのか。まずはユーザーさんが喜んで、その結果、会社も喜んでくれるかなっていう。いつも、そんな感じで動いていますね。
――それもまたすごく楽しみです。
外山
スタジオ・ゼロは『メタファー』のために作られたチームというわけではないんですよね。
橋野
アトラスという会社の中でファンタジーをやる軍団をスタジオ・ゼロと名付けましたけど、ユーザーさんにとっては関係のない話だと思うんですよ。いや、完全に無関係というのもよくないのかな。最終的には適材適所でおもしろいゲームを開発できたらいいでしょうから、あまりこだわりはないんですよ。
外山
橋野さんの中ではアトラスとスタジオ・ゼロの境目はどういう認識なんでしょう?
橋野
あんまりないんじゃないかな。「どういう会社ですか」って海外からのメディアから聞かれたことあるんですよ。ふつう、スタジオ○○って会社じゃないですか。別会社じゃなくて、新しい取り組みの場所として、スタジオ・ゼロって名乗ってるだけなんですよね。
外山
プロジェクトって感じなんですかね。『メタファー』=スタジオ・ゼロみたいな。
橋野
そうですね。発売したら解散するとかではないので、どんな作品を作るにせよ、チームで新たなチャレンジができるといいなと思っています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a1573ceb7e2f3779ca132f2ab426bd5d4.jpg?x=767)
――では最後に、ありきたりではありますけど、おふたりからファンの皆さんにメッセージいただけますか。
橋野
10月11日、アトラスとして長年かけたファンタジーRPG『メタファー:リファンタジオ』がようやく発売になります。楽しんでもらえるかどうかは本当にお客さんそれぞれだと思うんですけども、作りたかったものは、ひとつまとまったという手応えがあります。ぜひ手に取っていただけたらうれしいです。あと、翌月には親愛なる外山ディレクターの最新作も控えております。こちらもこうご期待。
外山
『メタファー:リファンタジオ』さんに続いて、ちょっと遅れて『野狗子: Slitterhead』が出ます。キャラクターのルックスとか絵柄は、ある意味真逆の作品みたいに見られるかと思うんですけど、根っこの部分でつながっている何かを感じると思います。日本のスタジオらしさが発露した作品には、こんなに振れ幅、多様性があることを見せられるような順で発売できるのはすごくありがたいです。両方の作品を手に取って楽しんでいただけたらなと思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a709907821bb66ef1a4da770e7edf519e.jpg?x=767)
対談の後半は少し趣向を変えて、ボーカゲームスタジオの一角のバーカウンターで撮影。話は尽きない。
関連記事
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a42c7d1dacdf2bccd572181a356e63745.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/af8ac6f514525efc19420efc6ff7b07a0.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a57f4d0c0667b136a86a32b5f77d6740b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/af30007f987e79e1f06c33e480267267a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/ab2a93fc6c49359fb18a9b6dbee3aa79a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a1c84ba46b6a85a54cceeb795fcea04bf.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a33133c93369138bed93d1e7956acc3a4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/aec7f76065b5c888c830bc5957aeca76b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a42ead9ec970ad4fec5eeebc510289ba6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a5de53d780910047cfa7d3c72dbbfd70e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a6c8cc684d2bf9a7a31ddbaee4d23f41c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a34d96fa14705d2a04d94176e3449c28d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a48da9143532fc800c5abbaa63f703fc9.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a713027473e3dd295a527c5503fdc53b1.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/aa509d92dac6bfe16bb01293fe794897e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a263a9413af314dbed98341dcaf5fff2b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/aaa21591deb5b9d6ed0bdba2bbdd81347.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a6c31aefc08c6e9a1758735706afe0fee.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a5f440ac3d8be8e0388f8cc5a949ea440.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a1573ceb7e2f3779ca132f2ab426bd5d4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20753/a709907821bb66ef1a4da770e7edf519e.jpg?x=767)