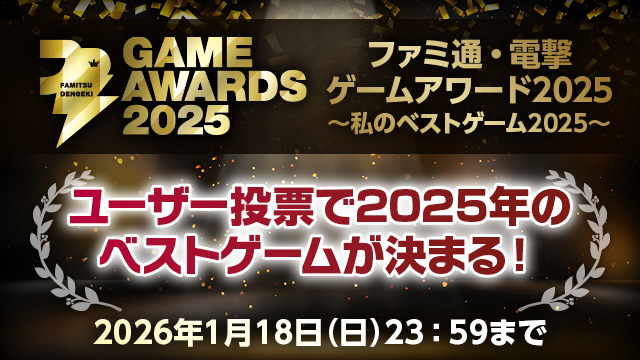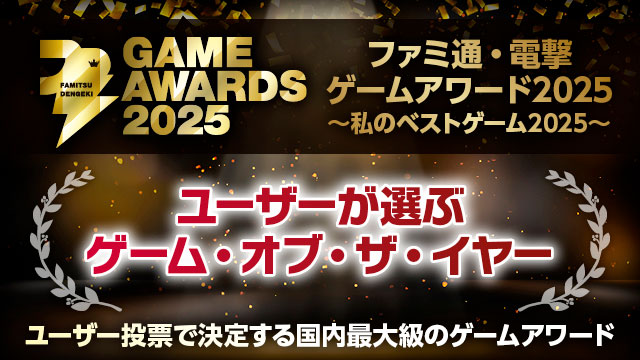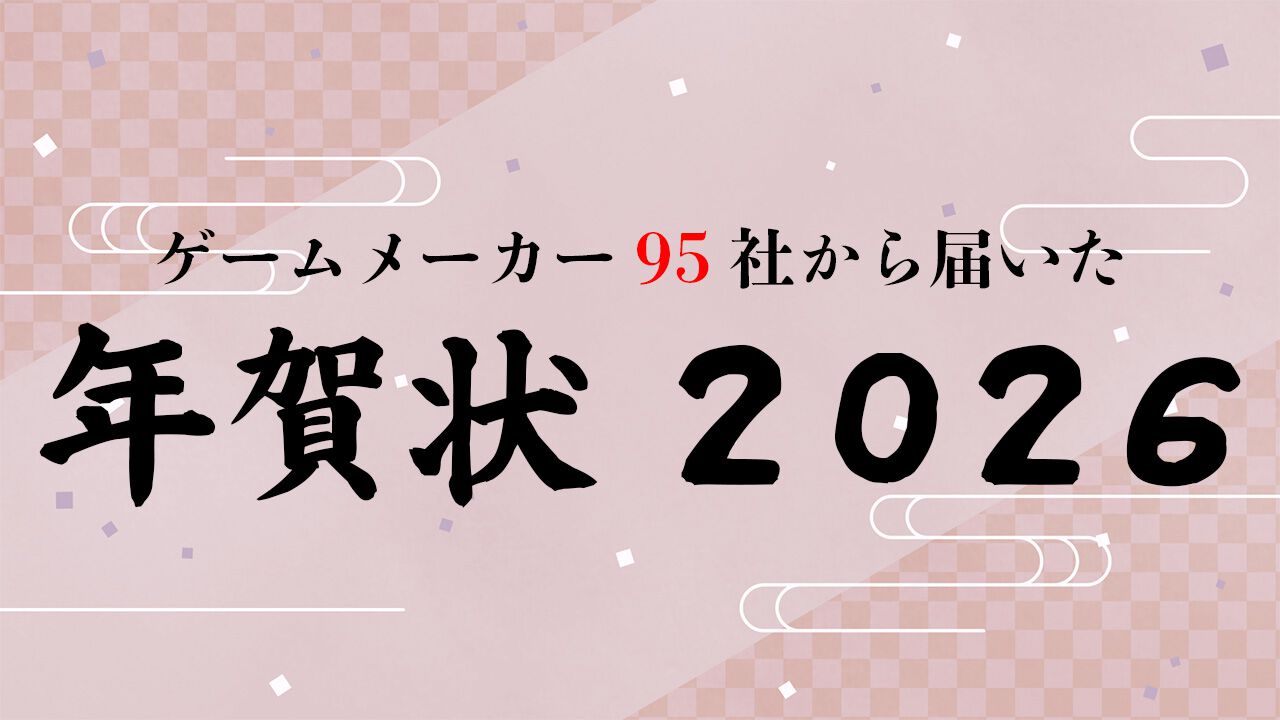あまりの人気で入手困難となっていた『 サイレントヒルf 』の小説版だが、沸騰する人気に応える形で急遽大量重版が決定し、2025年11月27〜28日ごろから書店に再入荷されるという。 サイレントヒル 』シリーズ最新作『 SILENT HILL f 』(サイレントヒルf)は、2025年9月25日(木)に発売されるやいなや、なんと発売翌日には全世界累計出荷本数が100万本を突破したほどで、現在もその勢いは衰えることなく、ファンアートも多数描かれたり、コスプレを楽しむといった思い思いのやり方で多くのファンが作品の世界にさらに浸りたいと願っているという、ホラーゲームとしてはとても稀有な状況となっている。 ひぐらしのなく頃に 』シリーズ作者の竜騎士07氏、アートには『 死印 』、『 NG 』のkera氏が参加するなど、スタッフにも新たな血が入った新しいストーリーは非常に高い評価と人気を集めている。出演俳優による実況配信も大盛況になるなど、Jホラーゲームが再び世界的に大きな話題を生み出すこととなった。 VIDEO
そんな小説版は、なんと発表段階ですでに書籍版も電子版もAmazonで1位になるほどの人気を獲得。ファミ通文庫編集部では前例のない異例の発売前重版が決定にいたったが、発売日にはそれでも足りず、SNSでも入手報告や買えなかったという声が相次ぐほどのベストセラーとなり、書店では売り切れが続出。現在、ようやく大量の重版分が店頭に並び、手に取れるようになった。
今回そんなゲームと同じく大ヒット作となった小説の刊行を記念して、岡本基プロデューサーと黒史郎氏の対談が行われた。小説の内容からファンの感想、そして刊行を受けての今後の『サイレントヒルf』への展望までが垣間見られた、作品への深い愛が滲むかのようなおふたりの対談となった。
岡本 基(おかもと もとい)
KONAMI所属、「サイレントヒル」シリーズプロデューサー。『サイレントヒル2』に続き、シリーズの新しい試みにも果敢に挑んで『サイレントヒルf』を大ヒットさせた。現在はさらなる新作群や、映画化など幅広い展開を準備中。(文中は岡本)
黒 史郎(くろ しろう)
1974年生まれ。神奈川県出身。2006年、『夜は一緒に散歩しよ』で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞。作品は、妖怪、怪談、クトゥルフ神話などをテーマにしており、リアルな恐怖と伝統的な怪談の要素を織り交ぜたもの。(文中は黒)
異例の発売前重版に続き
初版超え重版の大ヒット
岡本
はじめまして。お会いできて光栄です。個人的に黒先生の小説は読ませていただいていたので。
黒
こちらこそ、「サイレントヒル」シリーズの大ファンで、『 サイレントヒル2 』はリメイク版も遊ばせていただいていたので、今回こうしてお会いできてうれしいです。 岡本
ノベライズがとても好調だとうかがっていて、品切れが続いているほどの人気とのことで、よかったです。発売前から重版が決定していたうえに、さらに次の重版は初版を大きく上回る部数が刷られるそうなので、書店で購入できなかったお客様にも、ぜひ広く届いてほしいと思っています。
黒
自分としても、執筆させていただいた作品がこんなことになるなんて驚きの日々です。すべて本当に『サイレントヒルf』の力だと思って。すごいものに参加させていただけたんだなと実感しています。
岡本
黒先生の書いてくださったノベライズは、生みの親だからそう思うのかもしれないものの、読み終わった感覚が、とても好きなんですよね。たとえば、「本音をぶつけ合えたね」という雛子の凛子へのセリフにしても、やりとりを読んでいると、まさにふたりが本音をぶつけ合っているところに立ち会っているかのようで、文章からも、その気持ちよさが伝わってくるように感じるところなどからも、不思議な読後感があるなと思っています。
黒
ありがとうございます。あの場面は書くのが楽しみで仕方なかったところのひとつでもあるので、うれしいです。ふたりの喧嘩の場面は、僕もゲームを実際にプレイさせていただいた時点で、青春小説を読み終えたかのような気持ちよさがあって、「こんなふたりの喧嘩を文章で書けるんだ」と思ってニヤけたくらいでした。……喧嘩っていうか、まあ殺し合いなんですけど(笑)。
岡本
大泣きした後とか、大きく喧嘩した後の気持ちよさみたいなものがちゃんとあったように感じて、すごくよかったんですよ。
黒
岡本さんにそういってもらえるだけで、もう報われます(笑)。執筆中は、本当に楽しかったのですが、同時に悩ましいことでもあったんです。どうやってこの重層的で、複数の結末のある物語を一冊にすればいいかというのは、ものすごく悩んだんですよね。 結果的には、ひとつのエンディングを軸に、大好きで読んでもらいたいあれやこれやを詰め込む形にしたんです。ゲーム機を持っていなくて遊べない人にも、この『サイレントヒルf』という世界で感動した場面ややりとりを、できるだけ見てもらいたいと。
ミームになるほどの
キャラクターたちを深堀り
岡本
その気持ちは読ませていただいて伝わってきました。それに、まさにこれだけのボリュームと周回で変わる物語を小説にするという大変さは、相当なものだったと思います。ゲーム制作においても、ストーリー担当の竜騎士07先生のフルスロットルで個性が際立つマンガ的なキャラクター性という、まるで濃厚な豚骨ラーメンみたいな部分が、「サイレントヒル」という醤油ラーメン的な味わいと混じり合ったらどんな味になるのか……ちょっと予想がつかないところがあって、プロデューサーとしても苦心しましたから。マンガっぽくなりすぎても「サイレントヒル」シリーズから離れてしまうし、逆に実写寄りになりすぎても、竜騎士07先生の味が損なわれてしまうので。
黒
まさに豚骨醤油ラーメンを初めて発明するようなものですね。混ぜようとはなかなか思えない。
岡本
ええ(笑)。でも、今回はあえてそうした相反する要素を調整しながら作っていく中で発見があって。奇跡的なバランスで雛子っていうキャラクターが生まれてきたり、友達の咲子や凛子、修や狐面の男といった、これまでのシリーズにはなかったような味わいも出てきたりしたんだと思っています。
黒
とくに『サイレントヒルf』は不思議な感覚があって、竜騎士07先生のシナリオとストーリーの印象からなのか、どこかノベルゲーム的なんだけど、しっかりとホラーゲームでもあるという。僕も竜騎士07先生作品は大好きで全部遊んでいるので、ノベライズに当たっても、登場人物たちの魅力を損なうわけにはいかないと、細心の注意を払いながら書いていきましたから。
岡本
我々も、ここまでキャラクターが人気になると予想していたわけではないので、いま多くの方に好きになってもらえているのはすごくうれしいし、ありがたいです。そんな中で、ノベライズでは黒先生のおかげで、ゲームでは描かれないキャラクターの別の顔を少し垣間見えるかのように、丁寧に描写してくださっていて、さらに全員が生き生きとして感じられるのもよかったんですよ。
黒
ゲームを何周も遊ぶことで、キャラクターの見え方が全然変わってくるじゃないですか。なので、その深さは絶対に描かなければと思って。咲子の描写だけでも、何日もかけた気がします。「この言葉は違うな、これも違う」みたいな感じで。
岡本
ノベライズは咲子と雛子の関係が深堀りされていてとてもよかったのですが、そこまで推敲されていたんですね。監修の時点でも、これは本当に好きで書いてくださってるんだって感じられましたから。そういう意味でも、小説を読んでさらに登場人物たちがグッとリアルに、身近に感じられるようになったというか。雛子の不思議なヒーロー感もより印象的に感じられて。
黒
雛子の人気もすごいですよね。毎日SNSでファンアートが流れてくるのを見て楽しんでいます。
岡本
なんかちょっと、雛子はミームになってしまっているような感覚もありますよね(笑)。今回ゲームデザインではアクション性を高めることにも挑戦したのですが、セオリーだと、ホラー×アクションというのは、若干矛盾する部分がある組み合わせなんですよね。でもまあ、あんまりセオリー通りに考えてもおもしろいものはできないので、チャレンジしてみたところ……結果的にはシリーズでも『 サイレントヒル2 』のジェイムスに匹敵するような、雛子というプレイヤーキャラクターとしても物語の軸としても魅力的なキャラクターが生まれたかなとは思ってますね。それがノベライズでキャラクター性の側面にも光を当てながら深く描いてくださったことで、さらに立体的になって。 黒
いや、キャラクター描写は本当に苦心したところなので、そういっていただけたら本当にうれしいです。でもそうですよね。雛子の強さは執筆中も、ゲームでの体験がにじみ出たというか……強いし、なんだかかっこいいんですよ。
岡本
そうですね。主演の加藤小夏さんの実況配信も毎回すごい視聴数になっていてびっくりしています(笑)。しかしここでも、役者自身がモーションキャプチャーまで演じるという2.5次元的なリアリティーが、一見すると相反する竜騎士07先生のノベルアドベンチャー的かつ、アニメ的なキャラクターの立て方と地続きに交じり合って化学反応が起きたんだと思うんですよね。そこに、ゲーム中の雛子のアクション性の強さなどが加わり、絶妙にキャラクターを立てているのかなと、ちょっと思ってはいます。
黒
それに、やはり寿幸の人気もすごくて”メロ狐”とか呼ばれていますよね。小説では、ミステリアスな彼の幼少期も描いてみたいと考えていました。
岡本
小説は冒頭から狐面の男と雛子の出会いの場面だったのもいいですよね。もちろんキャラクターの立ち位置的には、多少人気は出るんじゃないかな、とは思ってはいたんですが……こんなに!? と想像を超える愛され方にこれまた驚いています(笑)。竜騎士07先生の作品なので、愛されるキャラクターができるだろうと思ってはいましたが、いまの人気ぶりは、まったく計算じゃない領域で、ちょっと想像をはるかに超えて巻き起こっている感じですね。それだけに、ノベライズがキャラクターたちの側面をさらに掘り下げてくださったのは、本当にありがたくて。
黒
寿幸については、自分なりに狐憑きと寿幸本人の意識はどうなっているのか、という疑問についてのアンサーは考えていたのですが、今回のノベライズ版では入れきれなかったので、未掲載原稿として眠っているんです。じつはほかにも潤子についての描写も想像しながら少しだけ書いたりしていたのですが、同じくどうにも入れられず。
岡本
そうだったんですか。じつは、そういったゲームでは語られない内容についてのご要望も多いので、今後なんらかの形で答えていきたいとは考えていまして。でもゲーム自体、何周も遊ぶことで真相が見えてくるというボリュームなので、ゲーム発売前から準備していたノベライズでは、ページ数や〆切の都合上入れられないものも多かったはずですよね。なにしろ監修のときに最初の章から届いたものを順番に読んでいったものの、「途中でこれは一冊に収まるのだろうか?」と思いましたから。
黒
じつは、僕も収まるのだろうかと思いながら書いていました(笑)。
岡本
最後に“続く”となったりして?(笑)とかちらりと。でも、結果的に見事にきれいに一冊にまとまっていて、なんだか文字でできた『サイレントヒルf』のフィギュアを手にしているような満足感があるんですよね。
黒
うれしいです。とにかく、全部が好きで。この小説を書かせていただくに際して、資料や脚本をいただいたりもしたんですけれど、それでもまだまだ考察したいことがいっぱいあって。書いていく中で、別の話が生まれてきそうな感覚がずっとあって。「あれも入れていいんだったら、これも入れるけど」、みたいな感じのせめぎあいでした。
周回プレイで変わる
登場人物の印象を文字に
黒
それにしても、『サイレントヒルf』は、周回や条件による分岐によってプレイヤーに見えてくるものが変わるところが印象深くて、これをどうにか小説に落とし込みたかったんです。
岡本
おそらくこれは竜騎士07先生シナリオの特徴だと思うのですが、『ひぐらしのなく頃に』とか『 うみねこのなく頃に 』も、エピソードを重ねていくとどんどんキャラクターの別の面が見えていって、多面的になるというか。きっと『サイレントヒルf』を何周も遊んでくださった方は、咲子や凛子の性格や人物像に対して大きく心変わりする……最初のプレイでは「凛子最悪だな!」とか思っていたけども、だんだん周回を重ねると「ちょっといいやつかも?」みたいに感じるような(笑)。 黒
まさにそうでした! じつは凛子がいいやつだなという気持ちは、書きながら自分の感情も文章に乗ってきて、そのうち雛子との喧嘩の場面を描くのが楽しみで仕方なくなっていました(笑)。小説を書いておいてなんですが、何周もしていくうちに、そのキャラクターにこう感情が乗っていき、厚みが増していくっていう『サイレントヒルf』ならではの感覚を、ゲーム本編で体験してもらいたいと思っています。
岡本
いえいえ、すごく深いところまで理解しているだけでなく、実際に遊んで書いてくださったことがわかって、うれしいです。正直、ゲームのノベライズはゲームメーカーが提供する資料や映像をもとに実際のプレイはせずに書くものじゃないのかなと想像していたのですが、まさかここまでゲームをプレイしたうえで書いていただけるとは思っていなかったので。
黒
僕自身、ゲームのノベライズはやはりゲームから得られる情報をもとにして書いたものを届けたい、という気持ちがありました。だからこそ、ある場面を描くのであれば、とにかくゲームプレイでその場面を何度も何度も繰り返して体感し、そこでの人物の表情が見えたなら、この表情の時の感情をしっかりと文字に表さなければいけない。キャラクターどうしが向き合ったり、ちょっと間を取ったりする場面でも、いったいその間は何を考えてるんだろうかと。それをなんとか表現しなければいけなかったんですよね。それくらいに『サイレントヒルf』は、人間関係が本当によかったんです。どのキャラクターも書きながらゲームを4周するころには、嫌なところを含めた全部が好きになってしまった。
ファンの感想で
周回数がわかる?
岡本
ところで周回といえば、『サイレントヒルf』の感想をよく読んでいるのですが、明らかに1周しか遊ばれていない方と、1周目のエンディングは自力で見て、ほかのエンディングは動画だけで見た方、そしてちゃんと4~5周全部を遊んだ方、というのが感想を読むだけでなんとなくわかるんですよ。それが、キャラクターに対する感想の濃度が違うんですよね。
黒
なるほど、でもわかります。何周もプレイすると、キャラクターへの愛着も深くなりますし。
岡本
それがとくにキャラクターに対する感想とか、まさに多面的な部分に対する触れ方で見えるというか……この方はきっと、まだ一周しか遊ばれてないな、とか。なんとなく伝わってきちゃうように感じられるのが、すごくおもしろいなと。あとは、SNSなどであがってくるファンイラストを見ていても、この方はたぶん何周もしていくうちに、だんだんこのキャラが好きになってきているのではないかな、とかって勝手にわかる気がしてくるくらいで(笑)。
黒
わかります(笑)。蒐集アイテムにもキャラクターの性格などの情報が書いてありますし、なによりゲームプレイを通じて、そのアイテムを手に入れたときの状況や環境というのも、物語体験の一部だと思うんです。
岡本
そうなんですよ。ちゃんと書類系のアイテムを拾っている方とそうでない方でも、またキャラクターの見え方がかなり変わってくると思うんですよね。黒先生の書いてくださったノベライズは、やはりその辺が非常にうまい高度なさじ加減というか……さすがに4~5周すべての文献の情報を小説一冊に収めることはできないものの、かなりいいバランスでピックアップして会話や地の文に組み込まれているというか、ホラー小説の中に自然に溶け込んでいるなっていう感じがしていて。
黒
できるだけ入れたくて、もうパズルのように組み替えて隙あらば書き込む、という感じで延々とぎりぎりまでいじって推敲を続けていました。そのほかにも、僕は画面の端っこにちらりと見えている壁に貼られたポスターとか、扉とか置物などを、とにかくじっくり見たいタイプのプレイヤーなんです。
岡本
そこまで遊び込んでくださっていたからこそだろうと感じています。ゲームの小説などでは、とくにバトルシーンを長く書くと少ししらける向きがあるからなのか、あまり書かれることないように思うのですが、この小説だと、雛子は激しく長丁場を戦いながら、口でもちゃんと喧嘩をしていて読み応えがあったんですよね。
黒
それはゲームでも、終盤のバトルで複数の戦いが行われている演出に衝撃を受けて、必ず小説でも書きたかったところだったんですよね。
岡本
あの場面は、竜騎士07先生のシナリオを開発会社のNeoBards Entertainment(ネオバーズ)さんがゲームに落とし込む際に、バトルと言葉の戦いが同時進行しているようにしてくれたんですよね。小説は、うまくその雰囲気が出てるかなと思っていますし、あの終盤のところも含めて、かなり綺麗に描き切っているなと思っていて……何度読んでも、いいなと気に入っています(笑)。それに、お別れの場面なども、雛子ではなくて、咲子、凛子、修の視点で描かれているところも、小説ならではの視点と描写で、とてもいいんですよね。ああ、そうきたかと思って、ここもすごく好きなところですね。
黒
小説家としても、いちシリーズファンとしても岡本さんにそういっていただけるだけでうれしいです。
岡本
あととくに好きなのは、咲子の描き方で。ゲームでは早々にいなくなっちゃうキャラクターですけど、味があるじゃないですか。彼女の味わいもちゃんと出ていて、非常にいいと思いましたし。まさに映像ではなく、文字だけで読み手の頭の中に世界が再現されるのも、小説ならではのよさなんですよね。
黒
小説はゲームの体験をもとに文字にして書いていったものですが、じつは最初にプレイして「ゾクっ」と心を持っていかれたのが、咲子が最初に斃れる場面で。集合体恐怖症の人にはかなりビジュアル的にも恐ろしいシーンだと思うのですが、ビジュアルのインパクトがとにかく強烈なんですよ。咲子が斃れて、そして赤い花が咲きながら追いかけてくるっていう、見たことのないシチュエーションの鮮烈さと、おぞましい光景で。内蔵が飛び散っているように見えるけれども、花として眺めると綺麗なんですよね。
それに赤い花の侵食も、いろいろな表現をしなければいけないと思って。ゲームプレイで感じる町の侵食度合いも表現するように苦心しました。そのうち、戎ヶ丘がどんどん赤い花に侵食されていく様を書くのが楽しくなってきたというか(笑)。変貌していく様を小説の中でうまく表現できるか、ここはちゃんと書かなきゃいけないポイントだなっていうふうに思っていましたね。
岡本
そこまでしてくださっているからこそなのか、この小説は本当に不思議な感じがするんですよね。何周も周回プレイされた方の感想を見かけると、この作品はかなり怖い話だし、グロテスクなところもあるとは思うものの、どこか気持ちいい青春小説を読んだ後みたいな感想になるような。きれいにまとまった、まさに文字になった『サイレントヒルf』というか。きっと何周も遊ばれて小説も読んだ方なら、『サイレントヒルf』の物語が、この一冊の本に詰まっているかのような感覚に、共感していただけるんじゃないかなと思うくらいで。
文学になった『サイレントヒルf』
岡本
いや、じつは今回『サイレントヒルf』のノベライズをKADOKAWA Game Linkageさんに提案していただくにあたって、企画書に作家候補としてホラー小説家の黒先生のお名前が上がっていたのを目にしたときには、個人的に読ませていただいていただけに、非常にうれしくて。さらにはゲーム作品のノベライズとしても『NG』や『死印』、『 深夜廻 』などをご経験されている、慣れた方でもあるので、まさにさきほどお話されたように、ゲームを大事にしてノベライズにしてくださると思って。 黒
そんな。
岡本
黒先生のホラー小説 『夜は一緒に散歩しよ』 も、父子家庭で、主人公が自分の子どもに対してちょっと怯えるような描写がありますよね。どこか子どもを持つ親の“不安感”というべきものが色濃く出ているようで、“家族ホラー”として非常におもしろく読ませていただいたんです。黒先生の技術が詰まっているような作品かなと思ってまして。怪談的な部分もあるし、家族の物語でもある。チームにも紹介してメンバーにも勧めたりしたほどで。
黒
いやあ、うれしいです。あの小説は、本当に僕の幼少期のいろいろな思い出を詰め込んだ形なんです。
岡本
実体験も多分に含まれているんですね。僕も本好きで、文学からラノベまでだいたい年に100冊か200冊ぐらいは読んでいるのですが、シリーズをプロデュースするようになってからは、やはりホラー小説をよく読むようにしていて。もちろん黒先生の作品も大好きで、常々とても文章力のある方だなと思っていて
黒
そんなに活字に浸っている方に読んでいただけているなんて、ありがたいですよ。
岡本
本好きの悩みって、本とゲームの両立が難しいところなんですよね。ゲームプレイと同時に本は読めないので、プライベートの時間は、本を選ぶべきか、ゲームを選ぶべきかみたいなことは結構悩みながら生きてるんです(笑)。でもこの小説は『サイレントヒルf』を堪能するにはふさわしい一冊になっているので、ぜひ本を選ぶときに読んでもらいたいなって。
黒
まったく同じで、本かゲームかで悩み抜いている日々です(笑)。本とゲームが毎日せめぎ合いをしていますが、ゲームがもちろん大好きなので、この小説では、ゲーム『サイレントヒルf』の良さみたいなものを出したかったんですよ。
岡本
その点、ホラー小説って、文体が大事じゃないですか。あの、そこで黒先生というホラーの文体も優れた方にご担当いただけたので、今回はすごく安心でした。
黒
こんなにほめていただけて、すでに頭が真っ白です(笑)。でも、そういえば『NG』や『死印』のアートも、『サイレントヒルf』と同じくkeraさんでしたよね。ホラーのご縁があったのかもしれません。僕としては『サイレントヒル』の世界を書かせていただけるだなんて、夢のようで。
岡本
偶然にもそうなんですよね。いい縁がつないでくれた今回のノベライズなんですが、個人的にも、やっと“サイレントヒル“が“小説”になったなと思ったんです。
黒
小説になった感覚ですか。
岡本
ええ。本当に大昔の話なのですが、シリーズ作品のノベライズもあったものの、そのときはどちらかというとゲーム内の出来事の再現に重きが置かれた、ストーリーを補完するファン必携のアイテムという意味合いが強かった。でも、今回の『サイレントヒルf』のノベライズは、ガチのホラー小説家の方が本格的なホラー小説として書き上げてくれた、文体や地の文の描写を含めて初めての本格ホラー文学なんですよね。“サイレントヒル”って、非常に文学的な作品だと受け取られている方が多いシリーズとして知られてもいるので、今回『サイレントヒルf』が文学になったのは、非常に喜ばしいなと思っています。
美しいがゆえに、おぞましい。
コンセプトが執筆の錨に
黒
ありがとうございます。あの、僕は最初、全然ホラー作家になろうと思っていたわけではないんですよ。
岡本
そうなんですか?
黒
でもなんといえばいいのだろう……まさに『サイレントヒルf』のコンセプトというかテーマでもある“美しいがゆえに、おぞましい。”という言葉と同じだと思うのですが、作家として惹かれるテーマは魅力的なのですが、同時にそこにおぞましい恐怖も感覚的に感じていて。それを描いていたら、ホラー作品になったと言いますか。
岡本
おもしろいですね。僕もホラー小説が好きなんですが、ホラー小説を読むと明確に線引きできないような“どちらともいえない感覚”が文字化されているような気持ちになるというか。美しさとおぞましさを共存しているのが日本のホラー文学なのではないかと、ちらっと思うことさえもあります。
黒
ああ、わかります。
岡本
なので、おっしゃってくださった『サイレントヒルf』のコンセプトは、これまで読んできた作品に共通する、美しさとおぞましい感覚が“地続き”で、同時に持つような文学的感覚が発想の源のひとつとして頭にあったものだったりもしますから。
黒
そうだったんですね……もちろんシリーズは全作品大好きなのですが、強烈に自分が今回の『サイレントヒルf』に惹かれたのがわかる気がします。ノベライズを書かせていただいている中でわかったのが、本当に美しいものとおぞましいものって、一緒の位置でまさに“地続き”にあるのだなと。子どものころから僕は、綺麗な蝶々とか何か綺麗な虫など、とても綺麗に表現されているものを見るたびに……同時にすごく鳥肌が立ったり、怖かったりする感覚があったんです。それはこの年齢になっても変わっていないことを、執筆を通じて再認識したというか。
岡本
ノベライズを監修で読ませていただいたときに、当たり前ですけど、やっぱりしっかりとホラー小説になっていると感じたのですが、その理由がわかった気がします。ゲームのシナリオとホラー小説は違うメディアなので、そこには乖離がありますよね。でも、今回のノベライズで、『サイレントヒルf』がホラー小説としての身体というか……文体を手に入れたなと思って。文章を読んでいくことで、怪談的な雰囲気が立ち上ってくるような感覚があって、すごくよかったなと思うんです。
黒
ただただあの言葉に助けられた感覚なんですよ。僕はホラー作品を書いているときに体感しているのですが、グロテスクなものを本当にグロテスクなまま書いてしまうと、ホラーが好きだっていう人でも意外と嫌われてしまうんですよね。
岡本
おぞましいだけだと嫌悪されてしまいますよね。
黒
まさにそうで、「気持ち悪い」とか。僕の先輩から、“ホラーを書くときでも生理的嫌悪感っていうのはあまりよろしくない”と教わっていたので、その辺を意識しているんです。でも……まあ、そうはいっても内臓とか血とかウジ虫とかハエとかグロテスクなものをたくさん書かなきゃいけないんですけど。
岡本
ホラーに携わるものの、つらいところで(笑)。
黒
そうなんですよ(笑)。毎年ホラー作品を書いているので、ハエの描写の仕方ひとつにとっても、100通りは書けるぐらいに練習をしたりしているのですが、そういった中で思うのが、汚く書いたり、残酷に書いたりすることはいくらでもできるんですけど、“受け入れられるホラー”にするには、まさに美しさとおぞましさを両立させることが大事だと考えて、ずっと書いてきたんです。
ゲームをまた遊びたくなる小説
黒
しかし、今回ノベライズを担当させていただいて、いちゲームファンとしても大好きな“サイレントヒル”シリーズの、しかも『サイレントヒルf』の小説が書けるというだけでうれしかったです。同時にこれだけのビッグタイトルに携わらせていただくというのは、すごいプレッシャーでもありました。
岡本
いやいや、 そこはもう安心でしたよ。小説の発売も、4~5周ゲームをプレイしてくれたようなファンの方が、ちょうどその後に触れていただいて読むにもふさわしい、いいタイミングでした。それに、黒先生のこの小説を読んでいると、ゲームをまた遊びたくなるんですよね。
黒
ゲームをプレイして大好きになったものを詰め込んだ作品で、とにかく読んだ人にゲームを遊んでほしいと思いながら書いたので、これ以上ない感想です。
岡本
おもしろいゲーム実況を見た後に、自分もやってみたくなる感覚に近いような何かがあって、いいなと感じたんですよね。僕も「サイレントヒル」シリーズプロデューサーとして、完全オリジナルの作品としては、短編の『 サイレントヒル: ザ ショートメッセージ 』という新作を作ったものの、フルのホラーゲーム作品を、イチから立ち上げられたというのは、今回の『サイレントヒルf』が初めてだったんですよね。 黒
こちらこそ、本当に楽しい執筆時間をありがとうございました。この小説に関わってくださった皆さんと、手に取ってくださった方には、感謝しかありません。僕も機会があれば、お蔵入りの部分も何らかの形で世に出したいとたくらんではいます。UFOエンドも入れたかったくらいで、じつは試行錯誤して書いていましたから(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a4287e90a0ecf4f455c67e288bc334e31.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/ad79abd82a2cbe01ab04d906cfffe635c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a1934019101bedbfb535ad7bb4569c529.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a31401dab54b72b6f797fb0d9b3e004bb.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a4cf0aad78673bbc7f97b90a76097cdf9.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/ad3f211ba5640c6d689db90e7b94cb298.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a3698b4712c01102596622d1e3111637a_5JXty4Z.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a01726d61e13dddda8cca151a9040af32.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a6bcfdd59390609592cb95b12d22a6f85.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/af07ba14e0d6bea4c018ab2b275029ad0.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a2dd9ba1ea7c7c9225d2e4479e2960df5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a8b560a1236c9f36d46f04e272c0a505f.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/ab1ac4e3160f2b3fe649b6965afae7006.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/ac0a36fd0aad88f3759b11b5689d38c87.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a7e76b1abab5d5d36b9967a80122a16cf.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a31e8a6e6d1e0802065c7f90ac3516394.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/aac75a4c34922b83ff3a900d083699d23.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58311/a80b84c8d813d8f9ca30c750d50d06559.png?x=767)
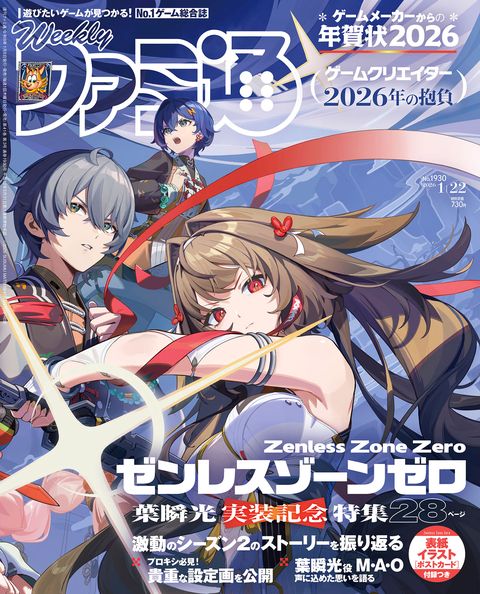



![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)