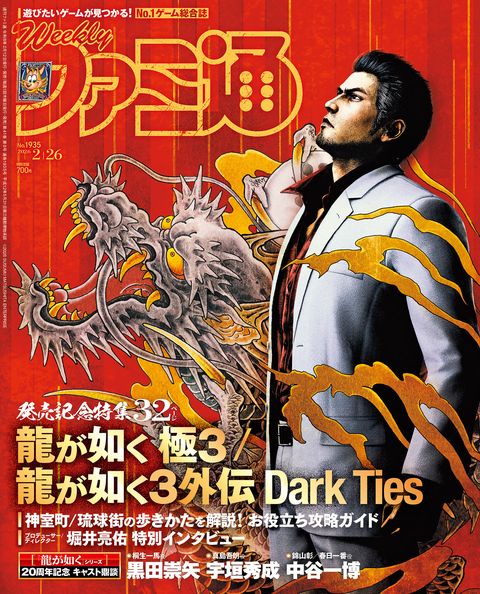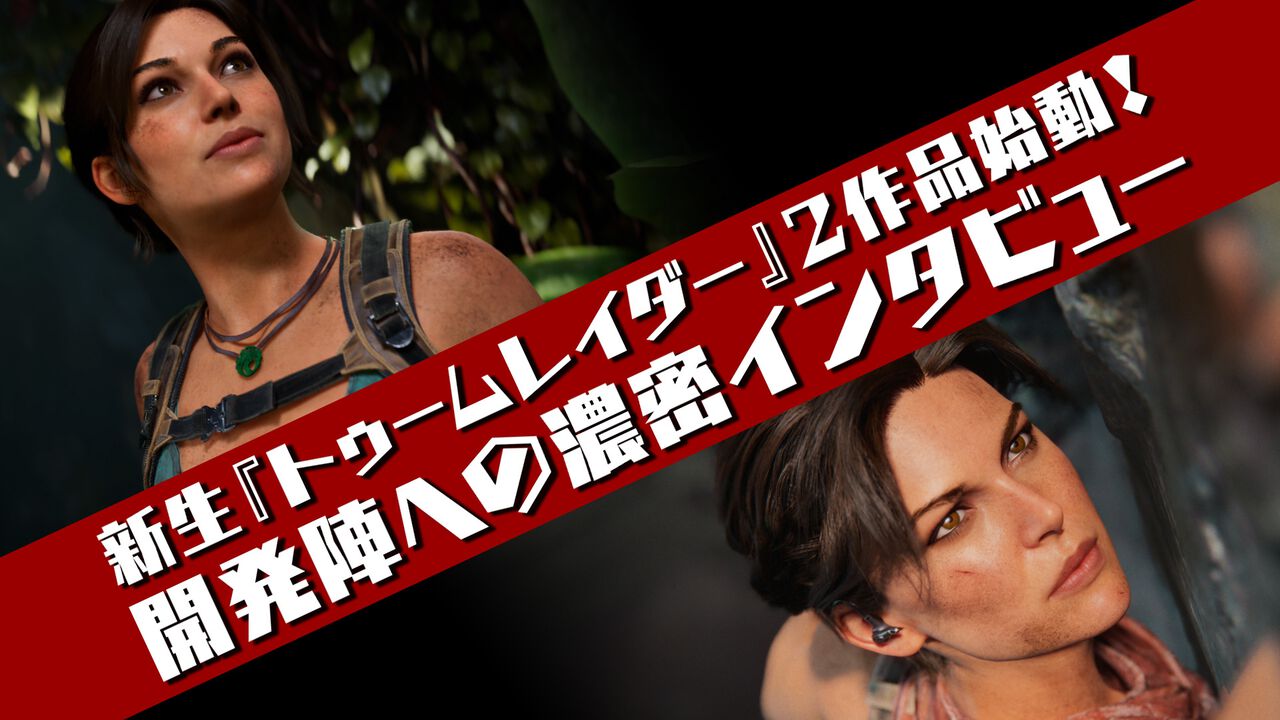2025年11月13日に発売を迎えた『桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~』。発売を記念して、総監督のさくまあきら氏を始め、本作を手掛けた開発陣にインタビューを実施。注力したポイントや、一貫して大切にしている精神について話してもらった。
さくまあきら 氏
1952年生。1987年にファミリーコンピュータ用ソフト『桃太郎伝説』をハドソン(当時)からリリース。翌1988年に『桃鉄』シリーズ第1作『桃太郎電鉄』を発売。『桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~』では総監督/ゲームデザインを務める。(文中はさくま)
桝田省治 氏(ますだ しょうじ)
1960年生。広告代理店勤務時代にPCエンジン用ソフト『天外魔境 ZIRIA』(1989年発売)の制作に協力した縁でゲーム制作へ転向。『俺の屍を越えてゆけ』や『勇者死す。』などの代表作がある。本作では副監督を務める。(文中は桝田)
岡村憲明 氏(おかむら のりあき)
KONAMIのゲームプロデューサー。『桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~』、『桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~』に続き、本作でもシニアプロデューサーを務める。(文中は岡村)
『桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~』とは
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/ac1b40c65c62e4e065433432dfee22145.png?x=767)
日本全国が舞台のすごろく型ボードゲーム『桃太郎電鉄』シリーズの最新作。初の試みとして“東日本編”と“西日本編”というダブルマップが採用されている。
両方のマップを合わせると、物件駅の数は『桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~』の約3倍(約1000駅)。物件数は6000件以上になり、『桃鉄』シリーズ史上最大のボリュームになっている点でも話題の1作だ。2025年11月13日発売。対応ハードはNintendo Switch 2、Nintendo Switch。
米不足、猛暑の最長記録など、最新トピックも作中に反映
―― 本作は驚きの東西2マップ展開です。こうしようと決断された理由から教えていただけますか?
さくま
これは単純に、ユーザーさんからの「俺の住んでいる町も入れてくれ」という要望に応えようとした結果ですね。とはいえ、ただ単に町(物件駅)を増やすだけだと、ゲームバランスは悪くなるので、従来の『桃鉄』と同じ感覚で遊んでもらえるように、マップをふたつに分けたという感じです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a9155c6a50af77d5fbf729ed26f107c3e.jpg?x=767)
―― ひとつのマップのままだと、どのような障壁があったのでしょう?
桝田
気持ちよく遊んでもらうには、やはり1年に1~2回は目的地に到着できるくらいの距離感がベストなんです。
これまではカードを駆使すれば、北海道~沖縄間でもそうした往来が可能だったんだけど、本作は駅の数が従来の約3倍なので、全国版のマップのままだと1年では目的地に到達できない、ということが多々あって。駅を増やしつつ、これまでと同じプレイ感覚も維持するには、マップは東日本、西日本くらいのサイズが適正の上限なので、この形を取らせてもらいました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a524b1a6ce24a69b02f3f43aa09ca324e.png?x=767)
――東西のマップを作る際に、どこからどこまでを入れるといった判断は、どのようにして決められたのでしょうか?
さくま
東西を分けるのは“関ヶ原”がいいと思ったので、そこを基準に東西を区切らせていただきました。
桝田
中部地方と近畿地方を境い目にしてわけるという、メジャーというか、わりとオーソドックスな分割になっています。ただ、都道府県単位で見た場合、三重県は地理的に、東日本編に入れたほうがしっくりくるんじゃないか? という話になって。けっきょくどうなったんでしたっけ?
さくま
三重県が含まれているのは西日本編です。
桝田
そうでした! いまだに「三重県ってどっちだったっけ?」と迷うことが多くて(苦笑)。
―― 作中には、ゲームプレイを盛り上げるさまざまな新要素も用意されていますが、その中でもとくにこだわられたポイントを挙げるとしたら、どこになりますか?
さくま
いろいろありますが、どれかひとつに絞るなら、注目していただきたいのは“歴史ヒーロー”ですね。2026年の大河ドラマに先んじて、豊臣秀長(豊臣秀吉の弟)が登場します。ほかにも上杉鷹山や徳川四天王が登場するので、仲間にしてみてください。
桝田
歴史ヒーローの登場で、「俺の地元にはこんな偉大な人がいたんだ」と、地元を誇りに思ってもらえるのは、我々としてもうれしいところですね。
――『桃鉄』といえば、そのときに流行っている時事ネタもイベントとして取り入れられていますが、2025年は米不足や猛暑日の最長記録などが話題になりました。これらのトピックも本作には盛り込まれていたりするのでしょうか?
さくま
猛暑日が話題になったのは、ゲームがおおよそ完成したころだったんですけど、「これは導入しなければ!」と思い、急ピッチで要素を取り入れ、記録更新された“日本一暑い町”など、イベントとして反映しています。ほかにも線状降水帯だったり、暑さで食品物件がピンチになったりと、この夏に実際に起きた出来事が、ゲームでも体験できるようになっています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a735a27fb1bdcafd386964dd8ff6dc402.jpg?x=767)
―― 過去作でも、九州や関西エリアなど、特定の地域にクローズアップしたモードが入ることがありましたが、本作のプレイ感覚はそれらに近いものになるのでしょうか?
桝田
そっくりそのままではないけど、その当時に調べた情報や、そこで得た知見で、いまも使えるものは流用しています。とはいえ、かなり期間が開いているし、コロナ禍でなくなってしまった飲食店も多いので、チェック作業はかなりたいへんでしたね。
岡村
テストプレイの際にもよく言われたのですが、従来の『桃鉄』は“新幹線や特急列車で日本全国を旅しているイメージ”だったのに対し、本作は“ローカル線に乗ってゆっくり旅をしている”ようなゲーム性で「これまでにない旅情が感じられてよかった」というご意見をけっこういただきました。
ここまでひとつひとつの地域を掘り下げて描くのは、シリーズとしても初の試みだったので、そうした評価をいただけたことは素直にうれしかったですね。
マップの規模拡大に合わせて、各地の情報も改めてリサーチ
―― 本作はマップがふたつということは、単純計算で制作コストも2倍になったということでしょうか?
岡村
最初に全国版のマップを制作して、それをふたつに分けただけだと思われるかもしれませんが、そうではなくて、東日本編、西日本編というふたつのマップを別個で用意しました。しかも物件数はそれぞれ『桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~』と比べて3倍に増加。発生するイベントなどもマップごとに過去作と同等以上の数を用意しつつ、バランスもしっかり調整しています。ですのでおっしゃる通りで、制作コストはいつもの倍以上掛かっています。
――今回そういう、リッチな制作体制を組むことができたのは、これまでのシリーズ作がすごく売れたから……というのが大きいのでは?
さくま
おかげさまで、販売本数は『令和定番』が400万本、『桃鉄ワールド』が150万本を突破しました。
――国内のみでの販売でこの数字というは、本当にすごいですね。
岡村
そうですね。皆さんに楽しんでいただいた結果ですので、たいへんうれしく思っております。
――マップが倍になったぶん、開発陣の作業量も大幅に増えたのでしょうか?
桝田
さくまさん自身もたいへんだったと思うけど、我々も相当がんばりましたね。ちなみに、これは開発途中でメンバーが気づいたことなんだけど、「今回の『桃鉄2』、100年プレイしても全部の物件買えないですよ」と言ってきて。
―― 大ボリューム過ぎる!(笑)
桝田
確認すると本当にそうなっていたので、進行系カードでふれるサイコロの数を増やして機動性を上げるなどして急いで調整しました。やっぱりいままでにない新しいことをすると、こういうことは起こるものですね(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/abc62a931a64d04e23a08ad22b189fc83.jpg?x=767)
―― 本作ではより細かく各地域の情報を盛り込まれていますが、リサーチはたいへんだったのでは?
さくま
情報収集自体はもともと細かくやっていたので、すでにある情報を精査しつつ、そこから派生して調べていく感じでした。
――2マップを同時に制作することになっても、すぐに対応できるくらい情報のストックがあるというのはすごいですね。
桝田
とはいえ、マップが大きくなることで新たな障害も出てきて……。これまでは簡略化して表示していたマップを、より正確に、実際の地図に近い形で表示できるようになったのはいいけど、過去作と同じ感覚で駅を載せていくと県境の位置が違っていたりして。
特定の駅が県をまたいで表示される、みたいなこともあったので、調整はなかなかたいへんでした。ついでに言うと、いくら細かく各地域を描けるようになったとはいえ、やっぱり町(駅)ごとに、物件数には多い少ないの差があって。それに、都市部であれば駅の数も多くなるので、それらをバランスよく配置しようとすると、どうしてもマップには歪みが生じてしまう。県境や河川は正しく引きつつ、そのうえで駅の配置まで考えるというのはもはやパズルゲームをやっている感覚でしたね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/ac2be3dadf47ad64cc052eaf13acefe07.jpg?x=767)
―― 本作はNintendo Switch 2にも対応していますが、同ハードならではの遊びであったり、オススメしたいポイントはありますか?
岡村
遊んでいる皆さんの顔が表示される“カメラプレイ”がおもしろいんですよ。ちょっとした追加要素ではありますが、実際にお互いの顔を見ながら遊ぶと、いつも以上に盛り上がるので、ぜひ体験していただきたいですね(※)。とはいえ、まだNintendo Switch 2を購入できていない方も大勢いらっしゃると思いますので、あえて言いますが、Nintendo Switch向けのソフトでも、本作はばっちり楽しんでいただけますのでご安心ください。
※カメラプレイで遊ぶには、ver1.0.4以上へのアップデートが必要。――まずはお手持ちのNintendo Switch 向けのソフトで楽しんで、Nintendo Switch 2が手に入ったら、アップグレードするのもアリだと。
岡村
最新ハードの性能に合わせてマップをかなり細かく描き込んでいます。
キャラクターもCGで制作したうえでアニメ調になるように縁取りを描き足すなど、グラフィック面でもいろいろと新しい試みを取り入れているんですけど、Nintendo Switch 2を基準に制作したので、Nintendo Switchだと十分に表現しきれないのでは……という不安があったんです。
ですが、開発チームががんばってくれたおかげで“ひろびろマップ”といった一部の追加機能を除けば、Nintendo Switchでも同等のクオリティーで遊んでいただける形に仕上がっています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/ac2e638025c113ae4b4862d7b184c41c5.png?x=767)
初心者でも楽しめる塩梅でゲームバランスを細かく調整
――『桃鉄』といえば、プレイヤー自身の実力と運に左右される要素が絶妙なバランスであるところが、多くのファンから支持されているポイントだと思うのですが、そうした調整をするうえで気をつけていることはありますか?
桝田
毎回、ひとつ前の『桃鉄』のチューニングを分析して。それをブラッシュアップしつつバランス調整をしている感じですね。本作は“桃鉄3年決戦!”モードなら初心者でも運がよければ勝てるけど、“いつもの桃鉄”で10年以上プレイするならしっかり考えないと絶対に勝てない……といったゲームバランスになっています。
――まずは気軽に遊べるモードでマップを覚えて、それから長期間のプレイを楽しむのがよさそうですね。
桝田
“桃鉄3年決戦!”は本当に、いいカードを1枚引けばそれだけで逆転することも可能なので、気軽に遊んでいただきたいですね。というのも、このモードで遊ばれるのは、正月とかに家族や友だちで集まって「ひさしぶりに『桃鉄』やろうぜ!」といった感じの方が多くて。だったら難しく考えるより運次第で一発逆転が可能な設定のほうが楽しんでもらえるので、意図してこういう設定にしたという感じです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a63c24b56cbe2e615eba3fa12b9711864.png?x=767)
―― 本作において、プレイヤー個々の技術、テクニカルな部分の調整はどのような塩梅ですか?
桝田
運次第の要素もそれなりに取り入れてはいますが、上級者であればマップのじょうずな使いかたとか、「ここでこう立ち回れば有利だな」と、ひと目見ただけでピンとくる作りになっていると思います。ここは無理せず、こちらのマスで止まれば、つぎのターンで確実にゴールできる……みたいなポイントにやり込んでいる人ならすぐに気がつくんじゃないかと。
それが醍醐味でもあるんだけど、気軽に遊んでくれている方にそこまで求めるのは、少々酷といいますか。どんなに不利な状況でも、たまたま立ち寄った駅でラッキーなイベントが起こり、一発逆転の切っ掛けになるという可能性は残してはいます。
さくまさんもそうした要素は大事だと考えられていて。いつも「上級者の方ではなく、初めて『桃鉄』をプレイされる方を想定して、ゲームバランスを考えるように」と言われているので、その精神は本作にもしっかり反映されていますね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a1c5b6a4faa74f8e5d55cf955e083434b.png?x=767)
――初心を忘れないといいますか、そうした“おもてなし”の姿勢が35年以上続くシリーズの人気の秘訣なのかもしれないですね。
桝田
先ほどの話の補足になりますが、「ひさしぶりに『桃鉄』でもやるか」となるのは、それぞれに「昔、遊んだことがあるので大体のルールはわかる」という前提があるからなんだけど、そこでいう“昔、遊んだ『桃鉄』”というのは、人によってバラバラなんですね。5年ぶりの人もいれば、10年ぶりの人や、20年ぶりの人もいたりする。
なので、5年ぶりの人でも20年ぶりの人でも「『桃鉄』といえばこんなゲームだよね」と認識している部分は変えないようにしています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a8fa74cf45579e692e3bcd182aae48ea7.png?x=767)
――マンネリにならないように気をつけながらも、基本的な部分は37年間、ブレずに一貫していると。
桝田
それともう1点大事にしているのが“ユーザーを飽きさせないゲームバランス”です。
「『桃鉄』だったら、これくらいの差があっても逆転できるはず」と感じられる絶妙なゲームバランスを保つことには、毎回気をつけています。プレイしていて「これはもう逆転できない」となると、投げやりになってしまうといいますか。途中で「楽しくない」と感じさせず、最後まで前のめりに遊んでもらえるように、本作でもゲームバランスにはこだわっています。
そういったところが安心して遊んでもらえるゆえんだと思っていて。ひさしぶりに友だちで集まってカラオケにでも行こうぜ……くらいの感覚で『桃鉄』を遊んでもらいたいですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a54f18d7c11ca79c97ed2de05937b9f3d.jpg?x=767)
つぎつぎに湧き出る“うんちカード”のアイデアに困惑!?
――『桃鉄』は地理や歴史の勉強になると好評ですが、本作にはこうした展開からフィードバックした要素もあったりするのでしょうか?
桝田
ないですね。ただ、「新作には僕の町も入れてください」という声が、いままで以上にたくさん届いて。それをそのまま反映したわけじゃないけど、『桃鉄2』では約3倍まで駅が増えているから、大勢の方により身近なものとして感じてもらえるようになったんじゃないかなという気はしています。
岡村
今回は東西の2バージョンになりますので、より深く、日本を知るきっかけになってくれるといいなという感覚です。
――改めて、『令和定番』は400万本、『桃鉄ワールド』は150万本を突破し、大ヒット作品になりました。振り返ってどのように思われますか?
桝田
ほぼ国内だけの販売でこの数字だから、なかなかのものだと思いますよ。コロナ禍だったからというのもあるけど、発売したタイミングが絶妙でしたね。
――プロデューサーの岡村さんから見て、この数字はいかがですか?
岡村
驚きの数字ですよね。桝田さんのおっしゃる通りいろいろな外的要因があったからというのは確かに事実なんですけど、そこにあぐらをかかず、今作はそれを超えるヒットを目指して展開していくので、ご期待いただきたいです。
それと『令和定番』や『桃鉄ワールド』は、発売から数年経ったいまでも大勢の方に遊んでいただいている非常に息の長いタイトルなんですけど、本作はそれを2作同時に発売するようなものなので、これまで以上に長く、そして幅広い層の方に遊んでいただきたければ思っています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a7520b0de0eeee0f0926d559b089e13f8.jpg?x=767)
――そうした精神に加え、実際にゲーム内で体験できる部分でも、一貫して大切にされている『桃鉄』らしい要素はありますか?
さくま
ずばり、うんちです。
――うんち!?
桝田
うんちカードだよね(笑)。
さくま
そう(笑)。
――い、意外な回答ですね……。
桝田
本当に毎回、さくまさんはうんちカードだったり、それにともなうイベントにめちゃくちゃこだわっていて。
よくそんなことを思いつくな!? という、うんち関係のアイデアがつぎつぎに飛び出してくるんです。本作では新たに“うんちストーカード”というカードが出てきますが、初めて話を聞いたときは、「うんちストーカーってなんだよ!?」となって。しばらく思考が停止するくらい衝撃的でした。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a4de8c61e5c8266f16d41447a68534f53.png?x=767)
岡村
哲学的なとらえかたをすると、うんちって意外と奥が深いんですよ。
見た目のおもしろさだけでなくそれをいかにしてゲームプレイに落とし込むかを考えるなど、ウイットに富んだ要素もあって。さらに、短いテキストでおもしろさと“うんこである必要性”を説明する技術も求められたりと、『桃鉄』の開発におけるすべての要素がうんちカードには詰まっています。
桝田
だからといって毎回、うんちカードの種類を増やすのはどうかと思いますよ。本作でも、うんちカードに関する打ち合わせだけでずいぶんな時間を費やしましたからね!(笑)
――(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a75ce859f6d3ceed3799bbe13e8884f80.png?x=767)
――最後に、本作について「これは声を大にして言っておきたい」ということがありましたらお願いします。
桝田
さくまさんの中ではすでに次回作の構想があって。それを聞かされたときは「うっ」となりました。そちらはまた、おいおいということで……。まずはいよいよ発売となった『桃鉄2』をお楽しみください。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/ac1b40c65c62e4e065433432dfee22145.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a9155c6a50af77d5fbf729ed26f107c3e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a524b1a6ce24a69b02f3f43aa09ca324e.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a735a27fb1bdcafd386964dd8ff6dc402.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/abc62a931a64d04e23a08ad22b189fc83.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/ac2be3dadf47ad64cc052eaf13acefe07.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/ac2e638025c113ae4b4862d7b184c41c5.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a63c24b56cbe2e615eba3fa12b9711864.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a1c5b6a4faa74f8e5d55cf955e083434b.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a8fa74cf45579e692e3bcd182aae48ea7.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a54f18d7c11ca79c97ed2de05937b9f3d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a7520b0de0eeee0f0926d559b089e13f8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a4de8c61e5c8266f16d41447a68534f53.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57243/a75ce859f6d3ceed3799bbe13e8884f80.png?x=767)