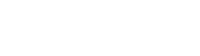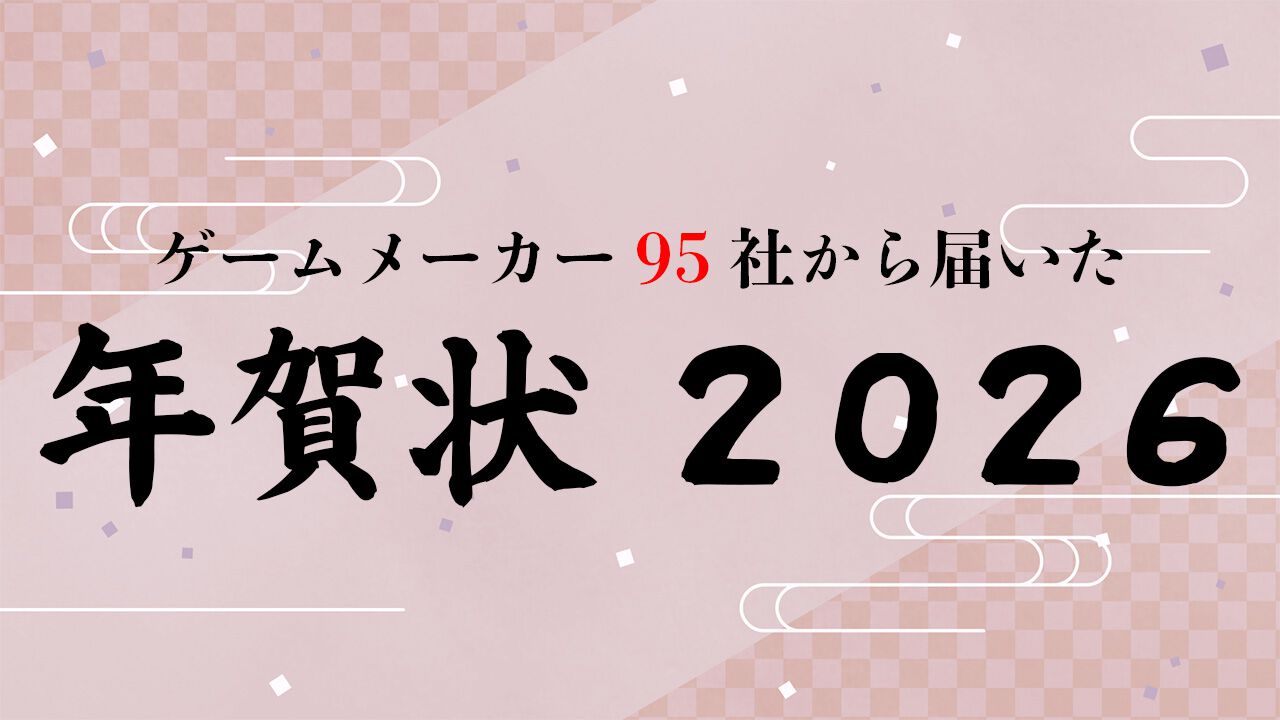![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56945/aa3186b0e6c3831a97b92949d4050f9ba.jpg?x=767)
株式会社闇の代表・頓花聖太郎氏が仕掛けた“10秒AIホラーチャレンジ”の話だ。
本企画は、OpenAIによる話題の動画生成AI“Sora 2”の登場をきっかけに、頓花氏率いる株式会社闇が企画したもので、Sora 2を始めとする動画生成AIツールを活用して10秒でホラーを描いてX(旧Twitter)で公開する投稿チャレンジ形式のSNSキャンペーンだ。
同社がキャンペーン告知をX上でぶち上げたのが、2025年10月7日。日本において、Sora2が招待コードにより拡散されはじめたのが9月30日あたりであり、わずか1週間という異例の速さであったと言える。
広報担当の木澤悠香氏によれば、投稿を呼びかけた株式会社闇のX投稿は、8000万インプレッションに上り、アカウントのフォロワーは、開始から間もなく6000人増という驚異的な数字を記録した。結果は想定を遥かに超える反響となり、驚きを隠せなかったと言う。
◆決断の翌日に立ち上げ──企画即断の裏側に意外な相談相手とネットワーク
頓花氏はそのスピード感を“ほぼ独断”と語る。企画発足にあたり、まず相談を持ちかけたのは、なんと人ではなくGoogleによる生成AIの最新版であるGemini 2.5 Pro。まさに生成AI時代の経営者らしい初手だ。つぎに相談したのが、生成AI界隈ではすでにクリエイティブリーダーのひとりとなっているクリエイター(イラストレーター)の852話(hakoniwa)氏だった。
「もともと交流のあった852話(hakoniwa)さんにSlack(ビジネス向けコミュニケーションツール)で気軽に声をかけたんです。そうしたら即「やります」って返事がきた。その1時間後には、告知用の動画まで作って送ってくれました」
そう、キャンペーン告知投稿に添えられた告知動画は、852話(hakoniwa)氏によるものだったのだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56945/abfe2aa909cf0cb32180cc169a8c3d8e8.jpg?x=767)
◆ユーザー参加型エンタメ運用のノウハウと生成AIの知見。必然だった“ホラー×生成AI×SNS“の融合
「2015年に、ホラー専門のコンテンツ制作会社として設立しました。お化け屋敷でのスマホ連動技術提供からスタートしたのですが、以降、ホラーテーマパークや体験イベント、映像制作まで、幅広くホラー関連のユーザー参加型エンタメを数多く手掛けてきました」と頓花氏。
直近では、“恐怖心展”や“行方不明展”といったイベントをプロデュースするなど、“ユーザー体験とストーリーテリングを結ぶホラー表現”をコンセプトにしたコンテンツを多数仕掛けてきた。“ホラー×生成AI×SNS”を融合した今回の“10秒AIホラーチャレンジ”の企画は、上記のコンセプトが息づく同社のDNAに合致しており、これが企画されたのも自然な流れだったと言える。
Sora 2登場が、頓花氏の企画着想へと一気に突き動かしたのは、頓花氏自身が生成AIを“企画の同僚”と呼ぶほど、日常的に活用してきたことが背景にある。同氏がコンテンツ生成関連のAIサービスに最初に触れたのは2022年ごろで、Stable DiffusionやMidjourneyといった画像生成系のサービスだった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56945/afb0039f2899c9d273de762a381b618cc.jpg?x=767)
さらに、動画生成サービスが普及し始めた2023年初頭には、動画生成AIのRunwayやPikaも活用し、さらにはComfyUIによる生成AI制作ローカル環境の構築にも着手した。そして、クリエイターのみならず、一般のユーザーにも手軽に扱えるようになった件のSora 2にいたるまで、生成AIの技術検証とクリエイティブへの応用について継続的に検証を重ねてきた。
「AIを使うには“癖”を理解しないと使いこなせない。だから自分ひとりでは無理だと感じて、たくさんの人に使ってもらって、知見を共有する場としてチャレンジを企画したんです」と頓花氏。この発想が、3378本という作品を呼び込む原動力となった。
今回、コンテストではなく“チャレンジ”としたのも敷居を下げる意図があったという。
「コンテストと言うと、“がんばらなきゃ”って感じますよね? それが嫌だった。もっと気軽に、誰でも投稿できる形にしたかったんです」(同氏)
ルールも独特だ。“1日何回でも投稿OK”とし、“その日の最後の投稿だけを審査対象にする”とした。これについては、「生成AIって毎回生成されるものが違うじゃないですか。何度か生成してみて後でもっとクオリティーの高いものが出る場合もよくあります。そのためにこうしたルールに行き着いたんです」と頓花氏は説明する。まさに、多数の動画生成AIサービスを使い倒してきた独自の経験に立脚した発想だ。
また、告知用の参考動画にSoraのウォーターマーク(Sora 2で制作したことを示す動画上のロゴマーク)が入っていたのも恣意的だったという。
「参考動画制作にあたっては、じつは852話(hakoniwa)さんから、ウォーターマークを消して再提出しますというオファーがあったのですが、断りました。誰でも”あ、これ自分でも作れるんだ”と思えるように」
これらの取り組みが、AI動画初心者の参加を後押ししただけでなく、“投稿→確認→再挑戦”というサイクルを生み出し、大量投稿へとつながった。まさに長年、ユーザーコミュニティーと向き合ってきたコンテンツ制作のプロとしての適切な判断だったと言える。
企画には、意図しないうれしい誤算もあった。当初の想定は、ジャンプスケア系ホラーや呪いネタなどの“ガチ怖”動画だったというが、「蓋を開けてみると、漫画家の方が4コマ的なストーリーを10秒でまとめたり、大喜利みたいにネタ化してくる人も現れて、完全に想定外でした」と頓家氏。実際、考察を誘う謎解き系や、10秒で物語を完結させるストーリーテリング型まで現れたという。
「“怖さ”にもいろんな形がある──それを改めて実感しました」
頓花氏は、ホラージャンルの奥行きの深さについて感慨深そうに語った。
◆“SCP”から着想しAIで実現する、ネオ伝承と共創型ホラーの未来
「我々がつぎに目指すのは、ホラー分野における新しい“シェアードワールド”の構築、“共創型ホラー”への挑戦です」
頓花氏は、共同創作コミュニティの代表例である“SCP”を挙げ、“みんなでひとつの物語を補完し合い、創ること自体を楽しむエンタメ”を生み出すことが、生成AI時代におけるクリエイティブの新たな潮流だと指摘する。
SCPは、イギリスにおいて大規模掲示板への書き込みから広がったグローバル規模の参加型創作プロジェクト。投稿されたとある超常現象創作コンテンツをベースに、物語の設定を共有、拡張し、新たな派生作品を創作するコミュニティサイト“SCP Foundation(SCP財団)“が開設されている。物語の設定として、同コミュニティーと同名の架空の組織も存在している。
「SCPみたいに、シェアードワールドをみんなで作っていく。物語の一部を誰かが作り、また別の誰かがその続きを描く。生成AIがある今なら、それができると思うんです」と補足したうえで、こう付け加えた。
「日本には、かつて、(源流は同じながらも)地域ごとに異なる妖怪譚や伝承があった。そうした文化伝承の現代版、“ネオ伝承”をAIとともに創り出したいです」
こうした“ネオ伝承”プロジェクト構想の背景には、頓花氏が描くAIの進化とエンタメ市場の変遷を見据えたビジョンがある。
「私は2031年に来ると言われるAGI(汎用人工知能)により、社会全体が予測不可能になると考えています。それを踏まえ、そこにいたるまでのロードマップを綿密に書いています」
そして、AGI以前のAI市場の変遷を、スマートフォンの普及になぞらえた。
「スマートフォンが出た当時、誰もTikTokの流行を予想できなかったように、AIにおいても”何が当たるかわからない”。だからこそ、何が正解かわからないいま、小さいチャレンジをたくさん作っていくのが最良の戦略です」
まさにこれこそ、今回のキャンペーンの核となった哲学だろう。頓花氏にとってAIは、ビジネスに直結しない日常においても不可欠な存在だ。
「私、基本的にいま社内でいちばん誰と会話しているかと言ったら、AIなんです」
AIを“企画の同僚”と呼び、対話をくり返すことで生まれた今回のチャレンジは、この”小さいチャレンジを量産する”という戦略の第一歩であり、その有効性を証明してみせた。
頓花氏は、今後、これまで株式会社闇として実績を重ねてきたイベント事業とは別の柱として、生成AIエンタメを確立させたいとの展望を示した。同時に、リアルコンテンツについても、AIの活用により、よりパーソナライズしたホラーをイベントなどのコンテンツとして楽しんでもらうこともできる」と、“ホラテク”と生成AIの融合にも将来的に大きな可能性があるとも語った。
そして、AIが持つもっとも大きな可能性について、頓花氏はこう断言する。「(“10秒AIホラーチャレンジ”の企画では、)いままで映像を作ったことがない人たちがたぶんたくさん応募してくれていると思います。AIは、そうした人たちであっても自分の頭の中で描いているものをコンテンツとして具現化できる力を実感させてくれたのです」
3378本の作品は、あらゆる人たちが関われる未来のエンタメ制作の可能性を証明してみせた。そして、ホラーというジャンルこそが、もっとも新技術との親和性を持つジャンルのひとつであると改めて実感したと頓家氏は振り返った。
以下が、多種多様な本コンテスト各賞受賞者である。誰もが参加でき、誰もが“ストーリーテラー”となれる時代が、すでに始まっている。
【“10秒AIホラーチャレンジ”受賞者】
■最優秀賞(1名)
HIROTO氏
⇒作品はこちら
■852話賞(1名)
優しいお湯氏
⇒作品はこちら
■優秀賞(3名)
青木ヒデオ氏
⇒作品はこちら
罪人氏
⇒作品はこちら
彩羅木蒼氏
⇒作品はこちら
そのほかの136作品は株式会社闇の公式Noteに掲載されている。
⇒株式会社闇 公式Note
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56945/a2cf3b86d841581ab21088f2c924187a6.png?x=767)
中村彰憲(なかむらあきのり)
立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。 おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。