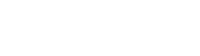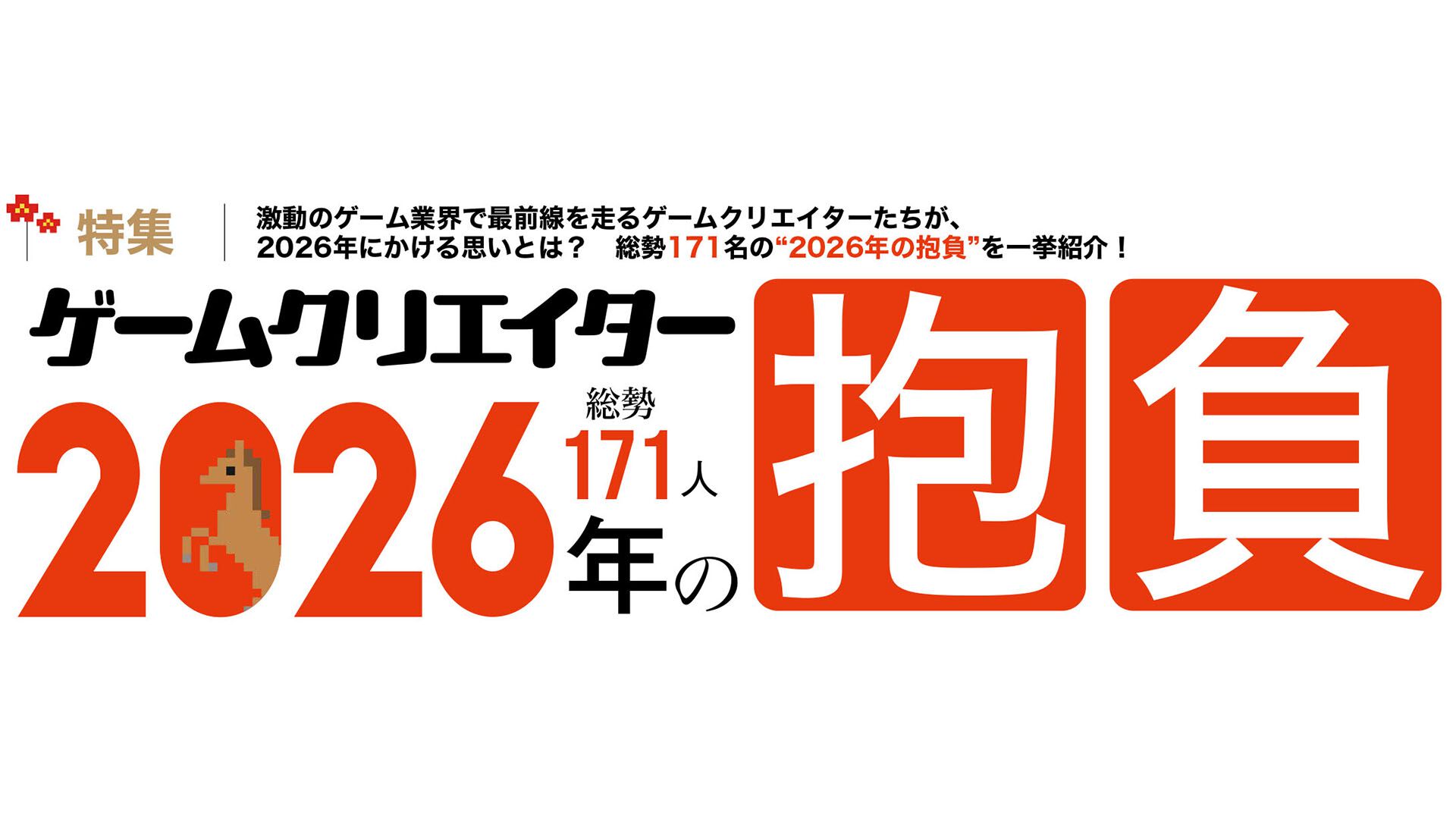2025年9月18日にリリースされる、バンダイナムコエンターテインメントとブラウニーズのタッグが手掛ける完全新作アクションアドベンチャー『 トワと神樹の祈り子たち 』(以下、『 トワ 』)。Nintendo Switch、プレイステーション5(PS5)、Xbox Series X|S、PC(Steam)で発売予定。 本作は、刀と法術を駆使して敵を殲滅しながらダンジョン最奥部を目指す、見下ろし型のハイスピードアクション。ダンジョンは、祈り子と呼ばれる仲間の中からツルギとカグラを選んで攻略する。ツルギは本差と脇差の2本の刀を振るうアタッカー、カグラは多彩な法術を使うサポーターで、同じキャラクターでも役割ごとに異なるアクションが楽しめるのが大きな特徴だ。
祈り子のひとり、レッカは本差による横に広い連続攻撃と、脇差による範囲攻撃を組み合わせて継続的にダメージを与えるのが得意。法術は火と土の属性を使用でき、これらの属性は敵にダメージを与える法術と、敵を足止めする法術が多い。
本作の全楽曲を、『 タクティクスオウガ 』や『 ファイナルファンタジータクティクス 』などを手掛けた崎元仁氏(ベイシスケイプ)が担当しているのもポイント。和風の世界観である本作では、どのように楽曲制作を行ったのか。崎元氏にインタビューを実施し、その裏側を訊いた。 VIDEO
VIDEO
崎元 仁氏(さきもと ひとし)
ベイシスケイプ代表取締役社長。『タクティクスオウガ』や『ファイナルファンタジータクティクス』など、名作タクティクスRPGを筆頭に数多くのゲーム音楽を担当。近年では、『十三機兵防衛圏』や『鈴蘭の剣:この平和な世界のために』などを手掛けている。文中は崎元。
珍しい3つのキーワードを受けてスタートした曲作り ──『トワと神樹の祈り子たち』の企画書などを見たときの第一印象を教えてください。
崎元
絵柄を見たときに、アジアのいいところを混ぜたような印象を受けたのと、日本の八百万の神をイメージしました。ストーリーでは、死生観に関わる要素が中心に据えられていて、ものすごく日本人っぽいゲームなんだなと思いましたね。
──プロデューサーの長岡大祐さんやディレクターの山下修平さんとの打ち合わせで、印象に残っていることも伺えますか。
崎元
音楽の内容に関して具体的な打ち合わせをしているときに、非常に特徴的なキーワードが3つあったことを鮮明に覚えています。ひとつ目は、ゲームは和風なのですが、音楽はあまり和風にしないでほしいと言われました。あくまで和風の作品であって、日本が舞台ではないので、音楽を和風にしたくないのかなと考えました。 ──最後のキーワードは?
崎元
全体の音楽をハリウッドサウンドみたいにしないでほしいと言われました。どれも珍しいオーダーでしたが、3つ目はとくに意外でしたね。というのも、ハリウッドサウンドを好きなクリエイターが多いので、むしろハリウッドサウンドみたいにしてほしいと頼まれることが多いです。僕も好きな一方で、どのゲームの音楽も似たような感じになってしまうので、できれば避けたいという想いがありました。何か違うことをやったほうがいいのではないかと考えていたので、いつも以上にやりがいがあるなと感じましたね。 ──それらのオーダーを達成しながら曲を作るのは、やはりハードルが高いのでしょうか?
崎元
不思議に思われるかもしれませんが、音楽は制限でしか定義できないんですよ。細かく言うと、ふだんは10以上の制限がある中で作曲しているので、3つくらいの制限が付くことは大した問題ではありません。むしろ制限がないほうが、自分で制限を考えないといけないので、たいへんだと思います。 ──公開されている崎元さんのコメントに、「和風のサウンドは避けつつ、日本人の死生観、日本の心を表現する」という方針で曲を書いたと記載がありました。和風のサウンドを避けながら、どのように日本人の死生観や日本の心を表現したのか教えてください。
崎元
まず、和楽器や和風のスケール(※音階)をできるだけ使わないようにすることで、和風のサウンドを避けています。和楽器はものすごく特徴的でピーキーな楽器です。和太鼓をドンドコドンドコ叩いちゃうとお祭りをイメージされがちですし、三味線をベベンと鳴らすと多くの人が和風だと感じてしまう。和楽器はそれくらい強力なんですね。
──その内容を具体的にお聞きしたいです。
崎元
いくつかありますが、たとえば楽器の奏法を変えています。今回は少しだけオーケストラも使っていて、ヴァイオリンは世界的にも著名なサラ・オレインさんにお願いしたのですが、最初に和風の旋律の曲を和風の奏法で弾いてもらったところ、ヴァイオリンでも想像した以上に和風になったんですよ。和と和の組み合わせは避けたほうがいいことがわかったので、和風の旋律を洋風の奏法で弾いてもらったり、逆のパターンで洋風の旋律を和風の奏法で弾いてもらったところ、ちょうどいいバランスになりました。
――(笑)。ヴァイオリンのほかに、和風になるのを避けるために使った楽器は?
崎元
ブズーキ(※ギリシャ音楽で中心となる弦楽器)やハンマーダルシマー(※多数の弦を木製のスティックで打って演奏する打楽器)を使っています。でも、これらの楽器を使うのもさじ加減が非常に大切です。どちらも味が強い楽器だから、表に出しすぎると色が強くでてしまうので。和楽器と同じように出しすぎないように気をつけました。 ──楽器それぞれに注意点があるのですね。
崎元
あとは旋律の扱いかたですね。日本人は旋律が好きな民族だと思っていて、みんなが好む音の流れというのがあるんですよ。そういった日本人が好みそうな旋律を使っていますが、ぜんぜん違う伴奏を合わせることで和風っぽく感じないようにしています。
久しぶりに悩んだテーマ曲と印象に強く残っている戦闘曲 ──全体で何曲くらい作曲したのですか?
崎元
54曲です。最初にテーマ曲、フィールド曲、戦闘曲から作り初めて、リストを見たときにこういう曲もあったほうがいいだろうなと思い、追加でテクノバージョンも作りました。そのぶんだけ少し増えていますが、ほぼ当初の想定通りの曲数になっています。 ──54曲の中で、作るのがとくにたいへんだった曲はありましたか?
崎元
全体的に楽しく作曲できましたが、テーマ曲は久しぶりにかなり悩みましたね。楽曲全体のコンセプトと同じようにテーマ曲も表面的な部分では和風のものを使わずに、内面的に和風のものを使うという方針は最初に決めていました。でも、いざやってみるとこれが難しくて。内面的なところで和風というか、日本人っぽい雰囲気を一生懸命出そうとすればするほど、ふつうのことしかできなくて、つまらない感じになってしまう。それでちょっとでもおもしろいことをやると、方針から外れてしまってこれは困ったぞ、と。 ──どのように解決したのでしょうか?
崎元
これといった明確な解決方法はなかったので、細かく細かくいろいろなところに手を入れて、調整するのをくり返した結果、納得できる形にできたという感じでしたね。 ──どれくらいの期間、テーマ曲と向き合ってたのか覚えていますか?
崎元
もちろん手を付けていない期間もありましたが、かなりかかったんじゃないですかね。それこそ年単位で取り組んでいた気がします。作業を進めてはうまくいかなくて、別のことをして……みたいな感じで。ただ先ほどもお伝えした通り、仕事としてはとても楽しかったんですよ。 ──テーマ曲やテクノバージョンの楽曲のほかに、とくに印象に残っている曲は?
崎元
ネタバレになってしまうので、具体的にお話できないのですが、ボスバトルの中に印象的な曲がありました。リストの中に“●●●みたいな曲”と、ひとつだけおかしな指定がって(笑)、そのイメージ通り作ればいいのかなと戸惑いながら作曲したのを覚えています。ほかの戦闘曲と編成は寄せているものの、ちょっと違った感じの曲になっているので、楽しんでもらえるとうれしいですね。 ──そもそもベースの戦闘曲は、どのようなイメージで作曲したのでしょうか?
崎元
戦闘曲も和風のサウンドは避けつつといった、大きな方針はちゃんと守りながら作っています。そのうえで、すべての戦闘曲で実現できたわけではありませんが、最初のほうに作った曲はできるだけジャンルがわからないようにしています。最初に書いた戦闘曲は中ボスの曲だったと思いますが、和風の音階の中で音が動くようにして、ぜんぜん違う形で音を鳴らしてみると、どうなるんだろうと考えながら作り始めました。 ──戦闘曲もいろいろ試行錯誤していると。
崎元
そうですね。そういった形で作り始めてわりとおもしろい戦闘曲ができたので、これならいけそうだと手応えを感じました。
──長岡さんや山下さんから、こうしてほしいといったリテイクはありましたか?
崎元
リテイクはほとんどなかったですね。最初の打ち合わせで曲作りの方針はカチッと決まっていて、その通りに進めることができたので、任せていただいたのだと思います。 ──最後に、発売を楽しみにしている読者やファンに向けてメッセージをお願いします。
崎元
『トワと神樹の祈り子たち』では、わりと変わった方向性と言いますか、すごく難しいことを狙ってやっているような感じがしました。それで音楽でも、ふつうではないと感じてもらえるものができたらいいなと思って作曲しています。どんな仕事でも試行錯誤をすると思いますが、今回は和楽器の扱いかたなど、これまでやってこなかったことにも挑戦しました。そういった試みが皆様の心に届いてほしいなと思いつつ、何よりもゲームを楽しんでいただけるとすごくうれしいです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/3fe07eee1f0268775c646e844b05bff2d.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/3d9b6f4554ead74cebd62effb6a671a52.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/39a11768d2c2eea7c331011b06a7d4eb2.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/a9675c1ff34145d7b1a68d3ddb6c0e555.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/a2394909de8985606ee3389c7361cd01c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/35f3b980f0213c331c10559468a556d31.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/a7d176595218be2c84e653f6446ce7e5d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/35f3b980f0213c331c10559468a556d31.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/3afc8e8f20f2d9785d7bcd30c11fbfe51.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48314/a90321fb40aff2d9b43327d0f3559d029.jpg?x=767)