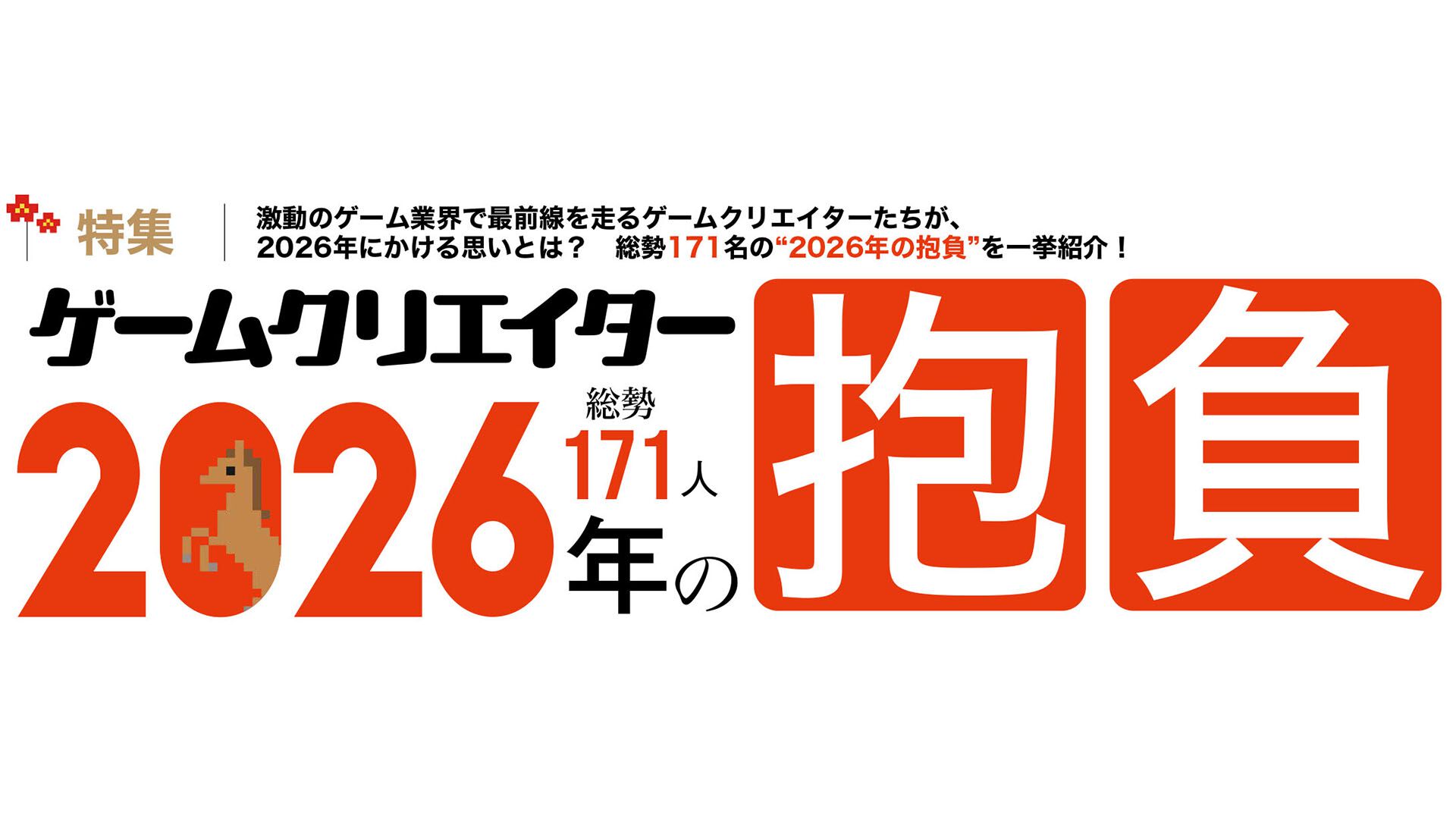名越稔洋というゲームクリエイターがいる。
1989年にセガに入社後、第8研究開発部に所属。『バーチャファイター』シリーズの生みの親である鈴木裕氏のもとで経験を積み、ディレクター・プロデューサーを務めた『デイトナUSA』が大ヒットを記録。その後も『スパイクアウト』、『スーパーモンキーボール』、『龍が如く』といったオリジナルIPをヒットさせてきた、業界きってのクリエイターだ。メディアに登場する機会も多く、ゲームファンであればその名を聞いたことのある人も多いだろう。
そんな名越氏がセガを辞め、信頼する仲間たちと “名越スタジオ”を設立したのが2021年11月。以降、自身のラジオ番組(※TOKYO FM『名越スタジオ presents THE Future Lounge』毎週木曜21時30分から放送)やメディア出演などは行っていたものの、ゲームに関しては「世界に向けたハイエンドゲームを制作する」といった宣言以上の続報が途絶えていた。
そんな中、スタジオ設立3周年を機に発表された、名越スタジオのブランド映像“MAKE/HUMAN”である。
氏がどんな意図を持ってこの映像を制作し、いま何を思い、どんな戦略を練っているのか。ファミ通グループ代表の林克彦がその真意を訊いた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/ae15e66fd3ab675b280487c2abab37bb7.jpg?x=767)
名越スタジオの3年間
林
スタジオ創設から3年が経ちましたが、ずいぶんスタッフの数も増えたようですね。
名越
そうですね、徐々に。いまでは、業務委託のメンバーも含めると80 人ちょっとくらいですね。
林
ファミ通で名越スタジオ1周年のときにお話をうかがったときは、「50人くらいまで増やしたい」とおっしゃっていましたけれど、すでに超えているんですね。
名越
ええ。もともと思い描いているものを50人で作れるとは思っていなくて。闇雲に人を集めるわけじゃないので、1周年の時点では一気に人が増えるイメージは描きづらかったんです。でも、結果的にはいい人が集まってきてくれて、いまの状態にあるという感じですね。とはいえ、ワールドワイドのタイトルとなると、いまの人数で作りきれるというわけでもないので、外部の協力会社さんの力もお借りしながら進めている感じです。
林
なるほど。モノ作りに関する詳細は追ってうかがおうと思いますが、まずはスタジオ設立3周年の節目ということで、名越さんにとってどういった3年間だったかを教えていただけますか。
名越
本当にあっという間でした。スタジオができて1年くらい経ったときに「ゲーム作りはどのへんまで進んでいますか?」なんて聞かれることもありましたけど、本格的なゲーム作りとは程遠い状態だったんですよね。2021年11月1日はスタジオが書類上できあがった日でしかなくて。当初は、会社のサーバーもないし、固定電話すらないっていう状況でしたから。そもそも、3年前の11月1日に在籍していた人数って、私を含めてふたりでしたからね。
林
ふたりでは、できることはあまりないですね(笑)。
名越
ゲーム作りなんて本格的にできるわけはなく(笑)。そこから、企画の精査とスタッフのリクルーティングが同時に進んでいって。「こういうゲームに向けて、具体的に走っていこうね」という指針が見えてきたのはスタジオができて半年後くらいでした。だから、「実際にちゃんとゲームを作っている段階になってからは、まだ2年ちょいなんだよな」という感覚ですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/ad6851ed6953b61530fc18da0ecc1d375.jpg?x=767)
林
最初から企画が整っている状態でもなかったわけではないでしょうし、そう感じるのも当然だと思います。
名越
最初に決まっていたことなんて、「Unreal Engine 5を使うよ」っていうくらいで。そのUnreal Engineも3年のあいだにバージョンアップしましたしね(笑)。
林
確かに(笑)。ここで改めてうかがいたいのですが、3年前に名越さんが独立されたときのいちばんのモチベーションと言いますか、何をしたくて独立を決断したのか教えてください。
名越
せっかくゲームを作るのであれば新しいものが作りたかったですし、前の会社でできなかったものを作りたかった。もちろん、前の会社でも新しいものを生み出せなくはなかったんでしょうけど、規模の大きな会社ではなかなか難しいこともあって。東京ゲームショウなどを見ればわかりますが、国内だけでなく世界的にも大規模な新規タイトルがそんなにボコボコ出てくる状況じゃない、というのが現実ですから。
林
そうですよね。
名越
もちろん、ヒットした作品を遊んで「楽しい!」と言ってくれているファンの方々に、続編という形で応えていくことに対してのモチベーションもあります。それは大事なことですが一方で、心のどこかで「新しいものを作りたい」という気持ちもあるわけです。
林
クリエイターですから、そういう気持ちはあるべきでしょうしね。
名越
ただ、そんな想いを抱き続けながら、現実には何も動けずに時間だけがどんどん経っていくことも多いわけで。そういった状況に抗うには「新しいものを作るんだ!」と具体的に行動し始める人が必要じゃないですか。自分がその役割を担ってみることでひとつの成功事例を作れるかもしれない、という考えにいたったことが独立の最大のモチベーションでした。
林
仲間たちといっしょにまったく新しいエンタテインメントを作りたい、というお気持ちが大きかったということですね。
名越
そうですね。
林
率直に、この3年間は楽しかったですか?
名越
いや、そこはですねえ……。やっぱり苦しいところも多いですよ、新しい環境でのゼロからのモノ作りって。
林
なるほど、それはそうですね。
名越
最初の話に戻りますけど、スタッフを集めながら企画も考えて……というのはなかなかタフなことです。でも、それはあらかじめわかっていたことですから、そんなに落ち込みはしなかったです。長いこと仕事をしてきたことから来る“腹の括り”みたいなものはあったので、ヘコタレはしなかったですね。そんな感じなので、「楽しかったですか?」と問われたら「そこまでではないです」というのが率直な感想ですね(笑)。
名越スタジオにおけるモノ作り
林
具体的にこの3年間の動きについてうかがいたいのですが、最初の1年間は、環境を整えることにすごく時間を費やされたのではないかと思うんです。
名越
おっしゃる通りです。
林
そのなかで……どういった言いかたが正しいのかはわからないですが、「いちばん時間を取られたな、大変だったな」と思ったものは何ですか?
名越
うちは新卒を採っていなくて、多種多様な会社でいろいろなタイトルに携わってきた優秀なメンバーを集めているので、みんな多くの経験やノウハウを持っています。一方で、それぞれモノ作りの手法やカルチャーみたいな部分も個々でぜんぜん違うんです。当然、そこにプライドもあるので、「じゃあこの手法でやって」のひと言では済ませられないところがある。ですから、「いまから作ろうとしている我々のタイトルにとって、もっとも有効な手法はどれなのか?」ということをひとつひとつ考え、みんなに腹落ちしてもらいながら進めなければならない。これが大変でしたね。
林
作りかたの土台を固める難しさ、みたいなことですね。
名越
ええ。ただ、それはある程度認識していたことでもあって。たとえばセガというひとつの会社の中で仕事をしていても、違うチーム、あるいは違うゲームを作っていると、手法も考えかたも異なっていましたから。今回、いろいろ知識や手法を持っている人が集まったので、せっかくなら彼らの知見を聞いて、ノウハウを活かしたかったんです。単純にほかの会社で皆がどうやっていたのか気になりますしね。
林
確かに。
名越
そして「なるほど、そういうことなんだ」、「話には聞いたことはあるけど、実際試したことはないよね」、「ハードルが高そうだけど、いったんその手法でやってみましょうか」みたいな会話をしながら進めかたを模索していくことになる。もちろん、それが思った通りの効果にならないこともありますけれど、たまに「ああ、いいじゃん!」となったり、「未来に向けて作っていくゲームにとっては、必要な感覚だよね」となる場合もあったりします。
林
これまでの手法をただ踏襲するだけではなく、押し付けるでもなく、いろいろな意見をフレキシブルに聞きながらワンチームにしよう、みたいなことですね。
名越
そうですね。うちのスタジオに新たに入ってくるスタッフも「社内はセガ出身の方が多いんですよね?」という先入観を持つことが多いようですが、実際のところ、いまはもう少数派ですし。ほかのやりかたを取り入れていくことも重要です。
林
あ、そうなんですね。
名越
本当にいろいろな出自の、個性的なスタッフがいます。それがおもしろいところだと言ってもいいかもしれないですね。うちはデザイナーにせよ、プログラマーにせよ、プランナーにせよ、すでに他社で結果を残してきたスタッフが多いんです。ゆえに、衝突が起きているとまでは言わないですが、「このやりかたが正しいと思います」とか「いや、できればこれでいきたいです」とか、ありがちなトライアルは起こっていて。皆が優秀だからこそ、逆に迷いますよね。議論の末に試してみて、出てきたものが結果的によくなっていると「ああ、この選択をしてよかったな」と思います。
林
いい衝突、いい試行錯誤ですね。
名越
博打ではないですけど、やはり来てもらったスタッフのスキルをまずは信じて挑戦してみることが大事だと思うんですよ。いろいろな会社のいろいろなタイトルのいろいろなパートを作った人たちの結果を集めて、規模の大きな新規タイトルを作っていくことは、エキサイティングです。トップの目線からすると、怖さもめちゃめちゃあります。でも、挑戦をしなければ新たなスタジオを立ち上げた意味がないので。
林
ふつうの会社組織なら、ルールがある程度固まっていることもあって、スタッフの皆さんが「こうしたほうがいいと思う」とか「こうしたい」という声が出しにくいこともあると思うんです。でも、名越スタジオはすごく健全に議論が行われているようですね。
名越
人によって濃淡はあると思いますが、議論できる場ではあると思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/a326028dde29a55cb1f22ee11dae0e01d.jpg?x=767)
林
ディスカッションがスタジオの中で日常的に行われていて、それが名越さんまでエスカレーションされるっていうのは、すごくいいことだなって。
名越
ふつうの会社でも、現場ではやられていると思うんですよ。ただ、現実に立ち返ったとき、予算や期限というものを最優先で考えざるを得ないわけで。そうすると “80点が85点になるとわかっていても、80点のまま行かざるを得ない現実”は、あると思うんです。ただ、“80点で行ったがゆえに保てる何か”があったりもするので、一概にどちらが正解かという言いかたもできない。難しいところですよね。
林
ただ、いまの名越スタジオだと、「ちょっと試してみよう」ができるわけですよね。
名越
そうですね。みんな新しいことを試せると思って入社していますから、試せないとなると話が違ってしまう。「前の会社を辞める必要がなかったな」と思われてしまうと、それは悲しいですし。
林
そういったチャレンジを積み上げて、クリエイティブ的にはいいものに仕上がりそうだ、ということなんですよね。
名越
そうですね。スピード感が出せているとまでは言えない部分もありますけど、でもクオリティーの向上という意味で言えば、しっかりと手応えは感じています。現段階において当初の企画内容を譲歩することはしていないので、そのぶん時間が掛かるということになっているんですけど。でも、それが新しいスタジオを作った意義でもあるので、それでいいのかなといまは思っています。
林
昨今、業界全般で見ると、人集めに苦労している会社さんが多いじゃないですか。その中で、優秀な方がこの3年で80人近く集まっているというのは、すごく順調に見えるのですが、人集めの部分で苦労はなかったのでしょうか?
名越
いい人がいたら、迷わずにあたっていますね。「あそこでこういう人が辞めたらしいんだけど、誰か連絡取れない?」といった感じでツテを探したりもしますし、うちの社員にいい人を紹介してもらったりもします。もちろん、いまは転職エージェントもたくさんありますから、そういったルートも活用しています。そこは、がんばったとは思いますね。
林
そうですよね。
名越
いま業界全体を見渡してみると、昔の基準で言ったら定年っていうような年齢になってくるクリエイターが増えてきている。そして、新規作がなかなか生まれづらいという環境もあります。そんな状況のなか、ちょっと前までキャリア組と言われていた人がゲームクリエイターとしての終活を考えるようなフェーズに入ってきた。そういう人たちが「自分が培ってきたものを、最後に何にぶつけたいのか」を考えたとき、冒険を求める人もいるんですよ。
林
なるほど。
名越
もちろん安定を求める人もいます。ゲーム業界も他業種のトップランクと比較して、お給料もベースアップがなされていき、待遇がよくなっている。それはすごくいいことです。でも、“モノ作りをするひとりのクリエイター”として考えたとき、「ちょっと冒険をしてでも、最後は自分なりに挑戦したい」という人が意外に多いのだと思うんです。ただ、大手から大手に移ると、手掛けるタイトルは変わってもモヤモヤ感はけっきょく引きずったままで、環境的には大差がなかったりもする。だからこそ、うちに人が集まったような気がしています。結果論ですけどね。
林
「名越スタジオなら新しいことができそうだ」と思えたのでしょうね。
名越
ゆえに、その声に応えられる作りかたというか、考えかた、やりかたはブレちゃダメだな、と思っています。
林
ちなみに、採用時の面接や面談には名越さんも参加されるんですか。
名越
最終面接は必ず参加します。
林
名越さんが面接で人を見るとき、重視している部分はどこですか?
名越
職種にもよりますが、アウトプットされるものはチームワークで築かれた結果なので、まわりとのコミュケーションがちゃんと取れるかどうかは重視します。アウトプットされるものにはこだわってほしいですけれど、モノ作りのこだわりを持っていることと、自分のやりかたに固執することって同じようで違う話なので。もちろん寡黙な人もいますが、寡黙だからとって言って、コミュニケーション能力がないわけではない。口数が少ないのとコミュニケーション能力が低いことはイコールではないので。
林
確かにそうですね。
名越
ですので、いままでのこだわりを持ちながら、新しいものを取り入れることにも拒否反応を持たずに挑んでいける人かどうかという、バランス感覚はなるべく会話の中で確認したいと思って面接をしています。
林
この先もスタッフは増やしていくのですか?
名越
だいぶ人も増えてきたので、より厳選したフェーズに入ってきています。ただ、いい人には来てほしいですけれど。
林
必要な人材を的確に採用したい、ということですね。
名越
そうですね。必要な人材で、かつレベルの高い人。いままでもそうだったので、そこはあまり変わりません。
ブランド映像『MAKE/HUMAN』に込めた想い
林
この3周年というタイミングで、ブランド映像『MAKE/HUMAN』が公開されました。拝見しましたが、驚きもありましたし、何より楽しかったです。おもしろかった。
名越
ありがとうございます。
林
開始早々、映画『トータル・リコール』にあったような演出があって。見た目のインパクトもありますけれど、やはりそこにはメッセージがあると思いました。「自分たちは仲間といっしょにハートでモノ作りをしていくんだ」ということを個人的には感じたわけですが、改めてなぜブランド映像を作られたのか、そして込められたメッセージについて、教えていただけますか。
名越
そう感じてもらえたならうれしいです。『MAKE/HUMAN』は、我々のスタジオで働いている社員のためのものであり、ゲームユーザーを含めた社外の方々に向けたメッセージでもあります。「自分たちはなぜモノ作りをするの?」、「自分らの存在理由って何ですか?」ということを、インパクトを持たせて伝えたかったので、ブランド映像という形にしました。文字でさらっと書いてもよかったのですが、モノ作りをする人らしい伝えかたを考えたとき「こういう見せかたもあるな」なんて思ったりして。そして、「これができるところもひとつのうちらしさなのかな」ということで、制作することになりました。
林
確実に“名越スタジオらしさ”は形になっていると思います。
名越
言葉にするとどう捉えられるかというところもあるのですが、「ハートでモノを作るって簡単に言うけれど、それは自分自身の強いこだわりと、開かれたコミュニケーションの大らかさの両方を持っていないとダメだよね」というところからスタートしている映像なので、そこはなんとなくでも感じ取ってもらえるとうれしいですね。また、あの映像は人によって受け取りかたが若干違うと思うのですが、その受け取りかたの余白みたいな部分は、新しい環境で新しいモノ作りをしているからこそ生まれるものでもあると思っています。いろいろと自由に感じ取ってほしいですね。
林
なるほど。
名越
あと、成長という意味で言えば、ゲームの作りかたもだいぶ変わりました。いまモーションキャプチャーを日々行っていますが、国内のスタジオだけでなく、スタッフが渡米する機会が増えました。日本のモーションキャプチャーが劣っているわけではないし、むしろ長い付き合いがあるから日本のスタジオのほうが安心感はあるんですけどね。アメリカでやれば時間も、お金も、手間もかかるんですが、それをやるだけの理由があり、手に入る表現のニュアンスもあるんです。今後、いま作っているタイトルを発表したとき「あの作りかたをした理由は、こういうことなのか」とプレイヤーの皆さんに“違い”を感じてもらえるようにしなければいけないというか。
林
いずれ発表される作品を見れば、表現の面で明らかに違うことがあるんですね?
名越
そうですね。そしてそれは、人間ドラマを作るという面でも大事な部分なのですが、そもそも作り手側がその違いがわかる人間でなければならない。『MAKE/HUMAN』は、違いのわかる人間を育てるというメッセージでもあるわけです。違いがわかる人が作るからこそ、いままでとは違うものを目指せるし、新しいものを生み出せる。それはスタジオを作ることもゲームを作ることも同じだと思いますし、どちらも高いレベルの技術と心を持っていなければならない。そんな意味合いを感じてもらえたらうれしいなと思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/abc04d54c6e9e3c6ec5630b4d3cd7359a.jpg?x=767)
林
どんな違いを見せてもらえるのか、期待しています! もう少し具体的に『MAKE/HUMAN』の中身についてもうかがいたいのですが、座っている名越さんの顔が分割するアイデアはどこから生まれたのですか?
名越
今回の映像を依頼したクリエイティブチームが提案してくれたものですね。ほかにもいくつかアイデアはあったのですが、半年くらい企画を練っていまの形になりました。映像ではビビッドな表現をしていますし、わりとリアルでもあるのですが、でもポップな感じも入れ込んでいて。そして、ポップだけど、軽くない質感、重量感みたいなところを目指しました。ラップも日本語、英語、中国語で表現していて、グローバルであるというメッセージ性もあります。ぜひ歌詞にも注目いただきたいです。
林
いい曲ですし、とても耳に残りますね。気付けば何度も見てしまう中毒性もありますし。
名越
楽曲は、Primaryさんという韓国のヒップホップアーティストのもので、ラップはBBY NABEさんが担当しています。最初は参考用に「こういうニュアンスで」と原曲を映像に仮で当ててもらっていたのですが、最終系を決める段階になったとき、何十回も聴いていたから「もう、この曲以外に考えられない」ということになり、そのまま決定になりました。
林
そういう経緯だったのですね。名越さんは東京FMで『THE Future Lounge』というラジオもやられて、多くの著名人がゲストとして出演されています。もしかしたら、そういうところからインプットを得る機会があったのかも? と思ったりもしたのですが。
名越
11月はNetflixの『地面師たち』でも話題の大根仁さんをゲストにお招きしていますが、映画監督やアーティスト、お笑い芸人まで、多種多様な方と番組を通じてお会いしていますね。セガにいたときは公式番組があったのですが、独立してそういう機会が減ってくると、やはり刺激が欲しくなります。私自身がラジオ好きでしたし、いずれやってみたかったことだったので、刺激を得る意味でも番組をやらせてもらっています。ゲストに来てくださる方は、いままさに話題になっているコンテンツに関わっている方たちで、そんな方々の考えかたなどが知れるのは興味深いですね。
林
わりと自由にしゃべられている印象です。
名越
もちろん台本はあるのですが、あまりそこに縛られずにトークを展開していく流れになっていて(笑)。私や構成作家さんがいちばん聞きたいこと、即ちリスナーの方が聞きたいであろうことに迫れているという感触はあります。
林
ゲーム開発で忙しいなかで、ラジオの収録をするというのは……ある意味、名越さんの息抜きのようなものになっているのでしょうか?
名越
あえて“助かる”という言いかたをしますけれど、本当に助かっているんです。収録があるのとないのでは、ぜんぜん違う。いくら恵比寿のオフィスにいるとはいえ、会社で缶詰になっていたら……山の中にいても変わらないじゃないですか。
林
そうですよね(笑)。
名越
できるだけ機会があれば外に出てインプットもしたいです。
林
インプットはもちろん、気持ちを保つうえでもラジオ収録は重要なんですね。
名越スタジオが手掛ける新作とは……?
林
以前のインタビューでドラマ性が高いコンソールのゲームを作っているものの、一度企画を大きく転換した、というお話をうかがいました。その後、開発は順調なのでしょうか。
名越
いま作っているのはアクションアドベンチャーになります。実験フェーズと、その実験をやり尽くしたフェーズを経て、アセットを量産するフェーズになるのですが、いまは量産フェーズの前夜とでも言うべき状態だと思っていただければいいかな、と。そういう意味では順調なんですが、いろんな意味でちょっと規模が大きいので。それに加え、一見するとゲームシステムが複雑ではあるんです。でも、面倒くさいゲームにはしたくないと……うーん、現時点で言えないことを抜き取って話すのは難しいですね(苦笑)。
林
(笑)。
名越
とにかく、遊び応えを担保しつつも、面倒くさいゲームにはしたくない。まったく新しいゲーム性のものは案外出てないと言っても、海外を含めると遊び切れないくらいのタイトルが世の中に溢れているわけです。その状況を見ていると、一般的なゲームファンの生活の中におけるコンソールゲームのボリューム感って、少し過剰かもしれない。いまも多くのタイトルは出ていますけど、ボリュームが売りになるようなゲームの時代っていうのは、そろそろ過ぎ去ろうとしていると感じていて。
林
そうかもしれません。
名越
もちろん、まずは数多くのゲームの中から選ばれなければいけない。そして選んでもらうことがゴールではなく、「選んでもらったうえで適正な時間の中で遊びきってもらえて、つぎに期待してもらえる」ということを目指したいです。とは言え、とくに海外のマーケットに通用するひとつの特徴として、ある程度のボリュームは必要で「最低これくらいはないと」みたいな感覚はあれど、それはある種の固定観念みたいなところもあると思っていて。ですので、「ゲームをリリースしたタイミングで、本当に適正なボリュームはどのくらいなのだろうね?」という議論を続けています。そのボリューム感の予想というか、測りかたみたいなものを、いま一生懸命に考えています。
林
ボリュームといっても、広さとともに密度も求められますからね。
名越
そうなんです。適正なボリューム、サイズに合ったゲームの密度感をどう配置していくかを考えているところですね。ただ、広さの中での遊びにドラマをきちんと織り込むことって、意外とほかのタイトルでもやれているようでやれてないことで。作ってみるとわかるんですよ。何しろ、すごくたいへんですから(笑)。
林
そのたいへんなことにチャレンジしているわけですね。
名越
はい。たいへんさを乗り越えられたら、このゲームでしか味わえないものができるということもわかっているので。いまいちばん考えているポイントなのですが、理想として掲げた高いハードルを保ったまま、諦めずに限界まで歯を食いしばってやってみようと思っています。
林
この2年と少しでゲームの骨となる部分を詰めて詰めて……ようやくそれが見えてきた?
名越
そうですね。ドラマにせよ、ゲームシステムにせよ、マップの配置イメージにせよ、試行錯誤を続けてぎゅっと詰めて作ってきました。ただ、開発をしているなかでも、いろいろな刺激的なタイトルが新たに出てきて。私も人の子なので、「うん、すごいよね」なんて言いながら焦りはするし、うちのゲームに直接は関係の薄い要素であっても、頭の中にそれが残っていたりもします。
林
でも、一度方針を転換してからは、芯をぶらさずに進めてきたわけですね。
名越
方向転換について少し補足をしますと、スタジオができて最初期のころにプランナーと詰めていた企画があったんです。ただ、わりと早い段階でブランディングの面から「うちのスタジオに求められるものではなかろう」という判断をしました。その後からはずっと変わってないですね。
林
なるほど。ちなみに、いま開発されているタイトルですが、作りたいジャンルなりゲームシステムなりがあってから、世界観やキャラクターを作ることになっていったのでしょうか。
名越
ドラマ優先ではありますけど、わりと並行ですね。ドラマを進めるということは、ゲームを進めるということでもあるので、同時にゲームパートも詰めていかなければならない。ここのゲームパートがこうだから、ドラマはこう進めなきゃいけなくて、いまの形じゃマズいよね、とか。ドラマとゲームのどちらかがスタックしたら、一度引き返して、もう一度作り直し……なんてことは、初期段階は多かったですね。というのも、これは昔も経験したことなのですが、どちらかを優先しすぎると、バランスが悪くなるんですよ。比較的、時間的な猶予があるプロジェクトであれば、ドラマとゲームを並行して進めながら「ああでもないこうでもない」とやっていくほうがいい。そして、今回はそれが許されると信じていたので、そういう作りかたにしてみました。
林
いまはまだ言えないことばかりで、言葉を選んでお話いただいているのがわかります。もうストレートに中身を聞いてしまいたいくらいです(笑)。だた、現段階でも規模が大きなゲームになりそうだということは伝わってきます。
名越
もうじきアセットの量産フェーズに入らなければならないので、そろそろ最終的なボリュームの見積もりを決める時期に入るのですが、「これで本当にいいのか」という部分について、いま考えているところですね。マップは当然あるんですけども、現段階のものは広すぎるくらいなので……。
林
それほどの広さなんですか!?
名越
今回は、既存のゲームを研究しつつ、あえてかなり広いマップを作るところからスタートしました。道や高速道路などもいったん作ってあって。いまは、そこから少しずつ縮めていって、ゲームとしてバランスのいいところを探っています。
林
マップが大きいのは魅力ですが、遊びの密度も並行してあってほしいですよね。
名越
そこですよね。密度感を出すために何らかの要素で埋めようと思えば埋められるのですが、似たような体験がくり返されるのもイマドキじゃないですし。マップの広さと遊びとしてのおもしろさを適正につなぐには、世界観と、自分は主人公として何のためにこの世界に存在しているかという部分の設計が重要だと思うんです。それを支えるのがドラマの役割だったりするわけで。すべてのバランスがよくなる、ちょうどいいサイズ感はどれくらいかを決めるタイミングが、もうまもなく……という感じです。
林
先ほどさりげなく“高速道路”というキーワードが出てきたので、現代劇なのかなと思いました。そうだとうれしいなと思いつつ、“高速道路”なら100年近く昔の話から遠い未来までがあり得るので……わからないですよね(笑)。もしかしたら、SFを作られている可能性もあるかもしれないですし。
名越
どうでしょうね(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/a1ca17dab9eb732f345b92629b632a723.jpg?x=767)
1日の90%をクリエイティブに充てる日々
林
いま開発が進んでいる作品について、どんなユーザーに遊んでほしいかといったことも考えていらっしゃると思うのですが、そのあたりはお答えいただけますか?
名越
子ども向けのタイトルかと言われたら……それはノーです。大人向けのゲームにはなりますね。レーティングは高めになると思います。
林
それを日本発で、ワールドワイド向けに。
名越
ええ。ただ、おそらく海外スタジオのライターやクリエイターはきっと作らないであろう世界観になります。「何それ? どんなものなのか見てみたいもんだ」と言ってもらえるようにしたかったので、そのユニークさにはすごくこだわっています。
林
名越さんや名越スタジオだからこそできるゲームにするぞ、と。
名越
そうですね。『龍が如く』も最初は「なんだこれ?」というところからスタートしていたので。「なんだこれ?」と言われるくらい攻める姿勢を見せることのよさは、身を持って知っていますし、今回もそのスタンスは変えたくないと思っています。
林
これまでのお話をうかがっていると、名越さんがどっぷり開発の中に入っているように聞こえます。これまでは総合監督という立場だったと思うのですが、今回はどのような立ち位置で、どういう関わりかたをしているのでしょうか。
名越
前の会社では作品ごとに関わりかたは若干違ったんですけども、以前は開発の全体を見たり、会社の経営にも携わる立場でしたので、直接的なクリエイティブに自分の時間をすべて割いてはいませんでした。そこはバランスを持ってやっていたんです。もちろんいまも「社長業があるでしょ?」ということにはなるんですが、そこは業務の比重がそこまでは大きくなくて。
林
そうなんですか!
名越
昔からずっといっしょにやってきてくれた佐藤(大輔氏)が取締役として会社経営の業務の多くを担ってくれています。彼の働きのおかげで、1日の 90% 以上はクリエイティブに当てられています。そういう意味では、ありがたい環境で仕事をさせてもらっていますね。
林
名越さんの関わりかたも、全体を統括する業務に終始するわけではなく……?
名越
もちろん全体を監督する仕事もしていますが、もっと個別のゲーム作りもいろいろやっていますね。たとえばシナリオにしても、監修のような立ち位置ではなくて、全部自分で書いているので。
林
すごいですね。
名越
ただ、シナリオもかなりのボリュームになってしまって四苦八苦していますが。
林
それは、ご自身で決められたことですから……(笑)。
名越
ゲームシステムも、かなりしっかり見ています。極端な話、これまで作ってきたようなゲームを作ろうと思ったら、もっとスムーズに進められるとは思うんですよね。ゲームシステムとシナリオのつながりや密度感を、すべてのイベントで整合性を取って考えているのですが、それはそれは気が遠くなるような作業でして。でも「自分で決めたんでしょ?」と言われたら、確かにそうなので。
林
そこは生みの苦しみですね。
名越
そうですね。なかなかしんどいですけど。
林
でも、やるぞっていう気持ちがあるんですよね。
名越
もちろんです。「やってみせるんだ」というのが心の支えなので。
林
ますます楽しみになってきました。タイトル発表は、まだ少し時間がかかると思ったほうがいいでしょうか?
名越
NetEase Gamesには我々以外にも多くのスタジオがありますから「どの順番で何を発表するのか」というプランもあると思うんです。編成の部分は私が把握できていないところもあるので、なんとも言えないですね。
林
名越さんご自身は、早く発表したいというお気持ちですか?
名越
当然です。もともと私は発表までにあまり時間をかけたくないタイプなので。できれば早めに皆さんの反応が見たいです。
林
それはそうですよね。ユーザーの皆さんがどんなリアクションをしてくれるのかは気になるところでしょうし。
名越
ええ。相変わらずフロム・ソフトウェアさんはがんばっているし、中国では『黒神話:悟空』がヒットしていたりする。ゲーム市場では少しずついろんなことが起きているなと思わせられますね。悔しいというわけではないですけど、「我々もがんばっているぞ」という証を早くお見せしたい気持ちは強くあります。
林
先ほど名越さんは「これから大量のアセットを作るフェーズに移っていく」とおっしゃっていました。その先には整えてバランスを見て……といった作業があると思いますが、ゴールが見えてきたという実感はありますか?
名越
当然ですが、すでに開発スケジュールは各所と握っています。そこを目標にゲームを作っていくだけですね。私の経験上、もうしばらく開発が進むと、締切から逆算してパートごとに泣きが入ってくるものです。もちろんゲームのおもしろさを削ぐようなことはしたくないわけですが、ではその泣きを解決するのはスケジュールなのか、お金なのか、断腸の思いで何かをカットするのか……みたいなことを決めていくフェーズにいよいよ入っていきます。
林
それは生々しいですね(笑)。
名越
それにしても、技術に関してはこの3年間でも随分進みましたね。テクニカルアーティストと呼ばれる人たちの重要性を再認識しましたし、“AIによる自動化”に対しての積極性をどう考えるか、なんてことも考えなきゃいけない。
林
AIの発達は、ここ数年で凄まじいですよね。
名越
ゲーム開発の現場は、エンタテインメントの分野ではAIと早い段階から向き合ってきました。その意味では我々の使いかたが、ひとつの指標になると思うんですよ。だからこそ、責任感を持ったAIの使いかたをしていくマインドを持つのは大事だと思いますね。加えて「AIで楽になるのはわかった、クオリティーが高いこともわかった。それで完結していいのだろうか? あえて人でなければできないことは何だろう?」なんてことも考えるようになったりして。
林
AIを使いつつも、自分たちらしさをどう載せていくのか、みたいなことですね。
名越
ええ。私はAIを敵視していないし、人の仕事を奪う脅威だとも思えない。関わる人たちがより輝くようなAI の使いかたは何だろうとか、そんなことを日々みんなで考えていたりします。
林
なるほど。名越さんが生みの苦しみを味わっていることは伝わったのですが、それでもゲームの話をしているときはすごく楽しそうに話されていて。それがすごくうれしいなと思いました。首を長くして作品を待っている方がたくさんいらっしゃるので、最後に皆さんに向けたメッセージをいただければと思います。
名越
日々、ゲーム作りと直接的に格闘しているのは本当にひさしぶりで、新鮮な毎日を過ごしています。そして、私は強いて言えばせっかちなほうなので、タイミングがくれば速やかに「こういうことをやっているよ」とお伝えしたいと思います。もしかすると、皆さんが知りたいと思っている以上に、私のほうが早くお伝えしたいと思っているかもしれないくらいです。その日を楽しみにもう少しだけ時間をください。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/acf2cf4bbc20d9e7e3261c21f33ea6e5d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/ae15e66fd3ab675b280487c2abab37bb7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/ad6851ed6953b61530fc18da0ecc1d375.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/a326028dde29a55cb1f22ee11dae0e01d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/abc04d54c6e9e3c6ec5630b4d3cd7359a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/a1ca17dab9eb732f345b92629b632a723.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/23768/acf2cf4bbc20d9e7e3261c21f33ea6e5d.jpg?x=767)