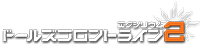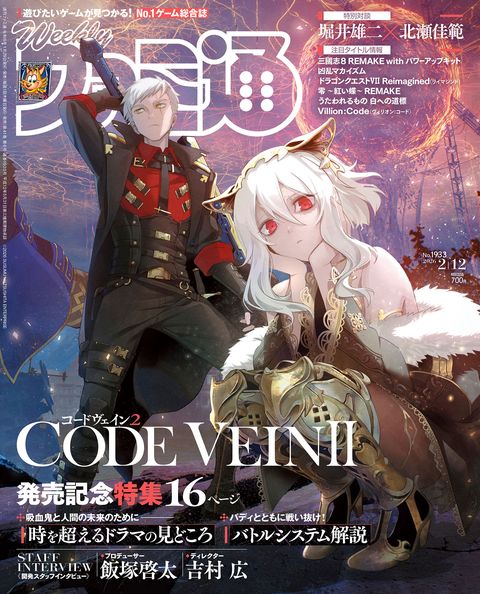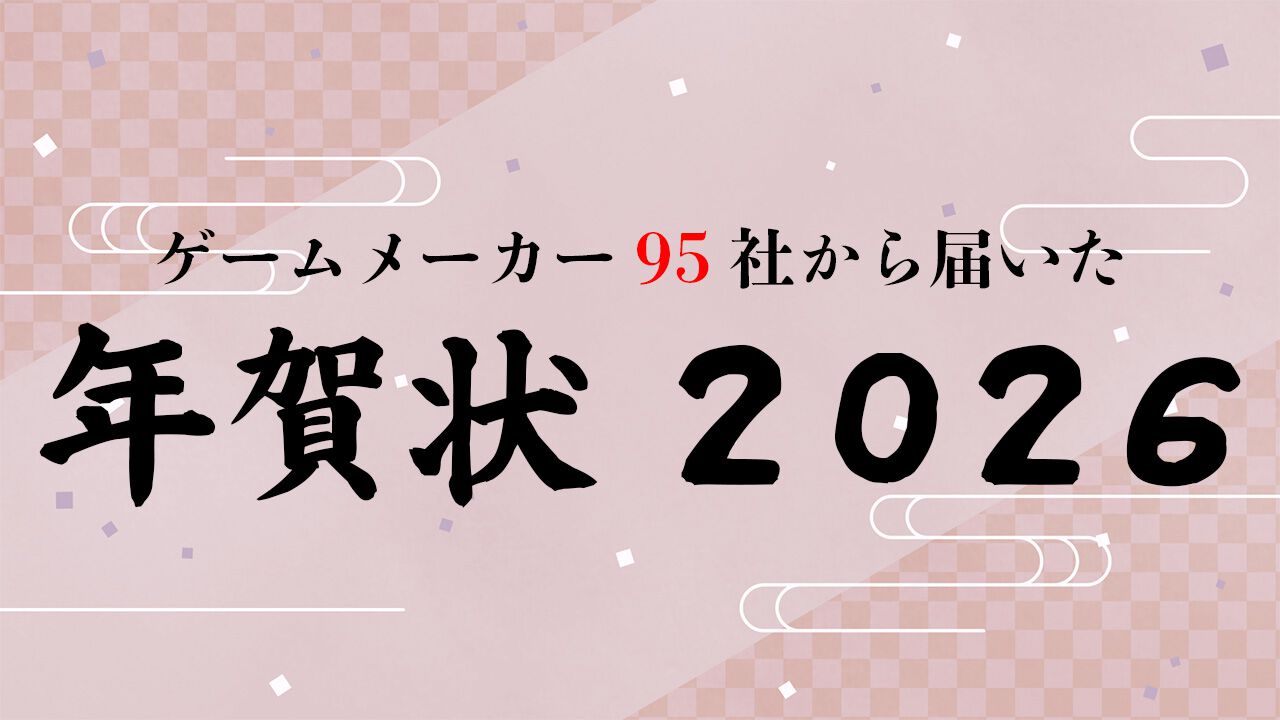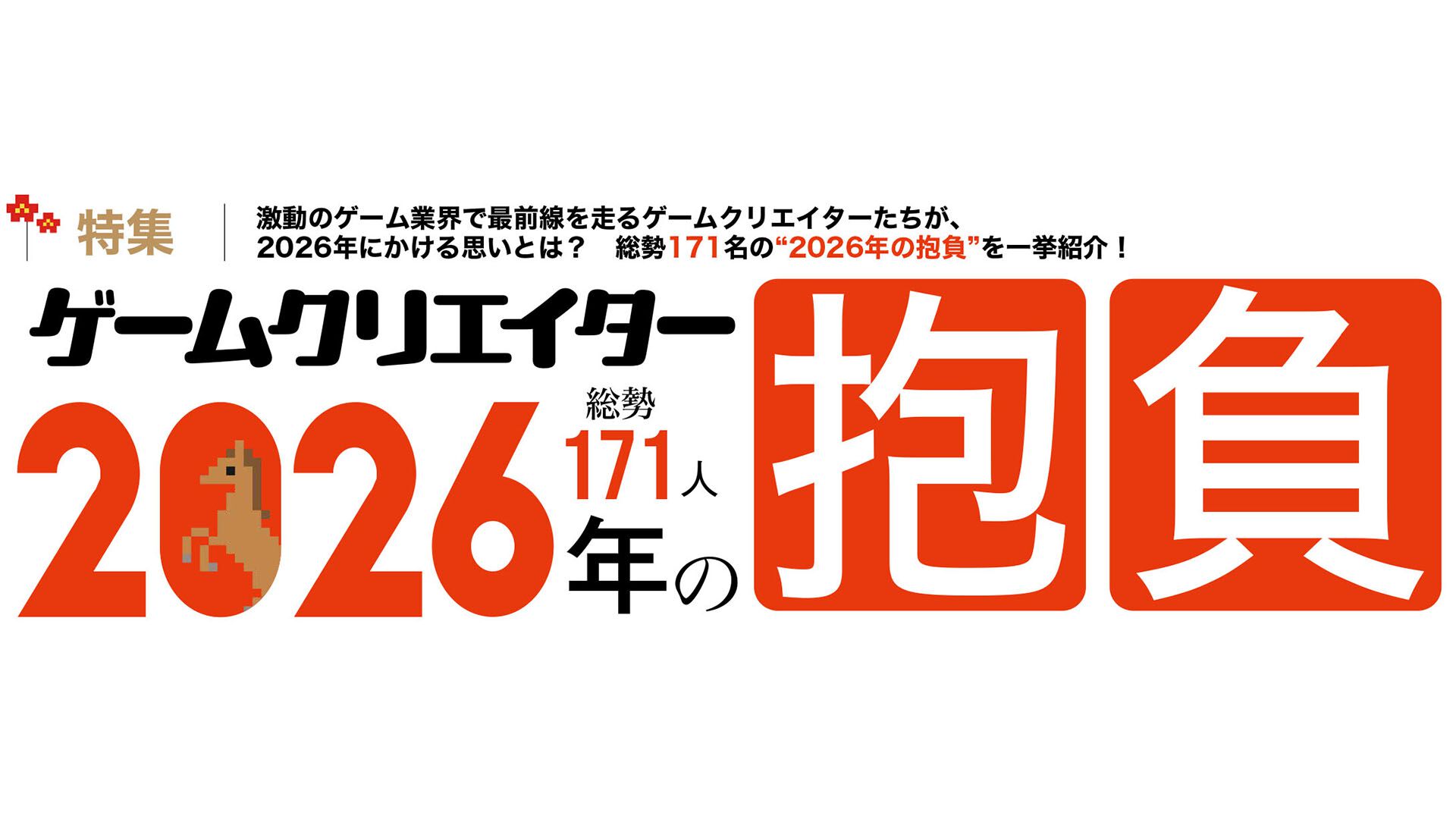映画史に輝く名作が完全新作でゲーム化
主人公の考古学者“インディアナ・ジョーンズ”を演じるのは、ハリソン・フォード(ちなみに“インディ”は愛称)。持ち前の行動力と知性、ひらめきとユーモアでさまざまな危機を乗り越え、歴史に秘められた謎に挑むインディの大冒険に、世界中のファンが魅了されている。
1981年に公開されたシリーズ第1作となる『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(以下、『失われたアーク』)は大ヒットを記録した。これまでに『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』(1984年)、『最後の聖戦』(1989年)、『クリスタル・スカルの王国』 (2008年)、『運命のダイヤル』(2023年)と、5作が公開。テレビシリーズなども人気を博し、“インディアナ・ジョーンズ”は時代を代表する文化的アイコンとなっている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/af08a80f823980709bd2602fc4073fc37.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a42041ae6afce5baa3d9dfc67d6513391.jpg?x=767)
その一端がわかるメディア向けのプレビューイベントで判明した、本作の魅力を解説していこう。さらに、ゲームディレクターのJerk Gustafsson氏とクリエイティブディレクターのAxel Torvenius氏による合同インタビューの模様もお届けする。
一人称視点が生み出す没入感
そんなインディ一行の行く手を阻むのは、インディのライバル考古学者であるエメリック・ヴォス。世界中でアーティファクトを探し求めており、その目的のためには手段を選ばない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a9b03bb16ea88163c512efe48f8efe938.jpg?x=767)
バチカンの中央部やエジプトのピラミッド、タイ族最初の王朝と言われるスコータイ朝の水中に沈んだ寺院(マーシャル大学も登場します)など、『インディ・ジョーンズ』ならではのロケーションが、本作には揃っている。
真夜中に忍び込んできた謎の大男との対決、そして遺物の盗難事件を発端に、大冒険は世界へと広がっていく。お馴染みの敵も入り乱れる中、インディは持てる能力を総動員して古代の謎を解き明かすことになる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a266d738cebfa4fc091002047c7925684.jpg?x=767)
本作最大のポイントは一人称視点。その没入感は、プレイヤーが映画の世界に入り込んでインディ自身になったような感覚を引き起こすだろう。映画でおなじみのチェイスやアクションシーンも一人称視点で展開され、迫力が大きく増している。
インディ最大の武器となるのは、その類まれなる知識だ。ロケーションに隠された謎を解くことこそ、本作の醍醐味。暗号を解読したり、残された痕跡から新たな道へ進む方法を見つけたり、ときには身体を張る必要もある。そのバリエーションは多彩だが、未知の世界に踏み込んで探索し、自分で道を切り拓いていく興奮は保証付きだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a5920afb4ab0f8f06002f588117e49dab.jpg?x=767)
また、探索の手助けとなるツールとして、カメラとジャーナルが用意されている。カメラで写真を撮れば、そのロケーションの歴史的な意味や謎解きにつながるカギを知ることができる。
ジャーナル(“聖杯日記”をイメージしてもらえればオーケー)はプレイヤーにとってガイドとなるもので、白紙からスタートするが、マップや写真、手紙など、冒険を進めることで詳細な旅の記録が記されていく。行った場所の記憶をたどることも可能で、鋭い観察力があればつぎに向かう目的地のヒントが見つかるだろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/af7e98572b3cfb9912f1a70c0f3a2ec2f.jpg?x=767)
鞭を駆使した独特のアクション
今回のイベントで紹介されたゲームプレイ映像では、インディが変装して行動するが、敵に気づかれそうになったとき、近くにあった酒を渡してその場を切り抜けるシーンも見られた。戦闘になった場合も、コンボ攻撃やブロック、パリィなどを駆使して最後にとどめの一撃をくらわすこともできるようだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a72b0fe29eaccab1251c6cf98acb329e4.jpg?x=767)
注目したいのは、インディのトレードマークである鞭。その使い道は多彩で、攻撃にとどまらず、移動時にも本領を発揮する。見張りの頭上をスイングしてやり過ごす、壁をよじ登る、遠くにある装置を動かす……その活用方法は多岐にわたる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a10e4a7bcf88232ec5e2a8cd7e3d45ac4.jpg?x=767)
ミッションをクリアーすると獲得できるアドベンチャーポイントを使うことで、インディはスキルを拡張可能だ。プレイスタイルに合わせて自由にアビリティをカスタマイズできるので、自分なりのクリエイティブな戦闘や探索が実現する。
もちろんインディ最大の“弱点”である蛇も登場するようだが……インディはどのようにして難局を乗り越えることができるのか。その方法はプレイヤー次第。自分の好奇心に任せて、世界を股にかけた大冒険を思う存分楽しもう!
MachineGamesが挑むインディの新たな冒険
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/abc6cc615ed2497a750a85c6835cf9778.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/aae2c509528c2e11fd1ecb8c03a0f9728.jpg?x=767)
――時代設定を『失われたアーク』と『最後の聖戦』のあいだとした理由は?
――ゲームシステムを一人称視点にしたのはなぜですか?
一人称視点ならばパズルのような仕掛けとプレイヤーの距離が非常に近くなり、ミステリーや不可思議なアーティファクトを表現するには一人称視点がもっとも適しています。
私にとって、キャラクターになりきって、ゲームで描かれる世界に存在するような感覚になれて、ゲームの主人公の目を通して世界を体験することができることが、もっとも重要なポイントです。
――プレイヤーはさまざまな行動を通してアクションポイントを獲得できるようですが、このポイントを使うスキルシステムがあるのでしょうか?
アドベンチャーポイントは何かを発見したり、アクティビティを行ったりすることで獲得できますが、これはゲームの中で非常に重要な役割を持っています。
――リニア(進行ルートがあらかじめ設定されているゲーム)とオープンワールドの中間という形になっているのでしょうか?
本作にはサイドも含めてたくさんのコンテンツがありますが、私たちはゲーム内でプレイヤーが行うすべてのことが、全体のストーリーラインに貢献するものになるようにしています。ただし、探索するかどうかはプレイヤーが決めることです。
――ロケーションによってはステルスが必須になるのでしょうか? たとえば、死体を隠して敵の注意から逃れるとか……。
ゲームデザインを考えるにあたり、自分の歴史を振り返る機会がありました。本作は一人称視点がメインで、状況に合わせて三人称視点になりますが、このような組み合わせのゲームは『The Chronicles of Riddick』(※1)や『The Darkness』(※2)とよく似ています。
先ほど挙げた『The Chronicles of Riddick』にもつながるのですが、一人称視点のゲームにおける課題であり、本作でも私たちが時間をかけて開発しているのが、緊張感溢れる近接戦、格闘戦です。ほかのゲームと異なるのは、ここに鞭が加わることです。近接戦と鞭が組み合わさったことで、プレイヤーそれぞれが異なるプレイスタイルを楽しめると思います。
――鞭はインディにとって大事なツールですが、この象徴的なアイテムをどのようにしてゲームプレイに落とし込んだのでしょうか?
もちろん、ビジュアルやサウンドも非常に重要な要素ですし、これらの要素がいっしょになったうえで、シナリオを正しく実行できるツールを確認しなくてはなりません。もちろんゲームプレイとデザイン、マップ内でのサポート、適切でおもしろいレベルデザインがあってこそ、プレイヤーはつねにクールかつドラマチックに鞭を使うことができます。
鞭を使ったアクションには非常に多くの要素が関わっており、ゲーム体験の重要な部分のひとつになっています。その完成度にはとても満足していますが、とにかく「たいへんだった」と簡単に言うだけでは済まされないほど、苦労しました(笑)。
――『大いなる円環』はアドベンチャーゲームに新しい風を吹き込む作品になっていると思いますか?
しかし、私たちは若い頃に観て夢中になった映画のように、楽しくて軽快なアドベンチャーをお届けできるよう開発しています。クールなロケーションを訪れ、トラップを避けて暗い墓所を探索しながら、異なる文化を持った特色あるキャラクターたちに出会うことができます。
すべての要素がすばらしいアドベンチャーを構築していますので、最初に述べた通り、本作は新しい風を吹き込む作品になると確信しています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a127b0d73ec5b15793878d7bc3cc9c3a1.jpg?x=767)
本作は銃をバンバン撃つようなゲームではなく、多くの人が楽しめるカジュアルでリラックスしたゲームとなっています。謎解きや探索にフォーカスしていますが、とはいえ開発のコアとなる部分は同じです。ゲームの世界に溶け込み、主人公になりきって大冒険の一部になったと感じられる体験を目指しています。
――サイドクエストもたくさんありそうですが、プレイヤーはいつでもクエストを自由に楽しめるのでしょうか?
プレイヤーが望めば、ストーリーラインに沿って一気に物語を進めることができる、いわゆる“ゴールデンパス”はあります。しかし、非常にたくさんのコンテンツやサイドミッションを用意していますし、確実に私たちが開発してきた中で最大のボリュームとなっています。
――謎解きはどれくらい複雑なものなのでしょうか?
私もレビューするためにプレイしたのですが、最初は難しくとも解けると「自分はなんて賢いんだ」と感じることができました(笑)。
Axelが言っていた大規模な謎解きは、メインのストーリーラインの一部に登場するものです。サイドクエストにも謎解きは豊富にありますが、プレイヤーはすべてのサイドクエストに挑戦する必要はありません。自分で選べるのはいいことだと思います。
ひとつ言っておきたいのですが、ゲームのスタート時点で難易度を設定することが可能で、謎解きが難しすぎないゲーム体験を選べます。また、プレイヤーはカメラとジャーナルを使えるのですが、これらがある意味で謎解きのヒントになっていると言えます。
――プレイヤーはロケーションを自由に移動できるのでしょうか?
そのため、さまざまなロケーションを再訪できるようにしています。クリアーなストーリーラインはありますが、何かしらの機会を逃したと感じたり、違う場所にあるサイドクエストをやりたいと思ったりしたとき、自由にロケーションを行き来できます。
――『インディ・ジョーンズ』という巨大なフランチャイズが持つ“伝説”に忠実であることと、そのフランチャイズで新しいものを作ること、そのバランスを取るのは難しくありませんでしたか?
最初に『インディ・ジョーンズ』が提供する“すべて”を捕らえることに挑戦しました。私たちは映画ではなくゲームを作ろうとしており、映画から何らかの情報やアイデアをつかんだら、それらを一人称視点のゲームで体験できるように置き換えました。
これらのバランスを取る努力をしました。そこには多くのものが関係しています。まずはナラティブの部分です。カットシーンも含めたストーリーがどのように描かれ、会話が交わされ、俳優がいかに演じるか……。動きやビジュアルの部分もあります。
そして、ゲーム内で描かれるシチュエーションを解決するために、インディは何をするのか。そのエッセンスをしっかりと抽出して描写することは、指針のひとつとしてつねに持っています。時には『インディ・ジョーンズ』というIPのコアとなっているテーマを優先することもありますが、私たちがゲームをおもしろくするために描きたいものとのバランスを図る努力が必要でしたが、Lucasfilm Gamesと密に連携することで“道”から外れないようにできたと思います。
意見を交換し、本作は『インディ・ジョーンズ』と冠するにふさわしいゲームになっているとLucasfilm Gamesが感じてくれているか、つねに確認しました。また私たち自身も、作りたかったゲームを開発していると感じているかも大事にしてきました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a8cadf1bf965fe872ecd313b305f36e68.jpg?x=767)
映画を監督したスティーブン・スピルバーグ氏は「インディアナ・ジョーンズはスーパーヒーローではないスーパーヒーローだ」と言いましたが、これは本作におけるインディの表現に影響を与えました。彼の動きや、彼が世界を冒険する際にはしっかりと地に着いた表現になるようにしています。
岩棚をよじ登ったり、鞭を使って移動したりするのは容易ではなく、非常に体力を使いますよね。私たちはその表現を、ゲームだけでなくキャラクターにおいてもプレイヤーが納得できる形で伝えるようにしています。これは楽しい作業でしたし、当初から実現したいと思っていて、その結果は理想に近づいています。
――Lucasfilm Gamesからリソースの共有はありましたか?
また、『レイダース』撮影直後のインディアナ・ジョーンズを描く必要がありましたが、時間を遡って若いころのハリソン・フォード氏の顔をスキャンすることはできません。そこで私たちは、Lucasfilmのアーカイブにある映画の資料や、80年代に撮影されたフォード氏の写真などを活用して、本作におけるインディのモデルを作成しました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/14738/a438e621755ae891eb98300c443ef33bf.jpg?x=767)
ただ、前述した通り、私たちが開発してきた中でも最大規模のゲームであり、その空間や領域だけでなく、プレイ時間も最長となります。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。