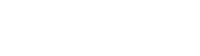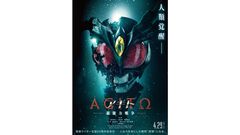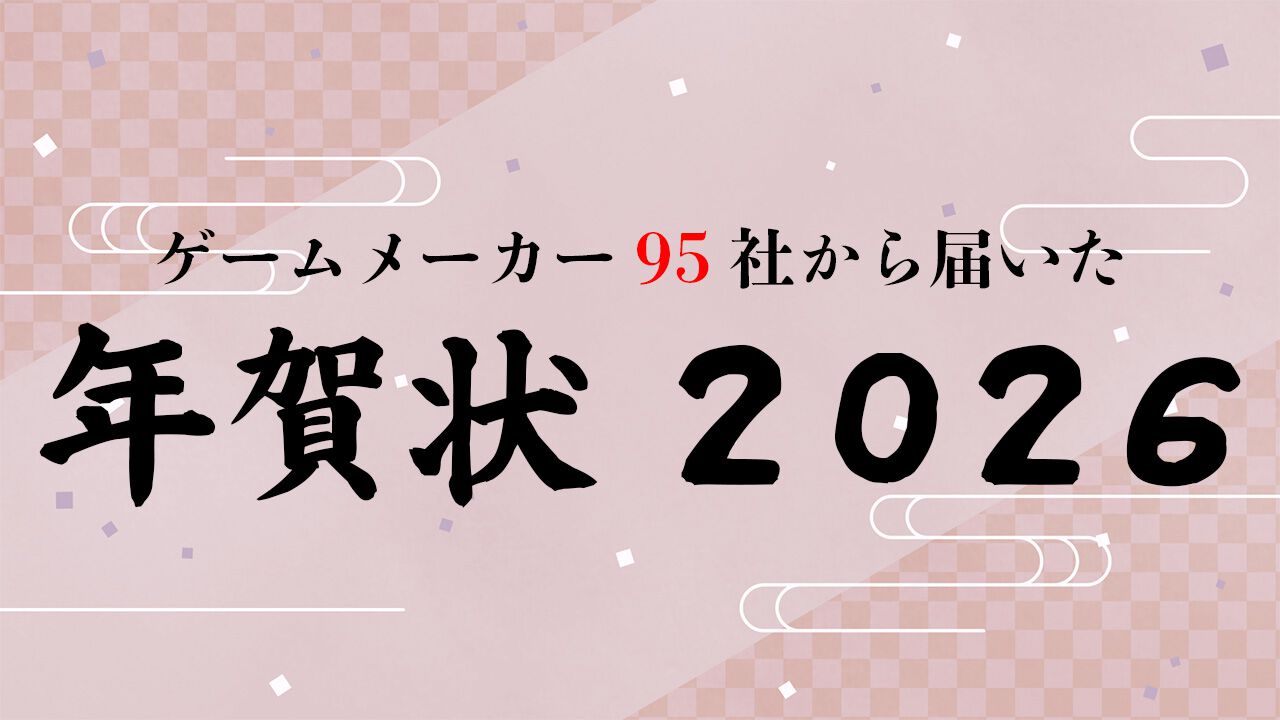講演を行ったのは、ハンティングアクション『モンスターハンター』(モンハン)シリーズのプロデューサーを務めることでおなじみの、カプコンの辻本良三氏(※)。今年(2025年)で21年目を迎え、“ほかのプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む”というプレイジャンルを確立した『モンハン』シリーズの継続と仕掛けに関して、当時の開発エピソードも交えて存分に語られた。
『モンハン』のテーマは、“誰でも参加できる”こと
そして2004年には初代『モンスターハンター』にてネットワークプランナーとして関わり、2007年に『モンスターハンターポータブル 2nd』のプロデューサーを担当。以降、『モンハン』シリーズのプロデューサーとして活躍している。
21年目を迎え、世界中から注目を集める『モンハン』シリーズ
そんな『モンハン』は、グローバルでトータル45万本の売り上げを達成している。開発としても手応えを感じていたが、同時にハードウェアやネットワーク環境面で、オンラインゲーム自体のハードルの高さが課題となっていたようだ。
大きな変更&追加としては、新4武器種の追加、そしてサーバー側企画の強化だ。前者は太刀、ガンランス、狩猟笛、弓の4種が加わり、よりやり応えが増している。後者は、モンスターの狩猟数によって素材の値段(価値)が上下したり、昼夜や季節が変化するとなど、より自然やリアルを感じられるシステムが導入されている。
また、国内で初の100万本突破タイトルで、感慨深い作品だと辻本氏は語る。事実、日常生活的にも『モンハン』という単語を目にする機会が増えてきたタイミングでもあり、シリーズ人気の火付け役であるのは間違いないところだろう。
また、こういったイベントでは、現地までの道のりや待ち時間などでゲームをプレイする機会が増えるため、それが携帯機の持ち寄りともうまく噛み合って、大きなプロモーション効果が得られたと同時に一大ムーブメントにつながったイベントだったと辻本氏は語った。
また、おなじみのフレーズ“一狩りいこうぜ”が生まれたのもこのとき。もともとは広告代理店でのコンペティションで発案されたもので、このフレーズを見て即座にプロモーションの方向性を決めたほどインパクトがあったそう。
しかし、水中は設地面がないためか、プレイヤーが距離間をつかみにくく、プレイヤーに求める操作難度と、開発面における制作難度の両方が上がることになってしまった。そのため、きちんと遊びとして成立しなければ水中戦自体を切ることも視野に入れて開発していたとのこと。
ちなみに、本タイトルには著名占い師であるゲッターズ飯田氏による占いが導入されているのだが、数十年分が貯蓄されているらしく、いま現在占ってもきちんとした結果が出てくるという。
また、本タイトルには温泉が出てくることから、長野渋温泉とのコラボも実施していた。温泉全体のデコレーションに加え、携帯機を持ち寄って遊べるスペースも設けるなど、コミュニケーションの場としても機能していたイベントだった。
当初は『モンスターハンター3(トライ)』の移植をベースに、モンスターを1体追加できれば……くらいのイメージで開発が進められていたそうだ。
『モンスターハンター4』で目指す高低差のあるアクションがどんなものなのか、モンスターが立体的な地形にどう対応するかを社内でイメージ共有することも考慮に入れて制作された映像だ。実際に『モンスターハンター4』では高低差を使った攻撃やアクションが多く導入されてもいる。
新システムとして導入されたのは狩猟スタイル。当時、多くのプレイヤーが独自のプレイスタイルで遊んでくれていることも考え、プレイヤー自身が自分のプレイスタイルをより突き詰められるようなシステムを盛り込んだ。自分の好きな武器種に、狩猟スタイルと狩技を組み合わせ、自分好みのプレイスタイルで遊べるという方向性は、企画段階からすでに決まっていた。
『モンハン』でもっともスポットが当たるキャラクターはモンスターである、と辻本氏。モンスターをクローズアップしつつ、アクションが苦手な人でも遊べるRPGジャンルの『モンハン』を作りたいと考えはずっとあったものの、なかなか立ち上げが困難な状態が続いていたという。後に大黒ディレクター(大黒健二氏)と出会い、完成にいたったが、ゲーム制作において人との出会いは本当に大切だと辻本氏は振り返る。企画考案から発売まで、じつに8年ほどかかっているそう。
現在は続編の『モンスターハンター ストーリーズ2』も発売され、シリーズ累計売り上げで300万本を超えるほどに。また、『モンハン』本編の未経験者が多く、新たなファン層の獲得にもひと役買っている。
同タイミングで、海外イベントへの出展や現地ファンとのコミュニケーションも積極的に。海外ファンのコミュニティも増加し、今後のグローバル展開にも好影響を与えたとのこと。
世界を見据えた戦略――グローバルで広く展開される『モンハン』
立体的なアクションとフィールドのさらなる進化、モンスターどうしの干渉や環境利用など、『モンハン』の世界を感じてもらいつつ止まらないアクションが楽しめることを目指して制作された。
それまでの『モンハン』にあった、回復薬を飲んでのガッツポーズも、フィールドがシームレスになった関係でゲーム性そのものがスピーディなものに変化したため、硬直時間を撤廃し、より止まらないアクションを目指すということになったようだ。
最終的にモンスターの体力ゲージは出さない方向で固めたため、状態を見て判断してほしいという大事な部分は残しつつ、プレイヤーの攻撃の成功と失敗はわかりやすくなったので、このタイミングで導入してよかったと辻本氏は当時を振り返った。
情報の出しかたにも気を遣っている。グローバルで同タイミングの情報出しはもちろん、各グローバルイベントでの情報発信も心がけて、日本、アジア、欧米での情報の切り分けも行った。
また、『モンハン』シリーズでは、開発初期の段階で各種出展イベントや体験版、ベータテストなどの予定を決めてしまう。そうすることで、緊急な作業が発生することを防げるそうだ。
各地域のユーザーの声も、コミュニティマネージャーから開発へ届くようにしている。『モンスターハンター:ワールド』時点ではコミュニティマネージャーは5名だったが、『モンスターハンターワイルズ』のタイミングでは9名ほどに増員しているそう。
そういったさまざまな施策の結果、『モンスターハンター:ワールド』は全世界で2850万本を超えるセールスを記録している。
続いて登場したのは、2021年に発売された『モンスターハンターライズ』。『モンハン』が広がったきっかけである携帯機に、どうしても『モンハン』を提供したいという思いから開発が決定。より立体的でスピーディなアクションを目指すため、翔虫(かけりむし)やオトモガルクといったシステムを導入している。
ここで、本タイトルの初出開発動画が流されたが、こちらは残念ながら撮影禁止。内容は、荒々しい生態系や群れの実現度の検証を行ったテスト動画だ。デザイナーなどもあまりいない時期で、当時使えたモデルなど使って作られていたそうだが、肉食モンスターの群れと草食モンスターの群れがぶつかり合う様が確認できた。