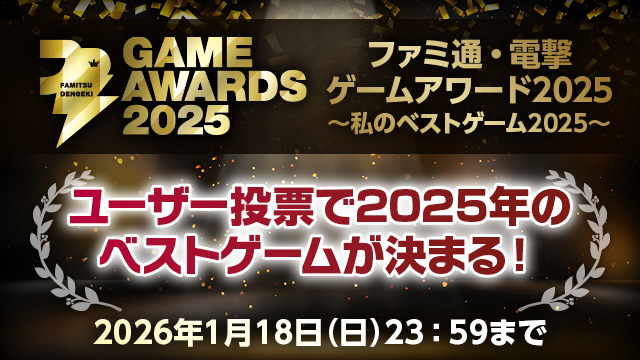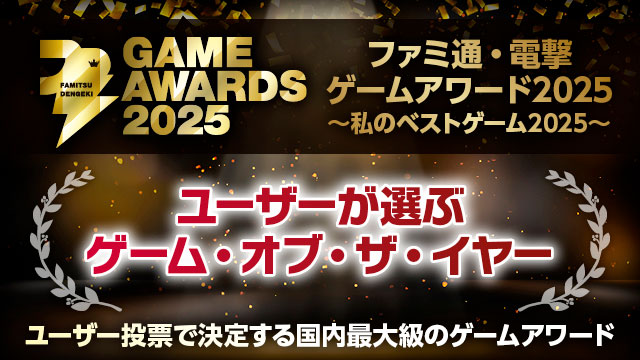ソウルライクとは、言わずと知れた高難度アクションの代名詞。ソウルライクアクションRPGでありながら、その個性を棒に振ってまでイージーモードを実装しようというゲームがある。『Lies of P』だ。
なぜか。きっとクリエイターが表現したいものは別の部分にあったのだ。最後までプレイして感じたのはある種の決意。このゲームが真に描きたいものは“人間性とは何か”であり、“嘘に込められた真意”である。
アクションが苦手な人は、戦闘に気を取られるあまり裏側に考えを巡らせる余裕がなくなる。ソウルライクのプライドを捨ててでも、難度を下げてでも伝えたいことがあったのだろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a3cb35a25157718920f7a6be13c3146b8.jpg?x=767)
この記事は『Lies of P』の提供でお送りします。
特殊な物質“エルゴ”の発見により多くの自動人形が生み出され、大いなる文化的発展を遂げた架空の都市クラット。しかし、優雅な生活はある日を境に起きた自動人形たちの暴走によって一転する。美しい街は、一夜にして殺戮人形が跋扈し死の病が蔓延する“崩壊した都市”へと変容してしまった。
そんな中、主人公である“ゼペットの人形”が起動する。1800年代の華やかなベル・エポック時代をモチーフにした、おぞましさの中に耽美さが蠢く崩壊都市を探索し、彼は事態の究明へと向かう。
これが『Lies of P』における物語の始まり。2025年夏発売されるDLC『Overture』では、本編の前日譚が描かれ、物語がより深堀りされる。その前に一度、このゲームが何を表現したかったのかを振り返ってみたい。
※企画の性質上、ストーリーのネタバレを含んでいます。気になる方はプレイした後に読み進めてください。おぞましい世界。だからこそ輝く、美しい嘘
このゲームのストーリーは“ピノッキオの冒険”が下敷きになっている。おしゃべりな人形・ピノッキオが主人公で、嘘をつくたびに鼻が伸びて……と、誰もが知るあの童話だ。
彼が人形から人間になるまでの様子が描かれるわけだが、それは本作も同じ。道中でいろいろな事件が起こるものの、大きな目標のひとつに“人間になる”という要素があることは間違いないだろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
この青年がピノキオに当たる主人公。原作では妖精(や魔女)が人形から人間にしてくれるが、このゲームでは自らの選択で人間になっていく。
では、人間になるとはどういうことか。ここで注目したいのが原作でも重要なファクターとなる“嘘”だ。『Lies of P』の世界における人形たちは、いくつかの制約のもとで働いている。そのひとつが“嘘をつけない”こと。彼らに発話する機能はあれど、嘘をつくことは許されていない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
人形たちには4つの“偉大なる約束”が義務付けられている。SFなどで定番のロボット三原則のようなもの。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
オープニングでは、生活に根付いて大いなる発展をもたらした人形たちが狂うまでの物語が描かれる。
しかし、主人公は人形でありながら嘘をつくことができる特別な存在だ。そして嘘をつくたび、彼自身の体には熱と鼓動が駆け巡り、“人間性”を獲得していく。
つまり、『Lies of P』において、嘘は人間性の象徴として描かれている(人形と人間の対比に限った表現ともとらえられるが)。嘘をつくか真実を伝えるかをプレイヤーが選択する場面がいくつもあり、選んだ選択肢によってエンディングが変化する仕様だ。“嘘をつく”要素自体が、結末に影響するレベルで重要視されている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)
嘘の数に応じて鼻も伸びる。ただし本人ではなく絵画の。
かといって、このゲームは嘘を“よくないもの”として定義しているわけではない。選択肢における嘘は、そのほとんどが相手を慮った結果、出た言葉になっている。
たとえば、登場人物のひとりであるアントニア婦人にかけた言葉。彼女は死に至る病“石化病”を患っている。『Lies of P』の世界で猛威を振るう疫病で、物語の中盤ではこの病の特徴である青い疱疹に顔の右半分が覆われてしまう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)
石化病の影響で顔の半分が動かない。笑顔を作ろうとしても片頬しか上がらないのだ。
そんな彼女は、過去の美しい自分が描かれた絵画を見て語るのだ。「いまの私にも、この絵画のような美しさは少しでも残っているのだろうか」と。
それに対し、主人公は「残っている」と、彼女を気遣うような言葉で応えることができる。彼女のための優しい嘘をつく。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)
アントニア婦人はお歳を召した姿もたいへんお綺麗。キャラクターとしてもとてもいい。プレイヤー心理的には真実と言えるだろう。
絵画の中で微笑む彼女は若く、美しく、まさしく社交界の華と呼ぶべき出で立ちであり、病に侵された老婦人の姿とは比べるべくもない。内に秘めた精神性や芯に秘めた美しさなどは変わっていない……とは言えるかもしれないが、あくまで外見上の話をするのであれば、“すでに失われている”というのが真実であろう。実際、この選択肢により人間性を獲得することからも、発した側も嘘と認識しているのは確かだ。
アントニア婦人はその気遣いをマナーがいいと褒め、「美しい思い出はまだ私の中に残り続けている。だから、あなたもそのような大切な思い出を積み重ねていってね」と続ける。退廃的な世界を描くゴシックホラーとは思えないほど、心地いい対話の時間だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
婦人の言葉で心に温かさが満ちたことも、人間性を獲得した要因のひとつかもしれない。
『Lies of P』のシナリオは全編にわたって人間の醜悪や欺瞞が目立つものの、主人公がつく嘘はそうではない。たまに自分が有利に働くような嘘をつくことはある。それは余計な戦いを回避するためであり、誰かを陥れることを目的としていない。全体的にきれいな嘘なのである。
無論、「汚い嘘をつく姿は主人公として受け入れられにくい」と商業的な事情もあるだろうが、筆者としては「嘘は、悪とは限らない」というメッセージを感じずにはいられなかった。ちょっと言いすぎかもしれないが、「人間とは美しい嘘をつける存在である」と思いたいのかもしれない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
ストーリー全体は、とある人物の大きな嘘が支配しているようなイメージ。だからこそ優しい嘘はささやかな光を放つ。
この世界をひと言で説明すると“希望がない”。先ほど人形が発達して~~と背景事情を書いたように、人形たちのほとんどはある日を境に人間を襲い始めるようになった。無論、たくさんの人形が街にいたので、クラットは一歩外に出ると殺戮人形がそこら中をうろつく最悪の都市と化している。
さらには石化病も蔓延。外に出れば死。待っているだけでも病で死。“この世の終わり一歩手前”のような状況だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
そんな世界観も相まって、演出には生理的嫌悪を抱かせるような気持ち悪いものが多い。人間を襲うため首のない姿でも徘徊する人形しかり、串刺しにされながらも無意味に踊り続けるステージ上のバレリーナ型オートマトンしかり。
ここまでは人形(機械)だからまだいい。問題は、謎の要因で怪物と化した元人間“カーカス”である。各部に人間らしい特徴を残しつつも、異常に発達した四肢と人間には存在しないはずの器官を振り上げながら襲い来る姿には吐き気すら覚えた。斬りつけるたびにこちらを汚す青い体液も気味が悪く、最初のうちは見つけても斬りかかることを躊躇してしまうほど。言ってしまえば、全体的に趣味が悪い。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)
美しいものは目に見えない
“狙って”演出しているであろう外見上の醜悪さの反面、言葉や音楽は“美しいもの”として描かれている。とくに音楽は顕著だ。収集要素のひとつにもなっており、ステージの各地に“レコード”という形で配置されている。
このレコードの人間性を高めてくれる要素のひとつ。蓄音機にレコードをかけて音楽を聴くことで、彼は人形から人間へと成っていく。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473.jpg?x=767)
最初は「嘘はわかるが、なぜレコードで人間性が獲得できるのか?」と疑問だった。芸術を理解する心=人間性とするなら絵画でもいいはずだ。しかし、クラットの街を歩くことで何となく見えてきたことがある。
街は崩壊寸前ながらも、まだ生きながらえている人がいる。そして時折、生き残った人々の歌や音楽が建物の一室から聞こえてくる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)
“明かりがついている部屋=まだ中に人がいる”描写だと考えられる。話しかけられるNPCも何人かいる。
筆者はこの光景に“人間”を思った。恐ろしい現実を跳ねのけるかのように美しい旋律を奏でる人々は、とても“人”らしいと。音楽に逃げようとしているのかもしれない。自分は最期までここにいたと証明しているのかもしれない。理由がどれだとしても、その姿に人間を感じずにはいられなかった。
映画『タイタニック』では、船が沈没する間際まで音楽を奏でる音楽隊がいた。パニックに陥る乗客が少しでも心の平穏を手に入れられるように楽器を手に取ったのだという。その姿を見たときの感覚に近いだろうか。
もう明るい未来は来ないかもしれないが、最期まで人間らしく、心穏やかに。古来より人とともにあった音楽を抱き、すばらしい日々を思い返しながら過ごす情景は、どこか儚い。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c.jpg?x=767)
光る窓を中心に漏れる歌声。それを聞いて「そういうことか」と何となく納得する。
思うに、目に見えない“人間性”を強調するために、ゲーム内で目に映るものをあえてグロテスクな表現にしているのではないだろうか。
ベル・エポック時代らしい華やかな耽美さを塗りつぶすように、殺戮人形と怪物により破壊されたおぞましいビジュアル。目に映るものが恐ろしく、気持ち悪いからこそ、目に映らない言葉や音は――暖かい嘘や蓄音機により奏でられる音楽は、よりきれいなものとして感じられる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)
殺戮人形により滅んだ街。だからこそ、まだそこに生きている人の生命力を色濃くを感じる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)
道中、主人公は激しい怒りを抱いたり深い悲しみに暮れたときも人間性を獲得する。『Lies of P』は、こういったいかにも“ロボット(人形)と人間の対比”以外に、嘘と音楽でも人間性を表現している。
非人間的であるおぞましいもの、人間的である美しいもの。それらを見えるもの、見えないものとして対比させた、“人間性”という不確かなものの証明。それこそが筆者の琴線に触れた。
もちろんまったくの公式見解ではないし、飛躍した意見かもしれない。いちプレイヤーの感想じみた結論だと思ってもらいたい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd.jpg?x=767)
難度が下がろうとおもしろいのは変わらない。そう断言できる
“ソウルライクアクション”としての魅力がフィーチャーされがちだが、シナリオやビジュアルによる見せかたにこそ『Lies of P』らしさがあるように思う。そう考えると、アクションのハードルは高くないほうが望ましい。話の続きが気になるのに先に進めないのはもどかしいから。
実際のゲームプレイを振り返ってみても、難易度は同ジャンルのほかタイトルと比較して優しめ。DLC『Overture』が発売されることもあって、せっかくだからプレイしようと思い立ったのがここ最近(2025年4月~5月)のことなので、発売直後の2023年時点の状況はわからないが、かなりマイルドな調整をされているように感じる。
ステージにいる雑魚敵の数がそこまで多くなく、ほぼすべてのボス戦で強力なNPCを召喚可能。あまり詰まらずに攻略できた印象だ。そのぶん物語考察の想像の翼が広がったので、まんまと開発者の手のひらで踊ってしまった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a030d7e8e966169ab4c7f67c291c333f4.jpg?x=767)
奥にいる白髪が呼べるNPC。召喚にはアイテムが必要だが、かなり集めやすいので数に困ることはない。
もちろん、「ソウルライクのゲームにしては」という評価なので、一般的なアクションゲームとしてはしっかり難しいものではあるだろう。筆者の場合、ひとつのボスで数日かけるような事態にはならなかった。
装備も優秀なものが多く、アミュレット(特殊な効果を持つ装飾品)の中には“スタミナがない状態でも回避が可能”のようなとんでも性能持ちもあったりする。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)
敵の攻撃はジャストガードか回避で何とかするゲーム性なのだが、このアミュレットのおかげで回避主体のプレイがやりやすかった。
武器はふたつのパーツを組み合わせて製作するシステム。モーションを担当する柄部分、攻撃力やリーチなどを担当するブレード部分に分けられるため、振りがコンパクトな軽量武器のモーションで、リーチと攻撃力に秀でた大剣を振り回す、みたいなこともできてしまう。この点も、比較的遊びやすいと思った理由のひとつだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec.jpg?x=767)
クラット警棒の柄+長リーチ大剣の組み合わせがお気に入り。中盤以降に大活躍した。
イージーモードが実装されるまでもなく、かなり遊びやすい部類とはいえ、物足りなさを感じることはない。むしろ濃厚で考察しがいのあるストーリーや華美なビジュアルを存分に堪能できたように思う。
「高難度なアクションを楽しみたい!」なんて人にはわからないが、少なくとも筆者としてはいいバランスだった。ソウルライクの登竜門として考えてもいいかもしれない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)
こんなことを書いてはいるが、実際いっぱい倒されてはいる。
これから先、イージーモードが実装されればさらに遊びやすくなるだろう。『Lies of P』の前日譚となる物語であるDLC『Overture』は2025年夏発売。遊ぶためには本編の物語をある程度まで進めなければいけないが、イージーモードであればかなり楽になるはず。手軽にDLCを体感できる面でもありがたい要素だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/acf5793938b321b67b3b667655b375703.jpg?x=767)
ボスは意味不明が言語をしゃべるのだが、2周目ではこの言葉の意味がわかる。難度の低下によってこういった周回要素も回収しやすくなる。
そういった実用的な面でももちろんだが、筆者の考えとしては最初に言ったとおり。『Lies of P』という物語を、ひいてはゲームの“味”を存分に楽しむために最適なモードになるだろう。これならアクションが苦手な人にもおすすめしやすい。
このアップデートをきっかけに、『Lies of P』が描く美しい嘘の世界に足を踏み入れる人が増えてほしい。そう願うばかりである。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aeb935669c45405844c35aafbd5fe43d7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a3cb35a25157718920f7a6be13c3146b8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a030d7e8e966169ab4c7f67c291c333f4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/acf5793938b321b67b3b667655b375703.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42634/aeb935669c45405844c35aafbd5fe43d7.jpg?x=767)