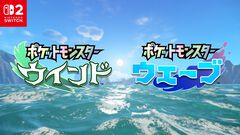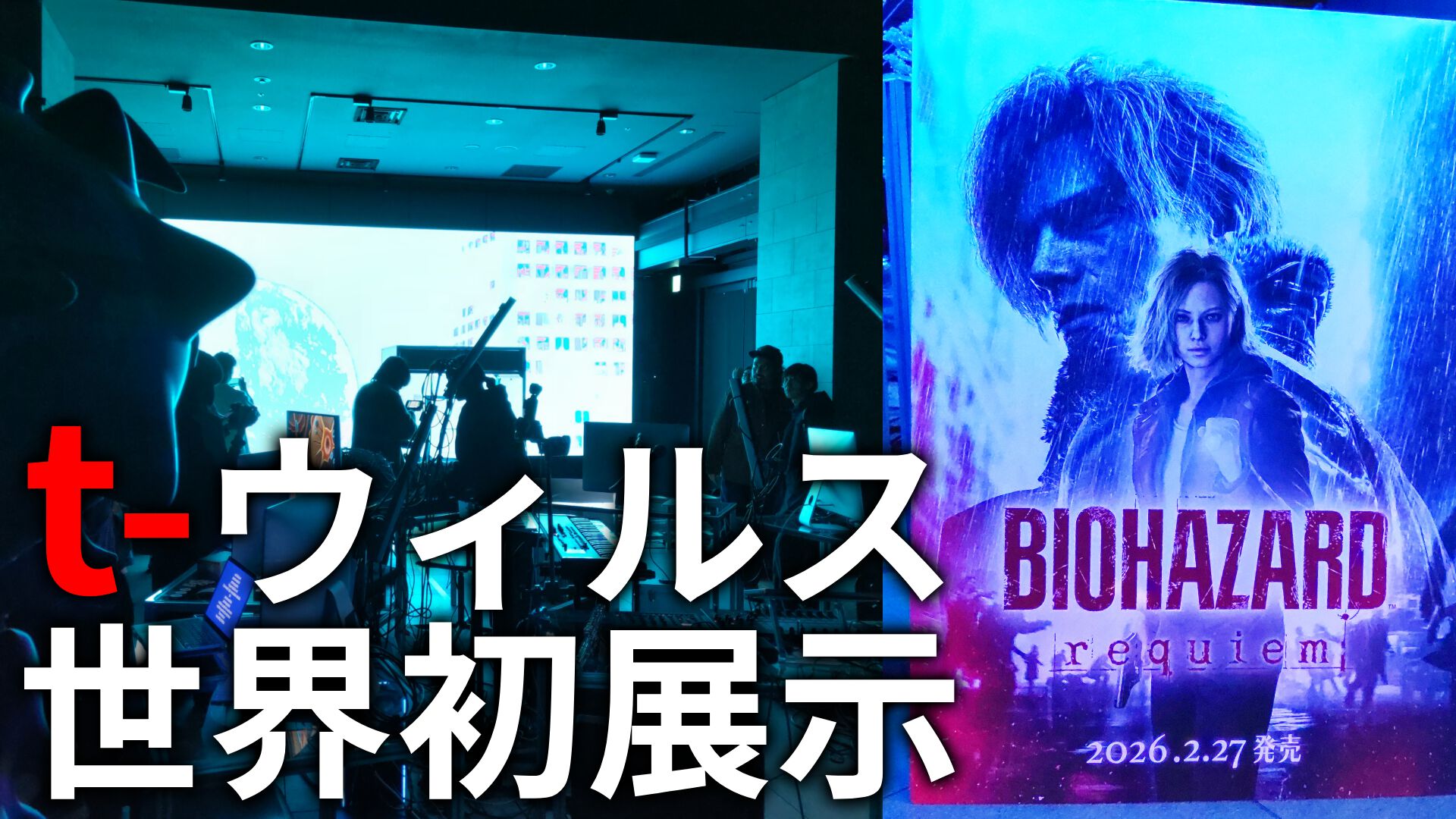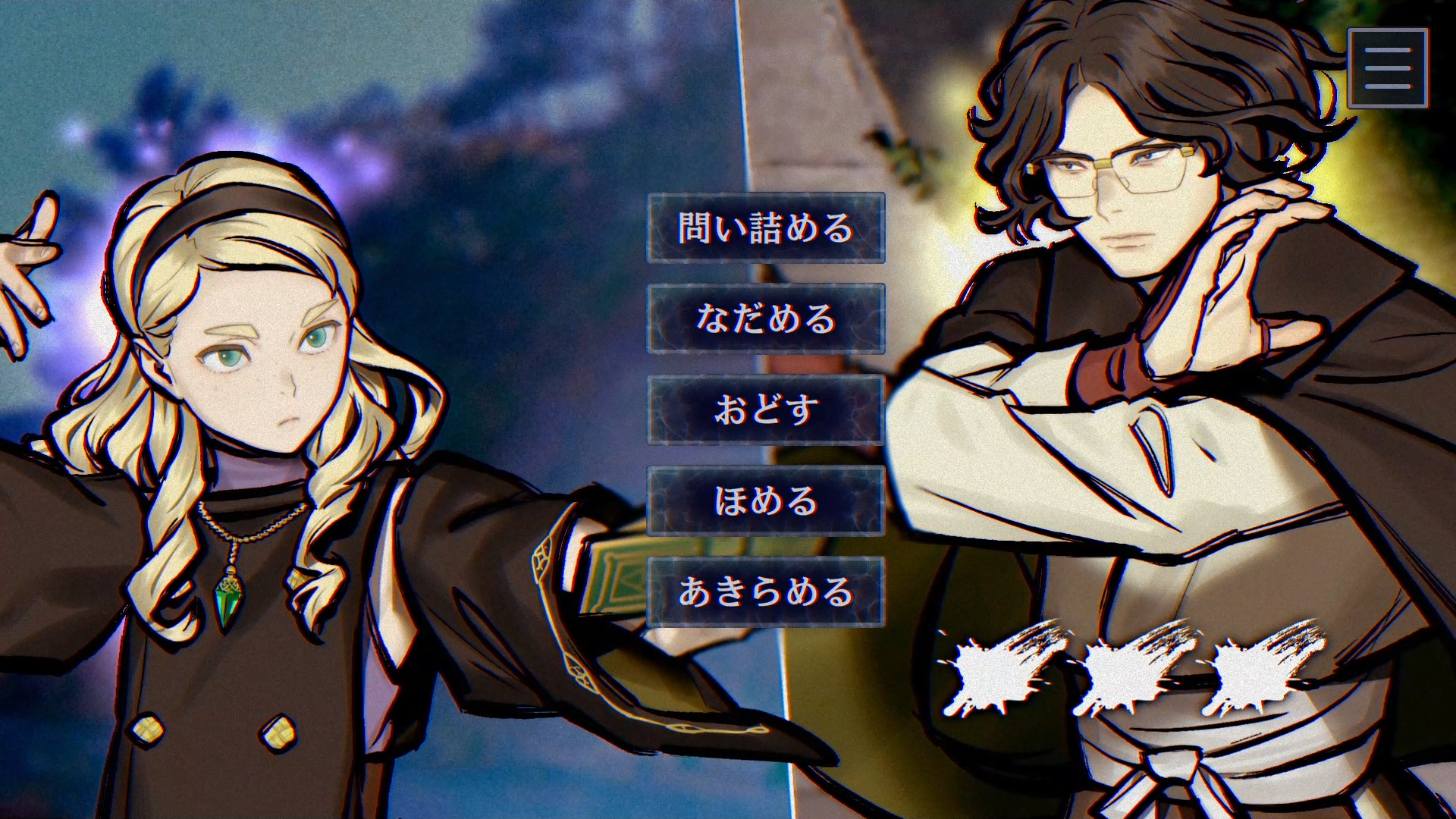Hypergryphが贈る最新作『アークナイツ:エンドフィールド』。2026年初頭にリリース予定の3Dリアルタイム戦略RPGだ。対応プラットフォームはプレイステーション5、PC、スマートフォン(iOS、Android)を予定している。
同社が開発の人気作『アークナイツ』から世界観を継承しており、3Dのアニメ調でフィールド探索をする同ジャンルと比較しても、4人同時戦闘の戦略アクション、建設&自動化シミュレーションがユニークで注目を集めている。
そんな本作だが2025年11月10日に中国・上海で同作の発表会が行われ、あわせて11月28日から開催されるベータテストIIの試遊会も実施された。
本稿では開催が近づくベータテストIIの試遊リポートをお届け。想定プレイ時間50時間以上の同テストの内容から、ベータテストIからの変更点や個人的に気になった部分まで紹介していく。
また、発表会とは別に本作でレベルデザイナーを務めるRUA氏にインタビューする機会をいただけたのであわせてチェックしてほしい。
※本記事で使用しているゲーム内画像は、会場の機材設定により一部画質の荒い箇所がございます。ご了承ください。細部まで作り込まれたキャラクター! 目の動きからわかる感情表現には脱帽
まず、冒頭のストーリーでのキャラクターのグラフィックや演出にはすさまじいものを感じた。とくに個人的に感動したのはキャラクターが声・体・表情における感情表現のほかに、目でも感情を表している点だ。
たとえば、管理人が長い時間から目を覚ましたとき、なにも覚えていないことをペリカに伝えると、ショックな感情を表に出さないものの、瞳に注目してみると動揺して目が泳いでいるのだ。チェンもなにか動揺したり、自分にとって都合が悪かったりした場面では目が泳いでいたりする。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a4e83441feda7a3f06cdf298427b3eba1.jpg?x=767)
画像で伝えられないのが悔しいが、こういった抑えきれない無意識的な感情表現が目の動きで演出されている。
惑星タロIIを開拓するエンドフィールド工業を覗く
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ac3b97db566262297980b144e3c1dfac1.png?x=767)
拠点エリアである“O.M.V.帝江号”を探索して回ってみた。ここには『アークナイツ』と同じく企業としてのロールプレイが楽しめる施設が多くあり、前作から共通の施設の指揮中枢(指令室のようなもの)では人員配置を指定して、各施設の運用をすることができた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a2c921a16f3bc7662598a4a8160b69ffc.png?x=767)
本作ではプレイヤーは管理人(主人公)として星と人々の危機に立ち向かい、開拓し最北の地を目指す、のだがそれはそれ。その前に目の前の企業運営も大いに重要なのである。
ここからがすごいところなのだが、先ほど実際に人員を配置した部屋に行くと、オペレーターたちが何かしていて、近くを歩くと挨拶されたり仕事の話をされたりする。彼らひとりひとりの動作にリアリティーを感じるのである。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ad5ebba65db6de9bfb1560e97735d01cf.png?x=767)
そういう力の入れどころ、イイと思います。Hypergryphさんの硬派というか、地に足のついた部分にこだわる感じが僕はすごい好きだ。確かにな~、実際に働いていたらこうだよな。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/aa400326d67e1f11274277789265ac499.png?x=767)
話しかけると調子が聞けて、休憩を勧めたりプレゼントを贈れたりして信頼度を高めることができる。
ベータテストIIから追加された応接室に行ってみた
応接室ではいろいろなものを飾ってカスタマイズができる。そしてフレンドの応接室を訪問したり、逆に来てもらったりできるのだ。ベータテストでフレンドがいなかったので実際に行き来はしていないが紹介する。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ae5b67dc5451bdd0a73dfcd32f86fe488.png?x=767)
フレンドの応接室と行き来するワープポイントの前にはプロジェクターがあるのだが、これもかな~りイイ。いろんなキャラのイラストを飾ることができて、その種類もめちゃくちゃ豊富だ。ここでしか見られないタッチや絵柄、キャラの一面を見ることができて大満足である。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a514abd30b7ad6be3ea34db599b367c97.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/acb3b86302e72b3fd33af182b832f24d9.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ae23742c7f560d17daa71b28c0afd58f9.png?x=767)
試しにアンタル(12Fみたいな子)を選んでみた。いや、かっけぇな。
じゃあどこでそのイラストが手に入るのかというとキャラの潜在解放(同キャラを重複して入手した際の強化要素)である。解放の1・3・5段階でそれぞれ手に入る。性能の強化以外でもキャラクターが重複して嬉しい要素があるということだ。これはおもしろいなと思った。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a14b7d7aebbcbf3b00e0c22fc1549c7f4.png?x=767)
武器とキャラの展示コーナーもあった。これもうれしい。先ほどのプロジェクターのイラストは同キャラを重複して入手しないと展示できないが、こちらはひとり確保すれば飾れるようだ。こういうインテリア要素は増やしていきたいとインタビューでも言っていたので期待している。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ab6aa2619f896deb7cb446d43221f7591.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a5ec8c160972df882d1334fe0c2619fcc.png?x=767)
ちなみにキャラ展示の各枠の右下をよく見ると、潜在解放段階が表示されている。これには自慢したい勢もニッコリだろう。
『アークナイツ』から引き続きの要素、勲章にも注目したい。勲章とは、ほかゲームでいうと実績、バッジ、トロフィー、アチーブメント、などに相当するものだ。“ストーリー1章クリア”や“エリアの探索度100%”などの実績を達成すると勲章が手に入り、武器などと同じく応接室に飾ることができる。
たとえば期間限定イベントの勲章や高難易度の勲章などは飾るとちょっとした自己紹介になって楽しいのである。そういう意味では本作は応接室全体が、ちょっとした自己紹介かもしれない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a06a3a6e6ab66283b1fdf1d7d28068224.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ad67967e9d5829323d44fe39fca08bc7a.png?x=767)
10個までスペースがあった。ベータテストではクリアデータなのでなんの苦労もないが、より難しい条件で達成すると虹色になる加工勲章要素もあるようだ。
自己紹介要素としてはふつうにプロフィールカードもある。下のレーヴァテインを見て欲しい。美しい、リリースされたら僕もこれにしたい。
しかしこれも潜在解放でゲット可能なものになる。最大解放の5段階目で、プロジェクター展示のイラストとは別で手に入るようだ。簡単に手に入るものではないが、プロフィールカード用に1キャラは最大までゲットしたいなぁ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a0d08db929cbf16b93dda2042b46ffe85.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a82455c8091242a86c2e6e8232671f80b.png?x=767)
ガチャ限定キャラのイラストゲットはいばらの道……。
応接室から出てすぐにある静止中枢では管理人の性別変更もできるようだ。僕は基本的に変更はしないタイプだが、これもうれしい人にはうれしいやつ。キャラクターストーリーをプレイする際には、性別を換えて、デートしたり、友情っぽくしたりと楽しめるだろう。設定的には、どうやって性転換しているんだ? 説明されなさそうな気がする。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/abe6ce94387d34e12f88c253ea0217139.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a53fb2c322bca63a85d205ffdc4c02671.png?x=767)
キャラクターストーリーとまではいかないが、こんな要素もあった。携帯端末でキャラクターとチャットでの会話が楽しめるのだ。写真とともに近況を話してくれたり、生い立ちを話してくれたりした。アルデリアなんかは「この火山の岩は~~~」と難しい学術研究の話をしてくれる。ストーリーで語られないキャラクターの側面が見られるのはうれしい限りだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a5cd7b9c5129df119468f7820597598c3.png?x=767)
惑星タロIIを探索するキャラクターたち
外のフィールドに探索に出るのだが、その話の前にマップがすごい詳細に要素をソートできたのでお見せする。フィールドを開拓して建設していく仕様上、これはありがたい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a5a79c5bb5175dd6ea76f41686c7ae814.png?x=767)
スクロールしないとソートの要素が確認しきれない。建築物の種類が多彩だ。
さて、フィールドに出たらまずは放置した。夕飯を食べてなかったからね。するとちょっといいものが見れた。本作は4人パーティ制で4キャラクター同時にフィールド探索や戦闘をするという特徴がある。放置するとどうなるかというと、操作中のキャラは当然待機モーションをするのだが、残りの3人はみずからの意思で自由に歩き回っていた。
よくあるような「十分休めたか?」とか言い出す感じではなく、隣の飲食店のお客さんと雑談しに行っている、コミュ力がすごい。確かに、実際に暇なときに隣にずっと立ったままなら、そのキャラは人間ができすぎている気がする。そんなリアリティを追い求めているのも個人的にとても好き。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a58f017ee89a26e6d768a08c580e3399e.png?x=767)
左奥を見て欲しい。アルデリアが結構遠いところまで行っている。
外に出てやりたいことといえば、風景を楽しむこと、だろう。フォトモードが実装されていた。それもポーズなど詳細に設定できる仕様なので、楽しくなってパシャパシャ撮りまくってしまった。アークライトかわいいな。待機モーションもかわいい。やっぱり白髪のキャラクター作りが上手いのは『アークナイツ』シリーズの大きな魅力だよなぁ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a6610aa1e5a165366717168fccccc8120.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a3e4ceeacbc5b07ba65d1da9204ea3577.png?x=767)
キャラクターの並び方や一人称視点・三人称視点の切り替え、フィルターなどがある。ズームもかなり遠くまでできた。
風景ではなくキャラを楽しんでしまった。風景ももちろんよかった。後ろの竹林の葉の細かさもやばいが、靄がかかっている空気感がすごかった。2Dのイラストと違って、雰囲気や空気感の表現は3Dではさまざまな工夫が必要なはずなのに。
水の反射や透明感がきれいなのはもちろんのこと、浅瀬では沈んだ石が見え、深場では石が見えないなど川や湖の深度によって見えかたが変化していたのが印象的だった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a72fe7b932947bc2e1b17acfb672d670c.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/add5ea4afac038b269c121592cfa9bb02.jpg?x=767)
風景? かは微妙ところだが龍泡泡(ろんぱおぱお)にも触れておこうと思う。武陵のマスコットキャラクターだ。街中のふとした場所で見かけることができ、とてもかわいかった。
本作はアニメ調にありがちな、主人公の相棒になる小動物ポジション、ピカチュウ役のようなものはいない。グラフィックも世界観も全体的にリアルでマスコット的存在はストーリーには絡めづらいのかもしれない。その補い方がご当地マスコットとは、いいね。今後実装の地域でもご当地マスコット、期待できるのか……?
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/97b80f5665c2d951eb570c052c230eae.jpg?x=767)
泡という名前のごとく、まんまるボディと龍の角が特徴的。ぷにぷにしたくなる。
アクションの楽しさと僕の個人的なオススメキャラクター
本作は4人パーティでかつ4キャラクター同時戦闘でバトルが展開される。また、リアルタイム戦略RPGを謳っているように戦略が大事なため、パーティ編成時点でも考えることがある。が、とりあえず全キャラ触って、一旦好きなキャラを詰めたパーティで遊んでみた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/aee51141b86d1202066c6581bfbe0b3f8.png?x=767)
4人のキャラクターから1キャラを選び操作するのだが、操作していない3キャラもそれぞれで戦ってくれる。イメージとしては近年の『モンスターハンター』シリーズに出てくるサポートハンターみたいな感じだ。しっかりと状況に応じて、立ち回ってくれていてストレスは感じなかった。また、基本的に自動だが連携スキルか必殺技を発動すると行動を中断して、自身がいま攻撃している敵に近付いて攻撃してくれるようだ。仲間が少し離れた場所の小型モンスターと戦っているときなどでも自分がターゲット中の敵にしっかり必殺技が入った。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a8873d66adb038e92b7943405f7f0821d.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ab559ddef246e013fe3722f05c561d1c4.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ae7829924d52a357ba9cb187defe4da66.png?x=767)
仲間には場面ごとに行動原理があるみたいで、僕とは違う方向性の戦い方をしていておもしろかった。たとえばこの場面、仲間ふたりと連携してボスを攻撃しているのだが、パンダ(ダパン)だけ逃げている。働け、と思ったが違う。おそらくこのキャラは敵の攻撃範囲外に出ることで回避しているのだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a182b3159aa90d717c6ee5130c961262d.png?x=767)
確かに僕も回避に自信がない攻撃にはそうする。そこもリアリティーか。
また、4人同時戦闘ゆえなのか、ボス敵はある程度体力を削ると小型モンスターを召喚してきたりする。すると、仲間はボスではなく小型モンスターを片付けにいってくれたりする。これはうれしい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/af34eed25a21116eee80d4a9cea63b55b.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/aeb067bfcff9c23db079a01f76d15ad44.png?x=767)
敵の大規模攻撃を避けるために特定のエリアに逃げるのだが、ひとり別行動のダパン(右奥)。
ジャスト回避が実装されたことでアクション性が少し増したそうだが、これもいいバランス調整に思えた。ジャスト回避でSPが回復するので戦略的にも幅が生まれているように感じる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ab102986b628d00468a74fde89378f0b1.png?x=767)
ジャスト回避が成功すると青くハイライトされ、スキルの使用コストであるSPが少し回復する。
個人的に使っていて楽しかったキャラクターは間違いなくポグラニチニクだ。あんた最高だよ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a3118ecc2bb5a7b2ebd4de9c3da3cbba7.png?x=767)
ポグラニチニクは先鋒の職分でSPの回復を得意とするキャラクターだ。編成するとパーティのスキルの使用サイクルが早まって楽しかった。そしてなにより必殺技がかっこいい。必殺技を発動すると盾兵を召喚するのだが、まずカットインがとてもよい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a2ea397fcefc8294bb76c208d9ddac03d.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a776a239ccec43cf1483a36ad2b634ecc.png?x=767)
初同時に盾兵が「ハッ、ヤッ」って掛け声を掛けてくれる。かっこよさと迫力がすごくて笑ってしまった。
必殺技は発動すると、まず盾兵とともに攻撃したあと、効果時間中は仲間の攻撃に合わせて盾兵も連携して攻撃してくれるようになるのだ。本作のアクションは4人での連携と戦略が楽しいが、盾兵も含めると5人での連携となり、ゲームが上手くなったような気がするのでおすすめである。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a98fa0fa7b50c904be2bad1682951edc0_LVRC8mX.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a3ac40ae961883cfd09b1198b90195d20_f1K2fFy.png?x=767)
連携のシステムが難しそうと思う人もいるかもしれないが、使いたいキャラクターをひとり選んで軸として決めてしまえば、なんとなく編成が見えてくるように感じた。また、最終的に僕は、ポグラニチニクで攻撃→それをトリガーにした連携→その連携をトリガーにした連携、盾兵も勝手に連携、というようなポグラニチニクで攻撃するだけ編成にたどり着き、ゴリ押していた。『アークナイツ』にも戦略よりも脳筋で攻略するプレイヤーはいるし、気にすることはないと思う。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a8a1aea111932572024beb953367acd4c.png?x=767)
ポグラニチニクの重撃に反応してペリカが攻撃、それに反応してギルベルタが集敵、そこに狭範囲だが高威力の攻撃を当てる。盾兵は勝手に連携。エンバーは被ダメージを軽減してくれる。
工業要素は図面システムが追加されたことでとっつきやすくなった!
目的の素材を作る施設を建設したい場合、その施設のプリセットが用意されていた。がんばってベルトコンベアを並べるといったことはなく初挑戦でも楽しめる内容に思えた。さらに図面はフレンドからインポートして使えるため、困ったらひとまずフレンドとまったく同じものを作ることで進められる。工業はハマる人はハマる要素なのは間違いないのだから、まずは初挑戦の敷居が下がったのはとてもうれしいね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a8525803bf888ab792a32c7745082d4af.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a83e06960321dccb29ddb3615a4b5bc93.png?x=767)
工業で手に入る素材の使い道も増えていた。地域ごとに拠点を作成・管理すると、そこで拠点取引や商品取引、配達依頼などといった素材の交換先が生まれていく。商品取引では時価商品なんてものもあり、工場の運営を考える楽しさが深まっていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a11895111a842b9b1658d8834f8525cf4.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a3cbfbf614a421c0f050678717547e8b4.png?x=767)
すこし拠点の展示の話に戻ってしまうのだが、中央ホールにも実績展示できる要素があるようで、取引にはとんでもない高額で展示の模型などが販売されていた。工業のエンドコンテンツ要素かもしれない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a6999c38d7c916cc0e5137f0d5b223176.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a186c3f5b20604026eae2b8a3b1ff06fb.png?x=767)
世界観が練られているため、設定資料も緻密
ゲーム内にエンドフィールドWikiという要素があり、そこには各種チュートリアルなどのガイド記録、武器図鑑、装備図鑑と欲しい情報が大体揃っていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a0f97baed14ef39b7e3759f6f8a420248.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a451f38b10a769e4f1ac1ea664f8b869e.png?x=767)
武器は強化段階が進むと見た目がかっこよくなるのだが、それも反映されていた。
情報資料もとても充実していて、『アークナイツ』を知っているとより深く楽しめる内容だ。“テラ”、“星門”、“源石”についての資料は、源石の脅威は軽減されたことや本作との歴史的つながりを知ることができて個人的におもしろかった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ad2729def05857790df8c98499e71b683.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a20460b3d2b46a2ad08bff8f1ac629add.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/acab09db6e7b159817b581fc302329a23.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a505b3c2b1249f453b239751fc9669671.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a4e83441feda7a3f06cdf298427b3eba1.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ac3b97db566262297980b144e3c1dfac1.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a2c921a16f3bc7662598a4a8160b69ffc.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ad5ebba65db6de9bfb1560e97735d01cf.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/aa400326d67e1f11274277789265ac499.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ae5b67dc5451bdd0a73dfcd32f86fe488.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a514abd30b7ad6be3ea34db599b367c97.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/acb3b86302e72b3fd33af182b832f24d9.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ae23742c7f560d17daa71b28c0afd58f9.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a14b7d7aebbcbf3b00e0c22fc1549c7f4.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ab6aa2619f896deb7cb446d43221f7591.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a5ec8c160972df882d1334fe0c2619fcc.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a06a3a6e6ab66283b1fdf1d7d28068224.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ad67967e9d5829323d44fe39fca08bc7a.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a0d08db929cbf16b93dda2042b46ffe85.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a82455c8091242a86c2e6e8232671f80b.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/abe6ce94387d34e12f88c253ea0217139.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a53fb2c322bca63a85d205ffdc4c02671.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a5cd7b9c5129df119468f7820597598c3.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a5a79c5bb5175dd6ea76f41686c7ae814.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a58f017ee89a26e6d768a08c580e3399e.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a6610aa1e5a165366717168fccccc8120.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a3e4ceeacbc5b07ba65d1da9204ea3577.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a72fe7b932947bc2e1b17acfb672d670c.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/add5ea4afac038b269c121592cfa9bb02.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/97b80f5665c2d951eb570c052c230eae.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/aee51141b86d1202066c6581bfbe0b3f8.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a8873d66adb038e92b7943405f7f0821d.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ab559ddef246e013fe3722f05c561d1c4.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ae7829924d52a357ba9cb187defe4da66.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a182b3159aa90d717c6ee5130c961262d.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/af34eed25a21116eee80d4a9cea63b55b.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/aeb067bfcff9c23db079a01f76d15ad44.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ab102986b628d00468a74fde89378f0b1.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a3118ecc2bb5a7b2ebd4de9c3da3cbba7.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a2ea397fcefc8294bb76c208d9ddac03d.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a776a239ccec43cf1483a36ad2b634ecc.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a98fa0fa7b50c904be2bad1682951edc0_LVRC8mX.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a3ac40ae961883cfd09b1198b90195d20_f1K2fFy.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a8a1aea111932572024beb953367acd4c.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a8525803bf888ab792a32c7745082d4af.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a83e06960321dccb29ddb3615a4b5bc93.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a11895111a842b9b1658d8834f8525cf4.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a3cbfbf614a421c0f050678717547e8b4.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a6999c38d7c916cc0e5137f0d5b223176.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a186c3f5b20604026eae2b8a3b1ff06fb.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a0f97baed14ef39b7e3759f6f8a420248.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a451f38b10a769e4f1ac1ea664f8b869e.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/ad2729def05857790df8c98499e71b683.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a20460b3d2b46a2ad08bff8f1ac629add.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/acab09db6e7b159817b581fc302329a23.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/58881/a505b3c2b1249f453b239751fc9669671.png?x=767)