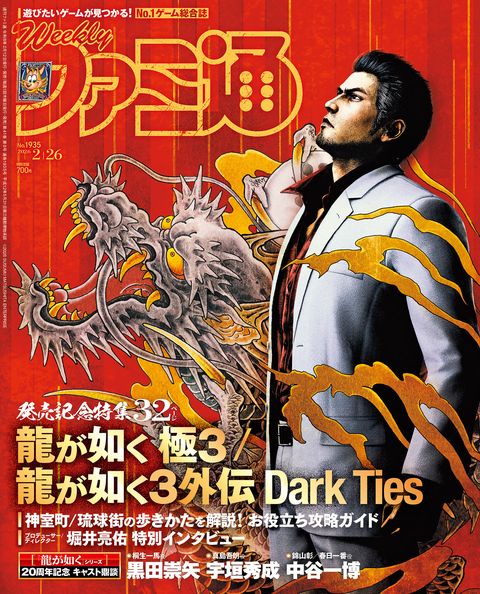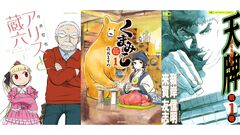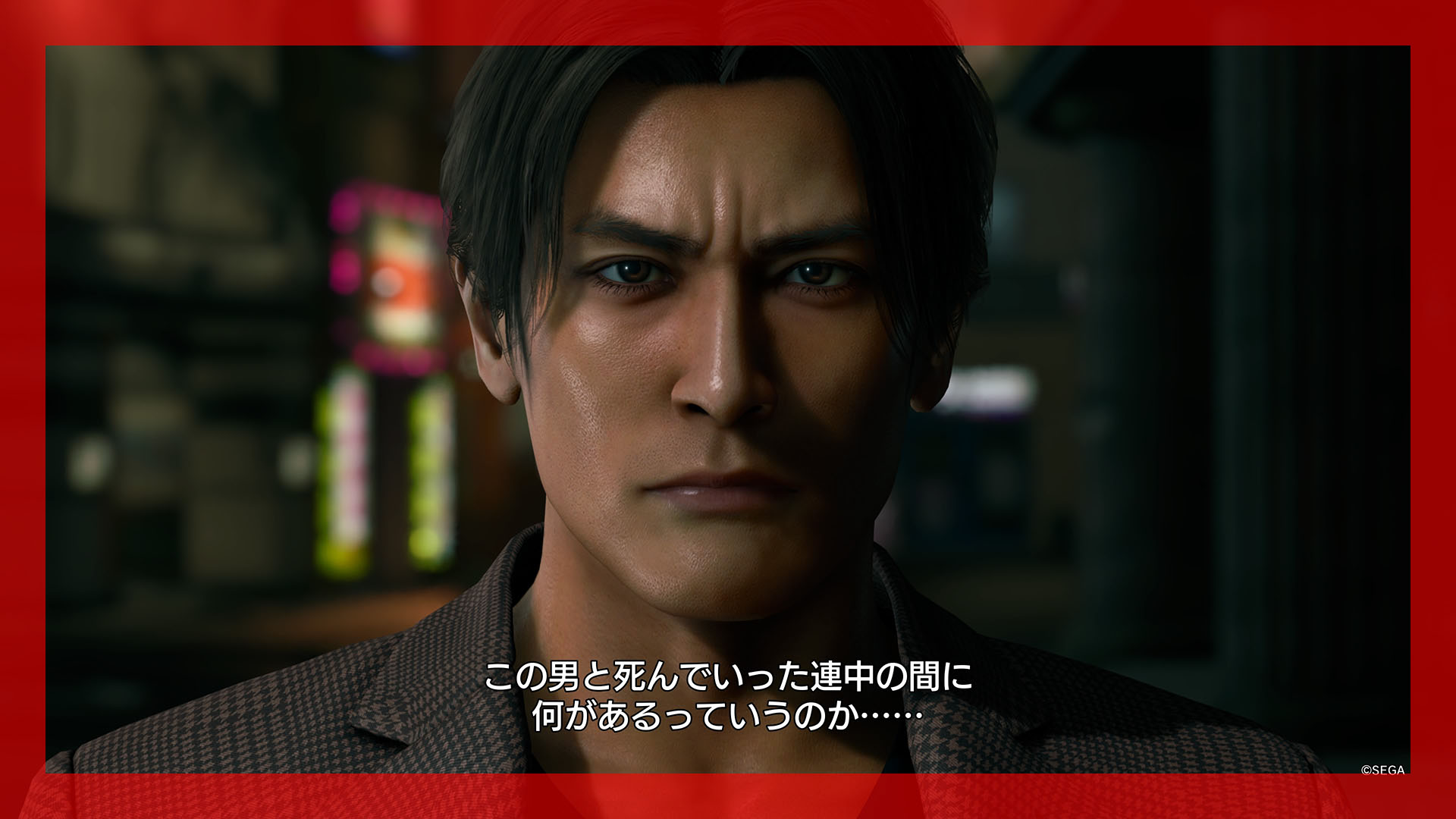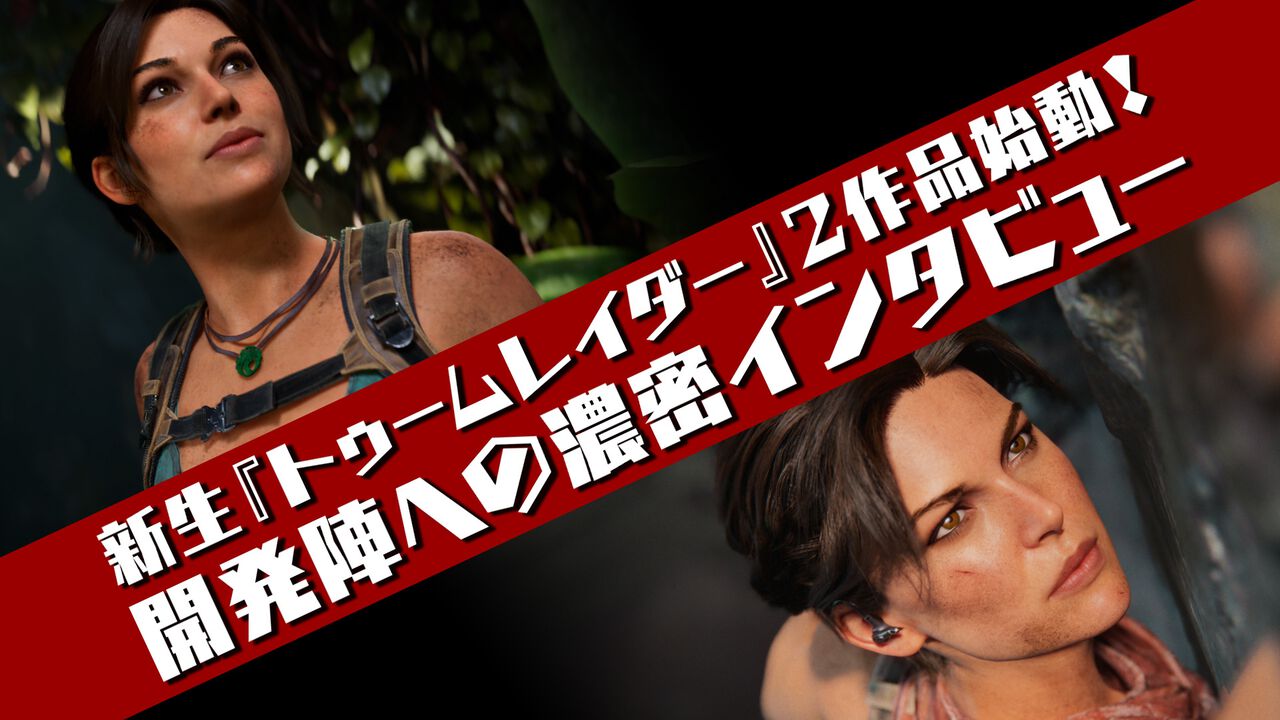『アストロボット』は、2024年9月6日にソニー・インタラクティブエンタテインメントより発売された、プレイステーション5用の3Dアクションゲーム。発売されるやいなや、世界中で高い評価を獲得。そして、日本時間2024年12月13日にアメリカのロサンゼルス・ピーコックシアターにて開催された“The Game Awards 2024”では、最多となる7部門にノミネートされ、その年のもっとも優れたタイトルに贈られるGame of the Yearを始め4冠に輝いた。この結果に、納得したファンも多いだろう。
授賞式では、開発したTeam ASOBIを代表してディレクターのニコラ・ドゥセ氏がステージに登壇。関係者やファン、プレイステーションプラットフォームを築いてきた先人への感謝とともに、以下のようにゲームの歴史を作ってきた人たちへの思いも語り、大きな話題となった。
ニコラ・ドゥセ氏:忘れてはいけないのは、プレイステーションの前から、プラットフォームを作って来た方々がいました。1989年、子どものころの私は、灰色のボックスをクリスマスプレゼントにもらいました。それを兄弟といっしょにプレイしたのは、本当にすばらしい体験でした。現在の私たちは日本の東京で仕事をしていますが、その日本の京都には、昔から継続的に質の高いプラットフォームを作ってきた方々がいます。言わなくても、誰だかわかりますよね。私たちは皆、その方々からインスピレーションを受けています。名前を挙げることはしませんが、今夜、その方々にもお礼を言いたいと思います。
本稿では、The Game Awardsに出席し、アメリカから帰国した直後のPlayStation Studios・Team ASOBIのニコラ・ドゥセ氏たちと、日本で受賞の様子を見守った主要メンバーに取材を実施。会場の様子や、Game of the Yearを獲得したときの感想などをうかがうとともに、本作の制作秘話を語っていただいた。ちなみに今回の取材は、特別にTeam ASOBIのスタジオ内で実施させていただいた。スタジオ内の風景を見ていると、『アストロボット』のように驚きとワクワクに満ちたゲームが生まれてくるのも納得できるような……。
※一部文言の誤りを修正しました(2024年12月30日12時)。※一部表記の誤りを修正しました(2025年1月7日11時)。※一部表記の誤りを修正しました(2025年1月8日16時)。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/adf83a8aa43014adb0203bc8bdf8c33a5.JPG?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/ab91f228c531cf30bacd5e009b32ba133.jpg?x=767)
スタジオ内の様子。この空間で、チーム全員がアイデアを出し合い、イメージを共有しながら作り上げていったのが『アストロボット』だ。
なお今回の取材では、発売後のいまだから語れる、エンディングのネタバレなども含むより深いお話もたっぷりお聞きしている。それについては、後編として後日ファミ通.comで公開する予定なので、ぜひチェックしてほしい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/af08dc08b676cac4ac7b8bb962d05c63a.jpg?x=767)
中井俊彦
Team ASOBI
シニアコンセプトアーティスト
『アストロボット』がGame of the Yearを獲得!
――“The Game Awards 2024”でのGame of the Yearの受賞、おめでとうございます!
一同 ありがとうございます。
――とても感動的な授賞式でした。『アストロボット』は、The Game Awards 2024で最多の7部門にノミネートされ、4部門でウィナーとなりましたが(※)、率直な感想を教えてください。
※Game of the Year、Best Game Direction、Best Art Direction、Best Score and Music、Best Audio Design、Best Action/Adventure Game、Best Family Gameの7部門にノミネート。Game of the Year、Best Game Direction、Best Action/Adventure Game、Best Family Gameの4部門でウィナーとなった。ニコラ
『アストロボット』のいろいろなところを広く見ていただけたので、すごくうれしかったですね。とくに、ファミリーゲームとして評価していただけるかどうかは、とても気にしていました。Team ASOBIのスタジオを立ち上げたときに、プレイステーションで新たなファミリー向けのゲームを作るという目標があったので、Best Family Gameにノミネートされたことは大事なポイントでした。もちろん、Game of the Yearやほかの部門にノミネートされたことも光栄でしたが、Best Family Gameを受賞できれば、すごくうれしいなと思っていたので。
――佐野さんと矢徳さんも授賞式に出席されたそうですが、ご感想を教えてください。
佐野
とてもうれしかったです。制作中は賞のことなどは考えず、楽しい世界や、ゲームの喜びといった見返りのない愛情のようなものを、いかにゲームに落とし込むかということだけを考えていましたが、いろいろな反響をいただいたことで、まったく期待していなかったご褒美をもらえたというか、私たちから一方的に送っていたと思っていたものに、何かお返しをもらったような、すごくうれしい気持ちになりました。チーム一同、がんばってよかったなと思っています。
矢徳
自分で納得できるものにしたいという気持ちが強かったので、僕も佐野さんと同じく、制作しているときはアワードのことはまったく考えていませんでした。僕たちは、2週間に1回、全員が集まって制作途中のゲームをプレイする機会を設けていましたが、そのときに考えていたのは、チームのみんなに、自分が作っているものを遊んでもらい、楽しんでほしいということでした。その積み重ねがあって、ユーザーさんたちに喜んででもらえたのかなと思います。あともうひとつ、メディアの皆さんも、僕たちが作っているゲームのユーザーさんになってくれることに、改めて気づかされました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a679d0d1d62bbdf7ba6b62a1fb8ec1f57.JPG?x=767)
――The Game Awards 2024の会場の雰囲気はいかがでしたか?
ニコラ
会場に入って後ろを見たら、本当に広くて、たくさんの人がいて……何人くらいいたんだろうね?
矢徳
すごくたくさんの方がいましたね。
ニコラ
それがいちばんビックリしたことだと思います。それに、スターのハリソン・フォード(※ハリソン・フォード氏がサプライズでBest Performanceのプレゼンターを務めた)が登場したのも印象的でした。イベントの前日、私は2~3時間しか眠れなくて、時差ボケもあったので、ちょっとフワフワしながら参加しました(笑)。
イベントでは、マーク・サーニーさん(※ゲームデザイナー兼プログラマー。PS4、PS5のリード・アーキテクトであり、『KNACK(ナック)』の総監督なども務めた)が隣りに座っていて、彼からいろいろアドバイスをもらいました。たとえば、イベント中はずっと席にいないといけないとか。これに関しては、スタッフにもけっこう言われましたね。
――佐野さんと矢徳さんはいかがでしたか?
佐野
ニコラさんとふたりで会場を歩いていたら、ファンの方たちに「アストロ~!」って声をかけていただきました。たくさんの声援をいただきましたし、『アストロボット』のパッケージを持った方にサインをお願いされたりもして。そのときに、「世界中のいろいろな方たちに『アストロボット』を好きになってもらったんだな」と実感することができて、心が温まる体験でした。
矢徳
会場にはファンだけではなく、ゲームデベロッパーやメディアの方たちもいて、ゲーム業界にはこれほどたくさんの人が関わっているのだということを改めて知ることができました。それに、The Game Awards 2024のライブ配信は約1億5400万回再生だったということで、ゲーム業界の方だけではなくて、本当にたくさんのユーザーさんがいて、注目しているのだと知ることができたのもよかったです。
イベントスタッフの方たちにも、「このたびはおめでとうございます」と言葉をかけていただいた後に、「プロとしての仕事はここまでです。私はあなたたちチームのファンなので、写真をいっしょに撮ってください」とお願いされたんですよ。僕たちの作っていたものが、ちゃんと届いていたんだな、とうれしかったですね。
――それはクリエイター冥利に尽きますね。
矢徳
会場の外は熱気に包まれていたのに、会場の中に入ると、人がたくさんいるわりにちょっと静かだったのも印象的でした。おそらく、皆さん緊張していたのかなと思いますが、そういう場所にはなかなか行く機会がなかったので、新鮮な気持ちになりました。
――Game of the Year受賞が発表された瞬間の感想を教えてください。
ニコラ
実際に『アストロボット』の名前が呼ばれたときは、信じられない気持ちでしたが、とてもうれしかったですし、本当に感動しました。Team ASOBIのメンバーの顔が瞬時に浮かんで、みんなはどんな反応をしているかなとも思いました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a8012ddd88b072a59ecee008ac67389e5.jpg?x=767)
Game of the Yearが発表された直後の模様(The Game Awardsの配信映像より)
――発表を待っているあいだは、どんな心境だったのですか?
ニコラ
当然ながら、Game of the Yearを受賞できるかどうかはわかりませんでしたが、Game of the Yearに選ばれるタイトルは、Best Game Directionとセットで選ばれることが多いです。先に『アストロボット』がBest Game Directionを受賞したことが発表されていたので、もしかしたらスピーチが必要になるかもしれないと考えて、カメラが向いてないときにスマートフォンでスピーチをメモしながら考えていました(笑)。
一同 (笑)。
矢徳
そういえば、スマートフォンを触っていましたね(笑)。
ニコラ
そうそう。スピーチで話したいことを忘れないように、話す内容と順番を考えていまいた。最初にチームへの感謝。そして、SIEの方、パートナーの方たちに感謝の気持ちを伝えて、その後に何を話そうかな……って。
――ということは、直前までスピーチの内容は考えていなかったわけですか? 具体的な名称を出さないながらも、ゲームのトリビュートも込められたものになっていましたが。
ニコラ
スピーチで話すことはまとめていませんでした。でも、私たちが作っているゲームの歴史を考えたときに、プレイステーションの歴史のほかに、いろいろなハードの歴史があります。私は、Team ASOBIのメンバーが影響を受けたゲームを忘れないように心掛けていて、つぎの世代へのサイクルを考えたときに、何をプレゼントするのかを、歴史と同時に考えなければいけないと強く感じています。『アストロボット』は、新しいイノベーションとしてがんばって制作しましたが、スピーチの最後に、感謝の気持ちを伝えたいと思いました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a20a190279a47b4d1416ea18c6cb0f861.jpg?x=767)
受賞スピーチ中のニコラ・ドゥセ氏(The Game Awardsの配信映像より)
――とてもすばらしいスピーチだったと思います。ステージに立たれたときの感想を教えてください。
ニコラ
もちろん緊張していましたし、Team ASOBIのメンバーのためにちゃんとスピーチをしないといけないというプレッシャーも感じていました。あと、しゃべりたいことはたくさんあったのですが、どれくらいスピーチできるのかわからなかったので、それもちょっとだけプレッシャーでしたね。事前にイベントスタッフの方から「スピーチが長くなったときはサインを送ります」とは伝えられていたのですが、大丈夫だったみたいです。ただ、スピーチのことはよく覚えていません(苦笑)。
一同 (笑)。
ニコラ
イベントが長かったですし、“Game of the Year”に選ばれた衝撃で、最後のほうの記憶がはっきりしていなくて。でも、チームのメンバーの顔や、ずっと泣いているスコットさん(※PlayStation StudiosのScott Rohde氏)の顔を見て感動しましたね。これは、私のスピーチを観ていた妻に後から聞いたのですが、「ニコが泣くのを初めて見た」と言われました。それぐらい、スピーチのときは感情をうまくコントロールできていませんでしたね。
佐野
今回は日本のゲームが数多くノミネートされていたので、日本のゲーム産業に長く関わってる身としては、そういう意味でも感動的でした。イベントもすばらしくて、新作の発表がたくさんありましたし、すばらしいトレーラーも見ることができて、すごく興奮したのを覚えています。
矢徳
Game of the Yearを受賞できたことはとてもうれしいのですが、受賞したときのことは、じつは僕もよく覚えていなくて(苦笑)。受賞で印象的だったのは、チームのみんなの喜ぶ姿を見たときでした。日本に残ったチームのメンバーは、会社に集まってストリーミングで受賞の瞬間を見守ってくれていたのですが、Game of the Yearに輝いたときに大喜びしてくれていて。その様子を納めた映像を何度も見返して、賞を獲ったとき以上にうれしい気持ちになりました。
――ほかに印象に残っている出来事はありましたか?
ニコラ
ひとつ思い出しました。“Game of the Year”のアナウンスのちょうど前に、Naughty Dogの新作タイトル『Intergalactic』が発表されました。私たちも知らなかったので、『Intergalactic』のトレーラーを観て全部忘れちゃいました(笑)。ゲーマーの視点で観ていたので、「わぁ、すごい!」って。
ニコラ
『アストロボット』がGame of the Yearに選ばれた後は、ゲーマーからプレゼンターに気持ちを切り換えないといけなかったのですが、Naughty Dogのトレーラーは本当にすばらしかった。プレイステーションの今後を考えたら、イベントの最後の10分は完璧でした。
佐野
気分が高まりましたよね。
矢徳
イベントの後に、Naughty Dogのメンバーの方とお話する機会があって。そのときに聞いたのですが、『アストロボット』がGame of the Yearに選ばれたとき、彼らも声を挙げて喜んでくれたそうです。改めて、PlayStation Studiosのつながりの強さを感じることができました。
チーム全員のアイデアを集めて作られた『アストロボット』の遊び
――ここからは本作がどのように作られたのかをお聞きしていきたいと思います。まずは難易度についてですが、『アストロボット』はボス戦やチャレンジステージなども含めて、全体的にステージの難易度調整が絶妙だと感じました。ステージの難易度調整で工夫した点、苦労した点などを教えてください。
矢徳
Team ASOBIでは、2週間に1回、チームのみんなでプレイしてレビューする機会を設けていて、ステージの難易度に関してもその場で意見を出し合うようにしています。レベルデザイナーは、担当しているステージを自分がちょうどいいと感じる難易度に調整して、みんなにプレイしてもらう。そこでいろんな意見をもらうんですね。
だいたいは「難しすぎる」という意見が多いです。何度もプレイしていると、だんだん慣れてきてコツを掴めてしまうので、ちょうどいい難易度に調整したつもりでも、ちょっと難しくなってしまう。みんなの意見をもとにわかりやすいように調整をするのですが、今度はユーザーテストを実施したときに、「簡単すぎる」という意見がきてしまって。
改めてバランス調整を行うときに、レベルデザイナーひとりひとりが考えているのは、このステージは何のために存在するのか、ということです。たとえば最初のステージは、初めて遊ぶ場所だからみんなにプレイしてもらえるようにしないといけないとか。チャレンジステージは、ゲーマーの方たちにも楽しんでほしいから、ちょっと歯ごたえあるほうがいいとか。ステージごとに自分の中で再確認して、最終的には担当者の判断で難易度を決めています。
――ただ、カクレオン宙域の“塗らせ!スプラッシュの試練”はメチャクチャ難しかったです。このステージで、初めて心が折れそうになりました(苦笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
“塗らせ!スプラッシュの試練”。一定時間しか使えない放水アイテムでマグマを冷やして道を切り開いていく序盤から、ゴールまでミスなく走り続ける必要がある難ステージ。途中の敵が放つミサイルの追尾性能がやけに高いのもキツかった……。
矢徳
“スプラッシュの試練”は、難しいポイントと少しわかりにくいポイントがあったので、先日のアップデートでユーザビリティーを少しだけ直しました。以前と比べて、プレイしやすくなったと思います。
――発売後もユーザーの反応を見ながら調整をしていると。
矢徳
はい。僕たちは、『アストロボット』をプレイしている方たちのストリーミングを見るのが大好きです。自分で想定していた難易度で楽しんでいただけているようなら大丈夫なのですが、思っていたよりもつまずいている姿を見ると心が痛むので、難しいステージの調整はしていきたいと考えています。
――“スプラッシュの試練”のほかに、難易度を調整したステージはありますか?
矢徳
ほとんどは細かい部分の修正ですね。難易度を調整したのは“スプラッシュの試練”だけです。
――アストロをサポートしてくれるパワーアップもバラエティー豊かで驚きました。アイデアはどのように出し合ったのですか?
矢徳
パワーアップはみんなでアイデアを出し合いました。
ニコラ
パワーアップのアイデアの出しかたには、ふたつのパターンがあります。ひとつ目は、ブルドッグ・ブースターやツインフロッグ・グローブ、鶏のロケットのように、ジャンプアクションゲームとしてマッチするパワーアップです。それ自体はよくあるアクションかもしれませんが、DualSense ワイヤレスコントローラーと組み合わせることで、新鮮な体験ができたと思います。
ふたつ目は、DualSenseの機能を表現するための研究から生み出されたパワーアップです。たとえば、スポンジのアイデアはテックデモから生まれました。スポンジの感触を表現するのが目的でしたが、その体験が楽しかったのでパワーアップに採用しました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
スポンジのパワーアップ。水を吸収すると巨大化して敵やオブジェクトを蹴散らせるようになる。また、巨大化状態の体を絞ると、吸収した水を周囲にまくことも可能で、これを利用したギミックもある。
矢徳
ポットもテックデモから生まれたアイデアですね。当初はシールドでガードしたときに、ガードした物の感触を表現する研究を行っていました。これをどのようにしてゲームに落とし込むかを考える中で、アストロ自身がシールドになって、ガードしたときの感触をハプティックフィードバックで感じられるようにしました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
ポットのパワーアップ。丸まるとカチカチになり、敵の攻撃やステージのトラップなどでダメージを受けなくなる。
――なるほど。個人的には、オクトパス惑星帯の“ミニでビッグな冒険チュー”に登場するマウスが大好きです。このパワーアップは、どのようにして生まれたのですか?
藤縄
マウスは私のアイデアです。『アストロボット』の開発の初期段階のときに、僕や佐野さんが3、4人で集まって、DualSenseのハプティックフィードバックを使った新しい遊びを作る研究活動を行っていました。そのときに僕が作ったテックデモに、操作しているキャラクターのサイズをいつでも変更できるというものがありました。小さくなると周囲の環境が大きく見えますが、その体験に加えて、ハプティックフィードバックで振動もガンガン伝わってくるんです。
この体験はゲームにも入れていて、ウサギが駆け回っているだけなのに、小さくなると恐竜がドシンドシンと走っているように感じていただけると思います。このように、マウスはハプティックフィードバックを使った新しい遊びを考えることを第一に作ったものなので、アストロのパワーアップとして作っていたわけではありませんが、小さくなるという体験自体がおもしろいと手応えを感じていました。みんなにレビューしてもらったときも非常に好評だったので、パワーアップで実装することになりました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
マウスのパワーアップ。大きくなったり小さくなったりしながらステージを探索するのが楽しい!
――先ほど、パワーアップのアイデアはみんなで出し合ったとお聞きしました。プランナーが中心になって提案するのではなく、サウンドやグラフィックが担当の方もアイデアを出されたのですか?
藤縄
担当に関係なく、チームのメンバー全員にチャンスがありますね。
佐野
ブレーンストーミングを行って、アイデアをもとに付箋に絵を描くんですよ。それをみんなでチェックして、おもしろそうなアイデアはテストで作ってみよう、といった感じです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a4a1d54c528abf397f77edfaae29b333f.JPG?x=767)
今回取材をさせていただいた、Team ASOBIのスタジオの一角には、チームのメンバーが出し合ったパワーアップのアイデアが書かれた付箋が貼られていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a769ddcf8b6729de3d808ac27437650d6.JPG?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a89deae3f167c6f2e137eca9ac7ee549e.JPG?x=767)
付箋はたくさん貼られており、じっくり観察すると、ゲーム内で見たことのあるアイデアが描かれた付箋も。
藤縄
レビューのときに、みんなの意見を聞くことができる時間もあります。ここはおもしろかった、あそこはもっとおもしろくしたい、こうしたらもっとおもしろくなるといった感じで、いろいろな意見を聞くことができますし、アイデアを出し合いました。
――パワーアップのレビューで、とくに反応がよかったものは?
ニコラ
マウスは大人気でしたね。
矢徳
みんなで、気に入ったアイデアに星をつける仕組みがあるんですよ。
――ということは、なかにはぜんぜん星がつかなかったアイデアも……。
ニコラ
もちろんあります。
藤縄
星がつかなかったときは、ものすごくへこみます(苦笑)。
ニコラ
ただ、どうすればよくなるかもしっかり話し合っていますので、みんな積極的に新しいアイデアを出してくれるのだと思います。
パワーアップのデザインはおもしろさを優先して動物をモチーフに
――パワーアップのデザインは、どのように考えていったのですか?
矢徳
先ほどお話ししたように、僕たちはテックデモや新たな遊びを考えるところからアイデアを生み出すことが多いです。見た目から入ることはほとんどないので、デザインはプロダクトに乗せるときにコンセプトアートを描いてもらい、どういったおもしろい動きをするかも、アニメーションを担当するスタッフにお任せしています。
担当者が自由に考えておもしろい動きをつけてくれるのですが、テックデモや新たな遊びから入っても、最後のプロダクトまでいけるのは、チームの中に強い信頼関係があるからこそなのかなと思います。とはいえ、スポンジのアイデアを聞いたときは、さすがにどうやってデザインするか、困ったかもしれません(苦笑)。
――(笑)。アニメーターとして、パワーアップのデザインでとくに印象に残っていることはありますか?
川
とくに印象的だったのは、パワーアップをゲットしたときの演出です。もともと演出はなくて、ステージに配置されているアイコンにアストロが触れると、演出が入らずにパワーアップするという仕様でした。ただ、この仕様だと「いつパワーアップしたのかわかりにくい」という意見が出て、わかりやすくするために演出を入れることになりました。
この演出は、アニメーターが自由に考えてテストしていいということだったので、まずはプリビズ(※仮素材を使って制作したCG映像のこと)でモンキー・クライマーの演出を考えてみました。プレイの邪魔にならない2秒弱の時間の中で、パワーアップをゲットする流れやポーズを考えてプリビズのムービーをみんなに観てもらったところ、ものすごく評判がよくて。モンキー・クライマーのプリビズをベースに、ほかのパワーアップをゲットしたときの演出を考えることになりました。
演出ベースで制作が進んで、なおかつ一発の実装でうまくいくことは、いままでの経験でもあまりなかったことですね。アニメーターの立場からすると、自由な発想で演出を考えられたので、楽しく作業ができました。ブルドッグ・ブースターの犬がアストロの顔を舐める演出や、ポットの腰に装着したパーツがずれ落ちたりする演出も、アニメーターがアドリブで作ったものです。
ニコラ
パワーアップをゲットしたときの演出は、何回観ても楽しいです。テンポもちょうどいい。
――パワーアップは、ブルドッグやフロッグ、モンキーなど、動物がモチーフになっているものが多いのも印象的でした。
矢徳
最初から動物をモチーフにしていたわけでなくて。最終的に、パワーアップの多くは動物がモチーフになっていますが、開発の最後のほうに決まって、コンセプトアートを作ったんです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a6e0157e2e655c64517beba08d7baa820.JPG?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a3a5bc44b078ce145ff9b0ea03eef77e8.JPG?x=767)
Team ASOBIのフロアに飾られた、パワーアップのコンセプトアートの一部。
ニコラ
(中井さんを見ながら)ブースターは、なんで犬になったんですか?
中井
ブルドッグ・ブースターのプロトタイプは、犬ではなく筒型のロケットでした。このデザインでも、ゲームとしては十分におもしろかったのですが、このまま開発を進めていいのか議論になりまして。もうちょっとアイキャッチになるデザインにしたほうがいいと考えて、ゲームプレイとはまったく関係ありませんが、犬をチョイスしました。
――最初に動物のモチーフを取り入れたのが、ブルドッグ・ブースターだったんですか?
佐野
最初は、モンキー・クライマーだったと思います。
中井
『ASTRO's PLAYROOM』ではサルに変身させていましたが、『アストロボット』では変身するという形を見直そうという意見が出て。それで、「サルを背負わせちゃう?」と、軽いノリで提案したのですが、意外とおもしろいかもという話になりました。
――ひょうたんから駒のような感じで、アイデアが採用されたのですね。
中井
ただ、そのときはパワーアップを動物で揃えようといったことは考えていませんでした。モンキー・クライマーは、ゲームプレイとリンクしているので、ある程度は必然的にサルがモチーフになりましたが、ブースターとブルドッグはぜんぜんリンクしていないので、決断するのに勇気が必要でしたね。「関係ないけど、いいのかな」って。でも、「バウバウと鳴きながら突進している姿はキャッチーな気がする」という意見もあって。当時はかなり悩みましたが(苦笑)、いまにして思うと犬にしてよかったなと思います。
――ブースターを犬にするかどうかも、レビューの場でメンバーにチェックしてもらったんですか?
中井
はい。「なんで犬なの?」って反応が多かったです。
一同 (笑)。
ニコラ
ブースターで動物をモチーフにするなら、鳥だとイメージに合ったかもしれません。ただ、鳥はロケットで使っていたので、鳥以外の動物を考える必要がありました。ほかの候補には、突進するイメージのある牛も挙がっていましたが、バウバウという楽しい音をつけて犬に決まりました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
ブースターと競合した(?)、鶏のロケット。急上昇して高い場所に移動したり、ものを引っ張り上げたりと、さまざまな使い道があるパワーアップだ。
中井
コンセプトアートを考えるときに、ロジックだけでは解決できないことがたくさんあるなということをよく感じています。
――たしかにロジックで考えると、ブースターを犬にしようとはなりませんからね。生み出すのがいたいばんたいへんだったパワーアップは、やはりブルドッグ・ブースターになるのでしょうか?
藤縄
ツインフロッグ・グローブもたいへんでしたよね。
中井
そうだったね。
ニコラ
ツインフロッググローブを観たとき、中井さんは天才だと思いました。ふつうのボクシンググローブだったのがカエルになっていましたし、グローブがふたつあるので、カエルの兄弟になっていて。本当にすごい。
――プレイした感覚では、ツインフロッググローブは自然に受け入れられました。伸び縮みするパンチは、たしかにカエルっぽいなって。
矢徳
でも、初めてみたときは「アレ?」って思いましたよね(苦笑)。「グローブがカエルになっている!」って。
中井
チームのメンバーは、数年にわたってボクシンググローブ姿のアストロを見てきましたから。ふつうのグローブからカエルにしたので、ユーザーさんがどのように受け取ってくれるのか、ツインフロッググローブもドキドキしました。実際の反応を見ると、こちらも冒険してよかったです。
川
そういえば、グローブの中の赤いところは、カエルのベロだと思ってアニメーションをつけていたんだけど、それでいいんだよね? 口の中に入っているときは、ベロのつもりで作っていたんだけど……。
中井
ベロとして考えてくれたデザインは、ちょっとやりすぎかなと思ったので、中身はボクシンググローブのままにしています。あくまで、見た目がカエルということで。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)
カエルが口を開けて、舌を……ではなく、ボクシンググローブを伸ばす。言われてみればヘンだけど、楽しいからオーケー!?
インタビューの前半はここまで。後半では、歴代プレイステーションの人気ヒーローに扮したスペシャルボットや、エンディングの開発秘話をお届けする予定だ。近日公開予定なので、こちらも乞うご期待!
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a16e02d95f3dccd1f0aabba6304dab127.JPG?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/ab91f228c531cf30bacd5e009b32ba133.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/af08dc08b676cac4ac7b8bb962d05c63a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a8012ddd88b072a59ecee008ac67389e5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a20a190279a47b4d1416ea18c6cb0f861.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/28871/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)