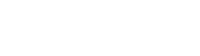今回は『Civ VII』から『Civ』シリーズに触れる方や、シリーズ既プレイだけど本作ならではの要素が気になる方に向けて、序盤のプレイと合わせてがっつり特徴や新要素をご紹介していきます!
- 指導者と文明が自由に選べるようになり、プレイの選択肢が大幅に増加!
- ワンプレイが古代・探検の時代・近代と3つの時代に分割!
- シンプルだけど親切なチュートリアル
- イベントが発生する発見と、各地に点在する独立した村
- 新たな土地を開拓! 都市と町の違い
- 他文明との遭遇、外交の始まり
- 自分の指導者を強化する指導者属性
- 戦闘を有利に進める司令官システム
- 時代ごとの目標となるレガシーパスと時代の進行を表す時代の進捗メーター
- 時代の変革期に襲ってくる危機
- 新たな文明の選択、そしてつぎの時代へ
- 終わりに……世界中を虜にしている名作をプレイすべし!
指導者と文明が自由に選べるようになり、プレイの選択肢が大幅に増加!
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)
ワンプレイが古代・探検の時代・近代と3つの時代に分割!
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512_X0aec4M.jpg?x=767)
時代が変わると文明が新しいものに変わり、ゲーム内目標や技術・文化の研究などもガラっと変わります。後述しますが、時代の切り替わりでは引き継げるものと引き継げないものも存在し、一旦リフレッシュするような形になります。開発者インタビューによればゲーム中盤以降、勝負が決まってダレてしまうことが多かったので、その改善にもつながっています。
なお、ゲームスピードにもよりますが、ひとつの時代がデフォルトで約100ターン、プレイ時間にして4時間程度。3つの時代合わせて300ターン、12時間くらいと考えると、従来シリーズと総ボリューム自体はあまり変わっていません。ただ、ゲーム体験的に時代の移り変わりは一段落するタイミングでもあるので、「今日はここまで」の目安にしやすいのは、まとまった時間を取りづらい人にはうれしいと思います。
シンプルだけど親切なチュートリアル
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
指導者と文明を選んだら、いよいよゲームスタート。本作はゲーム中の必要なタイミングで都度都度システムの説明や操作方法を教えてくれるチュートリアルが表示されます。ですので、シリーズ初プレイでもいきなりゲームを始めて問題ありません。
まずはチュートリアルに従い、文明のスタート地点である首都を建築し、マップを探索するユニットを作ってマップを開拓していきましょう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?x=767)
本作はマップのデザインがよりボードゲームっぽくなっており、建物もジオラマを意識しているそうです。未発見タイルを取り除いていくエフェクトや、マップタイルなども豪華なコンポーネントのボードゲームといった感じがあり、アナログゲームファンの方でもワクワクすると思います。
イベントが発生する発見と、各地に点在する独立した村
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)
発見マスは『Civ VII』で新しく追加されたシステムで、そのマップタイルを自分のユニットで踏むと選択肢が出現し、ゴールドやユニットをゲットしたりなど、選んだ選択肢に応じたボーナスをゲットできます。発見マスは早いもの勝ちとなっているので、他文明に取られる前に見つけたら早く踏みに行きましょう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)
独立した村はプレイヤーと同じくユニットを生み出している単独の国で、ゲーム開始時に敵対・中立・友好的が決まっており、敵対していると時々戦闘を仕掛けてきます。独立した村は、“影響力”というポイントを使って同盟を組むことができ、同盟が成立すると成立時にボーナスがもらえたり、他文明との戦闘時に手伝ってもらったりもできます。さらに影響力を使って併合することで、自分の土地にすることも可能です。
新たな土地を開拓! 都市と町の違い
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)
そして町は生産力の数値がそのままゴールド収入となるので、町を増やしてゴールドを生み出し、溜めたゴールドで町を発展というサイクルになっています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)
さらに、町の人口がある程度増えると町を“専業化”することができ、食料をより多く生産する農業の町、交易でメリットのある交易の町といったように特徴を強化することができます。
町はゴールドを支払って都市に転換することもできますが、町に戻すことはできません。都市にしか建てられない建物もたくさんありますが、ゴールド収入は減るし操作量も増えるなど一長一短となっているので、都市化は計画的に行いましょう。
他文明との遭遇、外交の始まり
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a030d7e8e966169ab4c7f67c291c333f4.jpg?x=767)
友好度が一定以上になれば同盟を組むこともできれば、逆に友好度が低いと戦争をふっかけられたりもします。
NPCの指導者はそれぞれアジェンダと呼ばれる嗜好があり、◯◯している文明が好き、◯◯する文明が嫌いといった感じで自動的に友好度が変化していきます。自文明の方針と一致する文明と同盟を組み、逆に嫌われている文明とは敵対することが基本となります。
影響力は溜め込んでもとくにいいことはないので、必要に応じてバンバン使って外交していきましょう。
自分の指導者を強化する指導者属性
そしてその中には“指導者属性”なる強化システムがあり、文化・外交・経済・領土拡張主義・軍事・科学の6種類の強化項目が存在しています。
特定の条件を満たしたときや、文明のボーナスなど、プレイ傾向に応じて各属性のポイントを取得でき、割り振ることで永続的なボーナスを得られるのです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)
どの属性にも使える“ワイルドカードポイント”もあり、プレイにあわせて指導者をオンリーワンに強化できるので、ポイントを取得次第すぐに使うといいでしょう。
戦闘を有利に進める司令官システム
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)
さらに司令官の指揮範囲内でユニットが戦闘を行うと経験値が入り、やがてレベルアップします。1レベルごとにスキルポイントを入手し、自由に司令官スキルを取得できます。展開後に即ユニットが行動可能になる便利なスキルや、指揮範囲内の能力アップ量を増やすスキル、町に置いておくだけで生産量が増える内政スキルなどいろいろあるので、オンリーワンの司令官を育成しましょう。
なお、司令官はやられてもそのうち自文明のどこかにリスポーンするので、前線でやられても全ロスにはなりません(結構なターン数がかかるので、不利にはなりますが)。ガンガン前線に出して、強力な司令官を育てるのも重要となるでしょう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/acf5793938b321b67b3b667655b375703.jpg?x=767)
時代ごとの目標となるレガシーパスと時代の進行を表す時代の進捗メーター
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/aeb935669c45405844c35aafbd5fe43d7.jpg?x=767)
それが“レガシーパス”と呼ばれるもので、科学・文化・経済・軍事の4種類の目標が設定されています。細かく中身を見ていくと、それぞれの分野では何段階かの目的が設定されていて、特定の段階まで達成するとつぎの時代でボーナスを得ることができます。難易度は高いですが、最後の段階まで達成できると、つぎの時代で“黄金の時代”というさらに強力なボーナスが得られます。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/ae0e28452229af52e70f87dd03c3a30c2.jpg?x=767)
レガシーパスを達成しなくてもデメリット自体はありませんが、古代・探検の時代ではつぎの時代のスタートが有利になり、近代ではどれかのレガシーパスを5段階達成することが勝利となります。ある程度まんべんなく進めるのもよし、プレイスタイルにあったものに特化するもよし。基本的にはこのレガシーパスを埋めるためにプレイするといいでしょう。
また、このレガシーパスを3段階以上達成すると、つぎの時代へ移行する目安である“時代の進捗”メーターがぐっと進みます。時代の進捗メーターは全プレイヤー共通の数値で、他文明がレガシーパスを達成しても進んでいきます。とくに時代の後半は一気に全員がレガシーパスを進めて進捗メーターが急激に増えることも珍しくありません。まだまだ余裕があると油断せず、達成したいレガシーパスは早め早めにこなしていきましょう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/ae25418821200a0f7c8f9f81b22d21691.jpg?x=767)
時代の変革期に襲ってくる危機
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/ae3e6f22244e557f1758d397a98734145.jpg?x=767)
この“危機”は基本的に時代の終わりまで耐えることしかできず、“危機政策スロット”と呼ばれるスロットに特殊な政策を設定し、メリットとデメリットを受けながら乗り越えていくしかありません。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/af0d0b070be593820651230120b0374be.jpg?x=767)
どんな危機が訪れるかはプレイごとにランダムなため、あらかじめ準備しておくということも難しいです。先行プレイ時にはすべての居住地が疫病にかかって壊滅したこともあれば、富裕層の躍動で幸福度とゴールドがどんどん減るなんてこともありました。
なんとか危機の対処をしながら時代の進捗メーターが100%に到達すれば、いよいよ時代の終焉。そしてつぎの時代の幕開けとなります。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a853b031a43495200d111d6f5239398a3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/adaa79432b242c16e82493597a4d8c41f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/afed1da6da79ca8f0cba2aa0c88e14d9e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/ab21f0bedce1dfeee7e158f1a8888beab.jpg?x=767)
なお、時代が切り替わると、ユニットは一定数だけ引き継ぎ(引き継ぎ後はその時代のユニットに置き換わり)、都市国家は同盟関係に関わらず消滅、再配置となります。時代が変わる前にチュートリアルメッセージが教えてくれますが、切り替わりには注意しましょう。
新たな文明の選択、そしてつぎの時代へ
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a1f9ffafcc4c0bbc70331f044b842b7fc.jpg?x=767)
探検の時代では11の文明が存在していますが、その中からすべてを選ぶことはできません。文明の移り変わりはアンロック式で、そのプレイで選んだ指導者、文明の種類によって探検の時代・近代で選べる文明が決まっています。一部の文明はプレイ中に特定条件を達成することでアンロックされるものもありました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a9bca1653601cfed0253482a381c1ad63.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/a9371882dcce45ee625a0ce0ba5d0b81d.jpg?x=767)
探検の時代や近代でプレイしたい文明が決まっている場合は、それを見越した初期選択も重要となってきます。
文明を決定した後は、レガシーパスを達成した分に応じたポイントと、つぎの時代でスタート時に得られるボーナスを選択。能力ボーナスをもらったり、ゴールドや町の取得、時代に合わせて首都を遷都するなんてこともできたりします。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/acd0d165e9302c73978d21d8cbf01c48a.jpg?x=767)
新たな文明とボーナスを受け取ったら、ふたつめの時代である探検の時代がスタート!
探検の時代では航海技術を研究し、外洋や新たな大陸の探索が始まる……といった感じになっています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/32525/ac7588853d975607658e9c3a1aa5a0dc0.jpg?x=767)
終わりに……世界中を虜にしている名作をプレイすべし!
前作『Civ VI』と比べ、操作は簡易化、もしくは操作量を減らす代わりに、プレイヤーが選択・決断する要素が増え、リソース管理に追われるのではなく、戦略を考えるゲームプレイに集中できるようになったと感じます。筆者はPCでのプレイヤーですが、家庭用ゲーム機のコントローラーでもプレイしやすいよう、操作量の大幅な見直しが行われたのではないかなとも思います。どうしても管理する情報が増え、操作が忙しくなりがちな終盤のプレイも楽々行えるので、やることが多すぎてパニックということもありませんでした。
眠れなくなるほどハマるというシリーズの評判を聞いて興味半分、恐怖半分という方もたくさんいると思いますが、時代の切り替わりによって区切りもつけやすくなっています。ぜひ一度、世界中を虜にしている名作をプレイしてみてください!