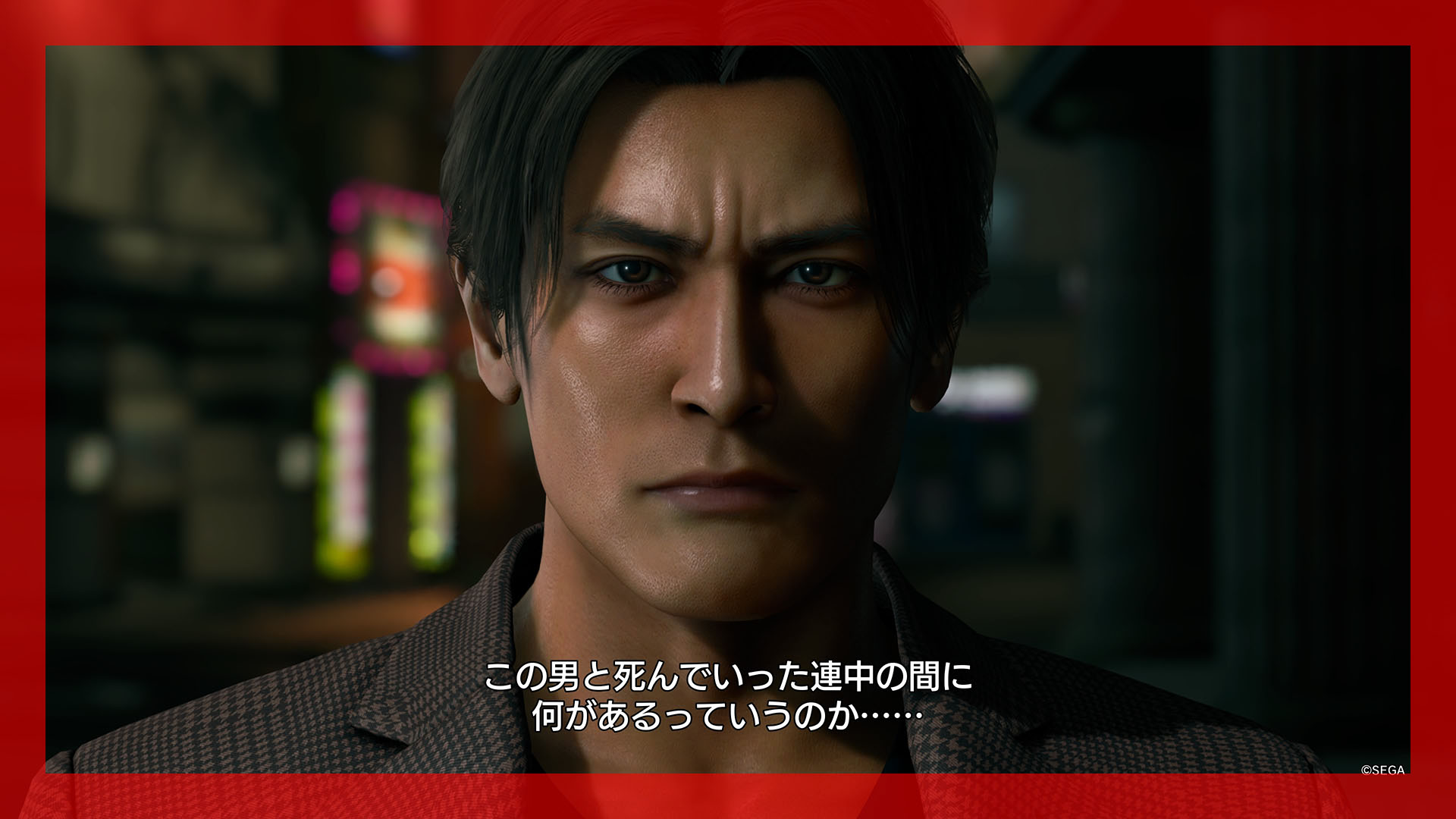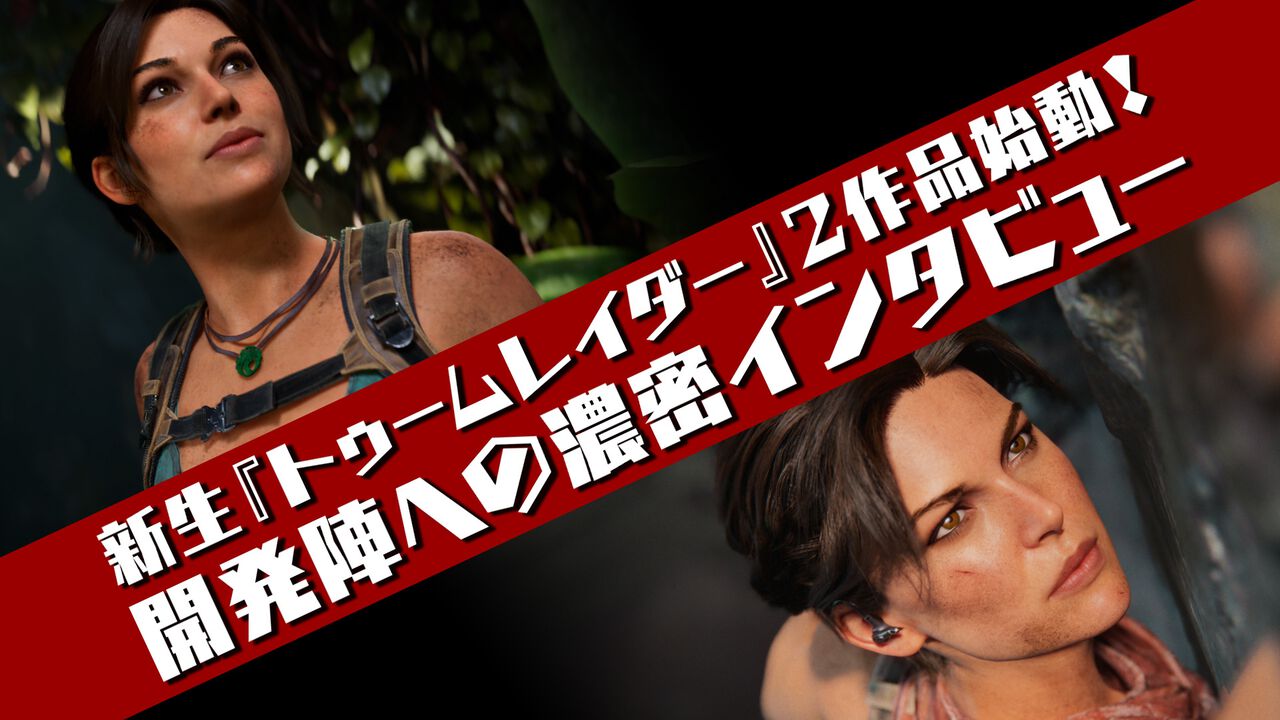本セッションで登壇したのは、株式会社QualiArtsの小沼千紘氏と今井駿汰氏。セッション前半では小沼氏より『学園アイドルマスター』(以下、『学マス』)におけるライブの演出や振付がどのように考えられているのかを解説。後半では今井氏よりツール上でどのようにライブシーンが作られているのかが語られた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
ライブ演出の土台にあるのはアイドルたちのパーソナリティ
『学マス』におけるライブのコンセプトは、プロデューサーとアイドル、1対1の関係性だからこそ得られる、“ソロライブ”ならではの魅せかた、表現を確立することだった。ソロならでは、『学マス』ならではの勝負の仕方を考えるうえで、アイドルの努力と成長のプロセスをダイレクトに感じられるリアルなライブ体験が重視されたという。
出会った時点ではそれぞれの課題や問題を抱えたアイドルたちが、プロデュースを通して精神的にも成長してパフォーマンス力を身に付け、その成果がソロライブでリアルに体験できる。これが『学マス』の目指したライブ体験の理想的なフローだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)
通常、振付を考える際は楽曲が中心になることが多いが、『学マス』ではよりパーソナルな要素を動きとして取り入れたうえでベースとなる振付を構築。そこにカメラやファンへのサービスも盛り込んだうえでモーションキャプチャーを進める。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)
振付そのものに加え、表情や視線といった顔まわりの表現もキャラクター性を伝える重要な手段として、各アイドルの特徴的な要素を言語化するプロセスがあるという。こういった言語化により、チーム内でキャラクター性の認識がブレないようにしていくことが重要であると小沼氏は語る。
表情については、自然体の状態とアイドルとしてステージに立った際の表情とで変化がある場合、それも個々のパーソナリティを踏まえてライブに落とし込むことで、より説得力のある魅せかたができるという。単純に曲や振付に合わせた表情ではなく、その子はどんなパフォーマンスをするのか、といった部分を深く考えているからこそひとりひとりの個性が光るのだろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
ライブ中のアイドルたちは、あくまで会場の観客に向けて全力でパフォーマンスをしている、という前提があるため、画的なかわいさだけを追い求めてしまうとご都合的な流れになってしまい、ライブのリアルさが損なわれてしまう。『学マス』では観客に向けた目線を多く取り入れ、そのうえでアイドルがカメラの存在に気付いてからアピールをする、という流れを1カットに収めている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)
また、カメラアピールの前後のカットではアピールを受けるカメラが見えるカットを入れ、カメラとアイドルとの位置関係が視覚的に把握できるようにすることでもリアルライブ“っぽさ”が演出されている。リアルのライブでは広い視野でライブを見るが、ゲーム内では決められたカットしか見えないため、その限られた画面でも変化をリアルタイムに追えるような工夫が凝らされているとのことだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473.jpg?x=767)
汗や瞳の表現だけでなく、観客の描きかたもライブのリアルさを支える
また、汗をかいた状態で身体を大きく揺さぶるような動きがあると、パーティクルエフェクトによって飛び散る汗が描写される。これもライブ中の時間経過を画的に表現しつつ、臨場感を増すための演出だという。リアルなサイズだと視認性が弱いため、飛び散る汗はあえて大きめの粒として表現しているとのことだ。ほかにもレイアウトによって頬やアゴを伝う汗など、5種類以上の表現が使い分けられている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)
観客のモデルについても複数のパターンを用意しており、観客が目立つシーンではポリゴン数が高いモデルを使うなど、演出や会場規模に合わせて使い分けがされているそうだ。また、カメラ手前に映る観客はローポリモデルを使用し、自然となじむ画作りを行っている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a030d7e8e966169ab4c7f67c291c333f4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/acf5793938b321b67b3b667655b375703.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/aeb935669c45405844c35aafbd5fe43d7.jpg?x=767)
シーンの主役を決めて視線を誘導する、画のコントロール
『学マス』では各アイドルの個性に合わせてカメラの構成演出を変えており、カメラワークそのものでもキャラクター性を感じられるようにしているという。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ae0e28452229af52e70f87dd03c3a30c2.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a129e458698c4745a32d44582161b51d8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ae25418821200a0f7c8f9f81b22d21691.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ae3e6f22244e557f1758d397a98734145.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/af0d0b070be593820651230120b0374be.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a853b031a43495200d111d6f5239398a3.jpg?x=767)
UnityのTimelineを使ったステージの演出技術
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/adaa79432b242c16e82493597a4d8c41f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/afed1da6da79ca8f0cba2aa0c88e14d9e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ab21f0bedce1dfeee7e158f1a8888beab.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a1f9ffafcc4c0bbc70331f044b842b7fc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a9bca1653601cfed0253482a381c1ad63.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a9371882dcce45ee625a0ce0ba5d0b81d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/acd0d165e9302c73978d21d8cbf01c48a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ac7588853d975607658e9c3a1aa5a0dc0.jpg?x=767)
ステージの上を移動するアイドルに追従するライティングが手軽に作れるようになったほか、アイドルが動いてもつねに一定方向から光を当て、色味などを保持することが容易になったという。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/afd107bec4a5eaaed6441a46280dcc929.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/acf5d3c0bfc6069452f2473d6904da38b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a4f7fcc45033f46b53db98b6c7db082d7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a9876c9a3f300f29c8ee619765c1ad768.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a32a03ccfe376e30cb0a7f869918353e8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a550319b866c18a57d557d61167728919.jpg?x=767)
オン、オフの比較で見ると各種制御の効果はまさに一目瞭然。これらの制御を組み合わせることで、『学マス』のハイクオリティなライブシーンが作られているとのことだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a217479a24f5b98bcd9028a1675b0f69e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a3f93da36e4dcc70910e18ac429cf2a3c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/acf0a5dcb4ca3264bc8a7c6c4f31cc65f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a615f58a4072d525b89081fc1b6b6382a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a3571adc2900d18ca7bbb29ffef49e706.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/abaaf94542a40d7deb9a8a917acb1b150.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a5f5f96e221fee78568ec8daee175f851.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/adb8e74df8d74f3efdd249a3fd3a466da.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a86fd4e2d2bd98b8b69279feff366ed30.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a2f1260d0365e4b9f93f3493b3444d38d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a4ede289aea6dc8ae16bc0bd78688af5c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a949badd3dad97d739d3ce3d200406f70.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a7946ff6cd3f75bb0582314ff7eb96971.jpg?x=767)
負荷を徹底的に可視化して制作をより効率的に
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a5aa7f8f71a707262ac6659cddc876e46.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ad313920de74f75604d2d60fd26c58558.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/ab241da9913cc47a13520f344e699f661.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15013/a4a9ce85c122e8b6c633518f8012b4180.jpg?x=767)
発表後には1問だけ質疑応答が行われ「1ライブごとの制作にはどの程度時間がかかるのか」という問いに対し、小沼氏は細かい部分については答えられないとしつつ、「楽曲をもらってから全体がフィックスするまでには半年以上はかかっていると思う」と回答していた。なお、『学マス』のモデルや構造などについては別セッションで解説されるとのことなので、気になる人はそちらもチェックしてみよう。