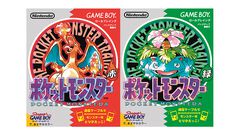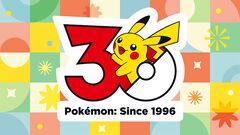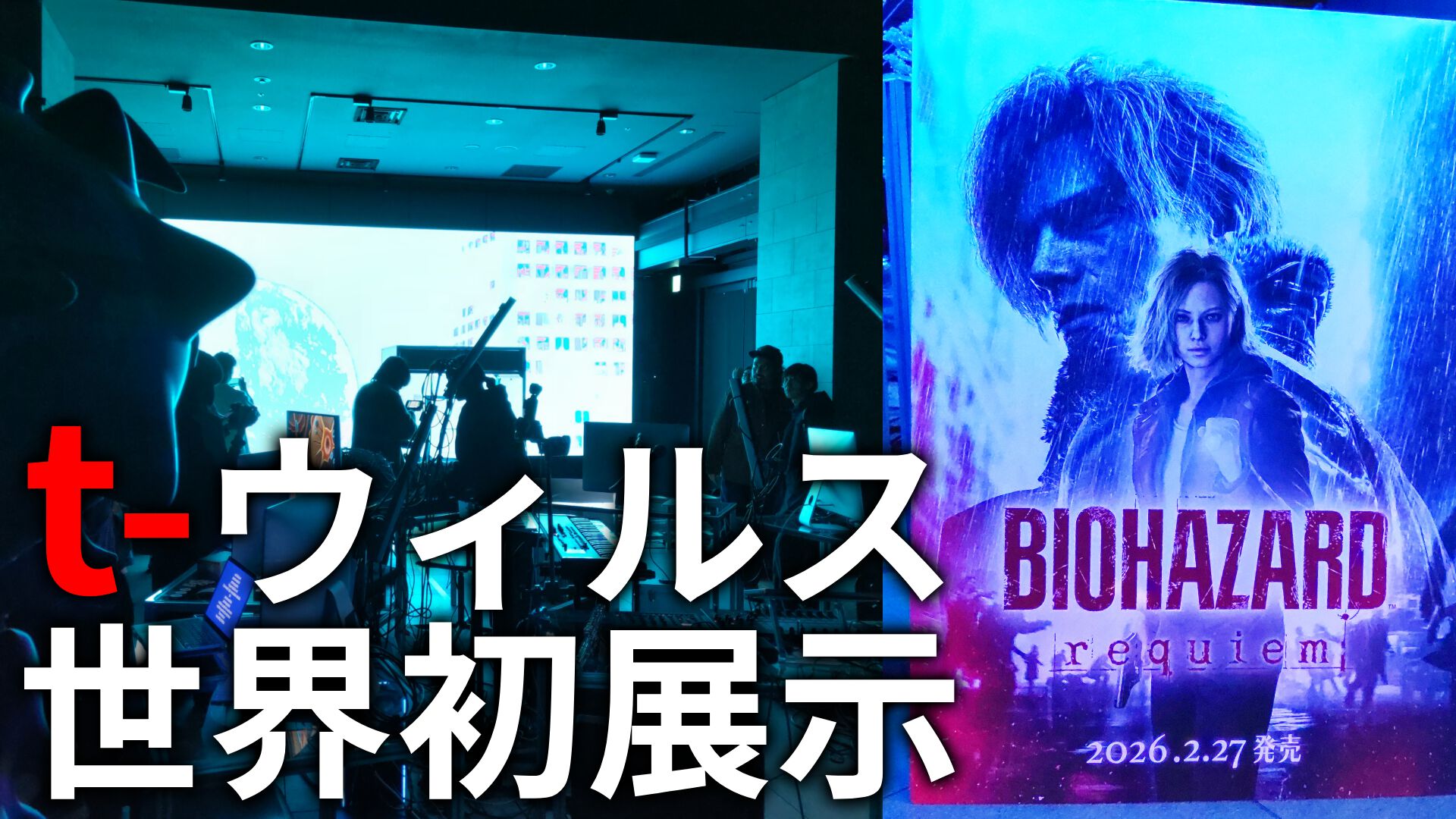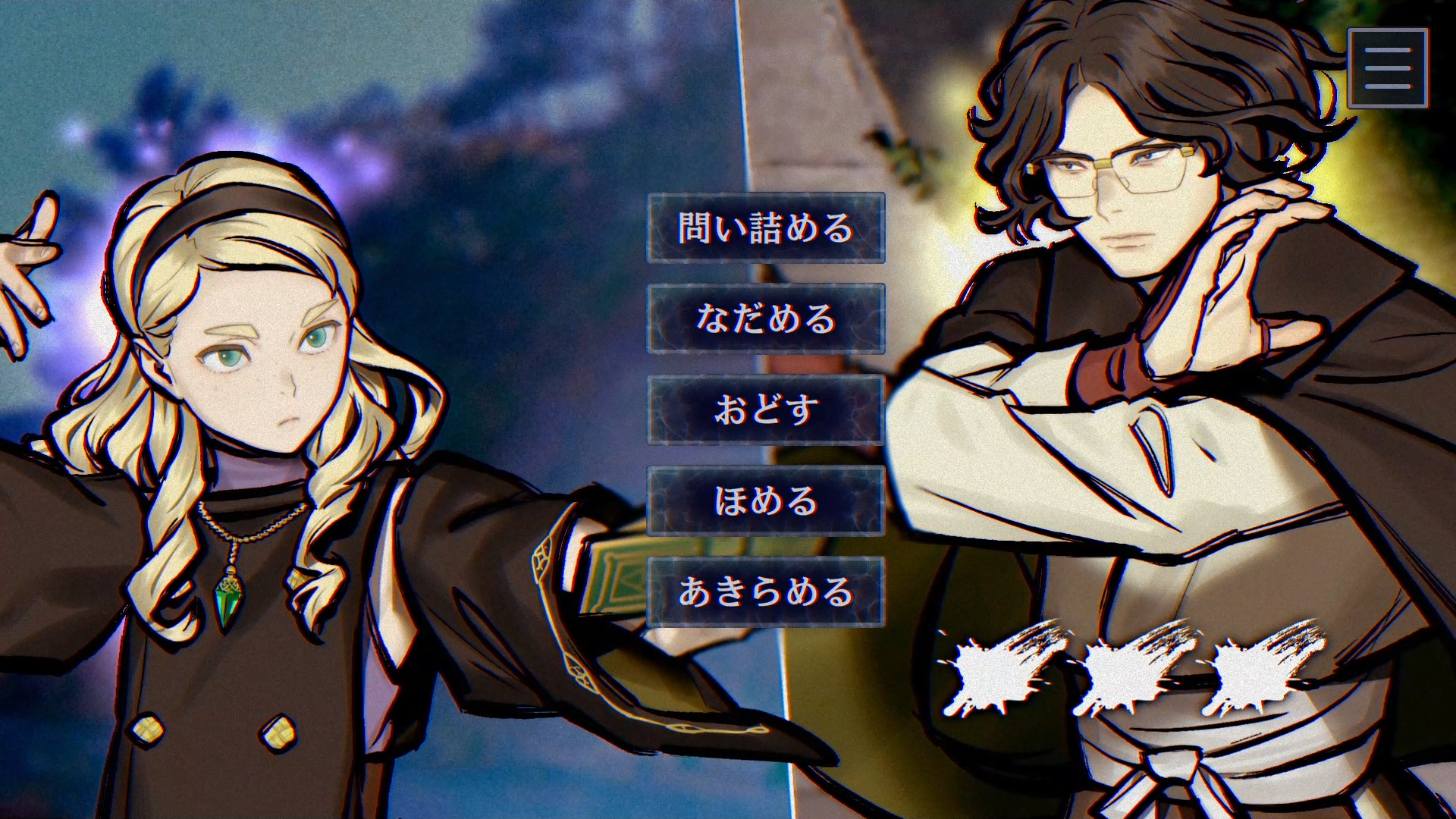本イベントは、ゲーム、XR、メディアアートの領域で活躍中のクリエイター・アーティストがチームを組んで作品を制作するイベント。『にゃんこ大戦争』などで知られる石橋廣樹氏や『スペースチャンネル5』や『街コロ』などに携わった堀田昇氏といった著名なゲームクリエイターたちも参加し、個性溢れる作品作りが行われた。
そんな本イベントでは、各界でユニークな取り組みを行う団体によるトークセッションも実施。5月12日には、イベントの協力団体である、特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)によるセッションが行われた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a5e381b89d26919223141358ee6bfc6f8.jpg?x=767)
VIPOでは、日本発のコンテンツの海外展開を支援し、関連産業の海外進出と訪日外国人の増加を促進することを目的とした補助金制度“JLOX+補助金”を展開している。
セッションでは、VIPOの担当者のほか、ソニー・ミュージックエンタテインメントやクラウディッドレパードエンタテインメントなどでゲームプロデューサーとして活躍し、現在はフリーランスで活動している伊東章成氏、先に紹介したゲームクリエイターの堀田昇氏、電撃ゲームメディア総編集長の西岡美道が登壇。ゲーム会社も対象となっている“JLOX+補助金”が、どのような創作活動に適用できるかを紹介しつつ、それぞれの視点から、この制度がどのようにクリエイターに恩恵もたらすのかなどが語られた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a643a42f4b0cf78e75e8d60fb01ac645d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a1d093ef6abf2723454de81bf8cbb3d15.jpg?x=767)
国内映像企画開発を行う事業(プリプロダクション支援)での補助金利用について
セッションではまず、国内映像企画開発を行う事業(プリプロダクション支援)での補助金の利用について、公募要項に触れながら紹介。
本補助金の目的は、海外需要獲得を目指す事業者が、海外展開を念頭に置いた高品質なコンテンツ(映像・ゲームなど)の本制作に向けて、多様な資金調達やパートナー獲得、クオリティーの高い企画・脚本などの開発、契約交渉、資金調達における権利処理を行う取り組みを支援することで、コンテンツの国際競争力や収益基盤の強化を促進すること。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/ab3820c52660f7ede6b066aaf1381b99e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a8e96d49b136b6833fdf650ea74a53f1a.jpg?x=767)
補助金の利用の流れとしては、事業者登録を行い、専用のシステムに沿って応募。その後、外部の審査委員会が応募の内容を審査する。そして、制作予定の成果物、そのための費用、具体的な海外展開の計画などをチェックし、採否が通知。交付決定後、補助金の支払いが行われる。なお、個人事業主は応募できず、あくまで法人が対象となる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a0698f74468b5d51ae690600fc4d89ef1.jpg?x=767)
交付決定後は、作品の企画書やプロトタイプの制作などの事業を行い、それらを書類などで報告。報告された内容をもとに、事務局の確定検査が行われる。補助金は採否が通知されてすぐもらえるのではなく、実際に事業が行われ、確定審査の後支払われるというのが留意してほしいポイントだと担当者は語る。それゆえ、必ず補助金が受けられるという前提のもと予算を組むのは危険で、受けられないかもしれないということを踏まえて各プロダクトを進行していくことが重要だと、伊東氏は強調した。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a9209d7d47b345b3a12d5b0a9a2727f01.jpg?x=767)
補助金の実施期間は、2024年3月4日~2025年3月31日まで、計4回に分けて応募を受け付けている。現時点では、5月10日~6月7の第2回目から応募可能となる。事業期間は2025年1月31日までで、この日までに報告しないと確定検査ができず、補助金の支払いも行われないので注意が必要だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/afd883a95ad5f71996c80da5ea7019831.jpg?x=767)
支援の対象は、本格的開発のための企画書・シナリオ・Verticalslice版、いわゆるプロトタイプ版の開発支援、コンテンツIP活用を容易とするための権利処理支援となる。ここで伊東氏から、Verticalslice版はゲーム業界においては完成度がかなり高いもの、製品版に近いものを指しているため、このレベルを要求されると苦しいと指摘が。これについては担当者からは、イメージとしてはパブリッシャーに資金調達を行う際、動いている様子がみたいという要望が入ることがあると思うが、その際に提出するレベル、つまりプロトタイプのような段階のものを想定してもらえればと説明があった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a737ee04cc895adbed90e74b4147f650d.jpg?x=767)
それを受けて伊東氏は、企画書やプロトタイプの制作までは、制作者の実費で行っているケースがほとんどで、最終的にその部分の費用を充ててくれる出資者はいるにはいるが、いないケースもあるので、その部分を補助金で補填してくれるのはすごく助かると制度の利点をアピールした。
続けて、対象コンテンツについて。家庭用ゲーム・モバイルゲーム・PCゲームなどが対象で、成人向けコンテンツや政治的・宗教的な意図のあるコンテンツは対象外になる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a7295992e42ccbfecd62270267b6ed5cb.jpg?x=767)
応募資格については、冒頭にも触れたが、日本の法令に基づき設立された法人(企業など)、本業務を円滑に遂行するために必要な組織人員などを有し、かつ資金などについての十分な管理能力を有している法人、そして本補助金の交付を受けようとする法人であること。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a2e58200f195bee620cd0ff99840584fa.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/aeaee14e43cc152faa6610f2923748f09.jpg?x=767)
審査基準には、コンテンツ力・海外展開への戦略性・事業内容・費用の合理性の4つがある。応募時にこれらの項目を記載する必要があり、こちらの内容を踏まえて審査員が判断するため、なるべくたくさん記載してほしいとのこと。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a4c7661a3f7ae6f2143a03ae7da52a0d2.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a6dec73852101b7e009501c955baafc2a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a143163c78793cc56dc5c9a2487eeb7b7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a348ae413b5fb82fc2de1ffd08957d4b2.jpg?x=767)
応募方法については、事業者登録書類を始め、事業計画書、契約書など(該当者)、実施体制図、収支計画書といった書類の提出が必要に。企画書などや、補足資料は任意となる。専用のシステムに沿って応募を行ったら、採択され、交付へ。各種書類を随時提出していくことで支援金が支払われる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/ac4596e1ebb373d96cdf25371c3b35478.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/ad4b67897945b225ad218d807bb258a9c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/ad5955bcf089b76fdefb96c90541f3ed7.jpg?x=767)
ここまでで、国内映像企画開発を行う事業(プリプロダクション支援)での補助金の利用についての紹介が終了。
堀田氏は説明を受けて、自身や周りの関係者も知らない制度ではあったが、本格的なゲーム開発の前段階であるプリプロダクションに支援金が支払われるのは開発にとってすごく助かるし、アイデアベースで終わっていたものを実現できるかもしれないとコメント。また、支援金を申請する過程で各種書類を制作することで、企画がより明確になるかもしれないと、クリエイターならではのメリットについても触れた。西岡氏も、これまで自費ですべて制作していた小規模の開発会社への支援の可能性が生まれるのはすばらしいことだと堀田氏に同意していた。
海外向けのローカライゼーション&プロモーション事業での補助金利用について
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/ae33ad14209d85c18985a3b9e4e5c699e.jpg?x=767)
こちらの補助金の実施期間は2024年3月4日~2025年3月31日まで。各月で隔週行い、随時採択通知を行う。対象コンテンツは、ゲームでは家庭用ゲーム・モバイルゲームなど。事業例としては、海外でのプロモーション費用、英語版のローカライズ費用などがあり、とくに多いのは、海外のゲームイベントでの出展費用だそう。
伊東氏は、現在は円安の影響で海外のイベント出展を諦める企業が非常に多いので、海外展開を想定しているのであれば、大きなメリットになるのではないかと補足した。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/aa9fda042ecc1e3116999f02b86739db7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/ad09d43b8d6e09ae0853735db47226648.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a2c9d5eb51092cd0904e09d68c1789e7c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a4e9e5db9ab612209d28e036c38c0a176.jpg?x=767)
補助金の対象となる経費は、海外渡航に関する費用、出展・参加(オンライン開催を含む)に関する費用、会場・施工(オンライン開催を含む)に関する費用、事業運営に関する費用、広報宣伝に関する費用、ローカライズに関する費用。コンテンツそのものの企画費・制作費は対象外となるのが、先ほどの国内映像企画開発を行う事業での利用と異なる部分だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/ac6bee0c2754967e99e851f3c2266ab06.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/5259/a883533559d4f757a610c2752716f05e0.jpg?x=767)
これについて伊東氏は、ふだんクリエイティブに注力している方はそこまで気にならないかもしれないが、海外で売ることを考えると、この支援はものすごく便利で役立つと力説。申請の有無によって海外展開ができるかに関わってくるし、直近の円安の影響によってたいへん役立つ支援機構であるので、注目してほしいとのこと。
なお、VIPOのホームページには活用事例も紹介されているので、参考にしてもらえたらと担当者は話した。
▼JLOX(令和4年度補助金) 活用事例(VIPO公式ホームページ)
海外向けのローカライゼーション&プロモーション支援の説明を終えたところで、堀田氏はふたつの事業への支援について、どちらも活用しやすい制度であるとし、とくに最近では、海外のイベントでのプロモーションを断念したという話を耳にしていたので、今後ぜひ利用を検討したいとコメント。
西岡氏は、支援を受けることでリスクを回避できつつ、作品のスケールアップも可能になるのではとコメント。申請にあたって作品を見直すことで、それがさらなるクオリティーアップに繋がる可能性があると、金銭問題に留まらないメリットを提示した。
ゲストがセッションを振り返ったところで、VIPOが現在実施中のゲーム開発者向けの取り組みについても紹介された。
VIPOでは、2024年8月21日~25日にドイツ・ケルンで開催予定の“gamescom2024”でジャパンブースに出展するのだが、そこでのプロモーションを希望するインディーゲームタイトルを募集しているという。募集タイトルは3つで、応募は2024年5月23日17時まで。VIPOのホームページで紹介されているので、興味があるゲームクリエイターの方は確認してみてはいかがだろうか。
▼【参加タイトル募集】2024年8月“gamescom 2024”ジャパンブース出展(VIPO公式ホームページ)
その後、伊東氏が、現在企業から独立して事業を始める人が非常に多い状況なので、そういった人たちに届けたかったと振り返りつつ、今回のような制度を活用して、よいゲーム作ってもらえたらとメッセージを送ったところで、セッションは終了した。