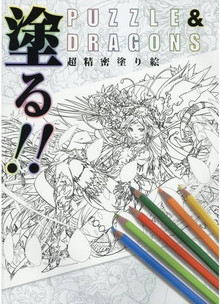- ファミ通BOOKS>
- 連載>
- 劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第1章 母の戦い
劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第1章 母の戦い
公開日時:2018-11-01 19:00:00

|
はじめに
第1章 母の戦い
第2章 再発
第3章 全盲生活
第4章 視力障害センター
第5章 光に向かって
第1章 ■1. 網膜芽細胞腫†
私は16歳の時に妊娠し、17歳で子どもを産んだ。
1985年11月22日、北海道室蘭市の某産婦人科病院にて新たな命が誕生した。
赤ん坊は男の子で、両親の共通の一字を取って「洋(ひろし)」と名づけられた。
洋が病院を退院してすぐに市営団地に引越し、親子3人での幸せな暮らしが待っているはずだったが、その夢はすぐに壊れるものとなってしまった。
洋が1歳になる少し前のこと。
ふと洋の目を見てみると、両目の黒目の部分が異常に光って、膜に覆われているみたいだった。さらに両目とも、あちゃ目(斜視)になっていた。
この異常な目を見て不安になり、すぐに何軒かの眼科に脚を運んだが、「赤ちゃんの眼底検査は難しい」、「たぶん大丈夫だろう」、「もう少し大きくなってから来てください」と、どこからも追い返されてしまった。
それでもどうしても気になり、地元の大きな病院でも半分無理やり診てもらったが、結果は同じ。洋の祖母とともにしつこく訴えて、最終的に札幌にある医大病院を紹介され、すぐに向かうこととなった。
医大では2週間もの間、入院しながら精密検査を行い、ついに診断された病名は「網膜芽細胞腫」という小児がんだった。この小児がんが、これから洋の人生を大きく変えるものとなる。
当時は、病気の情報などを調べる手段が乏しく、病名を知らされても頭に疑問符が浮かぶばかりだったが、小児がんという言葉には不安しかなかった。
医者は病気の詳細を夫にしか説明せず、よりショックが大きいと思われる母親の私には詳しいことは知らされなかった。
そんな中、検査入院中に洋は1歳となり、初めての誕生日を病室で過ごした。洋は何もわからず、無邪気に笑っていた。
その後、札幌の医大では手に負えない病気のため、東京にある専門の病院へと移ることになった。
それが過酷な闘病生活の始まりになるということを1歳の洋はもちろん、まだ18歳になったばかりの私も想像できなかった。
東京に向けて出発する日は父の親戚の家に一泊し、何が起こっているかわかるはずもない洋はただあどけない笑顔を大人たちに振りまき、癒しとなっていた。
この時には私にも洋の病気の真実が伝えられたが、笑顔の洋をただただ眺めながらどうしたらいいのかわからず、涙を堪えることしかできなかった。
その後、私たち3人は初めての飛行機に乗り、まだ希望はあるんだと信じて、東京国立がんセンターという築地にある大きな病院に向かった。
この病院には「網膜芽細胞腫」を専門に研究している権威の先生がおり、診察室の前でじっと順番が来るのを待った。
診察に呼ばれるまでの間、眼底検査のための散瞳の目薬(瞳孔を開く目薬)を数回さされ、病院内の暑さもあって洋はそれだけでも汗だくになりながら、目を腫れ上がらせて泣きじゃくっていた。
まだ小さい洋がなぜこんな目にと、拳を握りしめながらただただ切ない気持ちと闘っていた。
しばらくして、名前を呼ばれ診察室へと向かった。
小さい子はまともに眼底検査ができないため、動かないように診察室のベッドにタオルでグルグル巻きに固定され、目を閉じられなくする開眼機を装着され、恐怖のあまり泣き叫ぶ洋の両目の検査が始まった。
検査のために真っ暗にした診察室で泣き止まない洋を看護師が必死に押さえつけ、その間に先生が悪戦苦闘しながら眼底検査をしていた。その洋の泣き声を聞きながら、拳を握り締め、廊下でじっと検査が終わるのを待っていた。
やっと検査が終わり、抱きしめた洋の目は開眼するためにつけていた器具の跡がくっきり残っていた。その痛々しい姿を見て、もうこんなの終わりにしたいと自分を情けなく思った。特殊な病気でなければここまで小さな子が無理やり眼底検査を受けることはないので、私にはとても辛い仕打ちに見えてしまった。
そして、診断の結果は、やはり疑われた通り間違いなく、「網膜芽細胞腫」。目の網膜に発症する悪性の小児がん。
さらに、専門の権威の先生の口から残酷な診断結果が言い渡された。
「右目はもはや完全に視力がありません。さらには腫瘍が広がっていて、視神経や脳への転移が危険視されるため、すぐにでも摘出しなければいけません。左目ですが、こちらも腫瘍が確認できたため、これから治療していくことになります。左目を残せるかどうかは治療の経過次第となります」
右目の摘出。腫瘍の転移。左目の治療。
感情を見せない口調で淡々と説明され、理解できないままただ大変なことになっているんだと無我夢中で先生の話を聞いていた。
あらかたの説明を受けた後、このがんセンターは現在病棟が満杯なため、慈恵医大病院で場所を借りて右目の摘出手術を行うことになった。
次々と振りかかる現実に気が滅入っていたせいもあり、右も左もわからない東京はとても冷たく、厳しい空気だと感じながら、3人で慈恵医大病院へと向かった。
もちろん土地勘はなく、交通手段もわからないため地図とにらめっこしながら病院を目指したが、結局タクシーを使い、到着して紹介状を提出するとすぐに入院病棟へと案内された。
その病棟は雰囲気が狭苦しく、付き添いのできない病室だった。さすがに東京に来てすぐに子どもだけを病院に置いて行くなんて心配でできないと必死になって病院に掛け合い、まだできたばかりで使われていない新館だったら両親とともに3人で使ってよい、と案内された。これで摘出手術での入院は両親が付き添えることになった。
次の日、先生から早急な手術が必要だと言われた。洋のために予定を無理やり空けてくれたらしく、心の準備ができぬ間に全身麻酔の前処置を受け、洋はウトウトしてぐったりとなった。
とにかく無事に手術が成功することと、いちばん心配な転移がないことを祈りながら、涙を堪えて手術室に運ばれる洋を見送った。
1986年12月3日。まだ生まれて1年と少しの洋が、完全に片目だけになった瞬間だった。
手術は、麻酔が切れる時間を合わせても1時間半ほど。短時間で安心できたが、愛する我が子の片目がもうないんだと考えると、何ともあっけないような情けない気持ちとなった。
手術室から出てきた洋は、「んんーー」とわずかに唸りながら空ろな感じで、右目は山盛りとなったガーゼでがっちりと固定されていた。
そんな洋を見ながら、「ごめんね。洋ごめんね……」とただ泣きながら、何度も謝罪をくり返すことしかできなかった。
切なくて切なくて胸がはち切れそうで、仕方ないことだとしても悔やんでも悔やみきれないと、まだ小さな体で山盛りのガーゼに右目を覆われた洋を見てずっと泣いていた。
洋はその後、私たち両親にずっと見守られながら朝まで静かに眠った。
翌日、洋はいつもと変わらずの笑顔で目覚め、私たちを迎えてくれた。
もともと右目は見えていなかったせいか、行動にも支障があるようには見えず、それを見て少しだけ心が救われる思いだった。
第1章 ■2. 闘病生活†
その後、他への転移は見つからずほっと胸を撫でおろしたが、そんな気持ちなどお構いなく、すぐに残った左目の治療が開始されることとなった。
治療は国立がんセンターで行うことになり、すぐ移動した。
病院に到着して早速案内されたのが、6A病棟。ここは、小児科と眼科(小児)をいっしょにした病棟である。いまでこそ立派に建て替えられているが、当時は牢獄と言ってもおかしくないほど古びた感じの病棟だった。
がんセンターの小児病棟は完全看護で、当時はどんなに小さな乳飲み子でも、具合が悪くても、不自由でも、目が見えなくても、病気の我が子を預けていかなければならない辛い環境だった。
病気に冒され、辛い検査や治療、不自由だったり体力のない体、まだ言葉も話せず「喉が渇いた」など意思表示もできない小さな子や不安に怯える子たちが、親から引き離される。いちばん傍にいて支えてあげたい存在なのに、闘病する子どもの「何か食べたい」、「何か飲みたい」、「散歩したい」、「眠りたい」、「遊びたい」という要望をお手伝いしたいのに、それもわずかな面接時間でしか許されない。なぜ、闘病中の子どもがいちばん望むはずの両親から引き離すのか? ひとりにされた子どもが見知らぬ白い天井を見て何を思うのか? せめて傍にいて支えてあげたい私には、この病院の体制が不思議でならなかった。
午前中に到着して入院の手続きを済ませ、病棟内を案内されて荷物を片付けたらすぐに「また面接時間に来てください」と言われて、病棟を後にするしかなかった。少しでもいっしょにいたい気持ちを押し殺し、後ろ髪引かれる思いで洋を看護師に預けた。
その後、私と夫は適当な宿を探し、落ち着かない心持ながらひと息ついて、面接時間の午後3時にすぐ病院へと向かった。
小児病棟の入り口はガラス張りになっており、その入り口の正面が洋のいる病棟。各病棟もナースステーションや廊下から見やすくするため、壁の上半分はガラス張りになっている。
到着した時、どうやらちょうど昼食後の昼寝の時間らしく、病棟全体は薄暗くされていてナースステーションのみに明かりが灯されていた。
洋は眠ってはおらず、キョトンとした面持ちで大人しくナースステーションのほうを見つめていた。私たちが近づいていくと、それに気がついた洋は途端に顔をグシャグシャにしながら泣き出して、柵の間から私に向けて必死に手を伸ばしてきた。
その寂しさに耐えていた様子を見ると、この数時間どんなに不安だったのか、どんなに我慢して両親を待っていたのか……。これからのことを思うと、不安がぬぐい切れなかった。
そして、主治医からこれから行う治療内容が告げられた。
それは左目に対する放射線療法で、約1ヵ月間、左目に放射線を当てることになるというものだった。「放射線」と聞いただけで「こんな小さな子に?」と不安になったが、この治療で左目が助かるのならと希望を持ち、主治医を信じることにした。
放射線治療が決まり、しばらくの間東京に滞在しなければならなくなったため、話し合った結果、夫は仕事を続け、二重生活を支えるために単身室蘭へ戻ることになった。
あっという間に短い面会時間は終わり、あちこちで両親たちが帰り支度を始めると、途端にそれを察した子どもたちは我儘を言ったり機嫌が悪くなったりする。洋も同じく、立ち去ろうとする私たちに向け、手を伸ばし泣き始めるのであった。
親たちが帰るのを見送るため、子どもたちは大きめのサークルベッドに乗せられ、いっしょにエレベーターを下りて看護師が玄関まで連れて行く。
子どもたちはみんな一斉に手を伸ばし、柵の間から顔を出そうとしながら真っ赤になり、大泣きを始める。もちろん我が子を置いて行かなければいけない親たちも辛くて泣きながら「また明日来るからね」とくり返し、何度も振り返りながらお別れをする。本当になんて残酷な時間なのだろうと、悔しくてたまらなかった。
そんな環境を目の当たりにして、東京の空、いくつもの高い建物、よどんだ匂いのすべてが嫌な記憶となった。
次の日、夫は早くに室蘭へと帰り、私は単身、洋の好きな食べ物や飲み物、おもちゃを買って面会に向かった。病院近郊は銀座のため、買い物しやすいスーパーなどはなく、高級な百貨店ばかり立ち並んで、何を買うにも高い買い物となってしまう。さらに築地には市場しかなく、コンビニもない時代。違う場所で買い物しようにも土地勘もなく、何より早く洋の元に行きたかったため、仕方なく高い買い物を済ませて病院へ向かった。
病棟を訪れると、洋はベッドでひとり、遊んでいた。少し前に部屋についている小さなお風呂に入れてもらったらしく、その後は大人しくしていたらしい。
ベッドの上で大人しくひとり遊びをする洋を見たら、なぜだか涙が溢れてきてすぐに抱きしめた。これからこの子にたくさんの幸せが訪れますように、と願いを込めて。
この病棟では子どもたちが全員食堂に集まり、いっしょに食事をするのだが、洋は生まれつきの少食のため、この時期は哺乳瓶で牛乳を飲んでいるだけで満腹になってしまったらしい。1歳になってもまだ歩くことができなかったため、移動は抱っこか子ども用のバギー。さらに普段の生活はほとんどベッドの上で過ごすため、運動量も少なく、お腹が空くはずもない状態だった。入院中の洋は牛乳と小魚の栄養だけで育ったようなものだ。
ここには様々な病気の子が入院していた。治療により具合が悪くて寝込んでいる子、片足がない子、お腹が異常にふくれあがっている子、両目が見えない子、個室に監禁され自由に行動できない子など。そんな小児科病棟内でいいところは、入院している子どもたちが皆仲よしなこと。大きな子や他の子より体調のいい子が小さな子を支えてあげたり遊んであげたり、本当に心優しい子ばかりなのだ。そんな優しくお世話してくれるお兄ちゃんやお姉ちゃんを小さな子たちも信頼し、言うことを聞いてなついていた。数日その風景を見て、我が子を病院に置いて行かなければならない不安が少し和らいだ気がした。
さらに、同じ心情の親どうしも、難病の子を支える気持ちを分かち合い、仲よくなっていった。
あるタイミングから、病院に紹介された宿に宿泊することになった。個人の方が使っていない建物を多少改装し、低料金で提供してくれるとてもありがたい宿。いくつかの部屋があり、ひと部屋を何人か共同で使うため不便さはあったが、二重生活で出費がかさむ中での低料金と、何より皆同じ思いをしている親たちなので心強く、寂しさもカバーすることができた。当時は現在のような素晴らしいファミリーハウスなどはなく、中には短期間でマンションを借りることや、低料金の宿を借りられない人はやむなく銀座の高級ホテルに宿泊しなければならないこともあった。せめて親戚や身内が東京にいれば金銭的にも精神的にも救われるのだが、こればっかりは仕方のないことだった。難病を抱えた子どもたちを救うために東京の専門病院でしか治療できないとはいえ、地方から訪れた家族にのしかかる厳しい現実であった。
その後、周りの家族たちの支えもあり、闘病生活にも多少慣れてきて、洋の放射線治療も順調に進んでいった。放射線療法は本人の頭をピッタリ固定するため専用のマスクを作成し、頭をわずかにも動かせない状態で目に照射する。ふだんの生活にあまり支障は出ないものの、目は赤くなり痒みが辛そうな状態だ。
摘出手術を終えた右目も経過は良く、仮の義眼を入れることになった。そのため、午前中の放射線治療を終えた後に外出し、日本義眼センターへと行った。洋にとっては久しぶりの外の空気で、ほんのひと時の気分転換となった。
仮義眼を作成するためには、サイズや形、左目の瞳の色などを合わせるために何度も義眼を入れたり外したりする必要がある。これには洋も違和感を覚えて、ご機嫌斜めとなった。大人でも目の中に異物が出し入れされる感覚は嫌なものだろう。でも、これからほぼ体の一部となるもので、適当には作れないから我慢しなければならない。
ようやく仮義眼ができ上がり、はめた洋の顔を見てみると、やはり摘出手術後のため右目だけが窪んでいたり、義眼が見開いて右目だけ大きく見えたりと、その見た目はショックが大きいものだった。まだ1歳なのにこんなに見た目が変わってしまったことが辛く、母親として心が痛くなってしまった。
左目はキョロキョロと忙しく動いているのに、右目はただ一点を見つめるだけ。さらに術後間もないため、右目からはドロドロとした黄緑色の目やにが次々と出てきて義眼表面にベッタリとへばりついてしまう。これが固まってしまうと、瞬きをするだけで義眼表面や瞼を傷つけてしまうため厄介だ。まだ物心つかない洋にとっても、いきなり右目に入った堅い違和感に目をこすったり指でいじったりと大変だった。
まだ義眼をつけて間もないせいか、右目にピッタリとは合わず、義眼が左右にずれてしまって斜視状態となり、それを直すだけでも洋は嫌がってひと苦労だった。これから生涯つけていくものなので、本義眼をつけるまでに仮義眼で慣れてほしい。何もかもが大変な日々で、ひとつひとつクリアしていかなければならないのだが、その度に嫌がる洋を見ていると不安で仕方がなかった。
放射線治療も終わりに近づいてきて、洋はとくに強い副作用にも悩まされず、毎日はしゃいでいた。面接時間外で会うことのできない午前中も、プレイルームで教育テレビを見たり、友だちと遊んで楽しんでいるみたいだ。
地元の北海道ほどではないものの、東京の冬もやはり寒く、外と病院内の温度差で汗をかいてしまうため、体調管理にはとくに気を使った。親が風邪を引いてしまうと、治療などで免疫力や抵抗力が減っている子どもたちに多大な影響を及ぼしてしまう。治療を中断せざるをえず、最悪闘病している子どもに会えなくなることだってあり得るのだ。
この時期、小児科病棟ではクリスマス会の準備が進められ、看護師や小児科の先生、そして入院している小中高校生のみんなは忙しく動き回っていた。病院で苦しい治療ばかりの状況で、みんな自分でも何かできるんだと楽しそうに準備を進めていた。それに対して小さな子たちは、これから何が起こるのか興味津々な様子でワクワクしていた。辛い治療を続けている中で病棟内がこんなにも明るく楽しい雰囲気になるのは、闘病する子どもにも支える親たちにも心が救われる思いだった。
この年も暮れに近づき、洋の放射線治療がやっと終わった。その結果、左目の腫瘍は縮小し、散らばっていた小さながん細胞も消えたらしいが、完全に消えたわけではなかった。
できればこの治療だけで腫瘍が消えてほしかった。さらにこんな辛い治療を続けなければいけないと思うと、まだ何もわからない洋がかわいそうで、同時に申し訳なくて胸が苦しくなった。
次に行う治療は、コバルト照射という治療。簡単に説明すると、眼球の腫瘍付近の鞏膜に放射能を発する金属を直接縫いつける、というものだった。
説明を聞いただけでゾッとした。まだ1歳になったばかりの小さな洋が、そんな残酷な治療に耐えられるのか? それに、つねに放射能が出ているため、特殊で頑丈な壁で部屋を隔離され、もちろん付き添いもできない状態で、ほぼ両目とも見えないまま洋は1週間もの間ひとりで過ごさなければならなかった。放射能を必要以上浴びないために、主治医や看護師でさえも必要最低限しか近づくことはなく、その際には放射能を大量に浴びていないか探知するバッチをつける。そんな状態で、洋は本当に1週間も耐えられるのか?
そんな不安と憂鬱が続く中、洋は風邪を引いてしまった。早く治さなければいけないため点滴の日々となったが、不幸中の幸いか、風邪を引いたおかげで特別に面会時間外でも少しだけ付き添いできることになり、僅かな時間でもいっしょにいられるありがたさを実感した。
第1章 ■3. 父親失踪†
コバルト照射がとりあえず延期となり、まずは風邪を治すのに専念することになった。ウイルス感染予防のため個室に隔離されたが、洋は調子が悪いことに加えて狭い室内のため、ストレスがたまるのかグズグズと気分が優れないみたいだ。せめてもと床一面に敷物を敷き、自由に動き回れるようにしたが、それでも点滴のせいで動きは制限され、部屋の外が気になって出たがるので大変だった。
年末も近いことから、小児科病棟は外泊して実家に帰省する子が増えてきて、寂しい雰囲気となっている。
そして12月31日、私たちは外泊できないため、洋とふたりきりの病室でいっしょに紅白を見て、除夜の鐘を聞きながら寂しい年明けを迎えた。
この時くらいから、少し気になることがあった。
それは、室蘭に帰った夫と連絡が取れなくなっていたこと。当時は家に電話もなく、夫からの連絡を待つか、近くにある実家に言いつけしてもらうしか連絡手段がなかった。
自分でも何とかならないかと何度も手紙を送ってみたが、音沙汰はなかった。そのうち、実家の親からの情報で現在は仕事にも行っていないことがわかり、親が自宅に行っても明かりが点いているのに出て来ないなど、不思議な行動を取るようになっているらしかった。
洋とふたりでどうしたらいいのかわからず、ただ途方に暮れていた。
そこで、洋の体調も回復に向かってきたので、次の治療開始までの期間、体力回復の意味も込めて一度室蘭に帰りたい、と主治医に相談した。夫のこともあったので、わずかばかりの外泊を許可してもらった。
しかし、夫は音信不通で送金もないため、帰るお金すら危ない状態。それを見かねたふたつ年下の弟が心配してくれて、アルバイトで貯めていた貴重なお金を送金してくれた。まだ学生である弟が自分たちのためにと考えると、とてもありがたく、情けなく申し訳なかった。そして、弟の行為に甘えさせてもらい、やっとの思いで北海道に帰ることができたのだった。
病み上がりの洋を連れ、やっとのことで地元に到着し、とりあえず実家に上がらせてもらった。
自宅は向かいのアパートだったため、不安が募る中、私の両親と洋を連れていっしょに自宅へ戻ってみた。しかし、明かりは点いていて人の気配もあるのに、鍵を開けてもドアはまったく開かなかった。
真冬で雪もあり、地元はとても寒いため、病み上がりの洋が風邪をぶり返したら大変だということを考慮して、一度実家に戻り、自宅の様子を覗うことにした。
今日、私たちが帰ることは送った手紙を読んでいればわかるはずだし、何よりまだ小さい我が子が辛い闘病の果てに帰って来たのに……。何が起こっているのか、頭が混乱して理解できなかった。
そして、時間を置いて再度、自宅に戻ってみると、今度はいとも簡単にドアが開いた。家の中にはもう誰もいなく、ドアと柱は外から開けられないよう太い紐で固定していたらしく、急いで切断して逃げ出したような跡だけが残っていた。
それを見て、洋を抱きしめたままその場に呆然と座り込んでしまった。「惨め」、そんな言葉しか出てこず、何が起こったのか、まったく理解できない。夫は何を考え、どこに行ったのか? 誰ひとり知る由もなかった。
その日は自宅にいたくなかったため、実家に泊まって、もし夫が戻ってきた時のために弟が自宅で留守番してくれることになった。
少し時間が経ち、夫から実家に電話がかかってきた。
話してみると、洋の心配のひと言すら口にせず、とにかく意味のわからない弁解をするのみ。そんな夫の様子に、洋がとても不憫に思えて情けなくて、いまの状況がとても受け入れられなかった。洋の父親はもうそこにはいなかった。もはや言葉すら出なかった私に代わって、両親が怒りをぶつけていた。
電話があった日の夜中、弟が留守番していた自宅に夫が現れ、急いで布団一式とテレビを持ち出し、逃げるように出て行ったらしい。弟はまだ高校生で、何も言えずただ唖然とそれを見ているしかなかった。
やっと現れたと思ったら、我が子に会いに来るどころか、さらに理解不能の行動。ますます混乱し、精神がおかしくなりそうだった。
そのままショックで何も考えられない日々を過ごし、洋の次の治療のため、再び東京に行かなければいけない日が近づいてきた。
夫はあれから探しても見当たらず、これからの生活や闘病のこと、もともと職が定まらなかったため将来性の不安もあり、両家の両親のもとで無理やり離婚を成立させた。
そして、辛いことばかりで心労を抱えながら、洋のためにと再び東京へと向かった。
第1章 ■4. 治療結果†
長い移動を経て、再び東京へ戻ってくると、その日は洋とふたり寂しく宿泊先で過ごした。
洋の病気に加えて、夫の失踪。いろいろな現実を背に、ますます東京の空気は悲しく切なく感じてしまう。
このとき、まだあどけない洋を見ていると、これ以上痛い思いや辛い思いをさせてしまうなら、いっそふたりで死んでしまったほうが幸せなのでは? と考えてしまった。
しかし、そんなことを考えていると、洋は無邪気な笑顔を見せてくれた。そんな洋を見て、涙ながらにまだ希望はあるのかなと思えた。何もわからずに辛い治療を受けているのに、私に笑顔を向けてくれる。それだけで、もう少しがんばれるような気がした。
そして、今回の帰省中に両親や叔母、地元の知人の方々の温かい言葉や力強い激励があり、「みんなで祈って待ってるから」と勇気をもらったのを思い出し、私の中で「絶対、洋の病は治る」と、それまで混乱していた気持ちが変わっていった。
何より、こんな小さな洋自身ががんばっているのに、自分が負けていてはならないと決心がついた。地元で待っていてくれるみんなのことを思いつつ、洋とふたりで次の治療に進むため、再び国立がんセンターへと向かった。
病院に到着してすぐ、風邪の完治を確認してから目の鞏膜に金属を縫いつける手術が始まった。全身麻酔を施し、放射能を発するためふつうの手術室では行えないので、隔離された病室で手術は行われた。この手術が終われば、治療が終わるまでは洋を抱くことも近づくことすらもできない。唯一許されるのがオムツを替える数分のみで、それも放射能を探知するバッチが強く鳴り出したらすぐに離れなければならなかった。
治療中、ほとんど目の見えない洋がひとりで生活しているのを眺めることしかできないことに悔しさを感じながら、ギュッと拳を握りしめて無事に治療が成功することを祈っていた。そんな私の気持ちが通じているのか、洋はひとりで見えないながらに音の鳴るおもちゃや音楽を聞きながら、たまに少しぐずる程度で大人しく過ごしていた。
毎日、少し離れた場所から小さなガラス越しに眺めていると、洋は痛いはずの左目をわずかに開け、指差しながら健気に笑顔を向けてくれる。
そんな洋から決して目を逸らさずに、大切な我が子がこんな辛い治療を乗り越えようとしているのだからとさらに強い祈りを込めて、この1週間で絶対に決着をつけるんだと、何度も口にしながら日々を過ごした。
だいたいの子は、この辛い治療を続けていると恐怖のあまり泣き叫びながら目を擦ってしまったり、時には暴れ出したりするため、やむを得ず手足を縛ることもあるそうだ。それを聞いた時は不安になったが、洋は痛いはずの左目を気にしていないのかと思うほど大人しく過ごしており、主治医や看護師も手のかからない洋に驚いていた。
まだ1歳なのに、不安な眼を向ける私を心配させないために? と思わせるくらい、洋は強く逞しく、気持ちが通じ合っているような気がして、感謝でいっぱいだった。支える立場の私はいつも洋に救われている。毎日そう思えてしまうようだった。
そして、コバルト照射が始まってから1週間が経ち、いよいよ左目の金属を外す日が訪れた。
小さな体に何度も全身麻酔を使用するという心配と、何より治療の効果が気になって緊張が走り、手術が終わるまでずっと、心臓が爆発するように鼓動して止まらなかった。
短時間だったのにも関わらず、とても長い時間に感じた手術が終わり、1週間ぶりに我が子の手を握ることができた。しばらくしてから、洋はゆっくりと目を覚ました。洋の手術した左目は痛々しく真っ赤に腫れ上がり、治療中に流していた血の涙を今度は間近で見たら、胸は苦しくなり、かわいそうでたまらなく涙が止まらなかった。
それでも洋は、激痛のはずの左目を無理に開けようとして、その血で濡れた瞳で一生懸命私の姿を見ようとしていた。その純粋な強さに、私は震えながら我が子を包み込み、嗚咽を漏らすことしかできなかった。
それからは様子を見ながら水分を取れるようになり、点滴も外れ、まだ目は不自由ながらすぐに元気になり、その日の夕食も久しぶりにふたりでいっしょに食べて、久しぶりにいっしょに寝ることができた。その当たり前のことだけで、すごく幸せを感じた。
次の日、術後の状態が落ち着いてきたので再び眼底検査を行い、主治医から治療の結果を聞いた。
「今回の治療により腫瘍は石灰化し、言わば火事の燃えカスのような感じです。治療の効果がでましたね。洋君はとても生命力の強い子ですね」
そう説明した主治医は最後に、よかったですね、とつけ加えた。この時ばかりは、つねに感情のないような主治医の顔も明るい笑顔に見えた。
私は洋を抱きしめながら久々に心から喜び、心からの笑顔を顔に表した。病気が発覚して以来初めて、本当に心から笑えた。
私の強い願いと地元のみんなの祈りがしっかり届き、洋が立派に、過酷で辛い治療を乗り越えた瞬間だった。
その後、すぐに退院できることとなり、経過観察のための1ヵ月後の検査が決まって、一度帰省してみんなに元気な姿を見せてあげることにした。
無事に地元へ帰って来た洋をみんなはとても温かく迎えてくれて、治療中の辛さを忘れさせてくれるくらいの幸せを感じながら、私はひたすらみんなへの感謝の言葉を口にしていた。
久しぶりに家族でゆっくりした時間を過ごして、術後の左目の腫れや赤みも取れてきた1ヵ月後、再び東京へと検査に向かった。
洋はやはり検査だけでもその雰囲気を嫌がり、泣き出した。大事な時期のため、しっかりと眼底の奥底まで調べなければならないので、全身麻酔を用いての検査を行うことになって、二泊三日の入院となった。
治療の効果が現れたとはいえ、再発や合併症の危険性もあったため、まだ手放しで安心はできなかった。
そのため、検査を待っている間は食事も喉を通らず緊張していたのだが、それを気にしてくれた副師長さんが優しく声をかけてくれ、「洋君のためにもちゃんとお母さんも栄養つけなきゃ」と、わざわざ売店で菓子パンを買ってきて支えてくれた。そのさりげない優しさ、かけがえのない温かさは、いまでも心に残っている。
それでもやはり落ち着かずに待っていたが、検査の結果、経過は順調で安心してもよいとのことだった。腫瘍に冒され、過酷な治療を続けたのにも関わらず、視力にはまったく影響はなく、気になるのは合併症のみで、わずかに白内障が見られたものの今後とくに問題にはならない、とのことだった。
ひとまずは安心して、次は仮義眼から本義眼に替えるため義眼センターへと向かい、また悪戦苦闘しながらも、今後洋の体の一部となる義眼を完成させた。
その後、東京を訪れて初めてと言って間違いないほどの安心感を胸に、空いた時間で東京見物をした。長い期間、東京にいたが、洋とゆっくり外を歩き回るなんてこの時が初めてだった。
治療が成功したと言っても再発や二次がんの危険性は否めないため、1ヵ月に一度は検査に来なければならない。
しかし、その後の検査でもとくに異常が見られることはなく、1ヵ月に一度だった検査も3ヵ月、半年、1年に一度と間隔が空いていき、長い緊張した日々もいつしか安心しきった生活へと変わっていった。
生まれてから辛いことばかりだった洋がこれから幸せに生きていけますようにと祈りながら、ふたりでの生活を再スタートさせた。
とある検査の日、離婚した際に名字が変わっていたことを主治医に聞かれたことがあった。なぜそんなことを聞くのか不思議だったが、当時、洋のように難病を抱えた家族は子どもの病気が受け入れられず、両親で助け合うどころか病気の発端や原因をなすりつけあい、どうしても長い闘病生活を余儀なくされるために家族が離れ離れになって、父親が蒸発してしまうケースが多いようだった。
時には母親が蒸発するケースもあるが希なことで、主治医はこの事の重大さに失礼だと感じながらも統計を取り、何か対策はないかと考えていたのだった。
遠く離れていると、辛い治療と闘っている我が子は眼中になくなるのか? 死と隣合わせで闘病する我が子を何とも思わないのか? 洋の父親もそうだが、とても不思議でならなかった。
過酷な闘病や家族との別れ、その他様々な経験をする子はたくさんいて、その経験から闘病をしていた子どもたちは他人の痛みがわかり、逞しく心優しい子へと成長していく。何より、命の尊さを誰よりも知りながら生きていくことになる。
洋もまたこの経験を経て、心優しく他人を思いやれる人になってくれることを願った。
ーー第1章 おわりーー
はじめに
第1章 母の戦い
第2章 再発
第3章 全盲生活
第4章 視力障害センター
第5章 光に向かって
『エンターテインメントという薬 -光を失う少年にゲームクリエイターが届けたもの-』特設サイトはこちら
- ファミ通BOOKS>
- 連載>
- 劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第1章 母の戦い