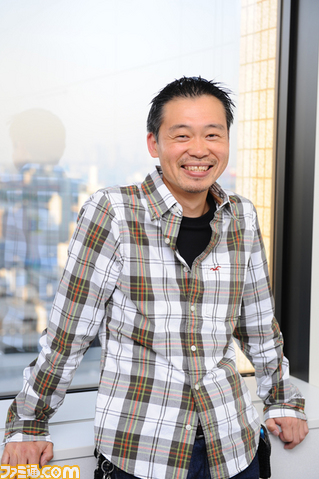●家庭用からソーシャルゲームまで激白
『ロックマン』シリーズや『鬼武者』シリーズ、『デッドライジング』シリーズなど、数々の名作を手がけてきた稲船敬二氏が、カプコンを退社後comceptとinterceptというふたつの会社を設立。以降、各方面で精力的に活動していることはご存じの通り。ファミ通.comでは、そんな稲船敬二氏に単独インタビューをする機会を得た。先日行われた“マーベラスAQL新タイトル制作発表会”より以前に行われたインタビューということで、稲船氏の最新作であるニンテンドー3DS用ソフト『海王』などには触れられていないが(⇒記事はこちら)、家庭用ゲーム機に対する認識や、ソーシャルゲームへの取り組み、そして、何よりも稲船氏のゲーム開発に対する熱い姿勢が伝わる内容となっている。稲船氏の熱いメッセージをお届けする!
■初めにコンテンツありき
 |
――comceptとinterceptというふたつの会社を設立されましたが、まずは会社をふたつ作った理由から教えてください。
稲船 comceptという会社のコンセプトをはっきりさせたかったというのが、いちばん大きな理由です。comceptという会社にコンセプト作りに携わらない人間がいることは許されない。comceptはゲームだけを作る会社ではなくて、いろいろなコンセプトを広げていこうということで作った会社なんです。一方で、「ゲームを作りたい」という思いをそのまま形にした会社がinterceptです。ふつう、僕のような立場の人間が作るとしたらinterceptのような会社なのですが、comcept を作ったのは、“コンセプト作り”というものを明確に打ち出したかったからです。
――最初からふたつの会社を作ろうと思っていたのですか?
稲船 そうですね。最初はcomceptだけでやろうとも思ったのですが、いろいろ考えた末、interceptも作りました。
――一連の動きを見ていると、稲船さんはソーシャルに行ってしまった……との印象も受けますが、ハードコアゲーマー向けのタイトルは出てくるのでしょうか?
稲船 もちろん! 何よりも、それを望んでいる方がいますから。それに関して言うと、どこよりもおもしろいハードコアゲームを作りたいというのは当然考えています。
――おお! それは心強いですね。
稲船 ただし、それだけでいいとは考えていないので、ソーシャルを含め、いろいろなことをやっていこうと考えています。ファミ通の読者からすれば、驚くようなことを発表するかもしれませんよ。「え、そんなことをやるの? それもたしかにコンテンツだけど……」というような(笑)。
――本もお出しになっていますし、ゲームありきの発想ではないということですね?
稲船 ゲームが前提としてあるわけではないです。ゲーム化ということももちろん考えますが。たとえば、「オレはこういうキャラを作りたいんだ」ということでキャラを生み出すじゃないですか。それに対して、「じゃあ、これはアニメにするの?」、「マンガにするの?」、「ゲームにするの?」というアウトプットにはたくさん可能性がある。それに対して、そのコンテンツがゲームに向いているのであれば、ゲームのチームを組むし、アニメに向いているのであればアニメのチームを編成するし……というだけの話です。
――初めにコンテンツがあり……ということですね。では、現状comceptという会社では、ソーシャルゲーム、ハードコアゲームのほかに、どのようなアウトプットを予定されているのでしょうか?
稲船 それは、言えないことが多いなあ(笑)。うーん、「やりたい」ということで言いますと、やっているかどうかは別にしてですよ、アニメもやりたいですね。映画もやりたい。やるやらないは別にして、小説もやりたいです。
――稲船さんが小説を書かれるんですか?
稲船 すでにビジネス書も書いていますよ(笑)。僕はカプコンでキャラクターデザイナーをやっていたときに、「稲船君はデザイナーなので、文章は書けないと思うけどね」ってプランニングを担当しているスタッフに言われてムッとしたことがあるんですね。そのとき「ふざけるな!」って思いました(笑)。デザイナーは絵しか描けないと思っている発想が許せなかったんです。当時、『ロックマンX』で、デザイナーをやりながらシナリオも書いていたんですよ。というようなことがあって、時間さえあればいろいろなことにチャレンジしていこうと思っています。時間さえあれば、マンガも描けますよ!
――あら、マンガまで?
稲船 もちろん、描きませんよ、絶対に(笑)。ものすごく時間がかかるから。まあ、子どものころにいちばんやりたかった仕事はマンガ家だったりするのですが……。で、そういうことも含めて、やりたいことはいっぱいあります。たとえば、このコップ。「このコップのデザイン、いけてないな。オレがやりたいな」と思うし、美容室に行ったら、「この店いけてないな。プロデュースしてみたいな」と思うわけです。東京ゲームショウの衣装デザインも、カプコン在籍中は僕がずっとやっていましたからね。でも、「ファッションのデザインをやりたい」とか言うと、ゲームにしか興味のない人はバカにするじゃないですか。「そんなことは止めておけ。ゲームだけ作っておけばいいんだ!」って。「ゲームもろくに作れないのに、何が映画だ、何が小説だ」と言われるかもしれませんが、そうじゃないんです。むしろ逆で、ひとつのことしかやれないのではダメなんです。いろいろなことに興味を持って取り組むのが大切で、やれないことは何ひとつない。チャレンジしないこと自体がダメなんだ! ということを、書いたのが、最初の著作の『矛盾があるからヒットは生まれる』(文藝春秋・刊)です(笑)。
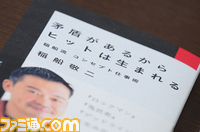 |
――それだけ、人間の可能性を信じてあげたいということでしょうか。
稲船 少なくとも、クリエイティブと言ったら、もうちょっと広いところにあるわけじゃないですか。そう考えると、「ゲームしかできない」と思ってしまっている発想はダメだと思いますよ。
――稲船さんにとって、コンテンツを生み出すモチベーションって何ですか?
稲船 「好き」ってことかな。自分が作ったものを誰かが遊んで感動してくれたりとか、感想を言ってくれたりするのってうれしいじゃないですか。ものを考える人間って、基本そうですよね。「オレ、こんなの考えたんだけど、どう思う?」って聞いたときに、「それ、おもしろいですね!」なんて答えてくれると、すごくうれしいです。何も触れてくれないと、やっぱりさびしいですね(笑)。
――ああ、それはわかります。
稲船 それは自分の中ではいちばん大きいし、とくに、自分のことを認めてくれる人たちが楽しんでくれるとうれしいです。わかりやすく言うと、自分の子どもが僕の作ったゲームを遊んで「お父さん、おもしろいね」って言ってくれると、ものすごくうれしい。
――ちなみに、コンテンツも時代によって向き不向きがあると思うのですが、それに対するアプローチに優劣はつけない?
稲船 そうですね。そもそも、“時代に合う合わない”という発想は、コンテンツを産み出そうとしている人間にとってはあまり関係ないんです。むしろ“時代を作る”んです。いま僕が取り組んでいるプロジェクトって、いまの時代のことはやってないです。1年先、2年先、3年先の時代に対して作っている。未来に対して作っているんですよ。時代を自分が作るんですよ。たとえば、『デッドライジング』が発売されるまでに、ゾンビをモチーフにしたゲームってそれほど出されていなかった。『デッドライジング』のあとに、バタバタとゾンビものが出たじゃないですか。『デッドライジング』が時代を作ったんです。自分は、そういうことをやりたい。『鬼武者』を作るまで、いわゆる“スラッシュゲーム”と呼ばれる、敵を斬って倒すというゲームはあまりなかった。でも、いまや“スラッシュゲーム”が華盛りです。時代に合う合わないは、あくまで結果ですね。
■大手パブリッシャーにはできない方法で勝負する
 |
――話をcomceptとinterceptに戻しますが、家庭用ゲーム機の市場で勝負していく上で、大手パブリッシャーに比しての両社の強みとは何ですか?
稲船 大手パブリッシャーのいいところはいっぱいありますよね。それも経験してきたので、わかっています。人材も豊富だし、できる人間も多い。でも、逆にできる人間が多いので、メジャーリーグで言うところの、ある種ヤンキース状態になるんです。つまり、4番バッターばかりになる。そうするとおもしろいもので、ヤンキースが絶対に優勝できるとは限らないんですよ。どうしても、「オレが、オレが」になってしまう。ひとつのチームの方向性を決めるのに、人材が豊富であればいいというわけでもないというのは確かにあります。
――確かに、スター選手を揃えたヤンキースが毎年優勝するわけではありませんね。
稲船 あと、判断力が遅いです。けっこうどうでもいいところにこだわったりして、スピード感がないというのがマイナス面としてあります。で、大手パブリッシャーのプラス面と張り合って勝負をしても、これは勝てないです。大手のマイナス面を、こちらがプラスにもっていけば勝てる。大手の“遅い判断力”というところに関しては、僕らは絶対に早くします。そして、「4番はオレが撃つから、後はおまえたちに任せる」ということができるんです。そういう意味で言うと、コンセプトを貫いていくということと、スピードという部分がうちの会社の優位点だと思います。これさえあれば、勝てます。
――おお、勝てますか?
稲船 スピードを3倍にすれば、コストは3分の1になりますよね。いまゲーム会社がいちばん苦しんでいるのは何かわかりますよね。コストです。大手パブリッシャーで、収益が上がらないとなると経営者はどう考えるかというと、「回収できるところでやりましょう」ということになる。いままで30億円かけていたものが今後回収できないとなると、10億でやろうということになる。となると、大手の作りかたの10億円なので、いままでの3分の1しかボリュームのあるものしか作れない。僕らが同じ10億円でやるとしたら、大手の3倍は動くつもりでやります。シャアですね(笑)。大手で言うところの30億円使うことが、僕たちの10億円に相当するわけです。そうなると、「どちらのゲームがいいゲームになりますか?」という可能性の話ですよ。一旦外に出て、僕たちみたいにいちからやらない限り、その発想は出てこないと思うんです。なぜなら、甘やかされているから。いろいろなことにお金がかかることに気づいていない。そういう部分で言うと、中小と大手では、お金の感覚はぜんぜん違うと思います。ですので、クオリティーを落とさずにスピードを上げていくという、大手企業にはできない方法で勝負するつもりです。
――なるほど。では、肝心の勝負のフィールドである、家庭用ゲーム機の市場に対しては、どういう認識なのですか?
稲船 ゲームというのを広く捉えないといけないと思っています。もっとゲームの枠を広げて、“コンテンツ”という意識をもって考えていくべきかなと。ゲームもコンテンツのひとつで、コントローラを持って遊ぶものだけがゲームなのではなくて、フィーチャーフォンやスマートフォンで遊んでもおもしろい。そういう発想をもっと広げるのが“家庭用ゲーム機”という考えかたです。それができない限り、日本のゲーム市場はシュリンクしていくばかりです。そういう意味では、読者も“家庭用ゲーム”を広く捉えないといけないし、ファミ通さんなんかも理解していく必要がある。
――作り手も、そういうことをどんどん提案していかないといけない?
稲船 そうですね。僕らも提案していかないといけないです。「稲船はソーシャルに行った」のではなくて、「稲船はソーシャルも作っているし、ハードコアなゲームも作る」です。いずれも「おもしろいでしょう!」というスタンスで提案するわけです。その点は、クリエイターがもっともっとやらないといけないし、受取り手側も「じゃあ、稲船がやってみたのなら、見てみようかな」と考えてもらえるといいのかなと思っています。
――以前からおっしゃっていましたが、日本のユーザーもあまり保守的にならずに、新しいゲームを遊ぶべきだということでしょうか?
稲船 やっぱり、アグレッシブじゃないです。それは、日本のユーザーだけではなくて、ゲームユーザーそのものがアグレッシブじゃなくなっているという傾向はあると思います。とくに日本はおもしろいゲームがどんどん減っているから、「失敗したくない」という気持ちはわかります。そう考えていくと、確実なものを選んでしまうんじゃないですかね。「そろそろこのシリーズにも飽きたけど、海のものとも山のものともつかない新規タイトルを掴まされるのなら、ある程度のおもしろさが保証されたこの続編を買おう」という。その気持ちはよくわかるんです。僕はホラー映画好きなので、TSUTAYAに行くとB級映画のコーナーに行くのですが、怖くて借りられないんですよ、あまりにもハズレが多くて(笑)。でも、怖くて借りられないんだけど、たまにすごい当たりがあったりするんです。「こんな低予算でよくぞここまでやった!」という傑作が。その10回に1回か、20回に1回かのために膨大な数の“ハズレ”を引かされるわけです。それを止められないのは、やっぱり当たったときの感覚が大きいからですね。ある意味“チャレンジ”なわけですが、本当に好きな人間はそうです。
――もし、ユーザーに提案があるとすれば、もっとチャレンジ精神をもって、作品を選べと?
稲船 はい。いま、海外のゲームオタクと呼ばれる人たちのほうが、チャレンジャーですからね。もちろん彼らも続編を遊びますが、新しい取り組みをしているタイトルも必ずやっているんですよ。『コール オブ デューティ』シリーズも遊ぶくせに、ほかのも一応やる。とくに北米は、コア層が日本に比べて大きいのかもしれません。
■遅くとも3年で決着は着く!?
 |
――ソーシャルゲームに対する取り組みは順調ですか?
稲船 いまは、ソーシャルゲームを作って勉強しているところです。誰よりも早く。それは、僕がソーシャルゲームのことをわかっていないからです。理論でわかってはいても、体ではわかっていない。それで失敗を覚悟でソーシャルゲームにチャレンジして、もちろん失敗はしたくないですが(笑)、経験を積み重ねることで、みんなが「ソーシャルをやらなくっちゃ」というときには、ベテランになっているんです。逆に言えば、いま作り手側でソーシャルゲームのベテランはいっぱいいますよ。でも、その人たちはコンソールのゲーム性の部分はわかっていない。コンソール向けゲームを作ったことがないからです。僕は、コンソールの実績を持っていて、彼らに追いつこうとしているわけです。そうすると全部作れるじゃないですか。2000万円のバジェット(予算)のゲームから、20億円のバジェットのゲームまで作れる。でも、従来のソーシャルゲームのヒット作を作ってきた人が、「20億円ですごいソーシャルゲームを作ってくれ」と言われても、作れないですよ。
――ソーシャルゲームは予算も少なめで済むから、ある程度失敗も許される状況にありますものね。
稲船 そうですね。そういう意味ではファミコンをやっていたときといっしょなんですね。ファミコンは4、5人で2000万円くらいの予算規模で作っていました。3〜6ヵ月くらいの期間で。ソーシャルゲームもいっしょです。2〜3ヵ月で作る。失敗しても3ヵ月で結果が出るわけです。いま、コンソールゲームって結果が出るまでに3年かかるんですよ。それに失敗したらまた3年かけて開発する。失敗をつぎに活かすのに6年ですよ! 6年あったら、ソーシャルゲームを何10本作れるんですか?という話ですね。経験の積み重ねが違う。僕は、ファミコンを作っていたころは数年間で何10本というタイトルに関わっていたわけですが、期間の長短に関係なく1本のゲーム作りです。3年かかろうが、3ヵ月で終わろうが、1本のゲーム作りにすべての過程が入っているんです。一方で、ソーシャルゲームにおいては“課金”というシステムをいかにゲーム性に組み込むかが大切になる。そのへんをいま学んでいるところです。
――ソーシャルゲームにおいては、稲船さんもまだ成功させる秘訣を掴みきっていないということですね?
稲船 もちろん成功は狙っていますし、おもしろいゲームは作れます。でも、ソーシャルゲームとして成功させられるかどうかというと、まだまだ難しいと思っています。それは、“大成功”という意味においてですよ。もちろん成功はさせます。でも、いきなり『怪盗ロワイヤル』を超えて……というのは、さすがに無理だと思っています。それはいきなり新人監督が、「カンヌ映画祭でグランプリを取ります!」と言っているのといっしょで、「あほじゃん?こいつ?」と思うじゃないですか。それと同じですよ。『怪盗ロワイヤル』を超えますと豪語したところで、それはただの強がりでしかないので……。でも経験を積めれば超えられます。だから、経験を積むんです。それが2回の経験で済むかもしれないし、50回の経験をしないといけないかもしれない。それは、僕の対応力次第ですね。いずれにせよ、ソーシャルゲームは、人と人とのつながりの部分といった心理作戦的な部分があり、人を集めるノウハウの部分もあり……と、おもしろいですね。
――一方で、アンリアルエンジン3がAndroidをサポートするなど、ソーシャルゲームがハードコアゲームに近づいていく可能性がありますが、それについてはどう捉えていますか?
稲船 うーん。。。ここは慎重に答えないといけないな(笑)。僕は長いことカプコンに在籍していたので、この業界のことをよくわかっているのですが、大手パブリッシャーと言われるところがソーシャルゲームを作るのと、いまソーシャルゲームをやっているGREEやモバゲーが上に上がっていく可能性は、どちらか高いと思いますか?
――なかなかに興味深い質問ですね。
稲船 それを考えると歴然としているじゃないですか。メジャーリーグを経験していた野球選手が、アジアのリーグで出場するのと、アジアのリーグで活躍していた選手がメジャーリーグに行くのと、図式としてはわかりやすいですよね。メジャーリーグで活躍している選手が、わざわざ落ち目になる前に、落ちてくることはない。メジャーリーグで辛くなってから出稼ぎに来るわけで……。そう考えると大手パブリッシャーが落ち目になってソーシャルをやるときには、すでにお金はないですよ。一方で、お金を持っているGREEやモバゲーが「オレたちメジャーリーグに行けるよね!」というときにいちばん簡単な方法は何か……というと、ゲームメーカーを買えばいいんです。現時点でも、彼らは海外市場に取り組むために海外のソーシャルメーカーを買っているわけですが、「コアゲームを出したい」と思ったら、大手ゲームメーカーを買収すればいいだけの話です。でも、落ち目になったところがGREEやモバゲーを買えますか? そう考えると、将来どうなるのかということは目に見えているじゃないですか。こう言うと「稲船は何を言っているんだ?」と非難されると思うのですが、僕はそう読んでいます。
――何にせよ、下からあがってきたほうが勢いはありますよね。
稲船 まあ、企業買収云々は別にしても、可能性があるのは下からあがってきたほうです。ゲーム業界もそうでした。最初は小さな会社から始めてここまでになってきた。それと同じ流れをGREEやモバゲーが辿るんじゃないですか。むしろ、昨年はGREEやモバゲーに勝てるチャンスがあったと思っていたんです。いま、GREEやモバゲーは世界へ羽ばたくためにスマートフォンでの展開を図っていますが、あのタイミングでなぜ彼らが必死になってやっていたかというと、“リセット”だったからです。フィーチャーフォンからスマートフォンに移行するにあたって、そのまま会員を引き継げないので、ゼロからのスタートだったんです。そのときに、「GREEやモバゲーよりもこっちのほうがおもしろい」となったら、市場は取れたんです。でも、大きな動きは見えなかった。「どこかが動いたらおもしろそうだな」と思ったのですが、結局何もなかった。となると、このままGREEとモバゲーで行きますよね。極端な話、ソーシャルゲームはこの2社に収斂されていくのではないかと、僕は思っています。それは早いですよね。5年とは言わないですが、遅くとも3年で決着が着くんじゃないでしょうか。それくらいゲームはスピードが早いですから。だって、GREEができて何年ですか? モバゲーができて何年経っていますか?
――なるほど。ゲーム業界の人からすれば、なかなか認めがたいことかもしれませんが……。
稲船 でも、認めないといけないですよ。認めたら、出版社の人も書くべきことや表現すべきことがわかる。だって、それは事実ですからね。GREEやモバゲーは、事実を正確に認識して、淡々とやるべきことをやっていますから。GREEやモバゲーには、クリエイティブ勝負だと有利ですが、ビジネス勝負だと旗色が悪い。で、いまはクリエイティブだけでは商売になっていない時代に来ているから、おもしろいゲームを作ったからといって、たくさん売れるという時代でもないんです。
――なかなか、家庭用ゲーム機の未来も暗そうだ。
稲船 いまの考えかた、やりかた、作りかたのままだったら、それは未来は暗いですよ。さきほども少しお話ししましたが、やっぱり業界は変わらないといけないですし、ユーザーの皆さんも変わらないといけない。少なくとも、単純にハードを25000円で買ってもらって……という時代は終わったと思います。たとえば、スマートフォンなんかで、「オレ、ゲームを遊びたいからスマホ買ったんだよね」という人はいないじゃないですか。たまたま買ったスマートフォンで、そこそこのゲームが遊べてしまうわけです。だから、同じ土俵で戦うということを、ある程度考慮したビジネス形態に変えて行かないとダメじゃないですか。それは当然、ゲーム業界全体で考えていかないといけない。
――いずれにせよ、変化が求められるということですね。
稲船 ひとつだけ注意していただきたいのは、僕は家庭用ゲーム機を否定しているわけじゃないですよ。
ぜんぜん違うものなので。たとえば、いま2シーターのスポーツカーって売れないですよね。好きな人は乗りますが、そうじゃない人は家族がいるのにわざわざ2シーターのスポーツカーは買わない。選択肢に入りませんよ。これといっしょなんです。ファミリーカーはスマートフォンのようなものですね。電話もできるし、メールもできるし、インターネットも見られる。一方、スポーツカーは走りを楽しむだけなんです。荷物もあまり詰めないし。専用ゲーム機といっしょですよ。ゲームしか遊べないのに、2〜30000円もするでしょう。そうなったら、スポーツカーとしてそれだけの付加価値をつけないといけない。ゲーム機も付加価値を考えないといけないんです。
――そんな家庭用ゲーム機の市場に対して、あえて稲船さんがハードコアなゲームを投入される理由は何ですか?
稲船 僕はスポーツカーが好きなので、この時代でも2シーターのスポーツカーに乗っているんです。それと同じです。「なぜ稲船さんは、2シーターのクルマに乗っているの? せめて4人乗りにすれば?」と言われるのですが、好きなんですよ(笑)。ハードコアに向けてのゲーム専用機というやつが。かと言って、「家族を犠牲にして、スポーツカーだけ持っていればいい」という発想にはならないです。「時代はソーシャルだけど、オレはコア向けしか作らないんだ!」とは言いません。ちゃんとソーシャルゲームを作りますし、学ばないといけないし、時代がそっちに行くのだったら、それを早く知らないといけない。
■開発者と経営者――相矛盾するふたつの顔をいかに両立させるか
 |
――この機会に伺いたいことがあるのですが、いままで大手パブリッシャーを辞めたクリエイターさんで、成功している例は少ないですよね。稲船さんはそれをどう分析していて、そうはならないためにはどのようなことを考えているのですか?
稲船 いままで辞めた人には失礼ですが、クリエイターだからですよ。単純にクリエイターだったら会社を作れないですよね。ゲームを作るということと、経営するということは別物なんです。
――いかにクリエイティビティーがあってゲームを作れる才能があったとしても、経営者として難しいですか?
稲船 難しいですよ。はっきり言いましょう。クリエイターとして何かを成し遂げたとしても、世間がわかってなかったら惑わされますよね。独立するやいなや、100戦練磨の猛者が「稲船さんのお力を借りたいんですけどー」と声をかけてくる。そうすると、後で権利だけ押さえられたり、「言ったことと違う」とか、揉めごとになるわけです。僕が絶対に負けないと思っているのは、カプコン在籍時は、ゲームを作るだけじゃなくて、部下が900人いて、マネージメントもしていたという点です。戦略も経営的なことも、開発も全部やっていたわけです。だから、独立した後は、「単純にゲーム会社を作ってゲームを出しましょう」ということはやっていない。でも、ほとんどの人間がそれをやったんですよ。「大手ゲームメーカーに負けないものを作る」ということで、人を集めて同じやりかたでやっても、勝てるわけがないじゃないですか。だから僕はcomceptを作って、そこで作ったコンセプトをほかのパートナーといっしょに展開するという方法論でいくことにしました。スタッフで集まって何10本のコンセプトを立てて、いろんな人の協力を得てそれを広げていく。こんなやりかたは、いままで誰もやっていないと思いますよ。自分たちの利点と経営のコンセプトをしっかりと決めて展開する。それがcomceptのコンセプトでもあります。
――コンテンツ作りは好きとおっしゃっていましたが、それと同じくらい経営もお好き?
稲船 魅力を感じているとしたら、矛盾ですね。何が矛盾かと言うと、本来経営能力と開発能力というのは矛盾しているんですよ。経営能力があれば開発能力はない。開発能力があれば、経営能力はないんです。だから、うまくやろうとすると、いい経営者といい開発者が仲よくするしかないんです。でも、絶対に相反するんです、ここは。誰よりも強い矛(剣)と誰よりも強い盾なんです。それが、「どっち?」という話になる。ヒット作を産むためには、それが融合しないといけない。経営ばかりでも、開発ばかりでもヒット作は産まれないですよ。カプコンが立ち直ったのも、いいゲームといい戦略の両方があったからです。つまり“矛盾”をクリアーしたからです。本質的な意味では、経営のことをわかっているクリエイターはいないし、開発のことをわかっている経営者は少ないです。
――では、稲船さんは、その矛盾をどうやってクリアーするのですか?
稲船 両方をちゃんと理解すればいいだけの話です。通常どちらかの立場を優先すると、どうしても壁を立ててしまう。クリエイターであれば「オレはこれを作りたいんだから、お金のことは考えたくない」となるし、経営者ならば「オレはお金のことをこんなに考えているのに、なんで開発はやらないんだ?」となる。それを両方わかるように、両方の気持ちに立ってやればいいのですが、なかなかそうはいかない。海外展開に関しても、じつはそうです。「日本のことはわかるけど、海外のことはわからない」というふうになってしまう。でも、知ったほうが得ですよね。僕は柔軟でありたいと思っているし、壁を低くしたいと思っているから、両方をわかろうと努力しているだけです。
――なるほど。理解しようとする姿勢が大切なのかもしれませんね。
稲船 でも、「両方能力があるのか?」というのは意識します。もちろん、得意不得意はありますよ。ピッチャーとバッターの両方ができるからといって、20勝するのは並大抵のことではない。でも、がんばって10勝くらいはしたいですし、バッティングもせめて2割5分は打ちたい。2割5分打って10勝できる選手って、そうそういないじゃないですか。
――重宝されますね、きっと。
稲船 そういうことなんですよ! 僕はどちらかと言えば、クリエイター寄りなので、クリエイターとしては90点は取ります。でも、経営は80点です。となったら、トータルで170点ですよね。どんなに実力のあるクリエイターが100点取ったとしても、所詮は100点止まりです。だったら勝てる。そういうことを自分で考えるんですよね。さっきの話じゃないけど、みんな「できない」って言っちゃうじゃないですか。でも、僕を見てもらえればわかるけど、あれもこれもやれているじゃないですか。本を出して、ソーシャルもやって、ハードコアのゲームも作る。アメリカでも日本でもソフトを売る。「できる!」と決めて、自分都合で作った壁を低くすればいいだけの話です。そういうことを1個1個やっていく努力が足りない。たとえば、海外に打って出るにしても、僕は「英語を学びなさい」というようなことは言ってないですよ。英語なんて知らなくていい。英語がペラペラでもアメリカのことがわかってない人間なんて、いっぱいいます。そうではなくて、言葉ではなくて、アメリカ人のゲームに対する嗜好を理解することが大事なんです。それといっしょです。だから、僕みたいに好奇心が旺盛で、あれもこれもやりたいという人のほうがいいのかもしれませんね。
――お話を伺っていると、気持ちよくなってくるというか、僕もやる気になってきます。
稲船 でしょう! 僕は人を元気にするというアビリティーを持っていますから(笑)。僕と話をした人は、みんな「元気になる」と言ってくれます。これは、僕はよく言っているのですが、人間には2種類しかいないと思うんですよ。光か闇か。
――あはは(笑)。そうかもしれません。
稲船 光のアビリティーを持っている人は、他人を元気にする。「この人と話すと、なんか元気になる」という人。一方で、「この人と話すといつも暗くなるんだよね」という人がいて、それは人の元気を奪う能力を持ったダークサイドの人間。闇の属性ですね。このふたつしかいない。そして、「こいつとしゃべっていると、けっこう元気になる」というのは、仕事をする上では本当に重要で、comceptという会社には「ネガティブな人間はいらない!」という話をしています。僕がいる限りは、そういう人間のネガティブさは出させない。
――稲船さんの光のアビリティーで、ゲーム業界を明るくしてください!
稲船 ありがとうございます。ぜひ、期待していてください。
 |
[関連記事]
※『海王』稲船敬二氏の新作はニンテンドー3DS向け!
※マーベラスAQL新タイトル制作発表会 豪華な顔ぶれが続々と新プロジェクトを発表
※何でもいいからいちばんになれ――稲船敬二氏がヒューマンアカデミーでセミナーを実施