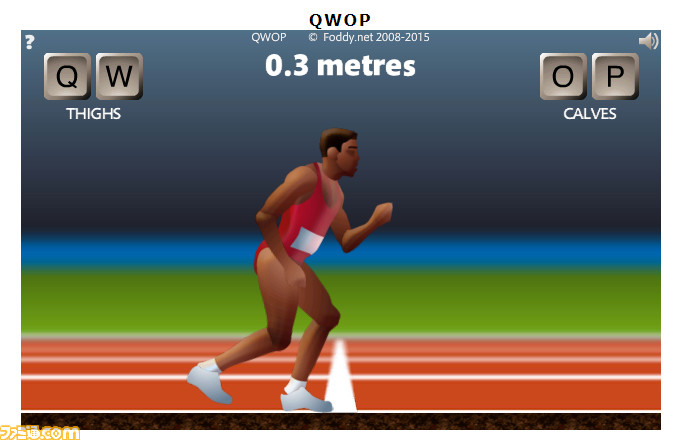『デス・ストランディング』がもうなんかヤバい。今だから正直に言うと、完全に好きな感じの俳優や映画監督が出てくるキャスティングに興奮しつつも、結構ギリギリまで実際のゲームプレイが明かされてこなかったから、「小島監督ってキャラやストーリーが注目されがちだけど、いやいや、第一にゲームデザインの人でしょ? なんでそこが出てこないの?」と正直ちょっと不安を覚えていた。「運び屋のゲームって言っても、なんだかんだと最終的に、ノーマン・リーダスが切れて人間殺戮兵器になるんじゃん?」などと思ったりもした。
でも実際に触れると、本当にとことんまで運ぶゲームであり、“繋ぐ”ゲームだった(資材のためにミュール狩りをする国道建設マニアは除く)。しかも海外のシニカルな連中に言われていた「コジマの新作はハリウッド俳優が出てくるJust Walking(※)ゲームかよ」という邪推を遥かに飛び越えた、画期的かつ練り込まれたゲームとしての仕上がり。やっぱり小島監督はゲームデザインの人だった。(※ここでは、インタラクティブな物語体験を重視する一方で、旧来のゲーム的な行動要素は移動+αぐらいに限定されたタイプのゲームのこと)
気がついたらゲームまわりでのエディターキャリアも10年となり、後戻りが効かない年齢に片足を突っ込んでいる自分だが、あまりにもぶっ飛んだゲームなので、『メタルギア ソリッド』とかいうなんかすごそうなゲームのデモを試遊したくて秋葉原で行われたファミ通の500号記念イベントに行った高校生のクソガキに戻ってしまった……。ので、普段「で、ある」なんてニュース記事を書いている自分の文体もこんなことになっているのである。
いやぁ、あの時500号を手にしていた友達を「ヒゲ(※)があそこで暇そうだからサインくれるべ」と送り出し、実際にサインくれたことに気がついた周囲の人々が全員サインを貰いだして、突然物販の横に行列ができてるのをゲラゲラ笑ってた側の自分が、その10年あまりして最下層の下僕として働くことになるとは思わなかったね。(※浜村通信という元編集長。自分は遭遇しなかったけど『デス・ストランディング』にも出ているらしい)
話を戻そう。気分はクソガキに戻ったけど、腰が抜けるほど一線で洋ゲーを取材してきた知識が今の自分にはある。心は子供、知識と体はほぼおっさんの“名探偵オレ”が、『デス・ストランディング』がどうすげえのかを自分なりに解き明かしていこうというのがこの文章なわけだ。
オープンワールドはスペースをいかに埋めるかが肝心
『デス・ストランディング』における「移動」がスゴいという事についてはすでにいろいろ指摘されているし、それは同意するんだけども、まずはオープンワールドゲームを山程やってきた人間として、スペースの使い方に度肝を抜かれたことを書いておきたい。ホントこれはヤバい。
かつて『レッド・デッド・リデンプション』のプロモでやってきたロックスター・ゲームスのリッチー・ロサードというプロデューサーにインタビューしたことがあるんだけど(誌面用だったのでWebには残ってないはず)、その時に「大変だった」と聞いたのがスペースをいかに使うかだった。これはオープンワールドゲームにとってめちゃくちゃ大事な要素なんだ。
っていうのも、いかに巨大で綺麗なオープンワールドを作ったとしても、プレイヤーにとって意味がない空間はゲームプレイ的にはただのがらんどうな空間でしかないからだ。だったら無理に大きなオープンワールドにせずに、やりたいことだけを詰め込んだ、いろいろなルート取りの選択肢がある小さなオープンエリアをいっぱい作り、普通にレベルデザインした方が安上がりでいい。実際そういうゲームもいっぱいある。
なぜ『レッド・デッド・リデンプション』でそれが大変だったのかといえば、街や家がちょぼちょぼとしかない荒野としてオープンワールドを作らなければいけなかったからだ。これが同社の『グランド・セフト・オート』シリーズなら、建物やNPCをいっぱい置いて街を作ればいい。何かと目を引くものやアクティビティを用意できるし、リアルな曲が入ったラジオを聞きながらクルマをかっ飛ばしたり、そこら中にいる住人NPC相手に勝手に暴れたりしてストレスが発散できる。でも荒野はがらーんとしていないとおかしい。
そこで『レッド・デッド・リデンプション』がどうしたかと言えば、狩りの要素を入れたり、道中でハプニング的に発生するイベントの仕組みを入れたりして、荒野にゲームプレイとしての意味を点在させるようにしたわけだ(この仕組みは後に『グランド・セフト・オートV』にも応用された)。その上で、馬のモデルやアニメーションを作り込み、ラジオの代わりにインタラクティブなBGMシステムを入れ、『グランド・セフト・オート』のクルマにちゃんと匹敵する、もしかするとそれ以上の、それだけでそれなりに没入できる移動手段を用意したんだ。
地形とゲームプレイ
『デス・ストランディング』は御存知の通り、もちろんBTやミュールといった敵キャラにあたる存在が各地にちらほらといるけど、特定のイベントを除けばステルスアクションのように立ち回って戦闘をほぼ回避することもできる。それに大半のスペースは敵キャラもNPCもおらず、単にアイスランド風の自然地形(テレイン)があるだけだ。
もちろんゲームを作る人は頭がいいので、実際は「テレインがあるだけ」ってことは絶対にない。「こっちに山があってー、川がこんな感じに流れてたらそれっぽくねぇ?」とテキトーに作っているわけではなく、テレインは背景アート寄りの要素だけども、ゲームプレイやストーリーとも密接に関連づけて作られている。
例えば火山地帯だったら熱対策が必要だったり炎を使う敵が出てきたりするだろうし、その土地やボスに関する火山ならではの歴史があったりする。レベルデザインの一環として想定攻略ルートをいくつか設けたり、溶岩に落ちたら大ダメージになったりするような、その場所ならではのプレイスキルを求める所も用意するだろう。
これは王道のやり方で、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』にしても、『フォールアウト』シリーズにしても、そうやって全体マップの構成に紐付いた形でゲームプレイのバリエーションを生み出している。『デス・ストランディング』も後半になると山岳地帯が連続するようになったり、雪山でホワイトアウトするシチュエーションが出てきたりする。
『ワンダと巨像』はちょっと例外的なゲームで、広大な地形を移動している間、そこに具体的なプレイ要素はそれほどない。でもあれは、各地にいる巨像というボス──あのゲームにとっての顔であり、パズルであり、ステージそのものであるような、とてつもなく中心的な存在──があるのが大きい。巨像は強烈な誘引力を持っていて、プレイヤーは剣をかざすことで文字通りそこに誘引されていくという流れになっている。
でもオープンワールドのテレイン自体がゲームプレイの顔になるなんてことはそうない。さっき書いたように、普通はいろいろなプレイ要素の配置などを通じて、一見単なる自然でしかないスペースにゲームプレイ的な意味を与えることが必要なんだから。それが簡単にできるんだったら、ロックスター・ゲームスは『グランド・セフト・オート』シリーズからすぐに『レッド・デッド・リデンプション』を生み出せただろう。
地形の中を移動することそのものを核にする
じゃあ『デス・ストランディング』はどうやってオープンワールドのテレインをゲームプレイの顔にしているのか。ここでやっと「移動」が出てくる。プレイした人はわかると思うけど、荷物を背負ってそのテレインをどう踏破するかがゲームプレイの最大の核として作られているから、それが成立するんだ。
『デス・ストランディング』で移動がどれだけ核になっているかは、実際にそれ以外の要素の多くが「移動」と関連付けて用意されていることからもわかる。
たとえばプランを立てるための立体的に見えるマップ機能、荷物の量や配置のマネジメント、蹴つまづいたり荷物が多い時に体が振られたりするのを立て直すアクション、「障害物」としてのBTやミュールを避けるルート選択、ハシゴやロープの設置や各種の施設および橋や国道建設によるルート開拓、一度カイラル通信が通るとルートがオンライン経由でシェアされて踏破プランの幅が増える嬉しさ、このように先人としての他プレイヤーの存在が確かに感じられること、見返りなしにシェアされてくるが故の「いいね」の促進、もちろんバイクやトラックといった乗り物の要素、寄り道を考えさせる落とし物システム、荷物マネジメントや建設とも繋がってくる装備作成のための素材集め、ラストストレッチで静かに祝福するかのように流れてくる楽曲……。ほとんどすべてのシステムが「移動」の周囲に寄せられて作られている。
でもそれだけじゃ足りない。つまらない要素の周囲にそれを補強する要素をいっぱい用意したとしてもあまり面白いものにはならないだろう。結局のところ、「移動」そのものが楽しかったり意義を感じるものじゃないといけない。
ちなみに『ワンダと巨像』では移動中と巨像戦とのコントラストが孤独な旅の感覚などを生み出していて、それが物語体験の一部となっている。緩急の付け方として『デス・ストランディング』でシティや各地の配達先に近づいていくにつれて感傷的な気分になるのと似ているんだけど、前者ではゲームプレイのコアは目的地である巨像にあって、後者では移動中にあるという逆の関係だ。
現実の感覚を参考に、限りなく誰でも歩ける
「移動」は普通、限りなくベーシックなプレイ要素だ。横スクロールアクションなら右を入力すれば、キャラは右に進んでいく。3Dアクションでも、アナログスティックを行きたい方向に倒せばそちらに進める。歩いたら、お次はジャンプだ。これもだいたいボタンを押すだけでいい。これが制動を効かせて降りたい所にぴたっと降りる「ジャンプ移動」になると、プラットフォームアクションの基礎になってくる。
ベーシックな要素ということは、それだけ多くの人が取り組めるということでもある。移動そのものを難しいものにする『QWOP』などのタイプもあるけども、『デス・ストランディング』で一歩を進む難しさは、他のゲームとまったく変わらない。誰でも歩ける。そこからの難度のつけ方がうまいんだ。
その難度も、ほとんど誰もが現実で体験する、「重いものを背負って歩く」という感覚に沿ってちゃんと作られている。このゲームでの基本的な問題として「多めの荷物を持ってこの斜面をまっすぐ行くのは難しい」というものがあるけど、これをプレイヤーは、「コッチに行ったら荷物が左に傾きそうだな」とか「一回斜めに登る方が登りやすそうだな」とか、そこに付随するよりミニマムな課題や解法を現実の感覚を参考にして発展的に考えることができる。
ここで大事なのが、荷物のバランスを取る時と駆け足で駆け下りる時のインタラクションで、どちらもデュアルショック4コントローラーの振動がとてもリアルな感覚をプレイヤーにフィードバックしてくれる(個人的にPC版で心配しているのがこの部分だ。マウス&キーボード操作で擬似的にこの感覚を生み出せるだろうか?)。プレイしながら、20年近く前、比叡山の山道を駆け下りた時のことを思い出したぐらいで、相当山歩きやトレッキングが好きな人が開発にいるんじゃないかと思う。
移動のサンドボックス
もうひとつのキーワードは「サンドボックス」だ。オープンワールドゲームでよく使われる言葉なのでごっちゃになっている人が多いけど、大雑把に言えばオープンワールドとは世界の作り方のことであり、サンドボックスとはそこでプレイヤーにどう遊んでもらうかという考え方のことを指す。
砂場(サンドボックス)で子供が遊ぶ時のように、開発が用意したツールを使ってプレイヤーが遊びや解法の幅を見出だせるなら、それはサンドボックス性が高いということだ。なのでオープンワールドゲームにもサンドボックス性の高いゲームと低いゲームがある。
極端な例で言えば、『マインクラフト』は自動生成した世界そのものをサンドボックスとして、ツールを使って遊んでいくことが主体のゲームになる。逆に『グランド・セフト・オート』シリーズは基本的に開発が用意したツールの使いみちは決まっていて、あまり遊びがない(昔は「自由度が高い」と言われたけど、それは許容された勝手な遊びの幅が大きかったからで、サンドボックス的な自由度の高さとはやや異なる)。
代表的なのは『ジャストコーズ』シリーズで、例えば戦車にバルーンやブースターを取り付けて空飛ぶ戦車にできる。ここで大事なのは、バルーンやブースターが「空飛ぶ戦車」を作るためのアップグレードとして用意されているんじゃなく、何にでも取り付けられる中で戦車に取り付けるとそういう遊びを作れる、という点だ。初期の『ジャストコーズ』は中途半端なオープンワールドTPSだったけど、こうしたバカで無茶なプレイを全部アリにして受け入れるサンドボックスな作りを志向するようになってから化けた。
『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』も、用意されたツールを本来の謎解き以外に活用できる。オープンワールドになったことについては誰もが言及するけど、あのゲームで新しいのはサンドボックス性を高めたことだと個人的に思う。
また小島監督作品で言えば、『メタルギア ソリッド V』も、それまでの作品と比較するとサンドボックスに近い部分がある。厳密なサンドボックス性はそれほど高くないんだけど、目的に対して使えるツールのバリエーションは非常に多く、攻略ルートも自由に取れるようになった。あれはオープンワールドのステルスというより、サンドボックス的なステルスへの移行なんだ。
そして『デス・ストランディング』のアプローチは『メタルギア ソリッド V』に近いものがある。さっきも書いたように、本作のゲームプレイの核は移動だけども、その難度はラダーやロープ、そして国道やジップラインの配置によって大きく変わってくる。これかがもしレベルデザイナーが難度のすべてをコントロールするタイプのゲームだったら、「悪路を踏破する」ゲームとしてのバランスを破壊するものになってしまうけど、『デス・ストランディング』はそれをサンドボックス的なプレイの幅として許容する作りになっている。
選択と集中が生み出す存在と非存在のコントラスト
このように、『デス・ストランディング』は荒野を歩くことそのものを核とするゲームとなった。その上で、キャラクターのいる場所を徹底的に限定したさらなる荒野化が行われている。『デス・ストランディング』にも街にあたるものやNPCは存在するが、それらはほとんど建築物とホログラムで構成され、「時雨を避ける」というSF的設定によって(ミュールやポーターといった僅かな例外を除き)、地上から人影はほとんど消え去っている。
しかし、普通なら誰も地表にいない世界は寂しいものになってしまうが、重要な拠点に着けば豪華俳優陣が現れてくるし、何よりカイラル通信というSF的なガジェットによって他のプレイヤーのルートや設置したものが出現することで、プレイヤーどうしは相互に存在を感じ取れるというのがポイントだ。
カットシーンに出てくる圧倒的な個と、道中で感じるゆるやかな他者の存在の痕跡。あるいは存在と非存在、生と死、繋がりと断絶。その極端なコントラストは物語全体を覆うテーマになっているし、プレイヤーが荒野で抱く感情とも繋がってくる。
人間が存在しない断絶された死の大地で、プレイヤーはサムを通じてもっとも根源的なアクションである歩みに生々しい生を感じ、そしてそこにはいない仲間の存在を感じて繋がりを味わうのだ。
また、生々しい話になってしまうけども、恐らくこれによって可能になっているのが開発リソースの集中だ。カットシーンに登場する重要なキャラクター以外はホログラムで話すだけなので、一度スキャンしてしまえばアニメーションをつけるコストも低く抑えられる。浮いた分のリソースはカットシーンに出てくるような豪華俳優陣に割くことができるし、さらにプレイに必要なアクションゲームの文法が限られている面も、その俳優陣のファン(特にハードコアゲーマーではない人)などのプレイのしやすさというサイクルを生み出している。
ひとつの要素がものすごく画期的というよりも、その組み合わせが生み出した全体的なゲームデザインが画期的なのだ。やっぱり小島監督はゲームデザインの人だった。